世界にはいろいろな神話があります。
ギリシャ神話、北欧神話、中国神話に、日本神話。
他にもまだまだ、ありますよね。
ところが、多種多様なそれらの神話は、実はたった2つのグループに整理できる、としたらいかがでしょうか?
トンデモ!?と思うでしょうか?
でもこれは「おもいきった仮説ではあるが」と言い添えられつつも、プロの神話学者さんたちの間から提出されている学説なのです!
Contents
まずは概要:世界神話学説とは?

世界神話学説の提唱者は、アメリカのマイケル・ヴィツェル博士。
この理論について、日本の人類学者である後藤明さんが、講談社現代新書から出している『世界神話学入門』という本の中でわかりやすく解説してくれています。
今回は、この後藤明さんの著作を参考資料として、大胆学説「世界神話学説」について紹介しますね。
ただしこちらの本、『世界神話学入門(後藤明/講談社現代新書)』は、「書いてあることの検証はまだまだこれから(=くつがえることもありえる)」という前提で非専門家が読み物として読むのであれば、神話好きにはめちゃくちゃ面白い本であることには違いありません!
さて、ここからが理論の説明となりますが、たとえば日本神話のイザナギ冥府下りと、ギリシア神話のオルフェウス冥界訪問のように、地理的には隔たっているはずの国でそっくりなモチーフの神話が継承されていることって、よくありますよね。
どうして神話では、こんなことが起こるのか?
ひとつの考え方は「人間はだいたい同じような物語を思いつく傾向があるのだ」として、この現象を説明するもの。
この考え方をとった場合は、「世界の各地に似た神話があるのはあくまで偶然である」、となります(そうだとしても、それはそれでまた夢のある話、「世界のみんなが好きな話はけっきょくよく似てくる!」ということになりますので、この説も捨てがたい魅力ですが!)。
もうひとつの考え方は、ある意味、スナオな解釈です。
「似た神話が伝わっている民族は、実は太古の昔には同じ土地に住んでいたのではないか?」と考えるわけです。
そうはいっても、先のイザナギとオルフェウスの話のような場合、「日本とギリシャが昔は同じだった」と考えるのはあまりに無理ではないか?
…というのが、かつての常識だったのですが。
最近の考古学や人類学の研究で、人類は実はみんな、アフリカ大陸で出現し、そこから世界に拡散したのだ、ということがわかってきています。
特に遺伝子の研究が発達したおかげで、人類の最初の母親はアフリカにいたかなり少人数(ひょっとしたら一人?!)の女性に特定できるのではないか、とさえ言われています。
いわゆる「ミトコンドリア・イブ」説ですね。
そうなると、「神話は、人類がまだアフリカや中東に固まっていた時に生まれたもので、人類の世界への拡散と一緒に分岐したのだ」と考えるのは、そんなに荒唐無稽とも言えなくなってくる。
神話が誕生した時代を、おもいきり昔、ミトコンドリア・イブの仲間たちがアフリカにいた時代にまで遡れば、「ホモサピエンスが陸続きの大陸を渡って世界中に散らばるのと一緒に、原始人たちが語り伝えていた物語も世界中に散らばって、各地で神話として洗練されたのだ」と考えることができるわけです。
「日本人もギリシャ人も、原始時代にはアフリカに住んでいた共通の祖先をもつ」ならば、「イザナギの神話もオルフェウスの神話も、原始時代に語られていた共通の物語の子孫である」という仮説も措けるのでは?というわけですね。
世界の神話は大きく2グループに分かれて地球上に伝わっていった?!
さて、ここからが上述した『世界神話学入門』の面白いところ、ともなります。
そうやって「似たものどうし」の神話をまとめて、整理していくと、これだけ多種多様な世界の神話は、大きく2つのグループに行きつく、というのです。
それが、ゴンドワナ型神話とローラシア型神話と称される2グループです。
ゴンドワナ型神話のほうが、古い時代のものであり、最初に地球各地に広まったもの。
ローラシア型神話のほうが、そのあとに出てきたものであり、ゴンドワナ型を「上書き」するように広まったもの。
ゴンドワナ型神話は、東南アジアやオーストラリア、パプアニューギニア、南米の一部といった「人類発祥の地からみて東の周縁」のほうに残っています。
ユーラシア大陸、つまりヨーロッパからロシア、中国や朝鮮までは、ローラシア型神話を持っていますが、これはそのあとやってきた人類移動の波によって「上書き」されてしまったと考えられます。
古いほうのゴンドワナ型神話の特徴は、
- 各物語の間に時系列の関連がなく、バラバラのエピソードの寄せ集めに見える
- 世界の始まりとか、世界の終わりには、関心がない(世界は最初からすでにあり、今後もある前提)
- 明確な主人公や英雄がおらず、登場人物も神も動物もみんな「対等」の群像劇
というところでしょうか。
ローラシア型神話は、その反対で、
- 各物語の間に、ある程度の時系列の関係が見える(ある神は別の神の子供と説明される等)
- 世界の始まりとか、世界の終わりについても言及がある
- 中心となる主人公格と、それ以外のわき役たち、に分けられる。優れた能力をもったヒーローが「努力と才能で」世界を変えていくことが劇展開の中心になる
というところです。
実に面白い総括:我々はローラシア型神話に慣れすぎていて、ゴンドワナ型神話の魅力は未来の課題?!
さて、ここからの展開は、学説というよりも人類学から現代社会への主張、となってきますが、このように世界神話を分類したうえで言えることとして、
- わかりやすくおもしろい、ローラシア型神話のほうが、けっきょく人気があるのは仕方ない
- けれどもゴンドワナ型神話のほうに、エコロジーやら生命倫理やらをめぐる、価値観のヒントがあるのではないか
ということになります。
ローラシア型に所属するのが、日本でも人気なギリシア神話や北欧神話などである、というと、この話はわかりやすいですね。
なんだかんだ言っても「神と英雄たちの戦いや怪物退治の物語」のほうが面白いし、大事なことに、メディア展開もしやすい(!?)。

「やはり筋が明確な物語のほうが、人間の脳に好まれやすいという理由もあるのではないか」という意味のことが前掲の『世界神話学入門』にも書いてあります。
そうかもしれません。
いっぽうで、より最古の神話であるゴンドワナ型の魅力の発見は、まだまだこれから、ということになりますし、今まで目立たなかったぶん、そちらのほうに「逆説的に現代人にとって斬新な知恵が含まれているかもしれない」ということですね。
いかがでしょう?
これらはすべて、あくまでも仮説なので、いろいろな意見があるでしょうが、ひとつの神話の見方として面白いもの、と紹介させていただきました。
ところで、肝心の日本神話は、どちらの類型なのでしょうか?
『世界神話学入門』の整理では、「日本神話は、ローラシア型とゴンドワナ型の、双方の特徴を兼ね備えている」という位置づけになっています。
これもまたあくまで仮説ですが、もしそうだとすると、日本神話というものには、世界の別系統の神話どうしを結びつける仲人としての役割が、可能性として眠っているのかもしれません。
そう考えると、なかなか夢のある考え方だと思った次第ですが、いかがでしょうか?




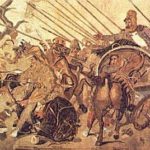


































大変参考になりました。
僕は神話と生物学を両輪としてゲーテ、シュタイナー的な自然観察を研究しております。
今後、フォローし、時々コメントさせて頂きます。宜しくお願いします。
[…] 引用:https://mythpedia.jp/mythology/sekai-sinwa-gakusetu.html […]
日本の文化が2大潮流のハイブリッドなのばなんとなくわかる。言語文化も表意文字と表音文字のハイブリッドだし。