Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。
Contents
中国神話が残ってないのは孔子のせい?
中国は世界有数の長い歴史を持ち、文献史料もまた豊富なのですが、神話についてはあまり充実しているとは言えません。
古くから多くの人が生活をしていたのですから、当然神の概念も発生し、神々についての説話も語られてきたはずだと考えられます。
しかし、その多くが文書に残されることがなく、消えていってしまったのです。
そうなった理由の一端を作ったのが、孔子です。

孔子は日本では「儒教の創始者」として知られています。
しかし、これは微妙に間違っています。
「◯教」と聞くと日本人は仏教やキリスト教のような宗教を連想するのですが、儒教は決して宗教ではありません。むしろそれに対立する存在なのです。
孔子は正確には、諸子百家(しょしひゃっか)のひとつである「儒家(じゅか)」の創始者です。
儒家は天下国家のあり方や個人の正しい生き方を模索する思想でした。
後に、孔子の思想を絶対視する人によって一種の神のように祭り上げられましたが、孔子その人はその著書「論語」において「怪力乱神を語らず」と明記しているのです。
つまり、理屈で割り切ることのできない不可思議なことは、この思想からは排除する、という宣言です。
「神話」からは最も縁遠いものであることは、これでおわかりでしょう。
そしてこの孔子の儒家が、しだいに勢力を伸ばしていきます。
それは彼らが、「論語」などを共通テキストとして、同じ文字を読み書きすることができたからです。
中国の文字は「漢字」ですが、孔子が生きた春秋戦国時代には、漢字は地方ごとにばらばらだったのです。
同じ文字を読み書きすることができる儒家の一党は、国同士でやり取りされる外交文書を扱える官僚として、各国で重宝されるようになりました。
現在でもそうですが、中国では地域ごとに話し言葉が異なり、会話では意思の疎通を図ることが難しかったのです。
異なる地域の人たちが考えを伝え合うためには、文字が必須でした。
文字の読み書きを握っている集団が「怪力乱神」を語らないことをポリシーとしているのですから、彼らの手により古代中国語(書き言葉)が統一されていくに従い、「怪力乱神」についての伝承は消えていくようになりました。
始皇帝により復活しそうだった中国神話
儒家の進めていた「古代中国語の統一」を最終的に成し遂げたのは秦(しん)の始皇帝です。

読者の方は、これまでのお話の流れからすれば「では始皇帝の時に中国神話は完全にトドメをさされたことになるのだな」と思われるかも知れません。
確かに始皇帝は漢字の統一事業を完成させました。
一般的に始皇帝が行った悪行のひとつとして「焚書(ふんしょ)」が挙げられますが、実はこれはそれまで国ごとにばらばらだった文字で記録された文書を焼いたのだ、という説が現在では有力になってきています。
そういう意味では、儒家の仕事を始皇帝が仕上げたと言えるのです。
ただし、始皇帝は文字統一の仕事は儒家から引き継ぎましたが、儒家の思想そのものは大嫌いでした。
孔子の教えを引き継ぎ、発展させた人物に孟子がいますが、孟子は君主が非道であったらこれを廃してよいという「革命」の思想を唱えます。
こうした点が永遠に続く皇帝専制国家を目指す始皇帝の気に入らなかったのかも知れません。
始皇帝は帝王としては「法家」を好み、個人としては「道家(どうか)」を好みました。
「道家」は孔子よりも少し前の時代の人であった(孔子よりも後の人だとする説もありますが)老子によって始められた思想です。
老子が説いたその内容は、一言でいうと「人為を廃して自然に生きよう」という感じのものでしたが、その後超自然的な修行を行って不老長寿を得よう、という一種の宗教に変質していきます。

始皇帝はこの「不老長寿」に取り憑かれました。
修行の結果不老長寿となった人間のことを「仙人」と言います。
不老長寿ですから、人間から神に成り上がったようなものです。
結果的に仙人たちは一種の神として扱われるようになります。
いや、ある意味「神以上の存在」として崇拝されるようになるのです。
道教の成立
秦が滅亡した後に成立した漢帝国においても、道家思想はもてはやされました。
漢の初代皇帝である劉邦(りゅうほう)の軍師だった張良(ちょうりょう)は独自の呼吸法を行うことによって仙人になろうとしましたし、第二代の宰相である曹参(そうしん)も道家思想を信奉していました。
前漢の最盛期を築いたといわれる武帝は、国家経営の思想として儒学を採用しましたが、この人も始皇帝同様個人としてはかなり道家にかぶれていました。
こんな調子でしたから、これから後の中国史には、「公的な立場では儒家信者、個人としては道家信者」という人が増えていきます。
公的な立場をそもそも持っていない庶民の場合は、道家のみという感じになってきました。
この頃になると、道家の核心であった老子の「人為を廃して自然に任せる」という思想的部分はほとんど消えてしまい、不老長寿を第一の価値とするオカルト山盛りの怪しい宗教に変質していきました。
この流れが決定的になったのが、「三国志」の発端となった太平道です。
太平道は主に庶民に対して病気治しを行う教団でした。
この教団が中心となった「黄巾の乱」は後漢の政府軍に滅ぼされてしまうのですが、同じ時期現在の四川省に「五斗米道(ごとべいどう)」という道家系宗教の教団がありました。
こちらの指導者が張魯(ちょうろ)です。
五斗米道は一時漢中地方を中心に独立した政治勢力となりましたが、曹操の攻撃を受けて降伏しています。
その後教主であった張魯は曹操が建てる魏の国に迎えられ、教団を再興して「張天師」として崇拝されるようになります。
この頃から道家は「道教」と呼ばれるようになり、張天師の一族によって指導されるようになるのです。
この道教が、古来からあった各種の神話を吸収するようになり、いくつかの書物にまとめられるようになります。
とはいえ、中国王朝における公的な学問は儒教でしたから、これらの書物は第二線級のいかがわしいものと位置づけられてしまいました。
神になる老子
諸子百家のひとつ「道家」は先に述べたように、老子と呼ばれる人物によって編纂された「道徳経(どうとくきょう)」という書物を中心テキストとして発達した学派です。
元々は政治学の派閥で、「人為によってあれこれするよりも、自然の成り行きに任せた方が万事うまくいく」という考えを基本に、各国の政治を運営していこうというものです。
老子の考え方の延長線上に自分の考え方を展開した莊子(そうし)も、どちらかというと政治学者に分類した方がいい人物です。
ただし莊子は、国家のあり方だけでなく、個人の心のありようについても考えを述べています。
政治学だけでなく、哲学に片足を突っ込んでいると言っていいでしょう。
莊子は比喩表現に非常に巧みな人物で、何か現代的(莊子の時代から見て)な物事を語ろうとする時に、大昔の別な話を持ち出し、そこから現代的な話題と共通するポイントを抜き出すという論理展開をよくしました。
莊子の著書である「莊子」の冒頭は、前置きなしでいきなりこの手の「古代の話」から始まります。

「逍遥遊篇(しょうようゆうへん)」というのがそれです。
莊子の語る所によると、その昔北方の海に鯤(こん)という馬鹿でかい魚がいて、ある時鵬(ほう)というこれまた巨大な鳥に変じた、といいます。
莊子は続いて、鵬が飛び立つ様を語ります。
凄まじい風を巻き起こし、超高空に上昇し、とてつもなく長い距離を飛ぶのだそうです。
蝉と若鳩が、「何の必要があってあんな大げさな飛び方をするのだね」とあざ笑うのですが、これに対し莊子は「小さな知恵では大きな知恵に基づく行動を図ることはできないのさ」と言ってのけるのです。
鯤も鵬も、恐らくは古代において神獣として、人々の信仰の対象であったと思われます。
莊子にはこのような形で、古い神々のエピソードが散りばめられているのです。
他に有名なものとしては「渾沌(こんとん)」があります。
渾沌は混沌とも書き、その名の通りカオスを擬人化した存在です。
短いエピソードですので、全体を紹介しましょう。
南海の神を儵(しゅく)といい、北海の神を忽(こつ)といい、中央の神を渾沌といいました。
ある時儵と忽が渾沌の元に行き、大層なもてなしを受けました。
喜んだ二人は、渾沌にお礼をしようと思い立ちます。
「人間には七つの穴があり、それを使って見聞きしものを食べ呼吸をしている。君にはそれがないからわれわれが作ってあげよう」と言って、二人は一日にひとつのペースで渾沌に「人間の持っている穴」を穿っていきます。
七日後に渾沌は死んでしまいました。
このように、神々の登場する壮大なたとえ話を次から次へと繰り出したため、死後莊子は神と同格の人間、すなわち仙人だと考えられるようになります。
もちろん、莊子の先輩格である老子も同様です。
戦国時代の終わり頃になると、老子や莊子の思想に、本来は存在しなかった「個人の健康を保ち長寿を獲得する」というものが追加されていきます。
漢の終わりになると、さらに「病気治しのまじない」が加わり、宗教化が加速されました。
その結果、老子は「太上老君(たいじょうろうくん)」、莊子は「南華老仙(なんかろうせん)」という仙人として祭り上げられます。
「三国志演義」の冒頭で、張角に「太平要術の書」を授けて太平道を始めさせたのは、この南華老仙だということにされてしまいました。
ちなみに、書物である莊子に登場した渾沌もまた、鴻鈞道人(こうきんどうじん)という名前で仙人化させられています。
中国史書と神話
日本の場合、国が正式にまとめた歴史書の最初の部分に、「神話」が収録されました。
中国においては日本よりもずっと早くに歴史書がまとめられていたのですが、そちらと神話の関係はどうだったでしょうか。
中国最初の正式な歴史書は、漢の武帝の時代に司馬遷(しばせん)によって書かれた「史記」であると言います。


それ以前にも「春秋」などが存在していましたが、それらはあくまでも統一王朝が成立する前のローカルな歴史書として扱われました。
この「史記」の冒頭に来るのが「五帝本紀(ごていほんぎ)」です。「五帝」というのは、古代の中国を治めたという伝説の聖王五代のことを言います。
具体的には、黄帝・顓頊(せんぎょく)・嚳(こく)・堯(ぎょう)・舜(しゅん)です。
ただ司馬遷は「自分は黄帝は実在したとは思っていない」という結構身も蓋もないことを言っています。
なお、五帝の前には三皇がいた、と司馬遷の時代でも言われていたようです。
しかし、五帝の存在すら疑っていた司馬遷は、三皇については「ただの迷信」として史記に伝記を加えませんでした。
現存する史記には、「三皇本紀」が存在するのですが、これは唐の時代に書き加えられたものです。
三皇
三皇五帝は、古代中国を統治した非常に徳の高い帝王たちであるとされています。
ただ。その数は必ずしも3+5=8人ではなく、その顔ぶれは三皇五帝伝説を記録した文献によってまちまちです。
ここではまず、神話により近い帝王たちのグループである「三皇」について語りましょう。
三皇として名が挙げられることが多いのが、伏羲・女媧・神農・祝融(ふくぎ・じょか・しんのう・しゅくゆう)です。
これらは恐らく太古は神として信仰されていたと考えられています。
伏羲と女媧は兄妹とも夫婦とも言われています。その姿は蛇身人面であるとのことです。
古代の絵画には、よく蛇の形をした下半身を絡めあった二人一組の像として描かれており、セットで信仰されていたものと考えられます。

女媧は人類を創造した神であるとされます。
人類は女媧が泥をこねて作ったものだ、というのです。
最初に丁寧に作った泥人形が貴人となり、後で面倒になって縄を使って適当に作ったものが庶民になりました。
泥から人間が作られたという神話、またその時支配者と被支配者が別種のものとして作られた、とする神話は、世界中いたるところで見られます。
女媧はその名に「女」の字を含むので一般的には女神だと考えられていました。
「いやそれは字だけの話で実際には男神だったのではなかろうか」という説も唱えられましたが、現在では「やはり女神だった」というのが主流になっています。
太古に最初に出現した神が女神であった、というのも、非常に一般的に見られる神話ですので、「女媧女神説」の方がわれわれには素直に信じられると思います。
なお、蛇身人面であったというのも、太古の神としてはふさわしい姿であったと言えます。
蛇は農耕に不可欠な水と強い関わりを持つ生物です。
普段は水辺に住んでいる癖に、水辺から離して乾燥した所に連れていってもなかなか死にません。
乾燥に強いだけではなく切っても突いてもなかなか死なない強い生命力を持っているので、世界中の古代人が原初の神、またはヤマタノオロチやインドのヴリトラ、メソポタミアのティアマットのように、原初の神と戦うモンスターとして神話に取り入れています。
中国では特に蛇から派生したモンスターである竜が尊ばれ、後には皇帝の象徴とされるようになります。
ちなみに漢字には、西洋でいうところのドラゴンを表す文字として「竜」と「龍」の二種類があります。
日本人の多くは、画数が多い方がなんとなく起源が古そうだと思い、「龍」の方が正字で「竜」は略字だと考えがちです。
しかし、実際は「竜」の方がやや古いのではないかというのが主流になりつつあります。
原初の神が女神であった、その神が泥をこねて人間を作った、というお話とともに世界的に見られる神話に「かつて大洪水が起こり、一組の男女が生き残った」というものがあります。
旧約聖書のノアの洪水の話はこれの変形で、生き残るのが人間の男女だけではなく、さまざまな動物の雌雄一対にまで拡張されています。
中国南部の長江流域にもこの話が伝えられているのですが、「生き残った一組の男女」とは実は伏羲と女媧であったのだ、とされるようになりました。
女媧とペアになる伏羲の方ですが、こちらは「八卦の創始者」とされています。

八卦というのは陰陽の二気を組み合わせてこの世のすべてを表現しようという考えで、そのシステムは現代のデジタルコンピュータによく似ています。
陰と陽の二要素だけでは、二種類のものしか表現できません。
しかし、これをニの三乗である八にまで拡張すると、さまざまなものが表現可能になります。
これを利用して、さまざまな自然現象を説明するとともに、未来に発生する出来事の吉凶を占うようになったのです。
八卦の発生は、「易経(えききょう)」に始まると言われます。
易経の著者は伏羲とされていますが、成立したのは周王朝の時代だと考えられています。
中国最初の王朝だと考えられている夏よりもさらに前の人物(神)である伏羲がこれを書いたとすると、結構深刻な矛盾が発生してしまいます。
このことから、「八卦の発明者」としての伏羲のイメージは、当初からのものではなく後世に追加されたものであるということがわかるのです。
伏羲のオリジナルに近いイメージは、女媧とペアであったということ以上はわからない、というのが実際のところです。
神農はその名に「農」が含まれていることから想像できるように、農耕の創始者として尊崇されていました。
神農は人間に、農具を作ること、土地を耕すことを教えました。

さらに、野山に生えている植物を自分で舐めて毒になるか薬になるかを確かめ、薬になる植物を人間に教えたとも言います。
さまざまな文献に、伏羲の後を受けて中国を治めたと記録されていますが、これは「三皇五帝」のイメージが普及した後で作られたものです。
実際には、神農は女媧・伏羲とは違う文化圏で信仰されていた神で、始皇帝の統一以降に一つの建国神話にまとめられていったのでしょう。
これは他の三皇五帝の神々についても言えることです。
祝融は火の神です。ただし具体的にどういう活躍をしたのかについては、ほとんど記録が残っていません。
ある書物では「炎帝の子孫である」とされています。
炎帝というのは神農の別名です。
初期の農耕は、原野に火を放って焼き、その灰を肥料とする焼畑農業が主流でしたから、農耕神の子孫を火の神とする設定は説得力が高いといえます。
祝融は共工(きょうこう)と戦ったといくつかの文献に記録されています。
共工は蛇身人面の水の神です。
基本的な性格は女媧とよく似ていますが、こちらは稔りをもたらす豊穣神としての性格ではなく、洪水を興して農業に害を与える水神としての側面が強調されています。
共工は後に「四罪」という悪神グループの一柱とされるようになりました。
四罪は主に五帝の一人である堯(ぎょう:治水の神)と対立する存在で、共工はそのリーダー格です。
四罪の中でもその強さ(凶悪さ)が際立っているので、時代をさかのぼって祝融や女媧・伏羲と戦ったとされるようになったのです。
文書によっては、共工こそが原初の神であった、とするものもあります。
このように「原初の神」が複数あり、それらが互いに争ったという伝説が残っているのは、それぞれが別の部族の祖先神であり、それぞれの部族が抗争を繰り広げて次第に大きな国にまとまっていった、という史実の反映であると考えられています。
主導権争いに負けた祖先神は悪神に変えられましたが、「実は勝ったのはこの神の方であった」「◯◯が帝位に就く前に天下を治めていたのはこの神であった」という話も、少なからず残されています。
五帝
三皇同様、五帝のメンバー候補も五人以上いて、文献により顔ぶれが異なります。
伏羲・神農のように、三皇の有力メンバーでありながら、五帝とされる神もいます。
司馬遷の「史記」によれば、五帝とされるのは黄帝・顓頊(せんぎょく)・嚳(こく)・堯(ぎょう)・舜(しゅん)です。
中国の史書に取り込まれた古代神は、多かれ少なかれ神としての要素が薄められ、文化英雄としての側面が強調されるのですが、黄帝はその中でも神としての要素を濃厚に残している一人です。

神農の治世の終わり(神農その人ではなくその子孫とされる祝融、あるいはさらにその子孫の時代だったのかも知れません)に世が乱れ、諸侯は横暴になって民をそっちのけにして互いに争うようになりました。
中でも最も暴虐であったのが蚩尤(しゆう)であったと言います。

蚩尤はのちに儒家系の文書において悪役として描かれていますが、元来は戦いの神であり、各種の兵器の発明者とされていただろうと考えられています。
黄帝はこの蚩尤を破り、分裂していた中国を統一したというのです。
蚩尤は数多くの妖怪を配下に持つだけでなく、天候気象も自由に操って黄帝軍を苦しめました。
しかし、黄帝は「指南車(しなんしゃ)」を使って悪天候の中正しい方向を進み、蚩尤を打ち破ったというのです。
「指南車」は恐らく方位磁針を組み込んだ戦車であっただろうと思われます。
黄帝と蚩尤の戦いを「涿鹿(たくろく)の戦い」と言います。
中国の覇権を争った最初の大戦争だとされますが、実はこれは後に行われた夏対殷(商)の「鳴条の戦い」、殷対周の「牧野の戦い」の焼き直しです。
大元になっているのは時代が最も新しい「牧野の戦い」でした。
周は建前上、殷に臣従していたので、主君を倒して覇権を奪ったことになってしまいます。
それによる悪評が広まらないようにと、「過去においても聖王が悪逆の王を討った例」として涿鹿の戦いや鳴条の戦いの話が作られたのだと思われます。
蚩尤が悪の権化とされたのと同じ理由で、黄帝の神聖化も行われます。
かつて黄帝という素晴らしい君主がいて、今の権力者はその黄帝と同じ行動を取っている。
だから今の権力者もまた天に選ばれた正しい存在なのだ、というのがその理屈となります。
黄帝はこの神聖化によって、中国人すべての祖先である、とみなされるようになりました。
しかしその事績はというとあまりはっきりとしたものは残っていません。
医療の神だともされていますが、これは神農の事績を乗っ取ったものでしょう。
黄帝の側には、「すべての植物を舐めて薬か毒か確かめた」などといった妙にリアルな説話はありません。
顓頊(せんぎょく)は、史記では黄帝の孫とされています。
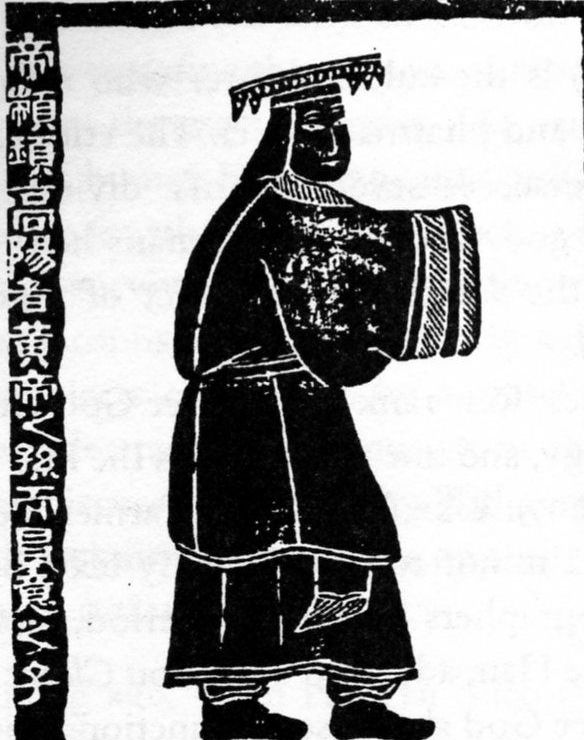
鬼神に仕えた、と書かれているので、どこかの部族のシャーマンキングが原型だったのかと思われます。
子に「四罪」の一人とされる鯀(こん)がいます。
鯀の子が夏王朝の創始者である禹王(うおう)です。

なお、鯀が四罪の一人とされたのは、治水に失敗してしまったためで、別に鯀が悪意を持って民を苦しめたとかそういうわけではありませんでした。
禹王は治水に成功したので夏王朝の創始者となり、後の世に聖王として称えられています。
嚳(こく)は顓頊とは別の系列の黄帝の子孫です。
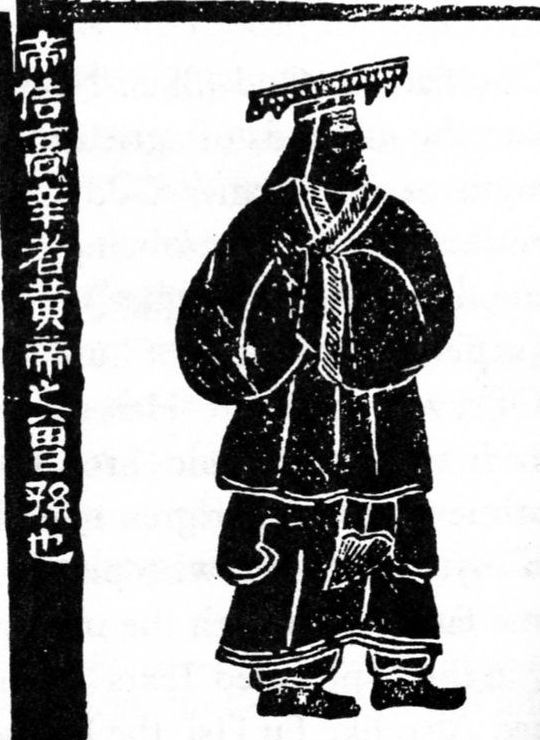
史記ではこれといった事績は伝えられていません。
どうやら史記では、五帝の時代を黄帝一族によって統治された時代、と位置づけたかったようです。
嚳(こく)の次の堯(ぎょう)は、嚳の子です。
五帝の最後のひとりである舜は、顓頊の七代の孫とされていて、やはり黄帝一族のひとりに数えられています。
堯(ぎょう)と舜(しゅん)
五帝のうち、堯とその次の舜は、儒家によって理想の君主とされました。
堯は暦の創始者とされます。
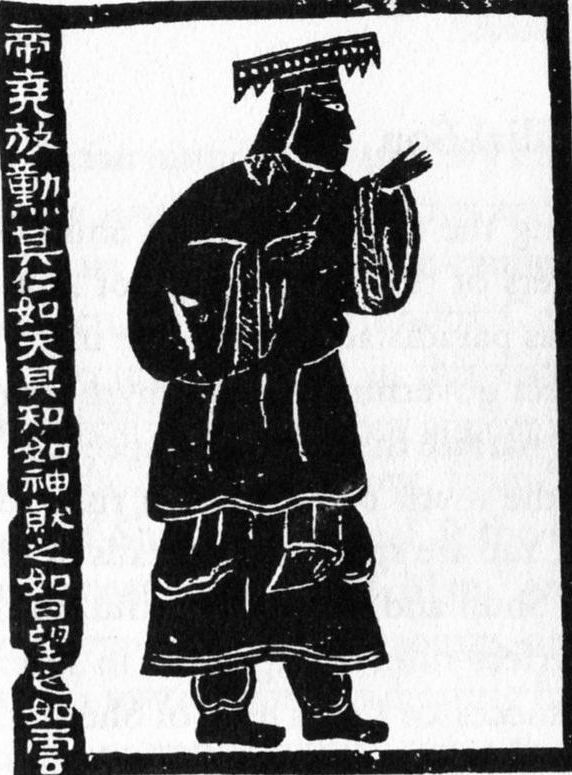
また、当時十個あって干ばつの原因となっていた太陽を、弓の名人羿(げい)に命じて九つまで射落とさせました。
また王者でありながら私生活は非常に質素であったといわれ、儒家によって聖王と持ち上げられるのも当然かと思われます。
ただ、堯には明らかにこれは失政ではないかと考えられるポイントもあります。
堯の治世、干ばつの方は太陽を射落としてなんとかできましたが、洪水への対策は不十分でした。
鯀に治水の実務を任せたのですが、鯀は九年経っても成果を出すことができなかったのです。
これは直接的には鯀の無能、あるいは運の無さのせいでしょうが、九年間放置した堯の責任も重大でしょう。
鯀は更迭され、代わって舜が登用されます。
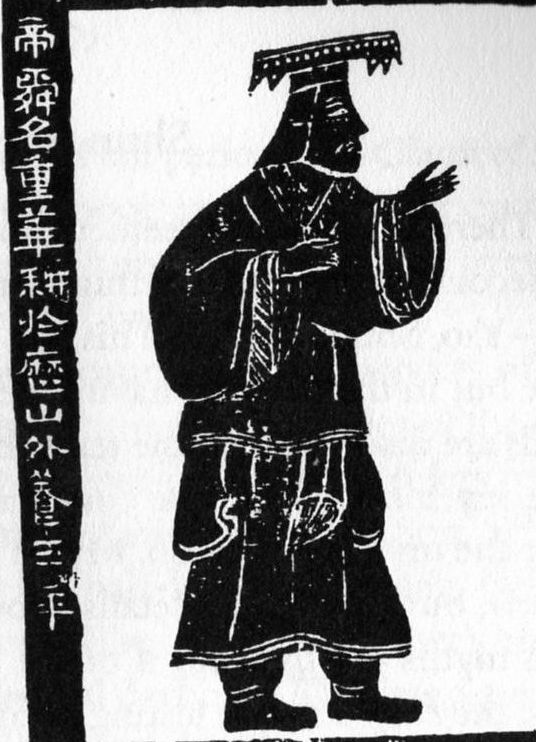
舜は早くに母を亡くしました。
舜の父は連れ子のある女性を後添えに娶ったのですが、この継母が舜に辛く当たったのです。
本来なら舜を守ってくれるはずの舜の父も継母に同調し、舜を殺して継母の連れ子に家を継がせようと策を巡らせるようになりました。
しかし、舜はこのような親に対しても孝養を尽くし、「あれは大したやつだ」という評判が近隣に広まります。
それを聞きつけた堯は、評判が事実かどうかを確かめるため、自分の娘二人を舜に妻として与えました。
するとみるみるうちに娘二人の性格がよくなって行ったので、堯は「これは本物だ」と思ったそうです。
みるみるうちに性格がよくなる余地があるほど、堯の娘は性格が悪かったのでしょうか。
舜の評判がさらに高まったので、舜の両親&弟は面白くありません。
彼らは舜に屋根の修繕を言いつけ、舜が作業をしている間に家に火をつけてしまいます。
舜は傘を両手に持って屋根から飛び、難を逃れます。
「傘がなければ焼死だった」と言ったかどうかはさだかではありません。
続いて舜の家族は、舜に井戸さらいを言いつけます。
舜が井戸に入ると上から土嚢などを落とし、圧殺しようとしたのですが、舜は横穴を掘って生き残ります。
そして殺されかけたことをなかったことにして、父と継母にさらなる孝養を尽くしたというのです。
「死ね」というのが親の意思であるなら、生き残ろうとあがくのは親不孝ではなかろうかと思えなくもないのですが、ここはツッコんではいけないところなのでしょう。
と思ったら、戦国時代の皮肉の天才・莊子にすでにツッコまれていました。
親の評価は得られませんでしたが、上司の評価はうなぎ登りです。
井戸事件の後、舜の姿勢に感動した堯は舜を大臣に抜擢します。
舜は期体に応えて善政を敷き、ついに堯は舜に帝王の位を譲ったのです。
完璧星人である舜と比べると、マイナスポイントが存在する堯ですが、王位を自分の子ではなく徳の高い赤の他人に譲った、ということで舜と並ぶ聖王としての評価をゲットしたのです。
さて舜ですが、王位についてから堯が失敗した治水事業をなんとかしようと、作業現場に視察に行きます。
そこで舜は、責任者である鯀が死んでいるのを見つけてしまうのです。
恐らく成果が出ないのを気にしつつも頑張り抜いた心労が加算された過労死だと思われるのですが、人々は「舜が殺したのでは?」と疑いの目を向けます。
困った舜は、鯀の子であった禹を後継の治水責任者に指名しました。
多分に自己保身目的だったように見えますが、この人事が大当たり。
禹は見事に治水事業を成し遂げました。
多分父であった鯀の方針を変えず、それを仕上げていったのでしょう。
さてこれまで「五帝」は世襲によらず、有徳の人物を見つけてその人物に王位を継がせる、という継承方法を取ってきました。
しかしよく見ると親子関係があったりして、とりあえず「非世襲」なのは堯から舜への継承だけであったような気がしないでもありません。
それはともかく、舜が王位を譲った禹は、その子が「たまたま有徳であった」という理由で王位を譲り、ここから最初の世襲王朝である夏が始まったとされます。
夏から後は、本格的な歴史時代と言われていますが、ことはそんなに単純ではありません。
中国の場合、「歴史時代」であっても後から神や仙人がぼこぼこ誕生してくるからです。
山海経(せんがいきょう)のモンスターたち
中国最初の正史が「史記」であることはよく知られています。
高校で世界史を学べば、一学期の中盤に教わることでしょう。
では、中国最初の地理書は何でしょう。
こう問われて即答できる人は、かなり中国史に通じた方です。
その「地理書」の名前は「山海経(せんがいきょう)」と言います。
戦国時代の頃から細々と編纂され、漢の時代になって完成した書物です。
建前上「普通の人が行くことのできない遠く離れた土地の動植物を紹介する」という趣旨で書かれた本なのですが、裏取りを全くせずに(多分取ろうと思っても不可能でしょう…)噂レベルで聞いたことを全部書き留めてしまったために、結果として「古代中国のポケモン事典」のようなものになってしまいました。
つまり、後の古生物学のセオリーからすればあり得ない架空の動物だらけとなったということです。
山海経に登場する妙な動物の大半は、キメラの手法を使って人為的に作られた架空の生物です。
キメラの手法というのは、既存の動物(人間を含みます)のパーツを寄せ集めて新生物を作ってしまうというやり方です。
蛇身人面の女媧も、キメラの手法で作られたモンスターだと言えます。
開明獣はそれらのモンスターの中の一種で、山海経の一篇で中国から見て西方にある文物をまとめた「海内西経」に登場します。

開明獣が住んでいるのは崑崙(こんろん)の丘だといいます。
崑崙は後にチベットの高山地方のこととされましたが、戦国時代から漢にかけては漠然と「西の果ての山地」を意味しているにすぎません。
この崑崙は天界の王者である天帝が、下界を治めるために設置した都だとされました。
崑崙は都城であるため門が九つ存在し、開明獣はこの門を守護する聖獣なのだといいます。
開明獣の身体は虎に似て、頭は九つあり人間の顔をしています。
典型的な、キメラの手法で作られた想像上の動物です。
山海経にはこうしたモンスターが満ち溢れているのですが、それだけではありません。
さらっと古代の神々の神話の断片が取り込まれているのです。
あまりにさり気なく挿入されているので、読者はそれが神話の断片だということにほとんど気が付きません。
山海経に隠された神話の謎を解明するのは専門の学者の仕事となりますので、われわれはその研究が一段落するまで待つことにしましょう。
「歴史」より後に発生する「神話」
これまで説明してきたことからうすうす気づいてきた方もおられると思いますが、実は中国においては、「歴史」の発生よりも「神話」の発生の方が後だったのです。
「仙人」という特殊な概念を間に挟むことにより、元は歴史上の人物だったものが、気づくと仙人や神に祭り上げられていた、というパターンが実に多いのです。
三国時代の武将・関羽などはその典型と言えるでしょう。
彼は疑いもなく歴史上の人物で、陳寿(ちんじゅ)がまとめた正式な歴史書である「三国志」に伝記が収められています。
しかし非業の死を遂げた人物であったため、死後庶民の間で人気が高まり、「関聖帝君」という神として祭られるようになったのです。
正史である「三国志」を元ネタにして作られた小説「三国志演義」においては、後に関羽が神として崇められる兆しが現れてきています。
正史の「三国志」では、関羽は諱である「羽」で呼ばれます。
しかし、「三国志演義」においては、字である「雲長」もしくは「関公」と呼ばれているのです。
すでに神として祭られている関羽に対して敬意を払ったものと解釈されています。
ちなみに、神としての関羽を祭る「関帝廟」は現代中国においては最も数が多い宗教施設だと言われています。

つまり関羽は、現代中国においてもっとも多くの信者を抱える神なのです。
なお、この世において関羽の上司であった劉備は、神としては祭られていません。
皇帝経験者は基本的に神にならないのです。
先に述べたように、中国では神は仙人よりも一格下の存在だと考えられています。
そして多くの皇帝が、不老長寿の仙薬を求め、仙人になろうとしました。
このため、「皇帝は神ではなく仙人になるもの」という常識のようなものが形作られていったのでしょう。
なお、唐の時代の後半は、皇帝たちが特に仙人になりたがった時代でした。
彼らは不老長寿を得るために効力があるらしい、と聞くと、どんな薬でも大金を払って手に入れたのです。
その中には毒物を主成分とするものがかなりあり、皇帝たちは仙人になるどころかばたばたと若死にしていきました。
ある意味、仙人願望が帝国を滅ぼしたとも言えるのです。
神話が記録された時代
中国の文字文化は原則的に儒家によって支配されています。
役人になるためには儒家関係の文書を山程丸暗記し、官吏(かんり)登用試験である「科挙」に合格しなければなりませんでした。
当然、公式文書は全部儒家思想に基づくものとなり、それ以外のことをテーマにした文章は、価値の低い駄文だとみなされたのです。
ところが、科挙を中心に据えた官僚制度は、一時的にモンゴル人によって破壊されます。
モンゴル人が打ち立てた元王朝では、科挙をパスした漢人官僚よりも、トルコ人やモンゴル人を上位に置きました。
この結果、失業する教養人が大量発生します。
彼らは、生活の資を求めて庶民が興味を持ちそうな文書を書くようになります。
この結果、「庶民が興味を持つ」道教の神々の話が書物としてまとめられるようになったのです。
モンゴルが北方の草原に引き上げた明代においてもこの流れは止まらず、現在も伝わる多くの小説が、この時代に集大成されました。
「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「封神演義」…これらすべては明代に完成した物語群です。
これらの中では一番「史実」寄りの「三国志演義」でさえ、神である関羽への忖度が満ち溢れています。
「水滸伝」に登場する好漢たちは、元を正せば百八柱の魔神だったとされています。
また、九天玄女(きゅうてんげんにょ)という女神が好漢たちを束ねる上で重要な役割を果たしていたり、好漢たちの中で反則級に強いのが、仙人の弟子である公孫勝(こうそんしょう)であったりという辺りが、神話的要素となります。
なぜ公孫勝が最強だと神話的なのか。
それは「水滸伝も現代ある多くのファンタジー同様、魔法が物理攻撃に優越する世界とされているからだ」と言えばわかりやすいかと思います。
ただ、最終的に明代に書物化された中国神話は、地域との関連性は極めて薄くなっている、という特徴も持っています。
世界の他の地域の神話の場合、地名の由来を語るものや、地域の独自の自然環境をベースにした神話というものが多く見られるのですが、この種の中国神話にはそれはないのです。
それは、神と名乗ってはいないけど事実上神々と変わらない能力を持ったキャラクターが活躍する小説の形態を取っています。
ですから、本当の神話ではなく「古代中国神話の二次創作」であるのかも知れません。
ただ、ギリシア神話にも似たような要素がある(遠く離れた地域からやってきたゼウスが地元の女神たちを妻にすることにより成立したため地域性が薄い)ので、あちらが「神話」であるならこちらも「神話」であると言うことも可能でしょう。
仏教の皮を被った道教神話「西遊記」
明の時代に完成した中国神話、あるいは神話的要素を豊富に持つ小説は、建前上なんらかの史実をベースにしています。
とはいえ「西遊記」の場合これを史実に基づいた話だと思う人は少ないでしょう。
何しろ「西遊記」の主要キャラクターの中で実在していたのは、天竺にお経を取りに行く三蔵法師(玄奘)、取経の旅を許可した唐の皇帝・太宗(李世民)、それにお釈迦様の三人しかいません。
お釈迦様は確かに歴史上実在した人物ではありますが、解脱して俗世を超越した存在となっていますから、神様の一種として扱われています。
太宗は三蔵法師の旅の最初と最後にちょっと出てくるだけなので、事実上実在の人物は三蔵法師ただ一人しかいないことになります。
「西遊記」は、三蔵法師の取経の旅という実際にあったことをベースにし、そこに中国の民間信仰を手当たり次第に放り込んだらこうなった、という作品です。
「手当たり次第に」だったため、放り込まれた要素相互に関連性はあまりありません。
たとえば主人公である孫悟空ですが、これは人類ではなくサルなので史実性うんぬんどころの話ではありません。
ちなみに、中国では類人猿は猴、それ以外は猿と文字を使い分けています。
孫悟空は取経の旅に出る前「美猴王(びこうおう)」と名乗っていた時期がありますから、類人猿だったということになります。
この孫悟空のモデルは何か、ということは、「西遊記」が成立してから多くの人によって議論されてきました。
どうやら「悟空」という法名を持った坊さんは実在していたようですが、この人が棒を持ち雲に乗って大暴れしたという話は伝えられていません。
関連があったとしても、名前を拝借した以上のものではなかったでしょう。
「西遊記」における孫悟空の本質である「スーパーパワーを持ったお猿さん」と共通の要素を持つキャラクターは、インドにいました。
「ラーマーヤナ」などに登場するハヌマーンがそれです。

ハヌマーンは見た目は猿ですが中身は神です。
父は風の神ヴァーユで、母は一説によれば水の精アプサラスであったと言います。
猿の子として生まれたわけではなかったわけです。
猿の格好をしているのは単なる本人の趣味でしょう。
同じように、シヴァ神とパールヴァティーという人間型の夫妻の子でありながら、象の頭を持つガネーシャなどという神も、インド神話にはいますから。
「ラーマーヤナ」においてハヌマーンは、主人公であるラーマ王子に助けられたり、その恩返しをしたりしながら活躍します。
その活躍において「外見が猿である」ということはほとんど意味を持っていません。
これも孫悟空と共通しています。
孫悟空は三蔵法師に弟子入りし、政府の許可を得ていない僧侶である「行者」になり、最後にはお釈迦様によって仏の位に引き上げられます。
その本質は完全に猿ではなく、「猿の外見を持った人以上のなにか」です。
このため、「西遊記」の成立期から孫悟空は道教で神「斉天大聖(せいてんたいせい)」として扱われ、中国各地にお堂が作られるようになりました。
もとは女の子だった?「猪八戒」
孫悟空は天界への反逆者で、天界のモラルから照らしてありとあらゆる「悪事」を働いたのですが、ただひとつだけ「好色の罪」だけは犯していませんでした。
実は「西遊記」の元となった各種の文献の中には、孫悟空の原型キャラに、好色の要素を追加したものもあったのです。
「西遊記」の元となったのは小説だけではなく、元の時代から盛んに演じられるようになった演劇も重要な要素となっていました。
演劇は小説よりもずっと観衆の反応がよくわかりますから、それに対応する形でキャラクター設定が変化します。
つまり原西遊記の場合、「強くて自由な猿」である孫悟空のキャラクターが受けたので、さらに観客を喜ばせるために「強さ」と「自由さ」が強調されるようになったのです。
その結果「好色」の要素は孫悟空のキャラクターからは跳ね飛ばされ、独立したキャラクターとして再構成されます。
それが「猪八戒」であったというのです。
猪八戒が豚の姿をしているのは、物語の中では天界で事件を引き起こし、天界を追放され、下界で受肉する際に間違えて豚の子宮に入ってしまったから、とされます。
豚は旺盛な食欲を持っていますから、欲望の化身である猪八戒のキャラクターと結びつけやすかったのだろうと思います。
猪八戒が三蔵法師に弟子入りし、取経の旅に加わったのは現在のチベットにおいてだったそうです。
チベットという具体的な地名が出てきたため、猪八戒とチベットとは何らかの関係があるのではないか、という説があります。
有力なのは、チベット仏教において「歓喜仏」として敬われている荼枳尼天(だきにてん)、すなわちインド神話のダーキニーが起源ではないか、という説です。
チベット仏教においては、ダーキニーは「金剛猪妃」と呼ばれていました。
歓喜仏というのは、性行為をしている男女の姿をかたどった仏像です。
日本ではガネーシャに起源を持つ、象頭の男神と、女神の抱擁で表現されます。

チベット仏教においては、男性的原理と女性的原理の結合により万物が生み出されると考えられており、歓喜仏信仰がその中核部分を占めていると言っても過言ではないのです。
猪八戒の原像は、こうしたチベットの信仰が雲南経由で中国に流れ込む形で作られたのではないか、といわれています。
その通りであるなら、猪八戒は元々は女性だったということになります。
河童ではなかった沙悟浄
三蔵のお供三人組のうち、最後に一行に加わったのが「沙悟浄」です。
流沙河という川に住み着いていたため、日本では水妖である河童の仲間だと思われていますが、そもそも中国には河童やそれに類する妖怪は存在しません。
お供三人のうち一番影が薄い沙悟浄ですが、実はキャラクターの造形が始まったのは三人のうち最も早かったと言われます。
沙悟浄はその首に九つの髑髏をぶら下げていますが、これはすべて三蔵法師の前世であったとされます。
つまり三蔵法師との縁は他の二人よりも深いのです。
起源が古い分だけ、沙悟浄はヒンドゥーなどの他のインドの信仰の影響が薄い、仏教的要素が濃厚なキャラクターだと言えます。
何度も取経の邪魔をし続けた妖怪が、悔い改めて高僧の守護者となり、それまで積み重ねてきた業を消し去る、というのはいかにも仏教的です。
「西遊記」に乱入する道教の神々たち
「西遊記」はその骨子にあるのは三蔵がインドにお経を取りに行く、という仏教的なストーリーですが、全体的には道教の信仰に基づく説話を集めたものとなっています。
特に、三蔵法師が登場しない前半部においては、仏教の「ぶ」の字も出てこないと言っても過言ではありません。
代わって活躍しているのが道教の神々です。
「西遊記」の世界観では、中国文化圏は「天界」の下部に位置しています。
「天界」を主催しているのは「天帝」で、政治権力を持たないけれど高い権威を持っている存在として、太上老君をはじめとする道教の神たちが配置されています。
太上老君は先にも述べたように、歴史的人物としての老子が神格化されたものです。
太上老君のようなおなじみキャラ以外で注目すべき「神」をあげてみましょう。
天界で暴れた斉天大聖・孫悟空を捕縛に行った神に、「顕聖二郎真君(けんせいじろうしんくん)」がいます。

彼は秦の時代の蜀郡(現在の四川省)の太守だった李冰(りひょう)という人物の息子です。
実在したかどうかは微妙ですが、少なくとも父は史書に記録のある実在人物でした。
史実の李冰は治水に努力した人物で、その息子とされる二郎真君も大元は四川地方のローカルな治水の神だったと思われます。
その信仰が中国全土に広まり、ただの人間から「天帝の甥」という地位に引き上げられたのです。
ちなみに神となった二郎真君は、天帝の妹と楊という人間の男との間の子とされています。
つまり姓は楊(よう)です。そして名前は恐らく戩(せん)でした。
「楊戩(ようせん)」の名を持つキャラクターは、「封神演義」でも活躍します。
「西遊記」の二郎真君は、多数の眷属を従えた武将神ですが、「封神演義」の楊戩はスーパーパワーをふるう仙人です。
つまり同じキャラクターなのですが、片方では物理攻撃中心、他方では魔法中心となっているのです。
先に二郎真君は、李冰の次男が元だと書きましたが、中国の他の神同様、その後にさまざまな人や神のイメージが追加されています。
その追加要素の一人に、隋の時代の趙昱(ちょういく)という人物がいます。
彼は道士で、仙術を駆使して竜を退治した、との伝説を持っています。
世界中多くの地で、竜は水を象徴するモンスターとして扱われていますから、「竜を倒す」ということは「治水を完成する」のと同じ意味として取られます。
こういう理由で、趙昱の逸話が李冰の次男の伝説と一体化し、「顕聖二郎真君」が誕生したのでしょう。
「西遊記」で、二郎真君とともに孫悟空の捕縛作戦に参加するのが哪吒三太子(なたさんたいし)です。
哪吒は托塔天王(たくとうてんのう)の三男であるとされます。
「三太子」という尊称がつくのは三男だからだ、と説明されます。
托塔天王とは、仏教から取り込まれた毘沙門天の道教風の呼び名です。
ただし毘沙門天の素直な輸入ではなく、唐初の名将・李靖(りせい)のイメージが混入しています。
このため托塔天王はよく「托塔李天王(たくとうりてんのう)」とも呼ばれます。
哪吒の原型は、父が毘沙門天、インド名クベーラであることから、クベーラの息子のナラクーバラである、とされています。
「西遊記」における哪吒は、斉天大聖孫悟空と戦って敗退してしまうのですが、個人の能力は非常に高いものを持っています。
何しろ、生まれて三日目に海中に飛び込み、蛟龍の背中の筋を引き抜いてそれを腰紐にしようとしたというのですから、恐るべき力を持っていたと言わざるを得ません。
父托塔天王はそんな哪吒の並外れた力を恐れ、幼児のうちに殺してしまおうとします。
哪吒はそれに反発し、父母から貰った肉体はいらないと自殺してしまいました。
哪吒の最初の肉体は滅びましたが、魂魄は西方の釈迦如来の元に行きます。
釈迦如来は哪吒を憐れんで蓮の葉や根(つまりレンコン)を使って身体を作り、哪吒に与えたといいます。
なんとなく実父に疎まれてよその優しいおじさんに拾われたアトムや百鬼丸を連想させる話です。
托塔李天王が天馬博士でお釈迦様がお茶の水博士といったところでしょうか。
「西遊記」に登場する哪吒三太子は、お釈迦様に新しい肉体をもらった姿となっています。
一応、お釈迦様が口をきいてくれて実父の元に戻ったようですが、それでも托塔李天王は哪吒三太子を恐れており、暴走したら自分の手で始末をつけてやろう、といつも考えているという裏設定があります。
このように、「西遊記」、その特に前半においては、さまざまな道教の神々が登場し活躍します。
全体的には取経の旅という仏教的なイメージの強い「西遊記」ですが、その実態はむしろ道教神話と言ってもいいものなのです。
神話的要素のごった煮「封神演義」
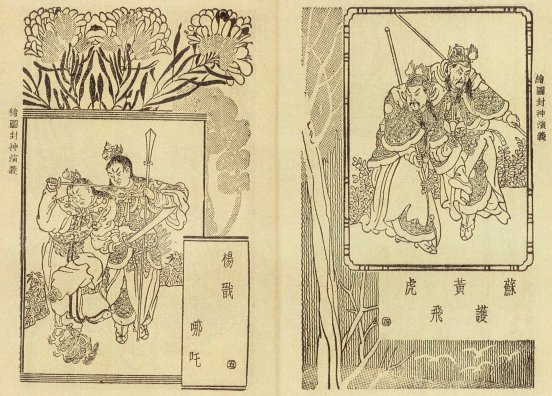
「封神演義」は長い間日本においては無名でした。
それだけでなく、中国においても文芸作品としては二流であった、と評価されていたのです。
その理由のひとつは、「荒唐無稽にすぎる」ということでした。
中国では文字で記録されるものは事実である、というのが基本でした。
小説であっても、「三国志演義」や「水滸伝」のように、ある程度史実を下敷きにしているものが中心だったのです。
「三国志演義」では、史書である「三国志」に登場する人物はある程度網羅されていますし、「水滸伝」でも徽宗(きそう)や高俅(こうきゅう)や童貫(どうかん)などの人物は実在しており、禁軍などの組織もその当時のものをかなり忠実に描写しています。
フィクションの産物だと思われがちな梁山泊(りょうざんぱく)の好漢も、宋江や史進についてはモデルになる人物が実在した、といわれています。
ところが「封神演義」の場合、史実的存在は文王・武王・周公・太公望・紂王(ちゅうおう)・妲妃(だっき)をはじめある程度いるのですが、これらのキャラクターを支える時代考証がめちゃくちゃなのです。
史実の太公望は文王・武王の軍師にして、周軍を指揮した戦略家だったのですが、「封神演義」の太公望は魔法(仙術)の力を駆使するこの世のものとは思えないキャラクターに変更されてしまっています。
さらには殷の配下にあった各国の君主も、教養人からすれば「誰だお前?」と言いたくなるような架空の人物に変更されていたのです。
教養第一主義の上流階層から見れば、それだけで「ただのホラ話だ」と評価されてしまうのも仕方がないでしょう。
ただ、庶民の側から見れば、自分たちの信じていた神や仙人の関係を説明してくれるありがたい書物だ、ということになったでしょう。
これらの「関係」は作者がそれぞれの神や仙人の信仰を実地調査して明らかにしていったものではなく、殷から周への革命の時期のおおざっぱな史実を骨組みとして要素を放り込んでいき、ごった煮にして作り上げたものに過ぎません。
しかし、書物にしたということで、それを新しい事実として受け入れた人々がおり、「封神演義」に書かれた内容を基礎にして新しい信仰が発生したというのもまた事実なのです。
「封神演義」には「西遊記」のくだりで紹介した哪吒も登場します。
一度死んで父母からもらった肉体を捨て、不死身の体に生まれ変わった(キャシャーン?)という設定は「西遊記」と同じですが、お茶の水博士役がお釈迦様から太乙真人(たいいつしんじん)という仙人に変更されています。
太乙は太一とも書き、北極星などの星を意味するといいます。
つまり北極星に関連のある天文現象の擬人化なのでしょう。
哪吒に最初の生身の身体を与えた父親も、「西遊記」で言うところの「托塔李天王(たくとうりてんのう)」で変わっていません。
ただし、こちらでは「托塔李天王」とは呼ばれず、ずばり「李靖(りせい)」と名乗っています。
李靖は先に述べたように、唐建国の功臣ですから、その名前で殷周革命の時期に登場することはあり得ません。
これが太公望や、秦の時代の実在の地方官の息子であった二郎真君(楊戩)と肩を並べて戦うのですから、教養人からすれば「でまかせを言うにも程がある」ということになってしまうでしょう。
あ、そう言えば仙人たちのナンバー2に位置するとされる「老子」も、殷周の時代よりも遥かに後(一応周王朝は存続していましたが)の実在人物でしたね。
ちなみにトップは鴻鈞道人こと「渾沌」です。
「道教の優位性」をうたうストーリー
「封神演義」のストーリーは、先に述べたように「殷周革命」です。
これは、中国二番目の統一王朝であった殷の王・紂(ちゅう)が暴政を行い、西方の信仰国家である周の文王・武王の親子に滅ぼされる、というものです。
ただし、単純に王朝交替を描いたお話ではなく、仙人たちの勢力争い等を絡めて複雑な展開を見せるようになっています。
「封神演義」の仙人たちは、元人間出身者中心の「闡教(せんきょう)」と、獣や自然物出身者中心の「截教(せっきょう)」、さらに西方の仏教世界に分かれていました。
「封神演義」では、仏教の仏たちも、中国のそれとは系列の違う仙人たちだ、という設定になっているのです。
実は仏教の開祖であるお釈迦様ことゴータマ・シッダールタは中国で言うと戦国時代の人物なので、殷・周戦争の時期に仏教はまるごと存在していないのですが、そんなことを気にしていては「封神演義」は読めません。
闡教の仙人と截教の仙人との間には争いが絶えませんでした。
また、闡教の仙人たちは千五百年に一回人を殺さなければ仙人としての力を保てないという劫(殺戒)が存在していたのです。
そこで闡教のリーダーである元始天尊(げんしてんそん)は、来るべき殷と周の戦争に便乗し、仙人たちの殺戒を晴らさせるとともに、邪魔な截教の仙人たちを殺し、仙人よりも一格低い「神」として封じてしまおうという陰謀を企てました。

この陰謀の実行者として、元始天尊は自分の弟子である姜子牙(きょうしが:太公望)を、人間界に遣わしたのです。
以後は、殷と周の戦争を舞台にした仙人たちのスーパーバトルが繰り返される展開となります。
闡教の仙人は主に周の側につき、截教の仙人は殷の側につきました。
戦闘そのものは、「宝貝(パオペエ)」と呼ばれるスーパーウェポンのぶつけ合いで、ともすれば単調な描写の繰り返しとなっています。
実はこの点も、教養人からの評価が低かった原因のひとつとなっています。
大戦争の結果、周が勝利して敵味方の仙人・人間の戦死者が神となって「封神榜(ほうしんぼう)」という碑にその名前を刻まれます。
結局のところ、本書の著者がやりたかったのは仙界・神界のランク付けであったようです。
本書によれば、それまで各地の民衆に個別に信仰されていた神々は、仙人よりも下位の存在で、その仙人・神それぞれも、またランク付けされることになりました。
神々のランク付けは、ある意味では神話の死を意味するものですが、すでに述べたように、「封神演義」は、実際に信仰が存在せずこの本の作者が勝手に考えたキャラクターも含めて、新たな道教信仰を生み出したという事実もあります。
なお、日本における「封神演義」は、小説家・安能務(あのう つとむ)によってまとめられたバージョンと、さらにそれを原作として作られた漫画・アニメが有名です。
しかし、安能版は中国に存在した「封神演義」を忠実に翻訳したものではなく、作家の独自解釈や独自展開が随所に盛り込まれており、「封神演義をベースにした同名の小説」と呼んだ方がふさわしいものとなっています。
漫画・アニメ版は小説版をさらに拡張解釈し、SF的要素も追加しているので、オリジナルとは相当に違っている作品です。
まとめ
このように、中国の神話は、他国の神話とは非常に変わった形で発展し、記録されてきました。
何より重要なのは、政権の手によるオフィシャルな歴史書が登場した後に、神話が書き留められていった、ということでしょう。
そのせいか、中国は現代においても「新しい信仰」が発生しやすい状態になっていると考えられます。
太平天国(たいへいてんごく)や義和団、さらには21世紀になっても法輪功(ほうりんこう)が活動を続けるなど、その勢いは収まっていません。
この意味では、中国はまだ「神話がその本質的な生命を失っていない土地」であると言えるかもしれません。







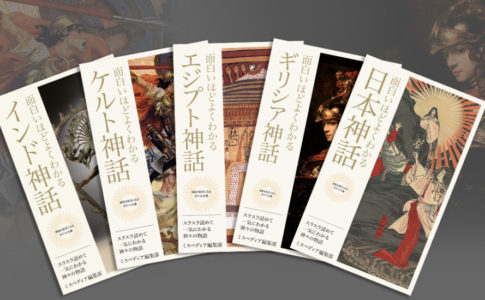

































コメントを残す