原点たる『Fate/Stay Night』に始まり、今ではスマートフォンアプリ『Fate/Grand Order』も好評配信中のFateシリーズ。
人類史に名高い英雄を英霊(サーヴァント)として召喚し、マスターである魔術師と共に最後の一人になるまで争う「聖杯戦争」を主軸としており、魅力的なキャラクターが多数登場する事から人気を博しています。
ゲームだけでなく書籍作品も多く展開しており、コミカライズや小説なども出版されています。
神話や歴史を題材にしている事で有名ですが、その中でも今回紹介させて頂くのが三田誠先生による魔術ミステリー作品『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』です。
2019年には原作4~5巻に相当する『魔眼蒐集列車』がアニメ化され、2020年12月25日には続編である『ロード・エルメロイⅡ世の冒険』が刊行され、現在3巻まで発売されています。
本稿の筆者である私はFate、ひいては昨年発売した『月姫』などを含めたTYP-MOON作品のファンなのですが、特にこの作品がずば抜けて好きでして。
というのも、この作品はキャラクターが皆魅力的な事に加え、現実に存在する神話、宗教・魔術的信仰をかなり深いレベルで取り扱っているんです。
ギリシア神話、北欧神話、インド神話、日本神話、ケルト神話、聖書、アーサー王伝説などの有名な神話・伝承は勿論、かの「セフィロトの樹」で知られるカバラ(ユダヤ教の神秘主義)を筆頭に、実在した魔術や宗教・神話学に纏わる要素がこれでもかと盛り込まれており、神話マニアにはたまらないシリーズです。
という事で、今回は『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』についてご紹介します。
Contents
簡単なあらすじと登場人物
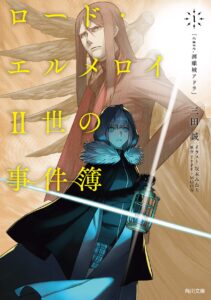
この『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』は『Fate/Zero』の第四次聖杯戦争から10年後を舞台としており、その時のマスターの一人、ウェイバー・ベルベットが主人公です。
ウェイバーはロンドンの「時計塔」という魔術を教える大学のような場所で講師として勤めており、時計塔を統べる12人の「君主(ロード)」の一人として日々を過ごしています。
彼が「Ⅱ世」と呼ばれているのは彼の師である「先代のロード・エルメロイ」が聖杯戦争で戦死してしまった事に由来し、先代の姪にして次期当主であるライネスに頼まれ、エルメロイ家の当主の座を預かる事になります。
そんな彼の下に、義理の妹となったライネスが数々の魔術事件を持ち込みます。聖杯戦争を経て成長したウェイバーはロード・エルメロイⅡ世として、弟子の少女グレイや他の教室の生徒たちと共に事件解決に赴く。そんな物語です。
徹底された神話・魔術考証
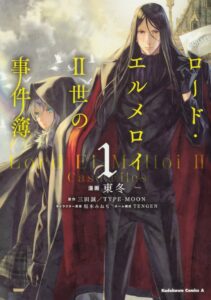
私がこの作品が好きな理由の一つはやはり徹底された神話・魔術考証です。
『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』に限らず、Fate作品は考証家である三輪清宗さんという方の考証が入っており、現実の神話・宗教・魔術に関する用語が頻出します。
その例を幾つか紹介、解説していきましょう。
天使のイメージ
『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』の第1巻「剥離城アドラ」はユダヤ・キリスト教世界における「天使」を題材にした巻です。
天使というと、ミカエルやガブリエル、ルシファーなどを想像すると思いますが、そういった「有翼の天使」はいつ頃根付いたものなのでしょうか。その点についても触れているのがこの巻です。
序盤で、Ⅱ世は弟子のグレイに対し「天使の図像」について説く場面があります。そこでⅡ世は
「人間の姿で翼が生えてってイメージが絵画として定着したのは、四世紀頃、ギリシャ神話における勝利の女神ニケから大きく影響を受けたものだがね。天使には別の系統もある。この場合、後から天使として解釈されたものというべきか」
(三田誠著『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿⑴剥離城アドラ』角川文庫、2017年、30p)
と説いています。
ギリシア神話における勝利の女神ニケはローマ神話ではウィクトーリアと呼ばれ、有名なスポーツメーカーNIKEの由来にもなっていますね。
実際、私達が普段目にしているような有翼の天使は、古代ギリシア・ローマ神話に登場する有翼神の影響を受けています。今挙げたようなニケ―以外にも、虹の女神イリス、死の神タナトスなどは有翼の姿で描かれ、伝令神ヘルメスは翼のついた帽子とサンダルを所持しています。
また現代社会において、天使とキューピッドは何かと混同される事がありますが、実はこの二つは本来全くの別物なんです。
キューピッドとはギリシア・ローマ神話における愛の女神アフロディーテ(ヴィーナス)の子であるエロース、ローマ神話におけるクピド、或いはアモルを指します。
エロース=クピドは元々は抽象的な神でしたが、時代と共にアフロディーテの子とする伝承が生まれ、愛の矢と翼を持った子供の姿で描かれるようになりました。
このエロースのイメージはルネサンス期になるとキリスト教の天使像と習合していき、それ以降、無垢な童子の姿で表現されるようになったとされます。
加えて、Ⅱ世はその後、聖書における異形の天使についても解説します。その部分がこちら
「もとは神話上の生き物だったものが天使として再解釈されたパターン。はたまた主の権能だったものが天使として独立したパターン。いくつも仮説はあるが、君が見ている座天使(スローン)は前者に近いかな。主の道からをその身に受けて運ぶという天使だ」
「運ぶから、車輪なんですか?」
「というより、車輪だったから主の力を運ぶと解釈されたんだ。聖書を読んでみるといい。エゼキエルという預言者の幻視では『緑柱石のように輝いていて車輪の一面に目がつけられている』って記述でね。変わったところでは、実は未確認飛行物体だったんではないか、なんて説もあるぞ」
(三田誠著『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿1「case.剥離城アドラ」』角川文庫、2017年、30p)
ここでⅡ世が解説しているのは、「座天使(スローン)」という種類の天使について。
キリスト教神学における天使の階級では第1位の熾天使(セラフィム)、第2位の智天使(ケルビム)に次ぐ第3位で、燃え盛る車輪の姿をしています。
聖書において座天使に関する記述があるのは旧約聖書『エゼキエル書』第1章16節などで、その部分を抜き出すと以下のようになります。
「それらの車輪の有様と構造は、緑柱石のように輝いていて、四つとも同じような姿をしていた。その有様と構造は車輪の中にもう一つの車輪があるかのようであった。
それらが移動するとき、四つの方向のどちらにも進むことができ、移動するとき向きを変えることはなかった。車輪の外枠は高く、恐ろしかった。車輪の外枠には、四つとも周囲一面に目がつけられていた」(エゼキエル書1:16-18)(日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年、(旧)1296p)
Ⅱ世の解説が、原典である旧約聖書の一節としっかり合致している事が分かります。
天使の図像に関する歴史に加え、原典との考証がしっかり為されていますね。
キリスト教神学における天使の9階級の第1位。単数形でセラフ。
神に最も近い位置におり、神への愛で身体が燃えているとされる。旧約聖書内では「燃える蛇」の名で呼称される事もあり、6枚の翼で顔や足を覆い、絶えず神を賛美していると記述される。
キリスト教神学における天使の9階級の第2位。単数形でケルブ。
神を取り囲んでその威厳や栄光を示す存在であるとされ、語源的にアッシリア語やアッカド語における「祝福された・崇拝された」「偉大な」を意味する。
獣、あるいは怪物のように描かれる事が多く、『エゼキエル書』においては「四つの顔と四つの翼があり、翼の下には人間の手の形をしたものがあった(10:21)」との記述が見える。図像的には古代メソポタミア世界における「ラマッス」という人面獣身の守護神に源流を持つとも伝承される。
神話における「金星」

剥離城アドラの次、原作2~3巻に相当する「双眸塔イゼルマ」では「美の概念」というものを主なテーマとしています。
物語の中盤、Ⅱ世が魔術師による殺人事件解決の為の推理をする中でこんな事を述べます。
「ええ。魔術においては、しばしばほかの惑星が太陽に見立てられます。とりわけ金星は太陽によく見立てられる。全天で最も明るい惑星であるためでしょう。この理由から、極東では金神と言われて恐れられ、聖書では天より堕ちたルシファーだとも言われた。曙の明星。宵の明星。さらに金星はヴィーナスの星でもあり、ルーツをたどればメソポタミアのイシュタルにも関連する。今回のように美の精髄たる魔術に応用するなら、最良の見立てだったとも言えるでしょう。」
(三田誠著『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿3「case.双眸塔イゼルマ(下)」』角川文庫、2017年、162p)
金星という惑星は最も明るい事から、世界各地で神格化、神聖視された天体でした。
最古の文明にして高度な天文学・占星術の体系を作り上げたメソポタミア文明では、金星の女神としてイナンナ、或いはイシュタルが篤く信仰され、西洋のアフロディーテやヴィーナス、シリアのアスタルテといった金星の女神達の源流にもなっています。
キリスト教における堕天使ルシファーは「明けの明星」、即ち金星を意味するルキフェルというラテン語を語源に持ち、旧約聖書『イザヤ書』における
「ああ、お前は天から落ちた明けの明星、曙の子よ。お前は地に投げ落とされたもろもろの国を倒した者よ」(イザヤ書14:12)
(日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年、(旧)1082p)
という一節から、金星と結び付けられています。
古代の中南米、とりわけマヤ人やアステカ人にとっても金星は重要な惑星であり、暦の作成の際に用いられたとされました。また、西で死に、東で復活するという金星の動きから「死と再生」という観念とも結びつき、ケツァルコアトルという重要な神格になっていきます。
またⅡ世が言及した「金神」というのは日本の陰陽道における神の事で、殺伐を好む恐ろしい神とされています。
太陽神や月神などは日本のアマテラスやツクヨミなどのように普遍的な存在ですが、金星神が有力な地域もあれば、比較的マイナーな地域もあり、国によって立ち位置が違っているというのも興味深いですね。
アステカ神話における主要神。その名は「翼のある蛇」を意味する。
マヤ神話におけるククルカンと同一視され、農耕神の他、人類に文化を齎した神であると伝承される。
「眼」に対する信仰

お次に紹介するのは、アニメ化された原作4-5巻『魔眼蒐集列車』のワンシーン。この巻では「魔眼」と呼ばれるものを主な題材に据えています。
そこでⅡ世が古来よりの「眼」に対する信仰について解説するシーンがあり、自然界の現象が瞳として解釈される事があると説きます。
「たとえば、太陽と月だ」
「いずれも天の瞳として言い伝えられる事が多い。エジプトにおけるホルスの目は極めて有名なシンボルだが、その右目は太陽、左目は月に譬えられた。人々はこれらの天の瞳によって常に見張られており、罪を犯せば罰せられると信じていたんだ。太陽神が司法の性質を持つことが多いのはこのためだ。実際、太陽は大いなる恵みをもたらすのと同時に、旱などの災いをもたらしてきたわけだからな」
(三田誠著『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿4「case.魔眼蒐集列車(上)」』角川文庫、2017年、40p)
Ⅱ世の解説の通り、エジプト神話における天空神ホルスは両眼に太陽と月を持ち、ホルスの最古の形であるハロエリス神の頃からその性質は備わっていました。また太陽は天空神の顕現、或いは息子として描かれる事もあります。
ロシアのサモエド人という種族は太陽と月の中にヌム(空)の両眼を見出し、彼らの信仰によると、太陽は良い眼、月は悪い眼であるとされていました。
太陽神が司法神の性質を持つというのは、太陽という天体の動きに由来するところが大きいです。
常に運行する太陽の性質から、太陽神は戦車を駆る、また舟に乗って天を駆けると考えられており、その過程で地上世界を見張るとされました。故に、太陽神は司法や契約、正義などを司ります。
例えば、メソポタミア神話の太陽神シャマシュ。シュメールではウトゥと呼ばれる太陽神に関して、ハンムラビ法典の跋文(ばつぶん)の中で「天地の偉大な裁判官シャマシュ」と記されています。
他にも、インド神話における太陽神ミトラ、ゾロアスター教におけるミスラは友情と契約を司るとされました。
また、ギリシア神話では叙事詩『イーリアス』において、英雄パリスとメネラオスが誓約を交わす際に太陽神ヘーリオスに対して供儀が捧げられており、契約神としての性質を持っている事が伺えます。
更に身近な例で言えば、「お天道様が見ている」という言い回しが挙げられます。これはお天道様、つまり太陽神が地上を常に見ており、邪悪を許さずに正義を守ってくれるので人間は正しく生きるべきである、という素朴な正義感、道徳観に基いています。
太陽はかなり身近な天体ですが、Ⅱ世はそれを「眼」とする解釈から太陽神の持つ象徴性などを非常に簡潔に纏めています。
純粋に神話を題材とするよりも、そこから派生した宗教学的な知識を物語の中に落とし込んでいる、という感覚ですね。
「神」の名を問う続編、『ロード・エルメロイⅡ世の冒険』

これまでは『事件簿』の作中で言及される神話的な用語、理論などについて紹介してきましたが、続編の『ロード・エルメロイⅡ世の冒険』からも紹介していきましょう。
1巻「神を喰らった男」のあらすじはこちら。
「これより、私は、神を問う」
時計塔支部での講義のため、夏のシンガポールを訪れたエルメロイII世とグレイ。
様々な文化が混淆するこの国で、ふたりはエルゴという名の若者と出逢うことになる。
謎多き若者を追って現れる、アトラスの六源。
かのアトラス院と彷徨海バルトアンデルス、そしてもうひとりの魔術師が行ったという太古の実験とは?
そして、II世が問うことになる神の名とは?魔術と伝説、幻想と神話が交錯する『ロード・エルメロイII世の冒険』、いざ開幕。
『冒険』は『事件簿』の数年後を描いており、ロンドンを中心としたイギリスだけではなく、シンガポールや日本など、異国の地を舞台として物語が展開していくのが特徴です。
また、続編からは「Fate/stay night」のメインヒロインでお馴染みの遠坂凛、そして、3柱の神を喰らった青年エルゴが新キャラクターとして加わり、一行は彼が内包する神を明らかにする為、そしてグレイの抱える問題を解決する為に世界を渡る事になります。
個人的な印象ですが、『冒険』は『事件簿』よりも各世界の神話やその伝播、神々の習合などに関する用語がかなり多く登場しているように思います。
神話好きとしてはかなりテンションが上がりますね!
日本における蛇神たち
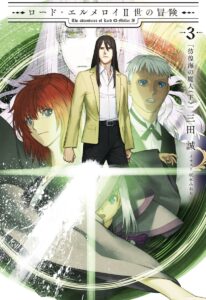
ここで紹介するのは『冒険』の第3巻「彷徨海の魔人(下)」の一節。
エルゴとグレイの問題を解決する為の手がかりを求めて日本に来日した一向は、とある事が原因で夜劫という魔術組織と対立する事になり、グレイと凛の二人で本拠地に乗り込む事になります。
その際、凛は有名な「因幡の白兎」の説話に加え、日本における蛇神について言及します。
「もちろん、そうなるわね。最初にくちなわの話をしたでしょう? 日本の蛇信仰は古くて幅広いんだけど、ここまではっきり地を這う蛇のイメージだと急に限定されちゃう。メジャーどころは四つぐらいね。人頭蛇身と伝えられる宇賀神、中部地方に信仰の広がっているミシャグジ、このミシャグジと縁深い武神タケミナカタ」
「オオナムチ」
「別名を大国主、大黒主、八千矛神、幽世大神、毛色の違うところでは大物主ってやっぱり蛇の神様と同一視されたりするわ。さっきの因幡の白兎では、ダイコクさんと言われる場合が多いかしらね。天津神への国譲りを為して、常世──常夜の主となった神」
(三田誠著『ロード・エルメロイⅡ世の冒険3「彷徨海の魔人(下)」』角川文庫、2022年、226、227p)
身近な生き物である蛇は脱皮するという生態から、往々にして「不老不死」や「死と再生」「循環」などを象徴し、信仰の対象となっている事が多いです。
一番分かり易い例では、WHO(世界保健機関)のマークです。あのマークには蛇が巻き付いた杖が用いられていますが、あれはギリシア神話における医療神アスクレピオスの杖に由来しており、蛇信仰との結びつきが見えます。
インドではコブラが神格化されたナーガという蛇神が信仰されていましたが、蛇を神聖な生き物と見做すのは日本も同様で、蛇は朽ちた縄に似ている事からクチナワと呼称され、また互いに巻き付く形で交尾を行う事から注連縄のイメージとも結びついたとされます。

宝厳寺蔵(1565年浅井久政奉納。頭部に小さく宇賀神が乗り、鳥居を構える。)
宇賀神というのは日本古来の神ではなく、中世において弁財天(インド神話のサラスヴァティ―)と関連付けられて祀られた神です。
図像的には凛の言う通り人頭蛇身で、弁財天の頭に乗せられている姿や、蛇の身体に老人や美しい女性の顔を持ち、蜷局を捲いた姿で表現される事があります。
また、この神は福神としても信仰される事があり、名前の音の類似から日本神話における穀物神のウカノミタマ(稲荷神社の主祭神)と結び付けられる事もあります。
ミシャグジは長野県の諏訪を始め中部地方で信仰されている土着神で、石と樹の精霊であるとも伝承される事のある神格です。この神と蛇の結びつきはその名にあり、ミシャグジは漢字に当て嵌めると「赤蛇」になるとされ、その源流は縄文時代にまで遡ると考えられています。石と樹という原始的な信仰の表れでもありますが、他にも蛇が石棒、神木、男根などと結び付く事に由来するともされます。
タケミナカタは諏訪大社の祭神ですが、タケミカヅチとの力比べに負けた後に諏訪の地に入り、その地の土着神であった洩矢神(ミシャグジと同一視される神)と戦って勝利したという説話を持っています。
そしてオオナムチ。この神は出雲大社の祭神として知られるオオクニヌシであり、かの大神スサノヲの子孫にして国造りを為した神です。
同一視されるオオモノヌシは『日本書紀』「神代巻」においてオオナムチの和魂、つまり一側面であると説かれており、蛇の姿で顕現したという説話が同じく『日本書紀』の中で伝承されています。
単に蛇神といっても在来のものから異国由来のものまで、その種類は多岐に渡ります。この場面ではその中でも代表的なものをピックアップしていますね。
神道において、神が持つ二つの側面のうちの一つ。
和魂は神の穏やかで優しい側面であり、対するものとして神の荒ぶる側面である「荒魂(あらみたま)」が存在する。
牛神と竜の神話
最後にもう一つ紹介しておきましょう。こちらも「彷徨海の魔人(下)」の一節です。
「彷徨海の魔人」には白若瓏(バイ・ルォロン)という魔術師の青年が登場し、彼は神話に名高い竜を喰らっており、その竜に由来する異能を操る事が出来ました。また、凛に会う以前の記憶をほぼ喪失しているエルゴの事を「親友」を呼んでいました。
下巻の終盤で、Ⅱ世はエルゴと若瓏の竜と神を推理する場面があり、そこで世界の神話に偏在する「牛と竜の戦い」という概念に触れます。
「もう一つ、これは若瓏の方だが、オオナムチに絡む竜であろうことも想像がついていた。兵主神としてオオナムチは中国神話の蚩尤にルーツを持つというのはエルゴに話したが、この蚩尤と応龍の戦いは、世界中に広がる牛種と竜種の戦いのひとつでもある」
「牛というと奇妙なようだが、世界最古の神話においてすら、牛の影響は強い。古代バビロニアにおいて、英雄王ギルガメッシュが天の牡牛を殺したことで、彼は王権を確立したのだから」
「ギリシャにおいては、主神ゼウスがこの牛の属性を持っている。本人が牛に変わった逸話や、その子がミノタウロスという牛種の筆頭であることを考えれば、これは分かりやすいだろう」
((三田誠著『ロード・エルメロイⅡ世の冒険3「彷徨海の魔人(下)」』角川文庫、2022年、365、366p)
蚩尤というのは中国神話における牛頭の軍神であり、古代中国の伝承を記した『山海経』の「大荒北経」の項において、応竜という竜に倒されると語られます。
ここで言及される「兵主神(ひょうずのかみ)」というのは全国の兵主神社に祀られる神を指し、オオナムチ、或いはスサノヲが該当します。しかし「兵主」という語が出てくるのは古代中国の「史記」という文献であり、その中では蚩尤に対して用いられています。
この事から、兵主神は本来異国に起源を持つとされます。
さて、本題である「牛神と竜」ですが、確かに世界の神話を見比べてみると、驚く程に同じ構図の神話が多く見受けられます。
古代メソポタミア世界においては、最古の叙事詩である『ギルガメシュ叙事詩』の主人公ギルガメッシュが天の牡牛(グガランナ)を倒す事で王権を確立したとⅡ世は語っていますが、バビロニアの創世叙事詩『エヌマ・エリシュ』にも同様の説話が存在します。
それが「マルドゥクによるティアマトの討伐」です。
古代バビロニア神話において、最高神マルドゥクは原初の女神にして水竜であるティアマト神を討ち、その死体を引き裂いて天地を創造すると語られます。
マルドゥクという名に注目すると、その意は「太陽の若い牡牛」であり、牛VS竜の構図が見出せます。
他にも例を挙げていくと、以下ような形で牛と竜の対立の構図が存在します。
- インド神話:雷神インドラは聖典『リグ・ヴェーダ』の中では「水牛」と言及され、彼は水を堰き止める蛇竜ヴリトラを討ち倒す
- カナン神話:主神バアルは祭儀獣を牛とし、水竜ヤム=ナハル、或いは「原初の蛇」と伝承される竜ロタンを殺す
- エジプト神話:直接的な対戦構図は無いが、戦争の神セトは蛇の姿でも現され、ギリシア神話の竜テュポーンと同一視される。セトと敵対する女神イシスは牝牛の頭を持つとされた。
- ギリシア神話:牡牛に変身する事からゼウスも牛神の性質を帯び、「肩から百の竜を生やす」と言及される怪物テュポーンを討つ
- 日本神話:嵐神スサノヲは牛頭の神「牛頭天王」と同一視され、水蛇神である八岐大蛇を討伐する。
このように、異なる地域でも似た構図が存在するというのが神話の興味深いポイントでもあります。
竜退治という括りではイランやヒッタイトなどの神話も含められますが、その中でも「牛と竜」という二つの種族の対立にフォーカスを当て、物語の展開に活かしているというのが非常に手が込んでいて面白い所ですね。
まとめ
如何でしたでしょうか。
今回紹介してきたように、『ロード・エルメロイⅡ世の事件簿』及び『冒険』には神話や宗教に関する要素が非常に多く、尚且つかなり深いレベルで物語の中に落とし込まれています。
勿論、この作品の魅力はそれだけではありません。
Ⅱ世やグレイを始めとするメインキャラクター以外にも、数多くの個性的な魔術師達が登場し、物語に関わってきます。
他のTYP-MOON作品とリンクする事も多く、1巻に一人は「Fate」や「月姫」、「空の境界」といった作品からゲストキャラクターが出演するのもファンとしては魅力的な部分です。
また、相手にするのが超常現象を普通に扱う魔術師相手である事が多い為、推理小説における「フーダニット(誰がやったか)」と「ハウダニット(どうやったか)」は通用しません。
ですがその反面、動機である「ホワイダニット(なぜやったか)」だけが意味を持ち、常にこのホワイダニットに重きを置いて推理が展開されていくのも特徴です。
他の作品のようにサーヴァントが多数登場する事は無いですが、それでも最近では作中に登場する魔術師もややパワーインフレをしてきており、三田誠先生の文章も相俟って戦闘シーンの迫力は全く引けを取りません。
現在ではTYP-MOON BOOKSに加え、角川文庫から『剥離城アドラ』~『冠位決議(下)』までが刊行されており、Kindle版も配信しています。Amazonのリンクを貼っておきますので、もし興味がありましたら一度読んで頂けると嬉しい限りです。
ここまで読んで頂き、誠にありがとうございました。
参考文献
- ミルチャ・エリアーデ著、久米博訳『エリアーデ著作集 第二巻 豊穣と再生 宗教学概論2』せりか書房、1979年
- 日本聖書協会『新共同訳聖書』日本聖書協会、1988年
- H・ガスター著、矢島文夫訳『世界最古の物語ーバビロニア・ハッティ・カナアン』社会思想社、1989年
- ジョン・ロナー著、鏡リュウジ訳『天使の事典ーバビロニアから現代まで』柏書房、1995年
- 宇治谷孟訳『日本書紀(上)全現代語訳ー全二巻ー』講談社、2000年
- 金光仁三郎ほか訳『世界シンボル大事典』大修館書店、2002年
- 山本ひろ子著『異神 中世日本の秘教的世界 上』筑摩書房、2003年
- 山本ひろ子著『異神 中世日本の秘教的世界 下』筑摩書房、2003年
- 伊藤聡・遠藤潤ほか著『日本史小百科 神道』東京堂出版、2003年
- 斎藤英喜著『陰陽道の神々』思文閣出版、2007年
- フェリックス・ギラン著、中島健訳『ギリシア神話』青土社、2011年
- 斎藤英喜著『荒ぶるスサノヲ 七変化 〈中世神話〉の世界』吉川弘文館、2012年
- 権東祐著『スサノヲの変貌――古代から中世へ』佛教大学、2013年
- ヴェロニカ・イオンズ著、酒井伝六訳『エジプト神話』青土社、2014年
- 戸部民夫著『「日本の神様」がよくわかる本 八百万神の起源・性格からご利益までを完全ガイド』PHP文庫、2015年
- 岡田温司著『天使とは何か』中央公論社、2016年
- 荒川紘著『龍の起源』紀伊國屋書店、2017年
- 高馬三良訳『山海経 中国古代の神話世界』平凡社、2017年
- 山本ひろ子著『中世神話』岩波書店、2018年
- 上村勝彦著『インド神話 マハーバーラタの神々』筑摩書房、2018年
- 小林登志子著『古代オリエントの神々』中央公論新社、2019年
- 岡田明子・小林登志子著『シュメル神話の世界』中央公論新社、2019年
- 廣川洋一訳『ヘシオドス 神統記』岩波書店、2019年
- 辻直四郎訳『リグ・ヴェーダ賛歌』岩波書店、2019年
- 矢島文夫著『メソポタミアの神話』筑摩書房、2020年
- 中村啓信訳・注『新版 古事記 現代語訳付き』株式会社KADOKAWA、2020年
- グスタフ・デイヴィットスン著、吉永進一訳『天使辞典』創元社、2020年
- カート・セリグマン著、平田寛・澤井繁男訳『魔法 その歴史と正体』平凡社、2021年
- 中村圭志著『宗教図像学入門』中央公論新社、2021年







































コメントを残す