観世音菩薩(かんぜおんぼさつ、一般には観音さまと呼ばれる)と言えば、日本の仏教でも御馴染みのお釈迦様、お地蔵様と並ぶ、人気の仏尊の1人ではないでしょうか。
その大法力の効能は計り知れなく、日本の仏閣では参拝者が連日途絶えないほどの大人気でもあることは、日本に住んでいる者ならば誰でも実感できることでしょう。
しかし、お隣の中国となるとまた面白い神話が観世音菩薩様に存在するのです。
そのリスペクトたるや、日本の観世音菩薩信仰にも引けを取らないほど、と言えるほどに面白く、観音様の格の高さが分かるような話に満ちているのです。
ここではその中国神話世界で躍動する観世音菩薩の神話体系について語っていきたいと思います。
Contents
過去は仙人だった?大胆な改変
観音様と言われると、なんとなくですが、女性的な外見を思い浮かべることも多いのでは?
中国の明代に成立した神怪小説「封神演義(ほうしんえんぎ)」の中にも観音様は登場するのです。
今なお、観音様は菩薩として如来となるべく修行の身であらせられますが、この物語の中では更なる過去が描かれています。
中国中世期において、神仏は三教合一(儒教、仏教、道教)の元に語られていたので、それをモデルにした神話(神怪小説)にも観音様の過去史のような話が存在するのです。
この封神演義の中では、その名も「慈航道人(じこうどうじん)」といい、道人の名の通り、道教の「道(タオ)」を究めんとして修行に励む仙人でした。
女性的な存在

上の図のように、最近の封神演義を扱ったドラマでも女性の演者が役に扮し、女性として描かれています。
日中問わず、観音様として大慈悲にして人間を救済してくれる存在。
その姿に、母親への敬愛を感じ、慈母の象徴のような存在として描かれるようになったのかもしれませんね。
時系列的なつながりを感じる西遊記にもこの女性としての観世音菩薩のイメージで登場することになります。
西遊記での活躍は後述するとして、ここでは封神演義での観世音菩薩(慈航道人)の活躍を見ていきましょう。
さすがな存在感、しかし…
観音様の存在感を強いかどうかなんてことで測ってしまうのは宗教的にはナンセンス極まりないでしょう。
しかし、封神演義は神仙仏が妖怪退治をする物語なので、あえてそれを言います。
結論から言えば、さすがというべきか、「極めて強い」です。
彼女は人間から修行して昇華した完成された仙人集団「闡教(せんきょう)」に属し、トップに君臨する「元始天尊(げんしてんそん)」12人の高弟の1人なのです。
物語中盤で、道根の深い(手練れの仙人)三人の仙女「三仙姑(さんせんこ)」が敷いた仙術が篭った戦陣「九曲黄河陣(きゅうきょくこうがじん)」に、他の11人と共に為す術なく捕らわれてしまいます。
ここがポイントであの観音様にもそんな時期があったのか?と思わせてくれるのです。
偉大な菩薩様にも為せぬこともある修行期もあり、それを突破して今の姿に至る。
宗教とは異なる神話物語ながら、学べることも多いと私は思っています。
封神演義には道教の最高神「元始天尊」という存在も出てきます。
道教上における宇宙の創造神にして、闡教(せんきょう)の元締めとして登場し、主人公である太公望の師匠にもあたります。
崑崙12大弟子は、太公望やその仲間となる楊戩(ようせん)、哪吒(なた)などの直接的な師匠や師匠筋にあたり、元始天尊→崑崙12大弟子→太公望達という系譜で繋がります。
崑崙12大弟子は、彼らの弟子筋にあたる太公望達が苦戦すると、山々に構えた洞府から下山してきて救援にくる頼もしい存在なのです。
| 名前 | 洞府 | 弟子 |
|---|---|---|
| 慈航道人 | 普陀山・落伽洞 | なし |
| 普賢真人 | 九宮山・白鶴洞 | 木吒 |
| 文殊広法天尊 | 五竜山・雲霓洞 | 金吒 |
| 広成子 | 九仙山・桃源洞 | 殷郊 |
| 赤精子 | 太華山・雲霄洞 | 殷洪 |
| 太乙真人 | 乾元山・金光洞 | 哪吒 |
| 玉鼎真人 | 玉泉山・金霞洞 | 楊戩 |
| 清虚道徳真君 | 青峰山・紫陽洞 | 黄天化・楊任 |
| 懼留孫 | 夾竜山・飛雲洞 | 土行孫 |
| 黄竜道人 | 二仙山・麻子洞 | なし |
| 霊宝大法師 | 崆峒山・元陽洞 | なし |
| 道行天尊 | 金庭山・玉置洞 | なし |
この他に、彼らを束ねる仙主「燃燈道人」がおり、弟子に李靖、霊鷲山・元覚洞という洞府にて修行を行っています。
ですが、観世音菩薩とは無縁といってもいいような無慈悲な話も封神演義にはあるのです。
見出し文の「しかし…」とは今から紹介する話の中にあります。
仕事に忠実!?真面目?無慈悲?
封神演義とは読んで字のごとく、「封じて神にする」ことの大義を貫徹するお話です。
封神演義の仙人界には、完成された仙人達の闡教(せんきょう)の派閥と半端者揃いな未熟派閥の截教(せっきょう)の二大派閥が存在しました。
この未熟者派閥の截教の似非仙人達を封神してしまおうというものが「封神計画」と呼ばれるものでした。
具体的には、殺して魂だけになった似非仙人達をそのまま「神」として祀り、天界で欠員状態だった「神」を補充するというものです。
つまりは、仙術と宝具である「宝貝(パオペイ)」(様々な効果を持つマジックウェポン)を使って意図的に完成された仙人に未熟な仙人達を抹殺させる、という計画なのです。
この遂行者の1人の中に、慈航道人、すなわち観世音菩薩も含まれているのです。
しかも、その中での慈航道人の活躍たるやプロフェッショナルと言わんばかりの大義に忠実な姿を見せるのです。
十絶陣での慈航道人

十絶陣(じゅうぜつじん)というのは、敵方の10人の仙人が敷いた妖陣です。
これは主人公たちの太公望では対抗できずに、崑崙12大弟子の出番となりました。
そこに登場する慈航道人は極めて淡々と敵方の処理に当たります。
ここで慈航道人は敵方の董全(とうぜん)という仙人が敷いた風吼陣(ふうこうじん)という妖陣を打ち破ります。
「瑠璃瓶(るりへい)」という敵を吸い込む花瓶のような宝具を空中に投げて黄巾力士(こうきんりきし)なる従者にその瓶を傾けさせ、一筋の黒い霧を出しそこへ董全を吸い込み倒すのですが、後処理が壮絶です。
「風吼陣は自分が破った!」と宣言すると、黄巾力士に命じて、瑠璃瓶を傾けさせます。
すると、瓶の口から出てきたものは既に溶けて血の塊となっていた董全だったのです。
封神演義の「封じて神にする」とはこのように生々しいやり方も当たり前のようにあるのです。
このような儀式めいたことをやってのけて、初めて魂は「封神台(ほうしんだい)」へ飛んで行き神なる栄転を果たせるのです。
道友の不肖の弟子へのけじめの催促
この話も「慈悲とは?」というものを考えさせられる話になっています。
同じ崑崙12大弟子の道友、赤精子(せきせいし)という者がいます。
彼の弟子の殷洪(いんこう)という存在が、師である赤精子の命令に背き、味方の闡教に反逆し敵となりました。
しかし、師である赤精子に捕まり、さて、どうなる?という場面。
背信した不肖の弟子とはいえ、可愛い弟子を守りたい赤精子。
慈悲深い後の観世音菩薩様の慈航道人も、そこで恩赦を与えて汚名返上の機会を…とでもいうのかと思いきや
「これも天命。速やかに処刑を遂行するように」
と、言ってのけ、赤精子に弟子を処刑させてしまったのです。
というのも、殷洪は師匠の言いつけを守らずに敵に回ることになれば、自分は師匠の手で処刑されても構わない。と、事前に誓約していたのです。
「慈悲」とは情けないほどまでに優しい甘えを許す、というものではないということではないしょうか。
赤精子は嘆き悲しみ泣く泣く弟子の殷洪を処刑しました。
殷洪は師匠の手に葬られたことによって、裏切り者の汚名を受けてまで生きながらえる恥に見舞われず、死して道理を貫く正当な神になることが出来たのです。
究極転身 観世音菩薩へ
慈航道人は封神演義の物語の中でパワーアップし、観世音菩薩と思わしき威容を備えた姿へと転身します。
これを次の話の中で紹介していきましょう。
物語も佳境に差し掛かり、封神演義で最高最大のクライマックス、高位大仙や西方からは仏までもがやってきて参戦する「万仙陣(ばんせんじん)」の戦い。
ここで慈航道人は師である元始天尊に導かれて、新たなる姿へと転身を果たすことになります。
元始天尊の命によって、金光仙(きんこうせん)という敵方の仙人と戦うことになった慈航道人。
元始天尊から聖なる如意玉と転身の法を授かります。
さらに金光仙の正体は犬に似た獣のような姿をしているため、彼を乗騎とするようにとのお達しを受けます。
さっそく、金光仙の方から打ちかかってきたのですが、さすがは慈航道人。
これを手中の剣で難なく迎え撃ち圧倒し、僅かに三合打ち合っただけで金光仙は自陣に逃げ帰ります。
これを追って、敵の妖陣へと突入すると、敵陣が無限の変化を見せ始めたのを見て急いで元始天尊に習った方法で自分の頭を叩きます。すると……
たちまち慶雲(けいうん)が生じて、道人の頭上を覆う。
同時に雷鳴轟き、慈航道人の化身が現れた。
顔は白く、三面六臂(さんめんろっぴ)。
両目からは炎が吹きだし金竜となる。
両耳からは金連(きんのれん=金の蓮華)と瑞彩(ずいさい=輝ける花々)が生じ、足には金鰲(きんごう=金色の大ウミガメ)を踏んでいる。
三宝玉如意を握った姿は瑞気(ずいき)に包まれていた。
歴史ポケットシリーズ『封神演義6 妖しの戦陣』許仲琳編 光栄 P.154より引用
こんな姿を見た金光仙はすっかり戦意を喪失し、慈航道人の三宝玉如意を打ちつけられ倒れこみます。
そのまま闡教陣地に連れていかれ、元の姿である野獣の姿を現し、慈航道人の乗騎となったのです。
封神演義の話の中では、この後に仏法へ帰依した慈航道人は観世音菩薩となる、と締めくくられています。
日本人の仏教観からするとおおよそ考えのつかないような話の数々です。
しかしこのような観世音菩薩の姿は私個人としては実に個性的であり、カルチャーショックを受けると同時に「面白い観音様の神話」として受け入れることが出来ました。
仏教説話では、元は他人の子供を食らう人食い鬼だった鬼子母神が、釈迦如来に自分の子供を取り上げられた時に、今までの自分の行いを悔悟して子供を守る神へと転生を果たす話もあります。
救世主とは「自ら荒事にも手を染めていた過去」があるのかもしれませんね。
さて、次項からは実に観音様「らしい」神話の数々になるので、王道をご期待ください。
西遊記の観世音菩薩
西遊記と聞けば、日本のドラマなどでも御馴染みですね。
三蔵法師一行が遥か西方彼方へ向けて、有難い経文をお釈迦様から得るための珍道中記、と思われる方も多いでしょう。
しかしこの西遊記こそは、中国仏教と道教をベースとした神話物語として極めて精度が高く完成された逸品なのです。
この西遊記と封神演義によって、中世の中国の人達は自分たちが祀っている神様を認識できるほどに完成された神話として磨き上げられています。
その中には、日本の宗教のイメージとさほど変わらない形で「観世音菩薩の神話」も存在するのです。
その姿は、まさに慈母の如し、読み手に「頼もしさ」を感じさせてくれます。
求道の導き手

西遊記の観世音菩薩はかつて孫悟空が天界で大暴れした時に、西方より来訪しています。
その時は西王母(せいおうぼ)という高位の神仙が開いた蟠桃会(ばんとうかい)の招きに応じました。
そこで孫悟空が傍若無人な大暴れをしていると聞き、弟子の恵岸(えがん)を派遣して事の鎮静化に当たらせます。
しかし孫悟空は手強く、弟子の恵岸は敗北して逃げ帰ってきました。
そこで観世音菩薩は二郎真君(じろうしんくん)という神を天界の最高神である玉皇上帝(ぎょくこうじょうてい)に推挙し、彼が孫悟空を封じることに成功したのです。
こうして孫悟空は五行山(ごぎょうさん)という山の下に閉じ込められることになりました。
孫悟空が五行山の下に閉じ込められてから500年後、釈迦如来は南贍部洲(なんせんぶしゅう=人間の世界)に争いが多いことに嘆いていました。
その地に行き釈迦如来の聖なる経典を授けるに相応しい者を探してくるように命じた際、観世音菩薩はその役を買って出ます。
釈迦如来から錦欄の袈裟(きんらんのけさ=豪華な刺繍模様が施してある袈裟)、九環の錫杖(きゅうかんのしゃくじょう=先端部九つの環に入れて音を鳴らす杖)、3つの金箍字(きんこじ=頭にはめる輪)を受け取り、弟子の恵岸を引き連れ、東へと向かいました。
道中、流砂河(りゅうさが)で沙悟浄、福陵山(ふくりょうさん)で猪八戒、蛇盤山(だばんさん)の鷹愁澗(ようしゅうかん)で白竜、そして五行山で孫悟空と出会い、彼らを仏法へ帰依することを説いて、仏への栄転の道を開きます。
そのために彼らに後日、この地を通るものに従って西方へ仏典を受け取るために共に西へ進むことを告げました。
更に観世音菩薩は東へと進み、唐の都「長安」へと降臨し、三蔵法師を新たな弟子として迎えます。
そして彼に釈迦如来から賜った錦欄の袈裟、九環の錫杖を授けて西天取教(西遊記第13回~第100回までの話)の旅へと向かわせたのです。
三蔵法師、孫悟空、沙悟浄、猪八戒、白竜は皆、西天取教の旅を終えた時に、功が成り偉大な存在へと昇華することが出来ます。
彼らをそこへ導いた立役者こそ、観世音菩薩に他ならないのです。
西天取教、すなわち西遊記の話の中で、孫悟空は何度も苦境に陥ります。
しかし救援を求めれば観世音菩薩はその都度、彼を救済し旅の成功へと導きます。
その姿はまるで観世音菩薩が母親であり、孫悟空が子であるかのようでもあります。
身なりを気にする観世音菩薩様!?
西遊記には、観世音菩薩の女性的な部分が顕著な意外(!?)な話があります。
西遊記第49回において、孫悟空は霊感大王(れいかんだいおう)という妖怪に苦戦し、観世音菩薩に救援を求めます。
しかしその時の観世音菩薩は竹林に篭って、竹ひごを削り竹籠を作っています。(この妖怪は観世音菩薩が飼っている金魚で、その金魚が逃げ出して悪さをしていたため、それが分かっていた観世音菩薩は既に金魚を捕まえるための籠を作っていました。)
その時に従者の善財童子(ぜんざいどうじ)が孫悟空に向かって
「今朝、自分の洞府を出られるや、お化粧もせぬまま竹林に向かわれた。」
という台詞が出てくるのです。
西遊記の世界では観世音菩薩様でも、お化粧をするのですね。
これが中国は明の時代のお話になりますから、中国では中世期から観世音菩薩様は女性である、という見方が世間一般では当たり前のように浸透していたのですね。
東遊記の観世音菩薩
東遊記とは、西遊記・北遊記・南遊記と並ぶ、神仙と神仙の戦い、もしくは神仙が下界を騒がす妖怪を退治する神怪小説、もしくは神魔小説と呼ばれるものです。
中国中世期の神話集である『四遊記』の一つですね。
中国は明の時代の中国仏教、道教を織り交ぜた神話集であり、中国で著名な八人の仙人「八仙」が主役の話です。
彼らが東の海へと赴く話の中で起こる出来事を描いており、この話の重要な締めの部分で観世音菩薩は救済の大法力を発揮します。
呂洞賓(りょどうひん)、鐘離権(しょうりけん)、李鉄拐(りてつかい)、張果老(ちょうかろう)、韓湘子(かんしょうし)、曹国舅(そうこくしゅう)、藍彩和(らんさいわ)、何仙姑(かせんこ)の8人

八仙が東の海に渡ろうとした時、龍王の子摩掲(まけい)が、八仙の1人である藍彩和の宝物「美しい玉のついた板」を欲しがり奪おうと襲い掛かります。
この板は踏んでいるだけで海を渡れる優れモノでした。
当然八仙と争いになりますが、この争いは次第に激化していきます。
八仙側の戦力に対して、摩掲も親の東海龍王に西、東、南の龍王の助成も得て、更にヒートアップ。
それでも八仙は強く、更に龍王側は天界にまで救援を求め、天界の援軍と激戦を繰り広げてしまいます。
もはや収集がつかない!となった泥沼の惨状を一気に回復させるために登場、となるのが観世音菩薩なのです。
これぞ観世音菩薩の神通力
東遊記の八仙 VS 龍王軍の最終局面は熾烈を極めるものでした。
仕掛けられた八仙は反撃の狼煙と言わんばかりに、摩掲軍を計略で打ち負かし、彼らが住処の海の中へ逃げ込むと、猛火を放ち海を干上がらせてしまいます。
更に法力で聖なる山「泰山(たいざん)」を海に投げ落とし、摩掲の援軍の龍王軍は壊滅状態に。
しかも八仙側には斉天大聖孫悟空が加勢し、龍王軍の援軍第二陣としてやってきた天界軍の天兵20万人を如意棒一振りで薙倒してしまう活躍ぶり。
これを迎え撃つ天界軍の主将たるや最強の武神である四人の「四大元帥神(しだいげんすいしん)」であり、この中には三国志で有名な関羽もいます。
しかし怨讐の連鎖もここでようやく終わります。
神仙の元締めの太上老君(たいじょうろうくん)と阿弥陀如来が降臨し、そこへ観世音菩薩も来臨を果たします。
そして彼らの仲裁役を買って出て、いとも簡単に泰山を元に戻し、泰山を投げ落とされた東の海も元通りに戻してしまいました。
しかも泰山はますます高く、東の海はますます青くなっているという大法力を見せつけたのです。

如何でしたでしょうか。
これが中国神話世界における救済の慈母、観世音菩薩様のお姿です。
日本での仏尊としての観世音菩薩様とは一味違う人間味のようなものがあると私は思います。
日中問わず絶大な信仰心をもって崇められている観世音菩薩様。
かの御大の神話などがあれば見てみたい!と思った際は、中国の西遊記や東遊記を読んでみることをオススメします。
- 参考文献
- 日本書籍
- 西遊記(一) 中野美代子訳 岩波文庫
- 西遊記(二) 中野美代子訳 岩波文庫
- 西遊記(五) 中野美代子訳 岩波文庫
- Truth In Fantasy 77
- Truth In Fantasy ⅩⅩⅤ
- 西遊記キャラクターファイル 三猿舎編 新紀元社
- 東遊記 竹下ひろみ訳 エリート出版社
- 歴史ポケットシリーズ 封神演義4 十絶陣の悪夢編 許仲琳編 光栄
- 歴史ポケットシリーズ 封神演義6 妖しの戦陣編 許仲琳編 光栄
- 封神演義の世界 中国の戦う神々 二階堂義弘 大修館書店
- 封神演義 英雄・仙人・妖怪たちのプロフィール 遙 遠志著 新紀元社
- 日本書籍
※ライター:パワーグリーン












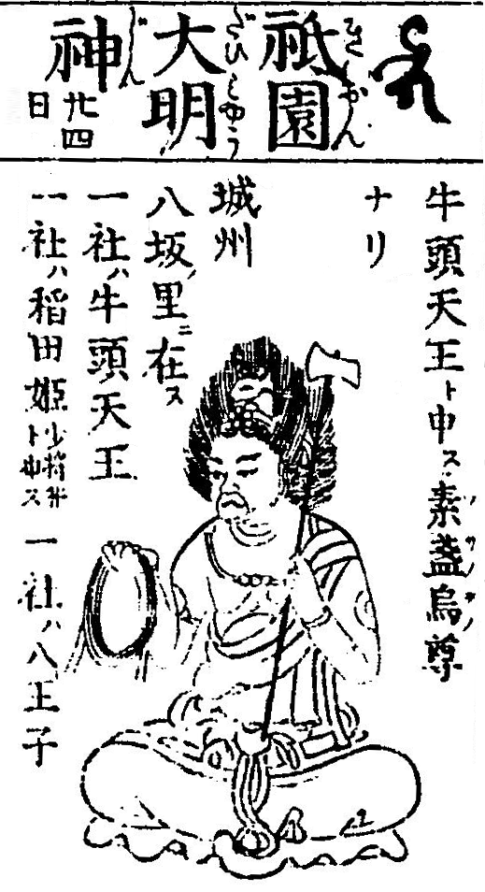





























コメントを残す