Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。
Contents
- 1 ソロモン王の死とともに衰え始めるイスラエル王国
- 2 北イスラエル王国を支配したファラオの祖国・エジプト第22王朝
- 3 その正体は超強い天使サンダルフォン? 預言者エリヤ
- 4 敵より先に味方を粛清する「クソコテ」エリヤの帰還
- 5 実は名君だった? 「スケールの小さいソロモン」・北イスラエル王アハブ
- 6 本当に天に登ったのか? 預言者エリヤの昇天
- 7 「ナザレのイエス」の原型は彼? 「暗黒奇跡芸人」預言者エリシャ
- 8 対アッシリア帝国大同盟を台無しにした「イエフのクーデター」
- 9 北イスラエルの「名君」イエフ王による豊穣神バアル信仰の大弾圧
- 10 北イスラエル最後の繁栄期と消えた10部族
- 11 バビロニアに滅ぼされるユダ王国とバビロン捕囚
ソロモン王の死とともに衰え始めるイスラエル王国
サウルの時代に王国として統一され、ダビデ・ソロモンの治世に最盛期を迎えたイスラエル王国でしたが、ソロモン王の末期にはあちこちで矛盾が顕在化するようになりました。
「旧約聖書」の記述を読む限りにおいては、ソロモンは交易立国を志ざし、首都イェルサレムに来た外国の人々を驚かすために壮麗な建築物を次々と建てました。
この土木事業の原資を確保するために、ソロモンは人民に重税を課します。
イスラエル王国には、人民よりも厄介な存在として、ヤハウェを奉じる祭司団がいました。
イスラエル王国が交易国家化すると、外来の文化が流入してきます。
これは、イスラエルの民のものとは違う信仰が流入してくるというのとイコールです。
唯一絶対の神ヤハウェを奉じる祭司団にとって、これは非常に都合が悪いのです。
このため、祭司団も人民とともに、王朝に対する抵抗勢力となりました。
ソロモンの時代は、それでも王の卓越した「知恵」によってイスラエル王国の統一は保たれていました。
しかしソロモンの死後に各所の不満が爆発した、と「旧約聖書」は伝えています。
つまり、ソロモンの子レハブアムが人民に重税を課し続けたため、エジプトに亡命していたヤロブアムという人物を立て、北部の十部族を独立させます。
この、分離独立した十部族の国家が「イスラエル王国」の名を引き継ぎ、ダビデ・ソロモンの子孫を王として戴く南部の国家は「ユダ王国」と呼ばれるようになりました。
北部のイスラエル王国の王となったヤロブアムは、元ソロモンの家臣でしたが、ある時ヤハウェから「北部の十部族を与える」と告げられます。
それを聞いたソロモンはヤロブアムを危険視し、殺そうとしました。
ヤロブアムはエジプトに逃れ、シシャクというパロの庇護を受けたと言います。
そしてソロモンが死ぬと故郷に戻り、北部の王となりました。
その後、北王国も南王国も王権は不安定になります。
この頃の状況を記した「旧約聖書」の「列王記」「歴代誌」はその理由を例によって諸王がヤハウェに対して忠実ではなかったからだ、と述べますが、実際には違う理由がありました。
イスラエル・ユダ王国はエジプトに征服されていたのです。
北イスラエル王国を支配したファラオの祖国・エジプト第22王朝
ヤロブアムを匿ったエジプトのパロ・シシャクは、エジプト第22王朝初代のファラオ・シェションク1世だとするのが定説となっています。
「旧約聖書」にはこれまで何人も「パロ」が登場してきましたが、彼らが具体的にどのファラオであったのかはわかりませんでした。
「シシャク」は最初の「誰だかわかるファラオ」だったということになります。
シェションク1世はリビア出身の軍人で、それまで南北に分裂していたエジプトを統一し、パレスティナ地方に遠征を行いました。
この結果ダビデ・ソロモンの王国の南部は完全にエジプトの属国になります。
「列王記上」には、シシャクによる侵略とイェルサレム神殿の破壊が記録されています。
しかし、「エジプトに征服された」とは書いてありません。
北部がヤロブアムによって分離・独立したのはシェションク1世の遠征よりも前のことです。
前後の経緯から、シェションク1世はまずヤロブアムを派遣して北部を間接支配しようとしていたのですが、途中で方針を転換して遠征を行い、南部を直接支配したものと思われます。
ヤロブアムはこの遠征でエジプト軍に始末されそうになったため、逃亡して身を隠してしまいました。
シェションク1世は遠征後、戦勝碑を建ててエジプトに引き上げました。
第22王朝の力では、北王国を恒常的に支配することはできなかったようです。
この結果ヤロブアムが王に返り咲きますが、その支配は例によって安定しません。
南のユダ王国の方は、北イスラエル王国よりは多少マシなようでしたが、それでも安定というには問題ありありな状態でした。
ダビデやソロモンクラスがいなければ国として成り立たないという点、イスラエルの民の国はどこか欠陥があったのかも知れません。
もっとも、古代の国家の国力は多かれ少なかれ君主の力量に比例しており、他の国も暗君が即位すれば国運が傾くものですが、イスラエルの民の国はそれがちょっと極端なようです。
ユダ王国と北イスラエル王国との抗争は、両国が分裂してから40年程度続きました。
しかし、その後はなんとか融和を図ろうとするようになります。
元の通り一つにまとまろうとするのではありません。
分裂を前提とした上で仲良くしようという、かなりヘタれた考えになってきています。
なお、エジプト第22王朝ですが、シシャクことシェションク1世が亡くなると南北に半ば分裂して対立するようになります。
元々第22王朝は南北に分裂していたエジプトをシェションク1世が統一して成立したものですから、偉大なるファラオの死とともに元に戻ったという感じです。
いずれにしろエジプトからの脅威はしばらくなくなるのですが、イスラエルの民は統一に向けて動いたりはしません。
特に北イスラエル王国においては、軍人のトップが王を殺して自分が王になる、ということが繰り返されます。
前王を殺した新しい王は、前王の親族までご丁寧に皆殺しにしています。
その結果また自分またはその息子ぐらいの代に同じことをされるのです。
「列王記」では北イスラエルの王は大抵「ヤハウェの前に罪を犯した」と罵倒されています。
ユダ王国の王はそれに比べると少しマシです。
ただ、「良い王だった」とされるアサ王は、「神殿男娼を追い出し偶像を焼いた」から善王だったと讃えられているのです。
つまりその前の王の時まで神殿に男娼がうようよしていたということですから、それを追い出したからといってユダ王国そのものの株があまり上がるようには思われません。
余談ですが、アサ王の次の王も神殿男娼の追放を行っているので、アサ王の「改革」は徹底してはいなかったようです。
その正体は超強い天使サンダルフォン? 預言者エリヤ
このように乱れた(と「旧約聖書」に書かれている)北イスラエルに、エリヤという預言者が登場します。
エリヤは日本においては比較的マイナーですが、アブラハムの宗教においては、モーセ以後最も偉大な預言者であるとされています。
「新約聖書」では、ナザレのイエスは死ぬ間際に「エリ・エリ・ラマ・サバクタニ」と言います。
これは「わが神、わが神、どうしてわたしを見捨てられたのか?」という意味ですが、刑場の周りの人々は「イエスはエリヤを呼んでいる」と囁きあったと言います。
エリヤは、それぐらい重要視された預言者だったのです。
伝説では、エリヤは死後昇天し、天使サンダルフォンになったといいます。
サンダルフォンは、「大丈夫だ、問題ない」で有名なイーノック(エノク)こと天使メタトロンと兄弟ともされる超強力な天使でした。
本当にエリヤがサンダルフォンになったのかはともかく、そういう伝説が残るほど重んじられたということは間違いないでしょう。
エリヤが預言者としての活動を開始したのは、北イスラエル王国をアハブ王が治めていた時代です。
アハブ王は、言ってみれば小型のソロモンとでも言うべき王でした。
ソロモンは周辺諸国と平和な関係を結び、交易を重視して国を富ませようとした王です。
交易と外交を重視した結果、外国人の宗教に寛容になる傾向が出た点も、ソロモンと同じでした。
アハブ王はシリアと友好関係を築き、シリアから妻を娶ります。
このため、シリアで信仰されていた宗教が、イスラエルの国に浸透してくることになります。
このシリアの信仰の主神は、「旧約聖書」においては悪神の代表扱いされているバアルです。
バアルはシリア・パレスティナ方面で広く信仰されている神でした。
地中海沿岸の都市・ウガリットで信仰されていた神話においては、バアルは天空神イルの子とされています。
このイルは、イスラエルの民たちが進行しているヤハウェと同じ起源を持つと考えられています。
つまり、バアルはヤハウェの息子なのです。
ヤハウェの信仰自身が、他の神と夫婦関係や親子関係を結ばない、絶対的な唯一神とするところから始まっていますから、ヤハウェの信者はバアルがヤハウェの子であることは絶対に認めませんが。
「旧約聖書」においてバアルは至る所で邪神として罵倒されています。
このため、聖書を読んだ後世のキリスト教徒の手によって、バアルはおどろおどろしい姿を持つ悪魔として描写されるようになりました。
しかし、「イルの息子」だった時代のバアルはイケメンの若い男性神だったのです。
バアルは地中海を渡ってくる西からの風の神であり、その風がもたらす雨の神でもあります。
そこからさらに発展し、農業の守護者、つまり豊穣神とみなされるようになりました。
バアルはアナトとアスタルテという二人の妻を持っている、と考えられていました。
アナトもアスタルテも、元々はバアルの妹です。
アナトはバアルの「美人な方」の妻で、アスタルテはバアルの「かわいい方」の妻とされました。
かなりあざとい設定です。
他方ヤハウェはというと、基本的には気難しい老人の姿をしていると考えられました。
ヤハウェが「独り神」としての立場を確立すると、ヤハウェ神官団はヤハウェの偶像を作ることを厳しく禁じます。
にも関わらず、現代人の間にも「ヤハウェ=気難しそうな老人」というイメージは残ってしまっています。
「気難しそうな老人」を中心とする信仰と、美人なのとかわいいのと二人の妻を両腕に抱くイケメンの豊穣神の信仰の二つを突きつけられて、人はどちらを選ぶものでしょうか。
ほとんどの人が、若いイケメン、すなわちバアルの信仰を選ぶでしょう。
古代のイスラエル王国においてもそうだったのです。
ヤハウェを唯一絶対の神として崇めているイスラエルの民は、常にバアルの「楽しい宗教」の攻勢にさらされていました。
イスラエルの民の国が豊かになると、バアルの攻勢は強まる傾向がありました。
逆に不景気になると、ヤハウェの信仰が強まるのです。
イスラエルの民の国家の最盛期は、ソロモン王の治世の時ですが、この時はかなりヤハウェ信仰の陰は薄くなり、バアル信仰が強まっていたのです。
ソロモンはバアルの信仰が広まることを黙認していましたが、何しろ国を豊かにしてくれた王様ですから、「旧約聖書」の執筆者はあんまりおおっぴらに悪口を書くわけにはいきません。
せいぜい「ソロモンは偉かったけど、その父ダビデほどではなかったよ」と書く程度の抵抗しかできなかったのです。
「旧約聖書」の行間を読むと、ダビデは徳川家康のように権謀術数大好きな食えないオヤジであったかのように思えてきます。
他方ソロモンはあけっぴろげであり、父ダビデよりは相当付き合いやすい人物であったように思われます。
またダビデはイスラエルの国の中のことにしか興味を持ちませんでしたが、ソロモンは中東地域全体の中でのイスラエル、ということを常に考えていたようで、政治家としても父よりスケールが大きかったように見えるのです。
脱線が過ぎました。エリヤの話に戻ります。
エリヤという人の性格を一言でまとめると「バアル絶対殺すマン」です。
西にバアルを称える人がいれば言ってさんざん罵声を浴びせ、東にバアル信仰を認める王がいれば、いって罵倒の限りを尽くす。そんな人物です。
このエリヤと激しく対立したのが、アハブ王の妻であったイゼベルでした。
国際派を標榜していたアハブ王ですので、その妻はフェニキアから娶った女性でした。
フェニキア人もまたバアルを信仰していた民族でしたから、イゼベルは実家の宗教であるバアル信仰をイスラエル王国にも広めようとします。
アハブとイゼベルの夫妻はバアルの祭壇を作り、また「アシラ」の像を作ったと言います。
これがエリヤの気に障りました。
「アシラ」はアーシラトのことだと思われます。
ウガリットではイルの妻とされていた官能的な女神で、エジプトのイシスと同じ起源を持つと言われています。
イル=ヤハウェなので、アハブはヤハウェの妻である女神の像を建てたことになります。
どこにヤハウェが怒る要素があったのでしょうか。ひょっとすると、ヤハウェは恐妻家だったのかも知れません。
それはともかく、エリヤはアハブ王のところに行くと、「わたしの言葉がないうちは、数年雨も露もないでしょう」と呪いの言葉を吐きます。
つまり邪教を信じているから、イスラエル王国に災いが及ぶぞ、と言ったのです。
エリヤが王に悪態をつくと、ヤハウェがエリヤに宿って言います。「逃げろ」と。
怒った王から危害を加えられるから、その前にトンズラしちゃえ、という意味です。
「カラスに養わせてやる」とも付け加えました。
エリヤは東に逃亡し、とある川のほとりに行きます。
すると一羽のカラスがエリヤに朝夕の食事を運んで来るようになったので、エリヤは生きながらえることができました。
ヤハウェの力がいかに偉大かを示す寓話なのでしょうが、「カラスに養われる男」というのはかなり惨めです。
やがて川の水が涸れてしまいます。
ヤハウェがまたエリヤの前に現れ、「シドンの街ザレパテに行け。ひとりの未亡人にお前を養わせてやろう」と言います。
エリヤはヤハウェの言うとおりにしました。
ザレパテの街の入口で、エリヤはたきぎを拾っていた女と出会います。
エリヤは彼女に「パンをくれ」と言います。
いくら神の指示とは言え、初対面の相手にいきなりこれかよ、という気がちょっとだけします。
女は、「わたしのうちには少しの粉と少しの油しかない。だからそれで子供とともに『最後の食事』をして、後は飢えて死ぬのを待とうと思っているのだ」という意味のことを言います。
それに対しエリヤは、「いいからパン作って持ってこい」と言いました。
「雨が降る時まで粉も油も尽きることはないから」。
言われた通り粉も油も付きなかったので、女とその家族とエリヤはしばらく食いつなぐことができました。
カラスよりはちょっとマシですが、貧乏な未亡人のヒモになるというのも、なかなか惨めな生活のように思えます。
しばらくすると、未亡人の息子が死んでしまいます。
栄養失調でしょうか、疫病でしょうか。
未亡人はエリヤに「あんたあたしに一体何の恨みがあるの? あんたはあたしの息子を死なせるために来たの?」と悪態とも愚痴ともつかない言葉を投げつけます。
「列王記」ではぼかされてますが、こう言うからには責任の一端がエリヤにあるような何かがあったのでしょう。
エリヤがヤハウェに祈ると、息子は生き返り、未亡人はエリヤが真の預言者であることを信じるようになったということです。
敵より先に味方を粛清する「クソコテ」エリヤの帰還
ネットスラングに「クソコテ」という言葉があります。
「コテ」は「コテハン=固定ハンドル」から来たものです。
匿名掲示板などで、固定のハンドル名を用い、他人から反感を買いまくる空気を読まない発言を繰り返すユーザーのことを、「クソコテ」と呼ぶのです。
そして「クソコテ」という言葉を知っている人が異口同音に語るのが「史上最大のクソコテはヤハウェとその預言者たちである」ということなのです。
旧約聖書にはこれまでも、モーセのように「クソコテ」と表し得る人物が登場してきました。
しかし数ある預言者の中でも、エリヤの「クソコテ度」は頭一つ抜けているように思われるのです。
エリヤがアハブ王に悪態をついて逃げてから三年が経過しました。
「時は来た」とばかりにエリヤはアハブ王の首都であるサマリアに出向きます。
久しぶりに会ったエリヤに、アハブ王はこう言いました。
「イスラエルを悩ますものよ。あなたはここにいるのですか」。
エリヤは相当王に嫌われていたようです。
エリヤは「俺が悪いんじゃなくて邪神バアルを信仰したお前の家が悪いのだ」と言い、さらに「バアルの預言者450人、アシラの預言者400人をカルメル山に集めろ」と要求します。
日照りが長く続いたので、雨乞いをしてどちらの神が真の神か決着をつけよう、ということらしいです。
バアルの預言者たちは牛を犠牲に捧げてバアルの名を呼びますが、何も起こりません。
エリヤが同じく牛を犠牲に捧げてヤハウェを呼ばわると、空から火の玉が降ってきました。
雨ではありません。火の玉です。傍から見れば嫌がらせ以外の何物にも見えません。
雨乞い勝負を見に来ていた民衆はびっくりして逃げ惑い、さらにひれ伏して「ヤハウェこそ真の神です」と震えながら言いました。
エリヤは「バアルの預言者たちを捕らえよ」と民衆に命じ、逮捕したバアルの預言者たちをキション川という川のほとりに連れて行って全員処刑してしまったのです。
雨乞い勝負でしたので、結局大雨が降るのですが、それはこの処刑が終わった後のことでした。
アハブ王はこのことを妻のイゼベルに告げます。
イゼベルは激怒しました。
アハブ王も激怒していいかと思われるのですが、「列王記」には王のリアクションについての記録はありません。
ただ、400人もの人間を私刑にかけたエリヤを即座に処刑したりしなかったあたり、感情を抑えて行動できるよい王様だったように思えます。
エリヤの背後には彼を預言者だと信じる民衆とヤハウェ祭司団がいます。
エリヤを処刑すると、彼らがどういう行動を起こすか、ということを考えたのでしょう。
ただ、放置することはできないので、バアル祭司団の保護者であった妻に告げたのだと思われます。
イゼベルは恐ろしいことをエリヤに言いました。
「神よ、もしわたしが明日の今頃までにエリヤをあの人々と同じ目に遭わせてなかったなら、わたしをいかようにでも罰してください」と。
エリヤに対する「絶対殺す」宣言です。
ただイゼベルもエリヤをその場で捕縛することはありませんでした。文明的なのか抜けているのか。
エリヤは逃走します。
実に四十日四十夜をかけて逃げ続け、「神の山」と呼ばれるホレブ山に至ります。
ホレブ山とは、モーセが神から十戒を受けたシナイ山のことで、アラビア半島とエジプトとを繋ぐシナイ半島の南部にあります。
エリヤがホレブ山の洞窟に隠れた時、ヤハウェが現れ「エリヤよ、あなたはここで何をしているのか」と呼びかけます。
エリヤは、「わたしは万軍の神、主のために非常に熱心でありました。イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇をこわし、刀をもってあなたの預言者たちを殺したのです。ただわたしだけ残りましたが、彼らはわたしの命を取ろうとしています」と被害者意識丸出しの返事をします。
バアルの預言者たち400人を大虐殺した結果王とその妻に憎まれて逃げてきた、というのが真実なのですが、そんなことは一言も言いません。
罪の意識を感じていないからでしょう。
ヤハウェはエリヤに対し、ダマスコのハザエル、ニムシの子イエフ、シャパテの子エリシャの頭に香油を注げ、と命じます。
そしてハザエルをシリアの王、イエフをイスラエルの王、エリシャをエリヤの後継者としろ、と言うのです。
シリアはイスラエルの民の土地ではないのですが、ヤハウェはしれっと「俺の土地」扱いしています。
さらにヤハウェは、「ハザエルの剣を逃れるものをイエフが殺し、イエフの剣を逃れるものをエリシャが殺すであろう」と物騒なことを告げます。
王や預言者を作るのは、有徳の人物を祝福してイスラエルの民に恩恵を及ぼすためではなく、殺すためだと言うのです。
ヤハウェはイスラエルの民を7000人だけ残し、残りを皆殺しにするつもりでした。
バアルの悪しき信仰に染まった、というのがその理由だそうです。
シリアやイスラエルの国王候補に香油を注ぎに行くのは難易度が高いので、エリヤはまずエリシャに会い、これを自分の弟子にしました。
実は名君だった? 「スケールの小さいソロモン」・北イスラエル王アハブ
預言者エリヤはその当時イスラエルを治めていたアハブ王の批判者として描かれています。
「列王記」ではアハブ王は北イスラエル王国最大の暴君とされているのですが、その実像は「列王記」に出てくるものとは微妙に違っているようです。
アハブについては、「旧約聖書」以外の記録も残されていて、その人となりや業績もある程度客観的にわかるのです。
ちなみに「歴代誌」はユダ王国に限定された年代記なので、アハブ王の事績についてはユダ王国と関係するもの以外スルーです。
先にも述べましたが、アハブは一言でいうと「スケールの小さなソロモン」でした。
大国エジプトが手を引いて群雄割拠状態になったシリア・パレスティナ地域で、小国北イスラエル王国の平和を維持し、繁栄させました。
北イスラエルは度重なる内ゲバで軍事力が疲弊していましたから、周囲の諸国を武力で屈服させることはできません。
傍から見れば多少卑屈に映っても、アハブは和を重んじ交易を行って自国の国力の充実を図ったのです。
当時のこの地域で最も有力だったのは、「ダマスコ」でした。
現在のシリア・アラブ共和国の首都ダマスカスを中心とする国家です。
アハブの妻イゼベルはダマスコの王女であったと言います。
「列王記」ではイゼベルはフェニキア人だとされていますが、いずれにしろ北イスラエルはダマスコを通じて地中海の海運を支配していたフェニキア人と交易をしていたので、イゼベルの出身地がどちらであってもその政治的立場は変わりません。
エジプトの脅威が去ったかに見えたシリア・パレスティナ地域ですが、別の脅威が迫っていました。
アッシリア帝国です。
シリア地域は木材(レバノン杉)の産地であり、なおかつエジプトへの交易路が通じています。
アッシリアはこれらを狙って南下してきたのです。
シリア・パレスティナ地域の諸国はアッシリアに対抗するため同盟を結び、紀元前853年に、カルカルという町の近郊でアッシリア軍と決戦を行います。
アッシリア側の記録によると、これはアッシリア軍の大勝利だったということにされています。
しかしその後アッシリアがさらに南下することはなく、ダマスコも北イスラエルも滅ぼされたりアッシリアの属国になったりしなかったため、少なくともアッシリアの侵略意図を挫くことはできたのでしょう。
しかしシリア・パレスティナ連合軍の方も無傷ではなく、特に連合軍の中核を形成したダマスコの被害は甚大だったものと思われます。
この戦いの結果、ダマスコと北イスラエルとのパワーバランスが微妙に崩れ、北イスラエルはユダ王国にそそのかされるような形でダマスコと戦い、返り討ちに遭ってアハブ王が戦死することになります。
ダマスコ侵略を決める会議では、アハブはかなり侵略に消極的でしたが、ユダ王国側やヤハウェ祭司団がノリノリであったように「列王記」には書かれています。
また、ヤハウェはこれを機にアハブを始末しようという気満々で、アハブの戦死が予定されている地にアハブをおびき寄せるために、ある預言者に偽りの神の言葉を語らせようとまでしました。
ちなみに「旧約聖書」では、「歴代誌」はもちろん「列王記」もカルカルの戦いには全く言及していません。
完全になかったことになっています。
アッシリアの征服から祖国を防衛したというのは王としては偉大な業績になるのですが、「旧約聖書」の作者たちは意地でもアハブが偉大な王であったということを認めたくなかったと見えます。
カルカルの戦いについては言及がありませんが、「列王記」「歴代誌」ともに、アハブ王が妻イゼベルとともにある人物を殺してそのぶどう畑を奪った、と国家存亡の危機からみれば小さな問題を長々と取り上げています。
そしてアハブ王の戦死はその報いだと言うのです。
イゼベルに至っては世界市場屈指の悪女というイメージを付与され、「新約聖書」の「ヨハネ黙示録」に、「大淫婦バビロン」という名で登場させられる始末でした。
本当に天に登ったのか? 預言者エリヤの昇天
アハブ王の死後、北イスラエルの王位は息子のアハズヤに受け継がれます。
アハズヤは「高殿のらんかん」から落ちて怪我をします。
なんらかの後遺症が残ったのでしょう。アハズヤは部下に、「この病気が治るかどうかエクロンの神バアル・ゼブブに聞いてこい」と命じます。
バアル・ゼブブはバアル神と同起源の神で、後に悪魔ベルゼブブとされます。
バアル・ゼブブの神殿に向かう部下たちの前に、みすぼらしい格好の男が出現します。
彼は「王はこのまま寝たきりになって死ぬぜ」と不吉なことを言って姿を消します。
部下たちが戻ってそのことを王に復命すると、王は「そのろくでもないことを言ったヤツはどんな風体だった?」と聞きます。
部下たちは、「毛皮の外套を着て、革の帯を締めていた」と答えました。
王は「そいつはエリヤだ!」と叫びます。
ろくでもないことしか言わない・しないクソコテがまた現れたのです。
アハズヤ王は役人50人と部下50人を派遣し、エリヤを逮捕しようとしますが、エリヤは「神の火」を使って100人を焼き殺してしまいます。
もう神の力をふるう預言者というよりは、邪悪な魔法で人に危害を加える暗黒魔道士といったノリです。
アハズヤ王はさらに役人50人に部下50人をつけてエリヤの元に送りましたが、こちらもエリヤに焼き殺されてしまいました。
「士師記」に出てくる怪力サムソンは、その生涯に数千人のペリシテ人を殺したとされていますが、エリヤもここまでにそれに勝るとも劣らない数を殺しているように思われます。
サムソンの場合、殺した相手は「異邦人」のペリシテ人ですが、エリヤの場合はバアルの預言者も混じっているとはいえすべて同胞のイスラエル人です。
結局、アハズヤ王はエリヤの予言通りに死んでしまった、と述べて、「列王記下」第一章は終わっています。
山もオチもなく、ただエリヤが「俺TUEEEE!」しているだけのように見えます。
そのエリヤですが、「列王記下」第二章でいきなり退場してしまいます。
弟子エリシャの目前で、つむじ風に乗って天に昇った、というのです。
あまりの急展開に目が点になりそうです。
唐突過ぎるので、「実際は誰かに暗殺されたのを『昇天した』と言い繕ったのではないか」とすら思えてきます。
エリヤはこれまでさんざん「同胞殺し」を重ねてきてさまざまな人々の恨みを買っていたと思われます。
「列王記」に出てくるエリヤの生涯の大部分は、誰かに憎まれて逃亡していた時期で占められています。
アハブ王は死んでいますが、その妻で「エリヤを必ず殺す」とバアル神に誓った前王妃イゼベルはまだ生きているので、疑惑はさらに深まるばかりです。
ただ、「エリヤの昇天」のくだりには、イゼベルのイの字も出てきません。
エリヤはくどくどとエリシャに「自分から離れるな」と言い、エリヤの支持者たちがエリシャに対し、「今日エリヤは昇天するが、そのことをエリヤに話してはならない」と複数回に渡って語っています。
エリシャはエリヤに「あなたの2倍の力を持つ後継者になりたい」と言い、エリヤは「自分の最後の瞬間を見なければ、そうならないよ」と答えています。
これらは、わかりづらい聖書独特の記述法で書かれているので、具体的にどういうことを意味しているのかよくわかりません。
しかし、ヤハウェの祭司団が、危険人物となったエリヤの排除を計画し、エリヤの後の指導者の座を餌にエリシャに師の殺害を命じた、と取れなくもありません。
エリヤが昇天した後、エリコにいたヤハウェの信者たちは、「50人を遣わして、エリヤを探させよう」と提案しますが、エリシャははじめこれを拒絶しています。
結局は押し切られてエリヤを捜索させたが見つからなかった、ということになっているのですが、これもかなり異様で、いろいろと勘ぐる余地があります。
「ナザレのイエス」の原型は彼? 「暗黒奇跡芸人」預言者エリシャ
かくしてエリシャは、空前絶後の「クソコテ」エリヤのあとを継ぎました。
エリシャは師エリヤ同様に、偶像崇拝を進めるバアル信者を罵倒しつつ、ヤハウェの信者を増やしていきます。
エリシャはその生涯にさまざまな奇跡を行っています。
その大部分は飲料である水を清めたり、食べ物を増やしたりといったものですが、病人を癒やしたり死者を蘇らせたりもしています。
後に出てくる「ナザレのイエス」のモデルになったかのようにも見えます。
イエスの「奇跡」は、彼が貧民の集団の中に入り、生活環境を向上させる活動を行ったことがベースになっているのではないか、と言われています。
この説が正しいのなら、エリシャも同じような活動を行い、その結果が「奇跡」とされたのではないかと推測することができます。
エリヤの時代から、「預言者」つまりヤハウェ教団の指導者は、俗世の権力者である王と激しく対立するようになりました。
全方位に喧嘩を売ったエリヤは逃げまくっていましたが、聖書の記述のように洞窟や森に隠れたり、未亡人やカラスのヒモになって暮らしていたのではなく、どこかの有力者に匿われていた、と考えた方が自然でしょう。
アハブやイゼベルがエリヤを捕縛しても即処刑することができなかったのは、こうした有力者に配慮したためではないか、とも考えられます。
しかしエリシャの時代になると、匿ってくれる有力者がいなくなり、「預言者」は民衆の中に入り込まなければならなくなったのではないでしょうか。
エリシャも性格はあまりよくなかったようです。
ある町で子どもたちがエリシャをあざけって「ハゲ!」と悪口を言いました。
子供の言うことですから無視すればいいのですが、エリシャは怒って呪いの言葉を口にします。
するとたちまち二頭の熊が出現し、子どもたちのうち42人を裂いて殺してしまったというのです。
師・エリヤ並みか、それ以上の残忍さです。
また、エリシャは完全に民衆の間に埋没してしまっていたわけではなく、軍人や貴族たちの間にもある程度の影響力を持っていたようです。
しかし、王の決定を左右するまでの力はありません。
王に自分の言うことを聞かせることはできないが、周囲の軍人や貴族ならなんとかなる、という人物が、さらに発言力を拡大しようと思った場合、どういう行動を取るでしょうか?
答えは「自分の息のかかった人物に謀反を起こさせ、その人物を王とする」です。
すでにエリヤの時代に、ヤハウェは「ダマスコの人ハザエル、ニムシの子イエフに香油を注いで王とせよ」と命じています。
エリヤは自分の後継者であるエリシャにだけ香油を注ぎ、他の二人についてはスルーしていたのですが、エリシャは二人に対して秘密の工作を進めたのです。
なお、聖書ではダマスコとか、シリアとか、アラムとかの表現があり、紛らわしくなっていますがだいたい同じ地域を意味しています。
シリアの王ベン・ハダド2世が病気になり、将軍ハザエルをダマスコに遣わし、たまたまそこに居たエリシャに王の病気が治るかどうか尋ねさせます。
エリシャは「王の病気は必ず治りますが、王は必ず死ぬでしょう」と一見矛盾するかのようなことを告げます。
さらに続けて、ハザエルは王になるだろう、とも言いました。
ハザエルは帰って王に「病は必ず治る」とエリシャが言っていた、と伝えますが、その翌日水で濡らした布を王の顔に被せ、王を殺害してしまいます。
そしてハザエル自身がシリアの王となりました。
このくだり、エリシャがハザエルをそそのかして王を暗殺させた、と読み取れます。
続いてエリシャはイエフに会い、「イエフを北イスラエル王国の王とする」というヤハウェの言葉を伝えます。
イエフはクーデーターを起こし、アハブ王の子ヨラム(アハズヤの弟)とその母イゼベルを殺して王位に就きます。
二つの国のクーデターの黒幕になるとか、この奇跡芸人かなり黒いです。
なお、ヨラム王が暗殺された時、そのすぐ隣にはユダ王国のアハズヤ王(アハブの子のアハズヤと同名ですが別人です)がいました。
アハズヤはとばっちりで重傷を負い、サマリヤに逃れましたがそこで死んでしまいます。
結果的に、この政変はユダ王国にも飛び火することになりました。
イエフは北イスラエル王国のバアル信仰を弾圧しましたから、「列王記」においては、北イスラエル王国随一の名君と称賛されています。
ただし、アハブ王の評価同様、「旧約聖書」の編纂者以外の目から見た場合、全く異なったものになるのです。
対アッシリア帝国大同盟を台無しにした「イエフのクーデター」
この時代、シリア・パレスティナ地域の小国たちにとって最大の脅威はアッシリアでした。
アハブ王はダマスコ王が提唱した、対アッシリア大同盟に参加し、カルカルの戦いでアッシリアの勢いをしばらく止めることに成功しました。
しかしカルカルの戦いの後、ダマスコと北イスラエルの関係が悪化し、小競り合いが起こります。
アハブ王は、紛争が拡大しないうちに丸く収めようとしたかに見えます。
しかし、それはエリシャとその支持者からすれば「屈辱外交」と思われるような内容だったでしょう。
「列王記」には、ダマスコ王が「俺のものは俺のもの、お前のものは俺のもの」とジャイアンのようなセリフを吐き、それについてアハブ王が「そうですね」と答えたと記録しています。
それでもなんとかアハブはダマスコとの外交関係を維持し、姻戚関係を使ってユダ王国もこの同盟に加えようとしていました。
エリシャが黒幕となって発生したダマスコ・北イスラエルでのクーデターは、対アッシリア大同盟を完全に破壊する結果を招きました。
同盟の象徴であった北イスラエル前王妃イゼベルをご丁寧にも虐殺していますから、もう同盟を回復することは不可能です。
アッシリア王シャルマネセル3世は、ハザエルのダマスコ王位継承を認めず、ダマスコを攻めます。
なお、アッシリアの記録では、ハザエルは前王ベン・ハダド2世の息子ということになっています。
アッシリアはダマスコを完全征服することはできませんでしたが、属国化することには成功したようです。
ついでに言うと、北イスラエル王国からも貢納を受け取るようになったので、北イスラエルもアッシリアの事実上の属国になったと思われます。
もちろん、「列王記」にはそんなこと一文字も書かれていません。
エリシャとその支持者たちからすれば、「邪悪なバアル信仰から祖国イスラエルを守り、正しいヤハウェの信仰に復帰させた」ということになるのでしょうが、客観的に見れば北イスラエルをアッシリアに売り渡す行為以外の何者でもありません。
ひょっとするとエリシャとその一党はアッシリアのスパイだったのでは? と思えるレベルです。
いずれにしろこの事件により、北イスラエルの「亡国」の運命は避けられないものとなりました。
北イスラエルの「名君」イエフ王による豊穣神バアル信仰の大弾圧
クーデターにより北イスラエルの王となったイエフは、恐らくその黒幕となったエリシャ一党とともに、北イスラエル国内の「大掃除」を始めます。
まず手を付けたのはアハブ王の遺児たちの虐殺でした。
アハブ王には全部で70人の子がいたとされています。
同じような政策を取っていたソロモンには及びませんが、なかなかの子沢山です。
彼らが認めたバアル・アシラ(アーシラト)・アナト・アスタルテらの神は皆豊穣神でしたから、王が数多くの子をもうけることを推奨していたのかも知れません。
少なくとも、ヤハウェのように性的なことにやかましい規制を設けていたということはなかったでしょう。
イエフはこの子どもたちをすべて殺してしまいます。
殺した子供たちの首を籠に入れて運び、ふたつの「山」にまとめたという、現代人からすればかなり不快な表現がされています。
続いてイエフは、「新王はアハブ王よりも熱心にバアルを信仰することにする。だから国内のバアル信者よ集まれ」と布告します。
やってきた人々をイエフはバアルの神殿に招き入れ、「バアルのための燔祭(ホロコースト・犠牲を捧げる祭り)」を行うようにと命じます。
彼らが祭礼を始めると、兵士を呼び集め、神殿の周りを包囲させ、バアル信者を皆殺しにしてしまいました。
ナチスドイツによるユダヤ人虐殺事件は、後に「ホロコースト」と呼ばれるようになりましたが、その原型は実はユダヤ人(イスラエル人)自身がバアル信者に対して行ったものだったのです。
虐殺事件の後、イエフは神殿の中にあったバアル神像を焼き、神殿を破壊して跡地をトイレにしてしまったと言います。
現代の公衆トイレのような清潔な施設ではありません。
手当り次第に糞尿を投げ込む、不衛生極まりないものだったでしょう。
さらにイエフは、サマリヤに向かう途中で出会ったユダ国王アハズヤの一族を皆殺しにしています。
ちなみに、ユダ王国の先王にはアハブの娘アタルヤが嫁いでおり、アハズヤはその子に当たります。
アタルヤを通じてバアル信仰がユダ王国にも流れ込んでいたので、イエフはこちらの根も絶ちたかったのでしょう。
かくして北イスラエル国内におけるバアル信仰は一掃された、と「列王記」は語っています。
イエフはヤハウェの「正しい信仰」に復するためにこれだけのことをしでかしたのですが、ヤハウェ信仰の派生版である「黄金の牛の像の礼拝」は続けました。
なのでヤハウェはイエフを手放しで祝福せず、「四代の間北イスラエルを支配させてやろう」と微妙にケチくさいことを言い出しました。
実際に、イエフの王朝はイエフの子から四代目の時にクーデーターによって滅ぼされます。
さて、アハズヤ王が亡くなってしまった後のユダ王国ですが、王の母であったアタルヤが女王として即位します。
イエフにより自分の親族を大量に殺されたアタルヤは、イエフとユダ王国の神官団および殺された自分の系列を除くユダ王族が繋がっていると考えました。
実際、エリシャを介して繋がっていそうなので、これは見当違いとは言い切れません。
というわけで、アタルヤは殺された自分の親族の報復とばかりに、ユダ王族の虐殺を始めます。
これにユダ国民は衝撃を受けました。
というのは、ヤハウェの信者の間には、「メシア(救世主)はダビデの家系から現れる」という伝承があったからです。
ユダ王国の王家はダビデの直系であり、これを滅ぼすということは、メシアの出現を阻害する悪魔の所業と考えられました。
アタルヤは、唯一残ったユダ王家の生き残り(アタルヤの息子でした)を擁立した大祭司エホヤダによって殺されてしまいます。
ユダ王国の王位は、その生き残りの子ヨアシュに受け継がれます。
ヨアシュはバアル神殿の破壊などの「善行」を積みましたが、後ろ盾となっていた大祭司エホヤダの死後はアシラ(アーシラト)信仰に傾いたため、これまた暗殺されてしまいます。
北イスラエル最後の繁栄期と消えた10部族
預言者エリシャはアハブ王が築き上げた「対アッシリア大同盟」を台無しにしてしまったのですが、皮肉なことに北イスラエル王国はエリシャが裏で糸を引いて成立させたイエフ朝の時代に繁栄期を迎えます。
エリシャはイエフ王の孫のヨアシュ王の治世中に死ぬのですが、死ぬ間際まで「アラム(=ダマスコ)を討ってその領土を奪え」と王に言い続けました。
この政策がうまく行ったのです。まぐれ当たりみたいなものですが。
先に、大同盟が崩壊した機を逃さず、アッシリアはダマスコを属国化することに成功した、と書きました。
北イスラエルも同様に属国化していたのですが、経済的・戦略的価値はダマスコの方が高く、アッシリアはこちらの支配を重視したのです。
アッシリアはダマスコに重税を課し、その国力を奪いました。
北イスラエルもアッシリアに貢納を送っていましたが、ダマスコに課せられた税ほど負担は重くなかったのです。
ついでに、国内のバアル信者、つまり国際協調派の大粛清を行って、国論がまとまってきました。
「侵略上等!異教徒は皆殺しだぜヒャッハー!」という気分で統一された北イスラエル国民は、哀れなダマスコに襲いかかったのです。
北イスラエル王国イエフ朝の「繁栄」はこうして築かれたものでした。
領土こそソロモンの治世と同等以上まで広がりましたが、偶然起きた国際的なパワーバランスの一時的な変化に乗じて弱いものいじめをした結果ですから、あんまり長続きしそうにありません。
その反動は確実に現れました。
イエフ王朝が終了した後、北イスラエル王国には5人の王が立ちますが、そのうち3人が暗殺されています。
性状不安定なんてものではありません。めちゃくちゃです。
イエフ朝の時代に、北イスラエルはダマスコを制圧し、地中海沿岸部まで領土を広げたのですが、結局のところそれは、アッシリアという虎の威を借りた結果に過ぎません。
北イスラエルが大きくなったと見たアッシリアは、今度は北イスラエルに対する支配を強化しようとします。
具体的には貢納の増額ということで、北イスラエル内ではアッシリアの強圧的な支配に反対する派閥が生まれ、これが時の王を暗殺するようになったのです。
先王を暗殺して権力を握った新王も、すぐにアッシリアに屈してしまうので、また別の反アッシリア派に暗殺されるという暗黒ループが始まりました。
先に、イエフ朝の後の王5人のうち3人が暗殺された、と書きました。
殺されなかったのは2名だけなのですが、そのうちの一人である最後の王ホセアはアッシリア王ティグラト・ピレセル3世の家臣です。
彼はティグラト・ピレセル死後にアッシリア本国が混乱したので、貢納を停止したら本国軍が攻めてきたので降伏した、という人物でした。
まもなくアッシリア本国では英主サルゴン2世が即位し、その移民政策により北イスラエル王国の地は完全にアッシリアの属州にされ、住民は残らずペルシア方面に移住させられます。
北イスラエルを構成していた10部族は、移住先の民族と同化して消滅してしまいました。
これがいわゆる「消えた10部族」の実態です。
この強制移住についての記録が、サルゴン王が残した碑文に書かれています。
これによると、ペルシア方面に連れて行かれたのは2万8000人ほどで、北イスラエル全住民の5%程度だったそうです。
逆算すると、60万弱の住民が残ったことになります。
ただ、やかましくヤハウェへの服従を説いていた人々は残らず移住の対象となっているので、残った人たちは誰に気兼ねすることもなく好きな神を信仰することになり、それぞれの信仰コミュニティに同化していったのでしょう。
10部族が「消える」のはあっという間でした。
オカルト系の書物などでは、アッシリアが北イスラエルを攻撃した際に、10部族は全世界に逃げ散った、などとされています。
「消えた10部族」については、現在のイスラエル政府が真面目にその行方を追っています。
日本でも多くの人が「与太話」扱いしている、「消えた10部族の一部が日本に来た。渡来人の秦氏はその子孫だ」という説は、イスラエルの政府機関が有力だと考えた4つの仮説のうちの一つだと言われます。
バビロニアに滅ぼされるユダ王国とバビロン捕囚
北イスラエル王国が完全にアッシリアに征服される少し前、ユダ王国もアッシリアの属国になります。
ただ、北イスラエル王国最後の王ホセアとほぼ同時期に王位にあったヒゼキヤ王は、バアル信仰を排斥し、ヤハウェ信仰を盛り立てようとしています。
ヒゼキヤ王の即位後数年は、アッシリアは北イスラエル王国にかかりきりだったようで、ヒゼキヤ王の反アッシリア政策はあまり問題視されていたようではありませんでした。
「列王記」の作者は、このことをもってヒゼキヤ王を、ユダ王国最大の名君と讃えています。
ヒゼキヤ王の在位14年めに、アッシリアはユダ王国に攻め寄せます。
ヒゼキヤ王が反アッシリア政策を取ったのは、エジプトを後ろ盾にしていたからのようです。
しかしユダ王国の首都イェルサレムを包囲したアッシリア王センナケリブは「エジプトなんぞ頼みにしても無駄だぞ」とヒゼキヤを脅迫します。
ヒゼキヤ王は莫大な貢納をアッシリア王に捧げたのですが、アッシリアはイェルサレムの包囲を解きません。
ここに出てくるのが「預言者イザヤ」です。
イザヤは「イザヤ書」の作者兼メイン登場人物として知られています。
「イザヤ書」は「エレミア書」や「エゼキエル書」と並んで「3大預言書」と言われますが、信心の足りない人間が読むと、何が書いてあるのかわかりません。
なんだかよくわからないけれど、作者が何かを警戒し、憎悪しつつ不吉なことを呟いていることだけはわかります。
「エレミヤ書」「エゼキエル書」もだいたい同じようなものですが、後の時代のものになると、読者に対して「悔い改めろ」「大きな災厄がまもなく来る」と訴えかける傾向が強くなります。
「大きな災厄」というのは、この場合イスラエルの民の国が外国勢力に滅ぼされ、住民がどこかに連れ去られることです。
その災厄から逃れるために、ヤハウェの信仰を盛り立てよ、というのが、預言書の主な主張です。
この「災厄」は、後の時代になるとアッシリアなどの他国による征服ではなく、神の怒りによるこの世の終わり、という内容に変わっていきます。
この段階に至ると、「悔い改め」を求める書物は、「預言書」ではなく「黙示文学」と呼ばれるようになるのです。
「預言書」の内容がわかりにくいのは、その表現形式が「黙示文学」のそれの原型のような形になっているためです。
このような理由で、自分の名前を冠した書物がある割に、イザヤという人はどういう生涯を辿った人物なのかわかりません。
「イザヤ書」によれば、神の命で三年間全裸で生活した後、イェルサレムがアッシリア軍に囲まれ、ヒゼキヤ王の相談を受けることになります。
「列王記」では全裸生活については言及されておらず、いきなりヒゼキヤ王のところに現れます。
ちなみに全裸生活の理由ですが、「エジプト人はやがて侵略されてこのように丸裸にされるのだ」ということを示すためにヤハウェに「やれ」と言われたせいだったと「イザヤ書」には書かれていますが、どうもよくわかりません。しかし「趣味」ではなかったでしょう。
イザヤは「アッシリア軍はイェルサレムを占領することなく引き揚げる」と王に語ります。
史実として本当にアッシリア軍は引き揚げたので、その点が歴史学上の謎のひとつとなっているのですが、「列王記」では、イザヤが「神の御使い」を呼び寄せてアッシリア軍18万5000人を撃ち殺したためだ、となっています。
預言の通りにアッシリア軍が引き揚げたので、イザヤの株は上がったようです。
アッシリア軍が引き揚げた後、ヒゼキヤ王は病気(腫物のようです)にかかって死にかけます。
イザヤに相談すると「あなたは死にます」とそっけない返事が返ってきました。
ヒゼキヤ王が泣いて悲しんだので、ヤハウェはイザヤを通じ「ならあと15年の寿命をやる」と告げます。
とりあえず死を免れたヒゼキヤ王の元に、東方の小国の使節がやってきます。
どこから来たのか、と問うと「バビロニア」と答えました。
ヒゼキヤ王は喜んでこの使節に宝物庫の中の財宝を見せてしまいました。
後でにこにこしながらヒゼキヤ王はイザヤに「今日こういうことがあったんだ」と語りましたが、イザヤは渋い顔をして「その財宝後で全部バビロニアに持っていかれますよ」と不吉な預言をします。
この当時のバビロニアは、アッシリア帝国の支配下にありました。
ですが、アッシリアで王位継承の争いがあって(困ったことにほとんどの王の死後に発生しています)統制が緩むと、すぐに叛乱を起こしていたのです。
バビロニアはその後どんどん勢力を拡大し、アッシリアを圧倒していきます。
ユダ王国では、「善王」ヒゼキヤが死んだ後、「悪王」マナセが即位します。
実はこの王位継承が行われた頃、アッシリアのアッシュールバニパル王はユダ王国と同盟していたエジプトに攻め込み、これを占領してしまったのです。
遠征後エジプトにはアッシリアの息のかかった王朝(第26王朝)が成立します。
ちなみにこのあたりの経緯は、「列王記」にも「歴代誌」にも一言も記されていません。
マナセの「悪事(≒バアル信仰への回帰)」は、エジプトを後ろ盾にした父ヒゼキヤの挑発がアッシリアを怒らせ、ガチの侵略を引き寄せた結果だということになります。
アッシリアにとって好ましからぬ人物であるイザヤを、マナセは処刑しましたが、マナセ自身もアッシリアに拉致されてしまいました。
マナセはアッシリアで悔い改め、神に対して許しを乞うた文章が「マナセの祈り」と名付けられ残されています。
「マナセの祈り」はカトリックでは外典扱いですが、正教会では聖典とされています。
強勢を誇ったアッシリアも、アッシュールバニパル王の死後急速に衰退していきます。
アッシリアの支配が緩んだので、ユダ王国ではまたヤハウェ信仰が強化されました。
国際情勢は刻々と変化します。
紀元前612年、アッシリアの首都ニネヴェは、バビロニア・メディア・スキタイ連合軍によって占領されます。
首都を逃げ出したアッシリアの残党は、エジプトと組んで失地回復を狙います。
エジプト第26王朝のファラオは、アッシリアの「舎弟」同然だったからです。
ファラオ・ネコ2世はアッシリア軍と合流するために軍を率いて北上しました。
ところがそこに空気を読まずに立ちふさがったのが、ユダ王国のヨシヤ王です。
ユダ王国軍とエジプト軍はメギドという土地で激突し、ユダ王国軍は惨敗。ヨシヤ王は戦死します。
ユダ王国は特にバビロニアと親しい関係であったわけではないので、これは完全に犬死でした。
それどころかメギドの敗戦でユダ王国はエジプトの支配下となったので、バビロニアから敵視されるようになってしまったのです。
ちなみにユダ王国軍を粉砕した後、エジプト・アッシリア連合軍はカルケミシュでバビロニア・メディア・スキタイ連合軍と激突しますが惨敗してしまいます。
この戦いにより中東世界におけるバビロニアの覇権が確立しました。
ユダ王国は今度はバビロニアの従属国になりましたが、バビロニアに反逆したためネブカドネザル2世の侵攻を受け、王と住民をバビロニアの首都バビロンに連れ去られてしまいます。
その後もしばらく独自の王を立てていましたが、またもバビロニアに反逆したため、再びイェルサレムは陥落、最後の王ゼテキヤは目前で子供を殺された後両目をえぐられ、死ぬまで鎖に繋がれたといいます。
ネブカドネザルにすれば、前の遠征の時に独自の王を立てることを認めるという恩恵を施したのに、性懲りもなく反逆したので見せしめにした、ということでしょう。






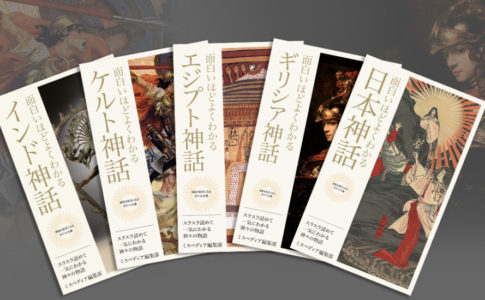


































コメントを残す