Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。
フィンランド神話は、現在のフィンランドに住んでいる人々のうち、比較的南部に住んでいる人たち(フィン人またはスオミ人)によって語り継がれてきた神話です。
個々の神話を語る前に、まずフィンランドに住む人たちについて解説しましょう。
Contents
フィンランドに住む人々
フィンランドはスカンディナヴィア半島の東側にある国です。
日本ではノキアの精密機器や、ミカ・ハッキネンのようなF1ドライバー、シモ・ヘイヘのような軍人が、マニアックな人々の間に知られています。
「ムーミン」も有名ですが、実をいうとあの作品はスウェーデン系フィンランド人がスウェーデン語で書いたもので、フィンランドのもともとの神話伝説とはあまり関係がありません。
「フィンランドに住んでいる人たちは、実はアジア人なのだ」という話がある程度広まってしまっていますが、これは間違いです。
フィンランドから来た、という人と会った人は少ないと思いますが、彼らはしばしば金髪であり、青い目をしています。
つまり典型的な白人、いわゆるコーカソイドです。
では、どうして「フィンランド人はアジア人」という話が広まったのでしょう。
彼らは身体の形質はごく普通の「白人」です。
しかし、話す言葉がいわゆる「インド・ヨーロッパ語族」に属するものではないのです。
フィンランドに比較的多く住んでいる人たち(フィン人)や、近隣諸国に住んでいる祖先を共通にする人々の言葉は、ウラル語族に属します。
ハンガリーに住んでいるマジャール人の話す言葉も、この系統です。
ウラル語族は、かつてテュルク語・モンゴル語・ツングース語などが属するアルタイ語族と一緒にされ、「ウラル・アルタイ語族」と呼ばれていました。
アルタイ語族を話す人々は、中央アジアから極東アジアにかけて広く分布しています。
これと根っこが一緒ということで「フィンランド人はアジア人」と誤解されるようになったものと思われます。
ちなみに、われわれが話している日本語は、これをアルタイ語族の一派とする説もあります。
しかし、あくまで仮説レベルに過ぎず、確実にそうだと証明されたわけではありません。
ただ、日本語はアルタイ語族の一派である、という説が強くなった時期があります。
そのタイミングに「フィンランド人まで自分たちの仲間だ」とする主張が広まったと思われます。
「日本人の親戚」のような俗説を排除して、はっきりしていることだけを述べると、
「フィンランド人は、フィンランドを中心とした北部ヨーロッパに住んでいる、インド・ヨーロッパ語族とは異なる系列の言語を話している人々」
ということになります。
周囲の神話からの影響と「カレワラ」
神話、特にインド・ヨーロッパ語族のそれは、現在の居住地が遠く離れていても共通の要素を保っています。
例えば、インド神話のインドラと、北欧神話のトールは同じ起源を持っている、と考えられています。
ギリシア神話の神々も、共通する要素を持っている神々を、インドやイランの神話の中に見出すことができます。
フィンランドの場合、言葉の系列が違うので、神話もまたインド・ヨーロッパ語族の神話からは独立しています。とりあえず。
とりあえず、となってしまうのは、フィンランドの人々は、長い年月をインド・ヨーロッパ語族の人々と交流しつつ生活していたため、外部の文化の影響も受けてしまっているからです。
特に強い影響を与えたのは、キリスト教でした。
フィンランドは12世紀から19世紀までスウェーデンの支配下にあり、19世紀から20世紀始めまでロシアの影響下にありました。
フィンランドを征服した当時のスウェーデンは、すでにキリスト教を受け入れていました。
フィンランド征服は「十字軍」という名目で行われたのです。
この結果、住民の間にはキリスト教が広まったのですが、彼らは古くからの信仰もそのまま保持していました。
フィンランドの神話をまとめた書物としては、「カレワラ」が有名です。

多くの人が、「カレワラ」はフィンランドの古事記や日本書紀に相当する書物だと思っているのではないでしょうか。
しかし、「カレワラ」の成立は古事記や日本書紀ほど古くはないのです。
「カレワラ」は19世紀にリョンロットというお医者さんの手によってまとめられました。
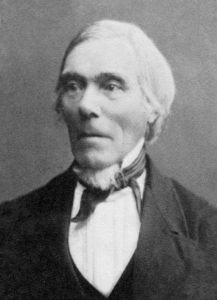
リョンロットは、各地に残っていた神話伝承をきちんと取材した上で一つの書物にまとめました。
しかし、その編纂姿勢は歴史家や民俗学者のようなものではなく、文学者・詩人としてのものだったのです。
つまり、複数の神話伝承を比較してどれがより古くオリジナルの形態を残しているか、ということを吟味したわけではありません。
それよりも、読み物としての面白さを第一に考えていたのです。
リョンロットは、集めた神話伝承を一つの大きなお話としてまとめ上げるために、部分的な改変を行っています。
その中には、キリスト教的な教養に基づいて修正された部分もあります。
この編集作業によって、「カレワラ」は優れた文学作品となりましたが、同時にフィンランド神話の原典と呼ぶにはふさわしくないものになってしまってもいるのです。
ただし、非常によくまとまっているので、ここでは「カレワラ」に準拠してフィンランドの神話を語っていくことにします。
神々と英雄
フィンランド神話がキリスト教に完全に駆逐されず、細々ながら生き残ったのには、理由があります。
ひとつはフィンランドの人々が話している言葉の系列が周囲とは異なっており、支配者からすれば何を話しているのかわかりにくかったからです。
もうひとつは、フィンランドの神話においては明確な「神」の概念は薄く、「神話」に登場するキャラクターの大部分は、神ではなく「英雄」であるとみなされていた、ということです。
日本神話でいうと海幸彦やヤマトタケル、ギリシア神話でいうとヘラクレスやオデュッセウスのようなキャラクターがメインだったのです。
そういう郷土の英雄がいた、ということは、キリスト教の神の存在を否定することには繋がりません。
このため、フィンランドの神話は生き残ることができたのです。
英雄たちが中心だとはいえ、明確に「神」とされるものは存在しました。
その神は、「ウッコ」と呼ばれます。
ウッコはフィン語での「雷」を意味する単語と共通の語源を持っており、雷神かつ天空神であったと考えられています。

ただし、同じ雷神でも北欧のトールやインドのインドラなどと共通の原型を持っていたわけではありません。
両者で雷神・天空神が最高神となったのは、偶然の一致というか、どこにおいても雷は最も恐るべき自然現象であったからでしょう。
ウッコはバルト地域のペールコンスと起源を同じくすると言われています。
ペールコンスは名前からロシア神話の主神ペルーンと関係があるのではないか、とも言われます。
ロシアというのがまた神話的にはややこしい土地です。
居住していたのはスラヴ人なのですが、後からいわゆるヴァイキング(ヴァリャーギ)が押し寄せ、キエフやノヴゴロドなどの都市国家を建設します。
この結果スラヴの信仰は北欧神話の影響を受けるようになりました。
これにより、「ペルーンのトール化」が進んだのです。
この変化がペールコンスに波及し、さらにウッコにまで及んだとするのなら、文献に記録されるようになった時代のウッコの性格が、トールとよく似たものになったのも理解できます。
ウッコはもともと雷の力を象徴する「ウコンパサラ」と呼ばれる石斧を武器として持っていました。
ウッコの祝福を受けるため、フィンランドの人々はウコンパサラをペンダントなどにして身につけていたのです。
このウコンパサラ、古い時代のものは石斧風のデザインですが、時代が下るに従ってミョルニル、つまりトールの持つハンマーに似たデザインに変わっていきます。

「カレワラ」におけるウッコは、ほとんど活動せず、「英雄」とされたものたちから崇められ、讃えられるだけの存在となっていました。
しかし、もともとは世界の創造者と考えられていたようです。
創造者でもある最高神は、キリスト教の神の概念と衝突します。
このため、ウッコは不活性化し、ウッコのものとされていた各種の創造行為は、別のキャラクターのものとされました。
ウッコの創造関係の仕事を引き継いだのは、鍛冶屋のイルマリネンです。
イルマリネンは、世界の豊かさを実現する重要アイテムである「サンポ」の鍛造者とされています。
「サンポ」が具体的にどういうものであったのか、詳細はわからなくなってしまったのですが、とにかくそれがあるだけで極北の地も地上の天国に変わってしまうような凄まじい能力を持っているとされました。
こんなものを作るのは、普通創造神・最高神の仕事です。
他にもイルマリネンはさまざまな魔法のアイテムを、自分の鍛冶場から生み出していきます。
しかし彼はもう最高神ではなく単なる鍛冶屋ですから、キリスト教が普及しても「異教の神」として排斥されることはなくなったのです。
ちなみにウッコの方は不活性化されているので、「キリスト教世界でいうヤハウェのことをフィン語ではウッコと呼ぶのだ」と説明できてしまいました。
この結果、崇められ讃えられるだけの存在として、こちらも生き残れたのです。
フィンランドのもともとの神話においては、別の系列の創造神・最高神がいました。ワイナミョイネンです。
ウッコ=イルマリネンが雷神・天空神であるのとは対象的に、ワイナミョイネンは水の神であったと考えられています。
ワイナミョイネンについては、リョンロットが「カレワラ」を編集する時にその性格を大きく変え、神的な部分を極力薄めてしまいました。
リョンロット自身がワイナミョイネンを神ではなく、古代に存在した実在の人物をモデルにした英雄だと考えたためです。
オリジナル(に近いと思われる)神話では、ワイナミョイネンは原初の海を漂っており、やがてその膝に一羽の鳥が卵を産み付けます。
卵は波に打たれて割れてしまいますが、その黄身が太陽になり、割れた破片から天空と万物が生み出された、というのです。
しかし「カレワラ」においてリョンロットは、ワイナミョイネンの母としてイルマタルという女神を作り出し、天地創造の仕事をイルマタルのしたことに移してしまいました。

イルマタルのモデルになったのはキリスト教の聖母マリアです。
マリアを挿入することにより、ウッコとイルマタルの関係性が作られ、本来別々だったと思われるイルマリネン(ウッコ)系の創造神話と、ワイナミョイネン系の創造神話がひとつに接ぎ合わされたのです。
ちなみに「カレワラ」には収録されていない別の伝承においては、ワイナミョイネンとイルマリネンは兄弟だということにされています。
イルマリネンが創造神としての性格以外に鍛冶屋としての性格を持つように、ワイナミョイネンも創造神以外に「偉大なる魔法使いにして詩人」という性格があります。
北欧神話でいえばオーディンの持つ性格と共通しますが、両者の起源は同じではありません。
これも偶然の一致または相互に影響を与えあった結果でしょう。
ワイナミョイネンは生まれた時から老人であったとされます。
このため外見的なイメージも、北欧神話の主神オーディンや、トールキン作「指輪物語」のガンダルフと被ります。

若者と老人の対立?
「カレワラ」に収録されているフィンランド神話では、ワイナミョイネンとイルマリネンが二大強キャラです。
しかし片方はジジイであり、もう片方ははっきりとした年齢描写はありませんが、全体的なイメージからすると中年以降です。
なんだか加齢臭が漂ってきそうだなあ、と思わないでください。ちゃんと若者も登場します。
「カレワラ」に登場する若者キャラクターの筆頭はレンミンカイネンです。
別名を「端麗なカウコミエリ」と言いますからイケメンです。
武芸もかなりの腕ですし、魔法も使えます。
ただ性格にちょっと、というかかなり難があります。
非常にムラ気で自己中であり、なおかつ女好きなのです。
このため、あちこちで騒動を引き起こします。
レンミンカイネンは、多くの神話に登場する「トリックスター」に属する英雄なのではなかろうかと思われます。
キャラ的には、もともとが堂々たる神であったワイナミョイネンやイルマリネンよりちょっと下です。
しかし、「人間の代表」として時にはこの二大キャラと対等に渡りあうこともあるのです。
なお、「カレワラ」では、話に整合性を持たせるために、本来別々だった伝承や歌謡の主役をレンミンカイネンにまとめてしまっている部分があります。
にも関わらず性格が分裂しなかったのは、もともとが「ムラ気」であるとされていたためでしょう。
若者キャラその二は、ヨウカハイネンです。
基本的な性格はレンミンカイネンと似ていますが、実力はずっと下で、ワイナミョイネンにあっさり負かされてしまいます。
三人目はクッレルヴォです。
こちらは、他地域の神話等に類例がない非常に特異なキャラクターです。
一言でいうと、「ついてない君」なのです。
力も知恵も優れているため、間違いなく「英雄」なのですが、一般的な英雄(たとえばヘラクレス)のように「功業」をなし遂げることがありません。
ただひたすら、自分自身の巨大な力に振り回され、破滅していくだけの生涯を送ってしまうのです。
クッレルヴォがいかについていなかったのかについては、後で改めてご紹介します。
「カレワラ」における魔法
「カレワラ」には、「神」とされるものはウッコなどごく少数しか登場しません。
しかもそれらはたいてい祈りを捧げられるだけの存在で、自分自身が神話の中で活動することはほとんどありません。
その代わりに「英雄」が活躍するというのは、すでに書いた通りです。
この英雄たちは、実に数多くの魔法を使いこなします。
その魔法は、大きく分けるとそれぞれの家に伝わっている一子相伝型と、あるものの起源を突き止め、それを自分の自由にできるようにする、というタイプの二種類になるのです。
どちらかと言うと一子相伝型はレベルの低い魔法で、起源を語る魔法の方が高級であるような記述がされています。
一子相伝型の場合、うかつな人物(だいたいレンミンカイネン)が不勉強で自分の家に伝わる魔法をすべてマスターしておらず、危機に陥るというパターンがよく見られます。
起源を語る魔法は、ほぼワイナミョイネンの独占物です。
彼はさまざまなものの起源や真の名前を知っており、それによって強大な力をふるうことができるとされています。
ある時、ワイナミョイネンは斧で自分の膝を傷つけてしまいます。
応急処置をしましたが、血は止まりません。
そこで彼は斧の刃となっている鉄の起源についての歌を歌い、強力な血止めの軟膏を作り上げます。
鉄の本質についてすべてを明らかにしているので、鉄によって作られた傷に対し、絶対的な効果を持つ、というのがその理屈です。
しかし、大賢者ワイナミョイネンでも時にその起源がわからないものがあり、「カレワラ」には秘密を求めて彼が各所に出向くエピソードが数多く収録されています。
ロールプレイングゲームにおける、サブイベントの元祖のようなものだと考えればいいでしょう。
ものの起源や真の名前を突き止めて支配する、という魔法のスタイルは、「指輪物語」や「ゲド戦記」などにも影響を与えているように思われます。
乙女アイノの話
ワイナミョイネンは偉大な詩人として、その名を広く知られていました。
元は神様だったのですから、まあ当然といえるでしょう。
その名声を聞きつけたヨウカハイネンは、無謀にもワイナミョイネンに挑戦しようと考えます。
ワイナミョイネンは大人ですから、ひと目でヨウカハイネンが自分に対抗できるだけの実力を持っていないことを見抜き、諭して帰そうとします。
しかし、ヨウカハイネンはそのことで逆に機嫌を損ねます。
いかに自分が優れた魔法使いであるか、覚えている魔法の歌のタイトルを並べ始めました。
ワイナミョイネンはそれを子供の知識だとあざ笑い、本当の魔法を見せてやるとばかりに詠唱を開始します。
するとヨウカハイネンの体は地面に埋め込まれてしまいました。
さっきまでの巨大な態度はどこへやら、このままでは殺されると思ったヨウカハイネンはワイナミョイネンに命乞いを始めます。
しかし、武具をやる、馬をやると言われてもワイナミョイネンは眉一つ動かしません。
最後にヨウカハイネンは「妹のアイノをやる!」と叫んでしまいました。
ワイナミョイネンは「不滅の賢者」なのですが、ただ一つだけ欠点がありました。
それは「女好き」だということです。
妹をもらえる、と聞いて態度を変えたワイナミョイネンはヨウカハイネンを解放します。
若者は「とんでもない約束をしてしまった…」と後悔しつつも、家に逃げ帰るのでした。
ヨウカハイネンを迎え入れた両親は、不滅の賢者が娘をもらってくれるというので狂喜します。
ですが、当の妹アイノは暗い顔で黙り込んでしまいました。
先に、ワイナミョイネンには「女好き」という欠点があると言いました。
しかし、実はさらに追加で1つ、欠点があります。
それは、「ワイナミョイネンはモテない」ということです。まあ、ジジイですから。
ノリノリの両親が、ワイナミョイネンの嫁になればどんなにいい生活が送れるかと説得します。
しかし、アイノは下を向いたきりです。
母親は暗い顔のアイノに花嫁衣装を着せて送り出すのですが、アイノは浜辺でそれを脱ぎ、海に身を投げてしまいます。

アイノが死んだと聞いて、ワイナミョイネンも嘆き悲しみ、アイノが身を投げた海へ船を漕ぎ出します。
そこで釣りを始めたワイナミョイネンは、やがて不思議な魚を釣り上げます。
ワイナミョイネンが釣った魚を料理しようとナイフを取り出すと、魚は「食べられるのではなく、妻になりにきたのに」と言って逃げてしまいました。
魚はアイノの生まれ変わりだったのです。
「あんたのことなんて好きでもなんでもないんだからね」と言いつつ自殺までしたのに、生まれ変わってから「嫁になりに来た」とは、凄まじいツンデレもあったものです。
それはともかく、しまったと思ったワイナミョイネンは、網を持ち出し海中を引き回してアイノを再び捕らえようとします。
しかし、乙女はとうとう捕まりませんでした。
かくしてアイノに決定的にフラれたワイナミョイネンは、母親にどうすればいいかを尋ねます。
すると母は、「あんなのよりもいい娘がいるから、ポホヨラに嫁取りに行きなさい」と言ったといいます。
ワイナミョイネンのポホヨラ行き
ポホヨラというのは、フィンランド神話に出てくる実在しない地名で、「北の国」という意味です。
フィンランドの属するスカンジナビア半島北部は、サーミ人(ラップ人)の住む土地で、ラップランドと呼ばれます。
ポホヨラは漠然と、このラップランドを意味すると考えればいいのでしょう。
このポホヨラの女主人はロウヒという名前でした。
「カレワラ」ではロウヒは強大な力を持つ魔女とされますが、これも元は神だったのでしょう。
ちなみにポホヨラと対になる、ワイナミョイネンたちの故郷が「カレワラ」です。
これは「英雄の土地」という意味になります。
ロウヒには名前の伝わっていない娘がいました。
これがものすごい美人で、大勢の英雄たちが「自分の嫁に」とポホヨラに押しかけてきていたようです。
さて、母親から「ポホヨラの娘を嫁にしてこい」と言われたワイナミョイネンは、さっそく旅立つのですが、森を通過しているところを隠れていたヨウカハイネンの弓で射られてしまいます。

ワイナミョイネンは海に転落しますが、大鷲に助けられてポホヨラの浜辺に打ち上げられます。
そこで大声をあげて泣いていると、ロウヒがそれを聞きつけてやってきました。
ロウヒは泣いている老人がワイナミョイネンであることに気づき、自分の家に連れ込んで歓待します。
しかし、ワイナミョイネンは故郷に帰りたいと、そればかりを繰り返します。
ロウヒの娘をお嫁さんとしてゲットしようとしていたはずなので、行動が一貫しませんが、そこらはもともと独立していた伝承をリョンロット先生が組み合わせてひとつにしてしまった名残でしょう。
泣いているワイナミョイネンに、ロウヒは「自分にサンポを作ってくれるのなら、故郷に返してやるし、娘もやろう」と言います。
ワイナミョイネンは「サンポを作るにはイルマリネンの助力がいる」と言い、イルマリネンを連れてくることを約束します。
サンポの鍛造
カレワラに帰ったワイナミョイネンは、まず魔法の歌を歌って巨大な木を生やし、枝に太陽や月を引っ掛けておきました。
しかる後にイルマリネンの所に行き、「ポホヨラに行ってサンポを作ってくれ」と頼みますが、イルマリネンは拒否します。
そこでワイナミョイネンはイルマリネンを騙して先程生やした木のところに行き、「枝に太陽や月がかかっているから確かめてこい」と言って登らせようとします。
イルマリネンが登ろうとすると木が「これはワイナミョイネンの悪巧みだ、登ってはいけない」と警告します。
イルマリネンははっとなりましたが、すかさずワイナミョイネンは魔法の歌を歌い、木ごとイルマリネンを風で吹き飛ばしてしまいました。
吹き飛ばされたイルマリネンは、都合よく(ワイナミョイネンの計画通り?)ポホヨラのロウヒの家の前に落下します。
ロウヒは空から降ってきた客人がイルマリネンだと聞くと喜び、娘を着飾らせてサンポの鍛造を依頼します。
イルマリネンは仕事場づくりから始め、長い期間をかけて、ついにサンポを作り出すことになるのです。

サンポは、すでに説明したようにその正体は不明なのですが、どうやら挽臼のようなものだと考えられています。
これを挽くと、臼の中から金や穀物がざくざくと出てくるようです。
ロウヒならずとも、欲しがるのは当然かも知れません。
サンポを鍛え上げたイルマリネンは、娘を要求します。
しかし、ロウヒがいいと言っても娘本人に拒絶されたため、ただ一人でカレワラに戻ることになりました。
トゥオネラの白鳥
ここで主人公はワイナミョイネンとイルマリネンから、レンミンカイネンに移ります。
すでに述べたように、彼は腕もたち、強力な魔法も使えます。
しかもイケメンなのですが、家柄はあまりよくなかったようです。
そのレンミンカイネンが、サーリという土地に嫁取りに出かけます。
狙いはキュリッキという名家のお嬢様です。
イケメンで口のうまいレンミンカイネンは、サーリの娘達を残らず自分のモノにしてしまいましたが、キュリッキはなびいてくれません。
怒ったレンミンカイネンはキュリッキをさらってしまい、強引に花嫁とします。
その際、自分は戦いに行かず、妻は家の外に出ない、という約束を交わしました。
ところがキュリッキがある日約束を破ってしまい、レンミンカイネンは激怒して「ポホヨラに戦いに行く」と言い出します。
ポホヨラに乗り込んだレンミンカイネンは、まず盲目の門番を除くすべての男たちに呪いをかけます。
その上で、ロウヒに対して娘を自分によこすように、と迫ったのです。
ロウヒは若者に対し三つの課題を与え、それを果たせたら娘を与えようと言いました。
最初の二つの課題は、ヒーシの鹿とヒーシの馬を捕らえるというものでした。
ヒーシというのは元は暗い森のことを指していたようですが、後にはそこに住む悪霊(神?)のことも意味するようになりました。
それはともかく、鹿と馬を捕らえたレンミンカイネンに、ロウヒは「今度はトゥネラの白鳥を捕らえてこい」と命じます。
トゥオネラはフィンランド神話における冥府です。
そこに住んでいる白鳥ですから、当然魔力を持った鳥です。
レンミンカイネンは臆さずトゥオネラの白鳥を捕らえようと出かけます。
しかし、彼が呪いをかけなかった盲目の門番(そのかわり侮辱はしていました)に毒矢で射られ、身体をばらばらにされて冥府の川に流されてしまいます。
このことを聞きつけたレンミンカイネンの母は、イルマリネンに頼んで熊手を作ってもらいます。
そして、息子の身体を拾い集めて再生させ、ひとまず家へと連れて帰りました。

なお、フィンランドの音楽家ヤン・シベリウスは、「カレワラ」のこの一節からインスピレーションを受け、交響詩集「レンミンカイネン組曲」を作っています。
「トゥオネラの白鳥」はその第二曲のタイトルです。
イルマリネンの結婚
ワイナミョイネンは船を作り、ポホヨラへと出発します。
目的はロウヒの娘を妻とすることです。
これを聞きつけたイルマリネンは、「その娘は自分の妻になる人だから」ということでソリでポホヨラに向かいます。
ポホヨラに先についたのはワイナミョイネンでしたが、ポホヨラの娘は彼が老人だからということで拒絶し、イルマリネンを選びます。
ロウヒはまたもイルマリネンに向かって課題を与えますが、イルマリネンはロウヒの娘の助力を受けて見事この課題を果たします。
またもフラれたワイナミョイネンは、「老人は若い娘に求婚してはいけないのだ」という戒めの言葉をつぶやきます。
もう一人の候補者ワイナミョイネンがギブアップしたため、ロウヒはイルマリネンを娘の夫と認め、婚礼の宴が催されます。
この婚礼には各種の歌謡が集められており、全部で50章ある「カレワラ」のうち実に6章分が割かれています。
とにかく、盛大な宴だったわけです。
しかし、この宴にレンミンカイネンだけは招かれませんでした。
怒ったレンミンカイネンはポホヨラに殴り込みをかけます。
彼がロウヒの家についた時、イルマリネンは新妻を伴って家に戻っていましたが、ロウヒの家族と客人たちはまだ祝宴を続けていました。
レンミンカイネンはロウヒの夫と術くらべをして勝ち、これを殺してしまいます。
レンミンカイネンは家に逃げ帰り、母親にどうすればいいのか尋ねます。
母はとある小島に三年隠れているように、と息子に言いました。
三年間の島での隠遁生活(その間島の娘大部分に手を付けたりとかやりたい放題でしたが)を経て故郷に帰ったレンミンカイネンですが、家はロウヒによって破壊されていました。
しかし、隠れ家を作って逃げていた母親と再会します。
クッレルヴォの不幸な生涯
クッレルヴォはカレルヴォ族の一員でした。
しかし、彼の属するカレルヴォ族は、ウンタモ族といさかいを起こし、身重の娘一人を除いて皆殺しになってしまいます。
クッレルヴォは、このカレルヴォ族最後の生き残りの娘から生まれました。
クッレルヴォは生まれた時からウンタモ族に対して復讐心を持っていました。
ウンタモ族はクッレルヴォを殺そうとしましたが、水につけても火で焼いても死にません。
殺すことをあきらめたウンタモは、彼を奴隷として使おうとします。
しかし、クッレルヴォは「英雄」なので、ありあまる力を持っています。
子守をさせれば子供を殺してしまい、開墾をさせると農具だけでなく畑も破壊してしまったのです。
あきれたウンタモは、クッレルヴォをイルマリネン(新婚)のところに売り飛ばします。
なお、カレルヴォやウンタモは、個人の名前とも一族の名とも解釈できます。
「カレワラ」はもともと歌謡集のようなものなので、さまざまな部分で記述が具体的ではなく、複数の意味に解釈できてしまうケースが多いのです。
カレルヴォとウンタモを個人名だとした場合、彼らは兄弟、またはそれに準じる関係であったということになります。
部族名だったとした場合、カレルヴォ族とウンタモ族は、祖先を共通にする血縁のある集団であった、となります。
ここでは、個人名なのか部族名なのかはあいまいにしておきます。
しかし、ウンタモの方は単に部族名としてだけではなく、現在のウンタモ族の族長のことも指す場合があるとして話を進めます。
イルマリネンの妻(つまりロウヒの娘)はクッレルヴォを牧童として使おうとします。
彼女はクッレルヴォに弁当としてパンを与え、牛とともに送り出します。
しかし、実はこの時クッレルヴォが持たされたのはパンではなく、石だったのです。
なぜイルマリネンの妻がクッレルヴォにこのような意地悪をしたのか、「カレワラ」には書いてありません。
何らかの呪術的な意味があったのかもしれませんし、単純に彼女の性格が悪かったかもしれません。
なにせポホヨラの魔女の娘ですから。
昼になり、クッレルヴォは弁当を食べようとしますが、パンではなく石であったため、父の形見のナイフを折ってしまいました。
彼は怒って牛を殺し、熊と狼を魔法で牛に変え、イルマリネンの家へと送ります。
イルマリネンの妻は、家で正体を現した熊と狼に殺されてしまいます。
イルマリネンの家を逃げ出したクッレルヴォは、やがて人に聞いて自分の家族が生きていることを知ります。
彼は生き残りの一族の元に戻り、母と再会します。
母はクッレルヴォの家族はみな無事だが、ふたりいる妹のうち年上の方が行方不明になっている、と告げました。
クッレルヴォはこうして一族とまた暮らし始めたのですが、やはり力の加減を知らないので仕事ができず、母親以外からは厄介者扱いされます。
困った一族の人々は、税金の支払いぐらいならできるだろうと、彼を遠く離れた役所に送り出します。
この当時の村には役所などありませんから、税を納める場合遠く離れた領主のもとまで貢物を持っていかなければなりません。
このあたり、隣国に支配されていたフィンランドの歴史的実態が反映されています。
税として納めるような価値あるものを大量に運んでいると、山賊などに襲われる危険性もあります。
クッレルヴォは屈強ですし、あちこち放浪して旅慣れてもいたため、「税の支払いならできるだろう」と判断されたのでした。
一族の期待通り、クッレルヴォは納税の仕事を大過なく終えることができました。
税を納めた帰り道、クッレルヴォは一人の娘に出会い、彼女を誘惑します。
彼女と一夜をともにした後、クッレルヴォは自分の身の上について語ります。
すると娘は驚き、自分の身の上話を始めました。
それはクッレルヴォの話とほとんど同じでした。
彼女は生き別れになっていたクッレルヴォの妹だったのです。
兄と寝てしまったことを恥じた妹は川に身を投げます。
悲嘆に暮れたクッレルヴォは一族の住む村へと戻ると、ウンタモを滅ぼすと母に誓います。
クッレルヴォの悲しみすべての原因が、ウンタモにあるからというのが理由ですが、なんとなく八つ当たりのような気がしないでもありません……。
クッレルヴォは武装し、ウンタモ族の元へと殴り込みに行きます。

その姿は映画「コマンドー」のメイトリックス大佐(つまりアーノルド・シュワルツェネッガー)もかくやといったものだったでしょう。
彼は言った通りウンタモを一人で滅ぼし、村へと戻ります。
しかし、彼の一族は(また)滅亡していました。
疫病であったのか、ウンタモの生き残りの再襲撃を受けたのかは、はっきりしません。
母の死にクッレルヴォは打ちひしがれます。
ただ、彼を冷たく扱った他の一族に関してはどうでもよかったようです。
悲しみに半狂乱となったクッレルヴォは森をさまよいます。
やがて、彼は自分が妹と出会った場所にいることに気づきます。
彼は剣を抜き、自分を殺すつもりがあるかどうかを尋ねます。

剣は答えます。「罪深い肉を喰らい、汚れた血をすすりたい。なぜなら自分はこれまで、罪のない肉を喰らわされ、汚れない血をすすってきたから」。
クッレルヴォは剣を胸に当て、そのまま大地に伏してその生涯を終えたのです。
「英雄」として生を受けながら、いいところがまるでなく破滅一直線の生涯を突き進んだクッレルヴォ。
これに関してワイナミョイネンは「きちんと育てられなかったからである」と感想を述べています。
なお、このクッレルヴォの物語に対しても、シベリウスは楽曲「クッレルヴォ」(交響詩とも交響曲とも呼ばれます)を作っています。
先に述べたように、自分の力をコントロールしきれない「ついてない男」の破滅の物語なのですが、不思議な魅力を放っています。
シベリウスも、そこに魅了されたのでしょうか。
黄金の花嫁
さてイルマリネンです。
クッレルヴォに妻を殺された彼は、嘆き悲しみます。
復讐しようにも、クッレルヴォはウンタモを滅ぼして自殺してしまいましたから、何もできません。
怒りを発散させることができなくなったので、彼は少々おかしくなったようです。
イルマリネンは、その神業といえる鍛冶の能力(元は神ですから…)を暴走させ、「黄金の花嫁」を作ってしまいました。
この花嫁、外見上はほぼ人間と一緒なのですが、話もしないし働きもしません。
夜ベッドに引き入れて一緒に寝てみると冷たかった(当たり前ですね)ので、「こんなものいらん」と思ったようです。
イルマリネンは黄金の花嫁をワイナミョイネンの所に運んでいきますが、「ワシにもそんな趣味はないわい」と拒絶されます。
ワイナミョイネンの家を出たイルマリネンは、再びポホヨラへと赴きます。
彼はロウヒに、失った妻の代わりにその妹を自分に与えよ、と要求しました。
ロウヒは「嫁にやってまた殺されてはたまらない」と拒絶します。
イルマリネンはロウヒの二番目の娘に直接求婚しますが、これも拒否されました。
逆上したイルマリネンは二番目の娘をさらってしまいますが、家まであと少し、というところで仮眠を取っていると、その間に新しい妻は別の男と浮気をしていました。
イルマリネンは激怒し、彼女をカモメに変えてしまいます。
そして自分はワイナミョイネンの元へと行きました。
ワイナミョイネンは、ポホヨラの様子はどうだったと尋ねます。
イルマリネンは「サンポがあるから豊かだった」と答えます。
ワイナミョイネンは、「あれはもともとお前さんが作ったものじゃないか」と言って、サンポを奪い返すことをイルマリネンに提案します。
サンポの奪回
ワイナミョイネンに説得され、サンポの奪回を決意したイルマリネンは、武器を鍛えます。
ワイナミョイネンは木の船を見つけ、千人の男女を漕ぎ手として集めます。
ただこの男女は老人と少年、それに若い娘だけでした。
このため海に出ても漕ぎ手としての役にはたたず、イルマリネンが自ら漕ぎ手をつとめます。
沖に漕ぎ出していく船を、レンミンカイネンが見つけます。
彼はワイナミョイネンに、自分も連れていくようにと頼み、ワイナミョイネンは承諾します。
しばらく海を進んだ船は、やがて「座礁」してしまいます。
しかし乗り上げたのは岩礁などではなく、巨大なカマスでした。
これを倒そうとしてレンミンカイネンは海に落ち、イルマリネンは刀を折ってしまいます。
しかしワイナミョイネンは見事に刀を突き立て、カマスを退治します。ジジイなのに。
さっきまでカマスだったものはワイナミョイネン一行のご飯になってしまうわけですが、ワイナミョイネンは残った骨から魔法の楽器「カンテレ」を作り出します。
船の乗組員ができた楽器を弾こうとしましたが、不快な音が鳴るばかりです。
ワイナミョイネンは、「ポホヨラの住民なら弾けるかもしれない」と言ってポホヨラに持ち込んだのですが、こちらも乗組員同様、誰もまともに弾けません。
「仕方がないのう」とワイナミョイネンはカンテレを手に取り、自ら奏でます。

その音は実に見事なもので、動物たちが集まって聞き惚れます。
動物たちだけでなく、妖精も集まってきました。
ワイナミョイネンのカンテレを聞いたものはすべて涙を流します。
ワイナミョイネン自身も涙を流し、それは海に落ちて真珠となったといいます。
ジジイの涙が真珠になるとか、美しいんだか美しくないんだかよくわからない話です。
やがて一行はポホヨラにたどり着きます。
さっきカンテレをポホヨラの人々に弾かせていたような気もしますが、神話なので細かいことを気にしてはいけないのです。
大事なのは、「カンテレを弾きこなせるのはワイナミョイネンだけ」ということなのです。
カンテレは普通の楽器ではなく魔法楽器なので、弾きこなすためには強大な魔力が必要だ、などの事情があるのでしょう。
ともかくワイナミョイネンは、彼以外には誰も弾くことができないカンテレをかき鳴らします。
その音を聞いたポホヨラの人々は皆眠ってしまいました。
ワイナミョイネン一行はサンポを収めてあった扉を破壊し、サンポを運び出そうとします。
しかしサンポが地面に根を張っており人間の力では持ち出せなかったので、牛に引かせてようやく運び出しに成功します。
一行はサンポを船に載せ、海に漕ぎ出します。
「大成功だ」と興奮したレンミンカイネンはいい気分になって歌いだしましたが、この歌声でポホヨラの人々が皆目を醒ましてしまいました。
ポホヨラの人々、というのはすべて魔法使いです。
魔法で「もや」を発生させて足止めをし、攻撃をしかけてきました。
ロウヒ自身は巨大な鳥に姿を変え、空から船を襲います。
大風が吹き、カンテレは飛ばされてしまいました。
危機一髪ですが、ワイナミョイネンは魔法で反撃を加えます。
ポホヨラの追っ手の軍船に対しては、火打ち石を使って魔法で岩礁を作り、次々と座礁させました。
空から迫る巨鳥と化したロウヒに対しては、まずレンミンカイネンが刀で一撃を加え、怯んだところをワイナミョイネンが外した船の舵で殴りつけます。
ジジイなのにとんでもない力です。

ロウヒの怪鳥は海に落ちていきましたが、その際サンポを足の爪にひっかけます。
サンポはばらばらになって海中に落ちました。
ただ、分解してもその不思議な力はなくなりはしなかったようです。
サンポのかけらの一部は、海岸に打ち上げられ、それぞれの土地に恵みをもたらしました。
ただし、サンポが元あったポホヨラの地にはサンポの破片はほとんど流れ着かず、ポホヨラは以後「パンを食べることができない土地」になったのだそうです。
カレワラに戻ったワイナミョイネンは、またカンテレが弾きたくなりました。
そこで彼はイルマリネンに、大きな熊手を作らせ、海の底をさらいますが、カンテレは見つかりません。
あきらめて帰る道すがら、ワイナミョイネンは一本の白樺の木が泣いているのに出会います。
フィンランド神話に登場するものたちは、その多くが魔法の力を持っており、人間のように話すことができます。
ですから、白樺がしゃべったとしてもワイナミョイネンはまったく驚きません。
「ああ、こいつも魔力持ちか」程度にしか思わないのです。
ワイナミョイネンは「何を泣いているのだ」と白樺に聞きます。
白樺は、自分は木であるからいつか人間に枝を切られ皮を剥がされ燃やされてしまう運命だ。
人間に切られることを免れたとしても、いつかは老い、貧相になっていくだろう。それが悲しいのだ、と答えます。
いつかは老いるだろう、とか彼は木ですから人間よりもずっとその寿命は長いと思われますが……。
本人が悲しんでいるのだから、そこはそれでよしとしましょう。
ワイナミョイネンはふとあることを思いつき、木に語りかけます。
「立派な道具に生まれ変わり、人々の喜びになるのなら、悲しむ必要はなくなるだろう」と。
そしてワイナミョイネンは「しゃべる木」を切り倒し、それを使って新しいカンテレを作り上げます。
ワイナミョイネンはカンテレをかき鳴らし、人々はそれを聞いて感動したと言います。
ワイナミョイネンが白樺に語った通りになったわけですが、多少「これでいいのか?」という気がしないわけでもありません。
ポホヨラの魔女の復讐
ポホヨラの魔女・ロウヒはワイナミョイネン一行にサンポを奪われてしまったことが悔しくてなりません。
確か彼女はレンミンカイネンに夫を殺されているので、恨むのならワイナミョイネンではなくそっちではないかと思われるのですが……。
亭主を殺された恨みよりも、サンポのかけらの恩恵で豊かに暮らしているワイナミョイネンとカレワラの民への妬みの方が大事だったようです。
そんな時、ロウヒはトゥオネラの盲目の老女が子を孕んだ、という噂を聞きつけ、彼女をポホヨラに呼び寄せます。
老女はロウヒに助けられ、「九つの災い」を産み落とします。
これは九種類の病、もしくはそれを使って人々に災いをもたらす「呪術師」たちだと考えられます。
ワイナミョイネンはサウナを作り、魔力のある木を燃やします。
そして、薬液を混ぜた清らかな水を沸かして、呪文を唱え、疫病を祓いました。
この説話は何らかの歴史的事実が下敷きになっている可能性が大きいと思われます。
流行病にサウナは、確かに効果が高いと思われますから。
疾病によってカレワラを滅ぼすことに失敗したロウヒは、今度は大きな熊をカレワラに差し向けます。
熊が来ることを察知したワイナミョイネンは、イルマリネンに槍を作らせます。
そしてカレワラの民に言い含め、やってきた熊を褒め称え、歓待します。
いい気分になった熊に、ワイナミョイネンは蜂蜜を振る舞おうと言い出し、熊はすっかり老人を信用してしまいます。
ころはよし、と思ったワイナミョイネンは槍を取り出して熊を刺し殺し、村人とともに皮を剥いで肉を食べてしまいました。
こちらは、いわゆる「熊祭」の起源をワイナミョイネンに求めようとして作られた説話だと考えられます。
実際に行われていた熊祭で歌われていた歌謡も、多数収録されています。
フィンランドは寒さの厳しい地域で、農耕にはあまり適していません。
このため人々は、森へ出かけていきさまざまな生活物資を得ていたのです。
森に祝福されれば、大いなる富を得ることができましたが、そうでない場合は命を落とすこともあったのです。
森は豊かさの象徴であり、同時に死をもたらす恐ろしい存在でもありました。
先に紹介したヒーシは、森の恐ろしさを神格化した存在でした。
これとは別に、森と狩の守護者として、ミエリッキという女神が信仰されていました。
熊という大いなる恵み(ちょっと凶暴ですが)を人類に与えたのは、もともとはミエリッキだとされています。
しかし、例によってリョンロット先生が話をひとつにまとめるため、ロウヒの仕業だとしたようです。
なお、熊祭は北方に住む人々の間では、地域を問わず広く行われています。
北海道に住むアイヌたちも、イオマンテと呼ばれる熊祭の伝統を持っているのです。
フィンランド版「天の岩戸」
熊祭の賑わいを聞いて、月と太陽がふらふらとカレワラの地に近づいてきました。
「熊作戦」が失敗したことに気づき、それでもワイナミョイネンに対する復讐心が収まらないロウヒは、新たなる仕返しの手段を思いつきました。
ロウヒはカンテレの調べに聞き惚れている太陽と月とを捕まえ、ポホヨラに連れていくと、「鋼の山」の中に閉じ込めてしまったのです。
世界は闇に包まれました。
光がないので、至高の神ウッコも憂鬱になります。
ウッコは自ら太陽と月とを探しに行きますが、見つかりません。
そこでウッコは新たなる太陽を作り出そうとし、剣から火花を出して、火を灯します。
ところが管理を委ねた大気の娘(人間以上神未満の存在)が、火を取り落としてしまい、火は天界から地上にこぼれてしまったのです。
ちなみに「大気の娘」とはいいますが、すべての女性の中で最年長の存在だそうです。
地上に落ちた火は、あちこちに大火災を発生させます。
ワイナミョイネンとイルマリネンはこの火事に気づき、原因を探ります。
そしてついに、大気の娘に出会い、その口から「すべては彼女が天界の火を取り落としたことが原因だ」ということを聞き出したのです。
大気の娘はさらに、火は地上のあちこちを燃やし、人々を殺した後に湖に落ち、そこで魚に飲み込まれたと話します。
多くの村を住民ごと焼き尽くすような火を飲み込んだ魚が、一瞬にして焼き魚にならなかった理由は不明ですが……。
魔力があればなんでもありな世界ですから、ここはツッコんではいけません。
火を飲んだ魚はさらに大きな魚に飲まれた、というので、ワイナミョイネンとイルマリネンは船で湖に漕ぎ出します。
しかし、目的の魚を捕らえることはできません。
魔法が支配する世界において、あるものが得られないのは、得ようとするものの魔力が低いためだとされます。
魔力を補うためにはどうすればいいか?
そう、強力なマジックアイテムを追加すればいいのです。
サンポ争奪戦の際には、カンテレがその役を務めました。
強力なマジックアイテムを作るためには、材料を厳選しなければなりません。
これもすでにワイナミョイネンが「カレワラ」のあちこちで実例を示しています。
ワイナミョイネンは亜麻を撒き、やがてそれを収穫して巨大な網を作り上げます。
そしてカレワラの人々を総動員して網を引かせ、ついに目的の魚を捕らえたのです。
ワイナミョイネンは魚の腹を裂いて火を取り出そうとしますが、火は彼の顔に跳ね、彼とイルマリネンにやけどを負わせます。
そしてさらに逃げようとしますが、ワイナミョイネンは火を捕まえ、魔法で逃げないようにしてかまどに閉じ込めることに成功しました。
閉じ込めることができたのはいいでしょう。
ですが、これでは本来の目的である、太陽の代役としては使えません。
そこで人々はイルマリネンに、新しい太陽と月とを鍛造するようにと願い出ます。
一介の鍛冶屋にとんでもない要求をするものですが、人々はたぶんイルマリネンの中の人が創造神ウッコだと知っているのでしょう。
ならば、さして無茶な要求ではありません。
イルマリネンは銀の太陽と金の月とを鍛造します。
しかしそれはオリジナルのように輝いてはくれません。
やはり代用品ではなく、本物が必要なのです。
ワイナミョイネンは占いを行い、太陽と月とがポホヨラに閉じ込められていることを探り当てます。
ワイナミョイネンは単身ポホヨラに乗り込み、鋼の山から太陽と月とを救出しようとします。
しかし、山の扉には魔法がかけられており、ロウヒ以外に開くことができなくなっていました。
慌ててカレワラに戻ったワイナミョイネンは、イルマリネンに扉を破壊できる道具を作るようにと依頼します。
そんなものを作られてはたまらんと、ロウヒは鳥に化けてイルマリネンの鍛冶場に忍び込みます。
イルマリネンは一心不乱に槌をふるっていました。
ロウヒはイルマリネンに、「何を作っているのか」と尋ねます。
イルマリネンは「ポホヨラの老婆の首輪だ」と答えます。
つまり、「お前の正体がロウヒだということには気づいている。邪魔をしようとしても無駄だ」と言ったのです。
ロウヒはここで道具製作の邪魔をするのはできないと悟り、ポホヨラに引き上げます。
戻った彼女は自ら扉を開き、太陽と月とを解放したのでした。
北極圏に近いフィンランドの冬の日照時間は短く、丸一日太陽が昇らない「白夜」も存在します。
太陽と月の幽閉の神話は、いかにもフィンランドらしいものと言っていいでしょう。
また、このお話の前半の部分には、ベースになったと思われる史実が存在します。
紀元前7世紀、エストニアのサーレマー島に、大量の隕石が落下しました。
その時のエネルギーは広島型原爆に匹敵すると言われており、あたりの森林は大火災を起こしています。
最も大きな隕石がぶつかった後は、カーリ湖とよばれる湖になりました。
恐らくこの話が、天上から落ちて村々を焼き尽くした火として伝えられたのでしょう。
火(隕石)を飲み込んだのは、湖の中の魚ではなく、湖そのものでした。
ワイナミョイネンの旅立ち
ここでお話するのは、「カレワラ」の最終章に収められているエピソードです。
あるところにマリヤッタという娘がいました。
彼女は男嫌いで、あらゆる男を近づけませんでした。
しかしある日、言葉を話す不思議ないちごを食べてしまい、それによって妊娠します。
父が誰ともわからない子を孕んだということで、マリヤッタは周囲から冷遇されます。
両親すらも、彼女の出産の手助けをしてくれません。
やむなく彼女は自分で産室を作り、男の子を出産しました。
その子は不思議な力を持っていました。
やがて男の子は成長し、マリヤッタは彼を聖職者のもとに連れていき、洗礼を受けさせようとします。
この「カレワラ」最終章の世界では、キリスト教がごく普通に普及しているようなのです。
聖職者は、「父のない子だから」という理由で洗礼を拒否します。
村の人たちは、男の子の処置に困り、ワイナミョイネンを呼びました。
ワイナミョイネンは、「その子がいちごから生まれたのなら人間ではない。殺せ」と言います。
これに対し、男の子はこう言います。
「ワイナミョイネンは古い掟そのものだが、掟はすでにほころびており、もし自分を掟で裁こうとするのなら、掟そのものであるワイナミョイネンも裁かれねばならない」
かつてワイナミョイネンは、乙女アイノを死に至らしめてしまうという過ちを犯しています。
このため掟にほころびができ、ワイナミョイネンは他人を裁く資格を失っているのだ、ということを子供は指摘したのです。
自己の存在の矛盾を指摘されたワイナミョイネンは、自分の時代は終わったと悟り、船で海へ漕ぎ出して行きます。

最後に彼は、「人々が自分を必要とする時、新しいサンポと新しいカンテレを必要とする時、自分は帰ってくる」と言い残しました。
マリヤッタは誰が見てもマリアであり、その子はイエス・キリストです。
この部分は特にリョンロット先生の「作文」が多く含まれており、彼はこの終章で古い異教の時代が終わり、キリスト教の時代になった、という結末を語ろうとしたものと思われます。
ただ、リョンロットが参考にしたと思われるエピソードは、展開が少々異なっています。
少年の父はワイナミョイネンその人だった、というのです。
ワイナミョイネンはポホヨラの娘への求婚に失敗した後、「老人は若い娘に求婚せぬように」という戒め(掟)を定めました。
しかしここに男の子がいる、ということは、どこかでジジイが掟を破ったということになります。
だから審判者としての資格を失った、というのです。
こっちの方が、お話としてはすっきりしていますね。
こちらのワイナミョイネンは、キリスト教に追われたのではなく、伝説の時代に終止符を打つべく、自ら姿を隠したのです。
「いつかまた来る」という言葉を残して消えていく姿は、アヴァロンに去るアーサー王と似ています。
ワイナミョイネンの最後については、静かに漕ぎ出していった、という話と、海の波に飲まれた、という話が伝わっています。
この両者の違いに意味はあまりありません。
というのは、ワイナミョイネンそのものが海から世界を生み出した神であるため、船でだろうが波に飲まれようが、それは人の姿を捨てて元の海に戻った、ということでしかないからです。
以上が、フィンランド神話のあらましになります。
先に述べたように、フィランド神話は「カレワラ」という一冊の本にまとめられています。
日本語訳の文庫本も出ていますので、このお話を読んで興味を覚えた方は一読してみてはいかがでしょうか。






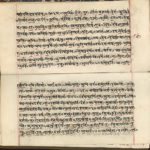




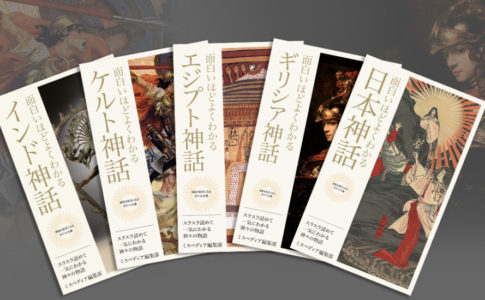





























コメントを残す