クトゥルフ神話を世に広めるのに貢献したもの。
一つは小説ですが、もう一つにTRPG(テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲーム)というジャンルのゲームがあります。
クトゥルフ神話TRPGもその一つ。
日本で1985年から始まったTRPGブームに乗り、一気に名前を広めました。
そんなクトゥルフ神話TRPGの概要と魅力をご紹介します。
クトゥルフ神話の概要

アメリカのホラー作家H・P・ラブクラフトとその友人達によって作られた、宇宙的恐怖を題材にした一大ホラー神話、それが『クトゥルフ神話』です。
90年前に創生されたものですが根強い人気を誇り、世界中の様々なクリエイターに影響を与えています。
小説だけではなく映画、ゲーム、アニメなどの題材として取り上げられている作品です。
ネクロノミコン、ニャルラトホテプ、ハスターなどの魔法的存在は、このクトゥルフ神話からの出典となっていることが多いです。
クトゥルフ神話について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
テーブルトークRPG(TRPG)について
TRPGは会話によって進めるゲームで、ロールプレイ=「役割を演じる」ことが中心となります。
参加するのは1人のゲームマスター(クトゥルフの場合はキーパー)と、複数人のプレイヤーです。
必要な物はキャラクターの詳細設定が書かれたシート、判定用のダイス、鉛筆、そして想像力となります。
ゲームはゲームマスターが用意したシナリオにそって進め、プレイヤーは自分が作ったキャラクターとなって参加します。
プレイヤーはルールから逸脱しないかぎり何をやっても自由です。
部屋に木箱がある場合、壊しても良いし、踏み台にしても良いです。
もちろん無視するという選択肢も与えられています。
その結果、箱の中にいた人を放置してしまった、中の宝物を壊してしまった、などということは当たり前のように起こります。
その先の読めない展開がTRPGの面白さでもあります。
クトゥルフ神話TRPGの特徴と魅力
これまで数々のTRPGが作られてきましたが、その多くは中世時代を舞台にしていました。
そこに1920年代を舞台とするゲームがでてきたわけですから、注目されないわけはありません。
これはクトゥルフ神話を知らない人への強いアピールとなり、クトゥルフ神話好きを増やすことに大きく貢献しました。
前述したとおりTRPGは想像力を必要とするゲームです。
マスターから詳細な情報を得て、それを想像しながらゲームを進めます。
しかし、ホラーゲームでは詳細を知れば知るほど怖さが薄れてしまいます。
そのため情報を与えすぎるのも問題になり、その加減が難しいジャンルです。
それに対しクトゥルフ神話には、「名状しがたき」「冒涜的な」という有名な形容詞があり、具体的な描写を与えなくてもプレイヤーは納得してくれるという、反則的なことができてしまいます。
もっとも恐怖を感じるものは個人個人で異なるため、抽象的な方が相応しいとも言えます。
つまり、クトゥルフ神話はTRPGと非常に相性が良かったということです。
現在のクトゥルフ神話TRPG
TRPG自体のブームは過ぎてすっかり下火となっていますが、クトゥルフTRPGをプレイする人はまだまだたくさんいます。
人が集まらなければ遊べないという欠点も持っているのですが、最近ではオンラインでやるグループもいたり、別のネットゲーム内でやるという強者までいるから驚きです。
ゲームシステムの完成度が高いため、時代を現代にし、ホラー要素を抜いても十分楽しめます。
また他のTRPG同様シナリオは自由に作れますので、様々なストーリーを楽しむこともできます。
また、クトゥルフ自体は宗教色が薄いため、日本人にも受け入れやすいというのも大きいです。
ゲームは難しいものではありませんので、もし機会があれば一度参加してみてはいかがでしょう。
プレイ動画などもありますが、やはり自分で遊ばないと楽しさは分かりにくいと思います。
自分の分身が宇宙的恐怖と遭遇して発狂するなんて、なかなか体験できませんからね。






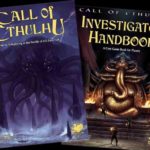




































コメントを残す