Kindle Unlimitedに加入している方は無料で読むことができますので、ぜひご利用ください。
Contents
猫をかぶっていたダビデ
イスラエルの民は、長い間「王」というものを持ちませんでした。
その理由は、神であるヤハウェ(とそれを奉じる神官団)が、「王というものはやがて自分を神格化し、ヤハウェを軽んじるようになる」と考えていたためです。
しかし、王という指導者がいないと周囲の異民族に対して立場が弱くなってしまうため、最後の士師サムエルはサウルという若者を王として選びました。
サウルはひたすら美青年で、ヤハウェにもそこそこ忠実で、王としてもそれなりに有能でした。
しかし、ちょっとしたことからサムエルらヤハウェ神官団と対立してしまいます。
この結果、サムエルたちは新しい王を立てようということになり、その候補者としてダビデを選びます。
このダビデは、サウルより遥かに有能でした。
有能過ぎました。
どういう面での能力があったかというと、一言で言うと「政治力」です。
ダビデは自分が今どういう立場に置かれているかということをしっかり認識し、感情を殺して先々自分に有利になるように振る舞うことができました。
サムエルが生きている間は、ヤハウェ神官団とぴったり寄り添い、その意見に背くことがありませんでした。
このため、ヤハウェにも強く愛されていた、と記録されています。
またダビデは、サウルに対しても常に忠実たらんとしていました。
サウルは自分の王位を脅かすものとしてダビデを激しく憎んだのですが、ダビデはそんなサウルを主君として立て続けたのです。
ただ、ダビデが清廉潔白な人物であったかというと、そうとも言えないようです。
サウルが自分を憎んでいるということを利用して、サウルの元から逃れて独立勢力となり、さらにイスラエルの民とは仇敵同士だったペリシテ人に取り入り、サウルと対抗できるだけの力を蓄えます。
ダビデの出世のきっかけとなったのは、ペリシテ人の勇者・巨人ゴリアテを倒したことでしたが、ダビデはいつの間にかそのゴリアテの出身地を根拠地としていたのです。
「サムエル記」にはそうだとは書かれていませんが、要するにペリシテ人の傭兵隊長として活動した時期があったのでしょう。
必要とあらば民族の仇敵とも手を結ぶあたり、非常にしたたかです。
ダビデはとにかく、己の感情を殺しながら、飛躍の時を待っていました。
やがてそのチャンスが巡ってきました。サウルが戦死したのです。
非常に都合がよいことに、これまでダビデを殺そうとするサウルを何度も諌めてきたサウルの有能な息子・ヨナタンも一緒に戦死してしまいました。
ダビデにとって「目の上のたんこぶ」が消えたのです。
手のひらを返すダビデ
これまで、ダビデはサウルから命を狙われながらも、サウルを王として立てていました。
ではサウル死後も忠誠を貫き、サウルの遺児を王としてイスラエルの民に君臨させたでしょうか?
答えは否です。
サウル死後、王位は四男のイシュ・ボシェテに受け継がれます。
サウル当人でも親友であったヨナタンでもない者に王位が移ったので、ダビデは忠臣の仮面をかなぐり捨ててイシュ・ボシェテと戦い始めました。
サウルとヨナタンの死の報を聞いた時には「衣を引き裂いて泣いた」にも関わらずです。
ダビデはユダの地において、自ら王を名乗るようになりました。
客観的に見ればこれは反逆です。
しかしダビデはヤハウェの神官団を抱き込んでいましたし、ヨナタンの子を味方として抱き込んでいました。
このヨナタンの子は「足萎え」つまり身体障害者です。
古代のメソポタミアなどでは五体満足であることが王となる絶対条件とされていたことが多く、身体の一部を欠損したために王の地位を失った神の話も複数伝えられています。
つまり、このヨナタンの子はサウル王家の生き残りではあるものの、王位継承権を持たないというダビデにとって好都合この上ない人物だったのです。
「サムエル記下」の第三章は次のような文章で始まります。
ヘブロンでダビデに男の子が生れた。
彼の長子はエズレルの女アヒノアムの産んだアムノン、その次はカルメル人ナバルの妻であったアビガイルの産んだキレアブ、第三はゲシュルの王タルマイの娘マアカの子アブサロム、第四はハギテの子アドニヤ、第五はアビタルの子シパテヤ、 第六はダビデの妻エグラの産んだイテレアム。
これらの子がヘブロンでダビデに生れた
複数いるダビデの妻に、次々と子供が生まれたのです。
それはつまり、後継者候補が増え、ダビデの王位がダビデ一代限りののものではなく、以後何代にも渡って継続する可能性が出てきたこと--少なくとも、当事者のダビデには継続する意思があることを意味します。
端的に言えば「もう誰にも権力は渡さない。未来永劫俺のもんだ」と宣言したということです。
ダビデの数多い妻は有力な他部族からの政略結婚で娶ったものですから、それはダビデを支援するこれらの部族の意思でもあります。
さて、落日のサウル朝の方に話を移しましょう。
イシュ・ボシェテは、有力な兄が戦死したため、棚からぼたもちの格好で王位を手に入れた人です。
王として十分な能力は、どうも持ち合わせていないようでした。
にも関わらず王として即位し、父の領地を受け継げたのは、父の部将アブネルの支持を得ることができたからでした。
サウルもダビデも、最初は一人の戦士として出発したのですが、勢力を拡大するに従い多数の部下を擁するようになります。
組織が拡大すると、次第に総大将であるサウルやダビデは軍勢の先頭に立たなくなり、部下の中で優秀なものに任せるようになりました。
その部将はやがて独自の勢力を蓄えるようになり、王の権力を脅かすようになったのです。
ダビデはサウルの「独自の勢力を蓄えすぎた部下」であったため、サウルから疎まれて追放されましたが、だからと言ってダビデが去った後またすべてを自分で取り仕切ることはできませんでした。
というわけで、また別の部将を取り立てることになります。
アブネルは、そういった経緯で出世した人物だったのでしょう。
賢明な王が亡くなると、有力部将の権力は相対的に拡大し、跡継ぎとなる王を超えてしまうことがよくあります。
サウル朝においても同じことが起きました。
要するに、イシュ・ボシェテはアブネルの操り人形に近い存在になっていたのです。
ここまでの「生き残り」の経緯から、ダビデがかなりの「政治家」であったことはおわかりかと思います。
その政治家が、こうした敵陣営の状況を見たら、どのような行動に出るでしょうか?
すべて無視して、力任せに敵軍を滅ぼして「全国統一」を成し遂げようとするでしょうか?
「大政治家」であるなら、王をもしのぐ権力を手にしつつある敵側の有力者を抱き込み、寝返らせ、戦わずして敵を屈服させる道を選ぶでしょう。
実際、ダビデはそのようにしました。
ある時、アブネルはイシュ・ボシェテから、亡きサウル王の妾の一人を自分のものにしてしまったことを責められます。
「サムエル記」にはあまり詳しく書かれていませんが、ダビデ同様、勢力を拡大・維持するために各地の部族から多くの女性を集め、妻や妾にしていたものと思われます。
だからアブネルがそれを自分のものにした、というのは、単なる好色が原因だったのではないのかも知れません。
妾の出身部族を自分の側に取り込み、王朝内での権力を不動のものにしようとした可能性も排除できないのです。
イシュ・ボシェテに注意されたアブネルは激怒し、堂々と「俺はダビデの側につくからな!」と宣言します。
そして直ちにダビデと連絡を取り、交渉を始めました。
アブネルはダビデに「俺と契約しろ。そうすればイスラエルはすべてあなたのものだ」と言い放ちました。えらい自信です。
実際アブネルは、そういい放てるだけの力をサウル陣営内に持っていたのでしょう。
ですが政治家ダビデははいそうですかと簡単に受け入れたりはしません。
自信満々のアブネルに対して条件を出しました。
「サウルの娘でわたしの妻であったミカルを引き渡せ」
奇妙なことに、ダビデはアブネルに対してこの条件を出しただけではなく、自分から直接イシュ・ボシェテに使者を出し、同じ条件を出したのです。
アブネルとイシュ・ボシェテの両方を天秤にかけた格好になります。
迅速に動き、ミカルをダビデに引き渡したのはイシュ・ボシェテの方でした。
これがこの後のアブネルの運命に大きな影響を与えたように思われます。
ダビデはアブネルをユダ王国の首都ヘブロンで歓待しました。
アブネルが去った後、ヨアブを筆頭とするダビデの部将たちがヘブロンに帰還してきます。
彼らは略奪に出ていたのだ、と「サムエル記」は伝えます。
アブネルはかつて、ヨアブの弟を殺していました。
そのアブネルをダビデが何もせず帰してしまった、ということを聞きヨアブは激昂します。
そしてアブネルを追いかけ、彼を殺してしまいました。
アブネルが死んだという報告を聞いたダビデは、こう言いました。
どうぞ、その罪がヨアブの頭と、その父の全家に帰するように。
またヨアブの家には流出を病む者、らい病人、つえにたよる者、つるぎに倒れる者、または食物の乏しい者が絶えないように。
酷い言いようです。
この一件、すべてがダビデの都合のいいように運びすぎています。
イシュ・ボシェテが自らダビデにミカルを引き渡し、恭順の姿勢を見せた段階で、ダビデにとってアブネルは利用価値のない存在になっていました。
利用価値がないどころか、無用な軍事力を持っているため排除すべき危険な存在になったのです。
なので、部将ヨアブをけしかけてこれを殺させたのではないでしょうか。
ヨアブはアブネルに対して因縁を持っていたので、ダビデ自身が後ろで糸を引いていたとしても、「あれは私怨だから」としらを切ることができます。
将来的には、ヨアブの権力がこれ以上拡大することも防ぐことができるでしょう。
イスラエル統一
大黒柱であるアブネルが死んでしまったため、イシュ・ボシェテの陣営はガタガタになってしまいました。
彼の元にはまだ何人か、アブネルよりはずっと小粒の部将がいたのですが、彼らが主君を裏切り、昼寝をしていた王の首を取ってダビデの陣営に走ったのです。
なんだか「三国志」の張飛の最期に似ています。
この裏切り者たちに対し、ダビデはどうしたでしょうか。
普通ならよくやったと褒美を与えるところでしょう。
ところがダビデは激怒し、呪いの言葉を吐くと、「若者たち」(恐らく親衛隊でしょう)に命じて、イシュ・ボシェテの首を持ってきた者たちを殺してしまったのです。
直接手を下さず「俺がやったわけじゃないからね」という言い訳の余地を作ってから。
先に述べたようにダビデの手元にはヨナタンの遺児がいました。
ヨナタンはサウルの長男ですから、この子はサウルの直系の孫に当たり、サウル朝の正統な王位継承権者ということになります。
五体満足であったら、ですが。
ところが非常にダビデにとって都合のよいことに、この子(当時5歳だったと記されています)は「足萎え」の身体障害者であったため、王となることができません。
ダビデは「サウルから受けた恩を忘れられない身としては非常に心苦しく気が進まないのであるが、他に適当な人物がいないのであるから仕方ない」というイメージを全身から漂わせつつ、統一イスラエルの王位に就きます。
中国の易姓革命ばりの偽善っぷりです。
いや、ダビデの政治力が古代中国の新王朝を建てた皇帝たちに匹敵するレベルだった、というべきでしょうか。
ともあれ、ダビデの生涯を追いかけると、随所に彼が卓越した「政治的人間」だったことを伺わせるエピソードが掘り起こされてきます。
自重しつつじっと機会を待ち、大義名分を揃えてから行動する彼が、イスラエルの統一を果たした後に望んだものは、一体なんだったのでしょうか。
ダビデの不倫
王となったダビデは、もう自分から軍を率いて戦うということはなくなりました。
即位後もアンモン人との戦いが継続していましたが、それはヨアブに任せきりということになったのです。
ある日ダビデはイェルサレムの「王の家」の屋上を歩いていました。
すると、近所の家でひとりの女性が身体を洗っているのが見えたのです。
その女性は非常に美しかったので、ダビデは人をやってその女性が何者であるかを探らせました。
その結果、ウリヤというヒッタイト人の軍人の妻「バト・シェバ」であることがわかりました。
ダビデは彼女を王宮に呼び寄せ、妾にしてしまいます。
やがて彼女は妊娠しました。
するとダビデは、アンモン人と対峙中のヨアブに使者を送り、「ウリヤをイェルサレムに戻せ」と命じます。
不思議に思いながらイェルサレムに帰還したウリヤに対し、ダビデは「前線はどうだった?」「ヨアブは元気か?」などと白々しい質問をし、「今日は疲れているだろう。家に戻ってゆっくり休め」と言いました。
「家に戻れ」というのがポイントです。
「家に戻って嫁と交わってくれれば俺が悪さした証拠がなくなる」とダビデは考えたのです。
ところがウリヤは王の家の門前にある兵士宿舎に行って寝てしまいました。
「ウリヤは家に帰らなかった」と聞いたダビデは焦り、ウリヤを呼び出して「なぜ帰らなかったのか」と問い詰めます。
ウリヤは「仲間が前線で苦労しているのに、自分ひとりだけ家に帰ってゆっくり休むことなぞできません!」と言い放ちました。
実に優等生な発言ですが、ダビデは内心歯ぎしりしていたことでしょう。
ダビデは表面上はにこやかに笑い、ウリヤを歓待し、もう一晩イェルサレムに泊めました。
ウリヤは当然のように兵士宿舎に行って兵士たちと眠りました。
翌日、ウリヤはダビデから託されたヨアブ宛の手紙を持って、前線に戻って行きました。
この手紙に、とんでもないことが書かれているということは知らずに。
その手紙には「ウリヤを最前線に放り込み、戦死させろ」という命令が書かれていたのです。
ヨアブは命令どおりにウリヤを最前線送りにし、ウリヤはダビデの望み通りに戦死しました。
邪魔者がいなくなったのを確認したダビデは、バト・シェバを妻の一人に加えます。
不倫の発覚を恐れてさまざまな小細工をするあたり、いかにもダビデらしいエピソードと言えます。
ただ、わたしたちがここまで見てきたダビデのことを考えると、単に美人を自分のモノにするというセコい目的のために、政治的な寝技を使うだろうか?という疑問もちょっと残ってしまいます。
ダビデの行動には、偽善的で手の混んだものが多いのは事実ですが、それはほとんどの場合巨大な政治的目的を無駄なく完遂するために行われたものです。
実はバト・シェバの身元を洗ってみると、これが単なる不倫劇ではなかったのではないか、という疑いが浮上してきます。
バト・シェバはアヒトフェルという人物の孫娘でした。
このアヒトフェルは賢者として名が高く、後に大軍師としてイスラエル王国で活躍するのです。
人の妻になれるほどの年齢の女性を孫に持っていたのですから、アヒトフェルはかなりの高齢だと考えられます。
ということは、彼が賢者であるという評判は、かなり以前から広まっていたことになります。
ダビデは賢者としての評判の高いアヒトフェルを自陣営に取り込もうとしたのではないでしょうか。
その結果、アヒトフェルとの話がまとまり、彼がダビデ陣営に投じる証拠として、孫娘を与える、ということになったというのも、あり得る話です。
というか、ダビデぐらいの腹芸の名人になると、それぐらいのことが背景にないと、不倫劇など演じそうにないように思えます。
前にも書いたように、ダビデは大量の妻妾に大量の子を産ませています。
その数多くの子の中で、最終的にダビデの王位を継いだのは、バト・シェバの産んだ子ソロモンだったのです。
徹底した政治的人間であったダビデの後継者の座を射止めたのですから、ソロモンの母のバト・シェバもまた、強い政治力を持っていたと考えられます。
ヤハウェとの確執の始まり
これまで、ダビデはヤハウェとうまくやってきました。
ヤハウェは妬み心が強く、しかもあまり公正ではありません。
ちょっとしたことで激怒し、人に祟ります。
これは神としてのヤハウェの本来の性格ではなく、ヤハウェを担いだ神官団の集団的な性格であったと思われますが、いずれにしろ扱いにくことには変わりありません。
サウルはこの神官団とうまくやっていくことができず、喧嘩別れしてしまいました。
その後神官団がサウルの代わりにダビデを担いでやってきた、というのはこれまで説明した通りです。
ダビデはこれまた繰り返してきたように、政治力に手足が生えたような人間でしたから、気難しいヤハウェや神官団を怒らせず、友好的な関係を維持し続けました。
ダビデが時折見せる極度に偽善的な態度は、ひょっとすると対神官団用の仮面だったのかも知れません。
しかしこの関係も、バト・シェバの一件でほころびを見せ始めます。
バト・シェバ事件の後、ヤハウェは「預言者ナタン」という人物をダビデの元に遣わし、ダビデの不品行を責めます。
この時ダビデは素直に、「わたしは罪を犯しました」とナタンに告白します。
ナタンはダビデに「あなたの罪は除かれた。あなたは死ぬことはないだろう。だが、あなたの子供たちは死ぬだろう」と言いました。
「不倫事件」でバト・シェバに宿った子は、出生はしましたがまもなく死んでしまいます。
「サムエル記」ではこれは神の怒りの結果だと言いますが、この後ダビデの跡目争いが激化していくので、果たして本当に神の怒り、つまり準自然死であったかどうかはわかりません。
さてダビデには多数の子がありましたが、その最年長者はアヒノアムを母とするアムノンでした。
ダビデの初婚の相手は、このアヒノアムかサウルの娘ミカルのどちらかではないかと言われています。
若い頃の妻なので、政略結婚としての要素は薄く、純粋な恋愛の結果結ばれた可能性もなくはありません。
逆に言うとそういう母なので、息子の政治勢力もまた大きくはなりません。
「最年長の男子である」という大義名分だけを利用されるような存在だったと思われます。
ちなみにダビデの次男は、アビガイルが産んだキルアブです。
アビガイルは政治的な思考のできる賢い女性でした。
その政治的基盤も弱小勢力だった時代のダビデにとっては非常にありがたいものだったでしょうが、ダビデが統一イスラエル王国の支配者となると、相対的にその地位は低下します。
賢いアビガイルはその点を理解し、徐々に身を引いていったと思われます。
次男キルアブはダビデの後継者候補に挙げられることはありませんでしたが、そのため血なまぐさい跡目争いに巻き込まれることもありませんでした。
ダビデの三男は、ゲシュル王タルマイの娘マアカが産んだアブサロムです。
王を名乗る人物の娘ですから、ダビデの初期の妻の中でこれを上回る政治力を持ち得たのはサウルの娘ミカルのみです。
ただサウルが死んだ後はその立場は非常に微妙なものになりましたし、ミカルはダビデとの間に子をもうけなかったので、「後継者争い」においては圏外となりました。
ともかく、ダビデの後継者レースの初期段階においては、「正統性」を持つ長男アムノンと、「政治力」のある三男アブサロムがトップ集団を形成していました。
情勢としては「アブサロムやや有利」といったところでしょうか。
「サムエル記」はアブサロムには美人の同母妹タマルがいた、と伝えています。
アブサロムとタマルの兄妹仲は非常によかった、とも。
このタマルにアムノンが横恋慕します。
アムノンはタマルの異母兄に当たりますが、ダビデの時代においては、異母であれば兄妹の結婚は認められていたようです。
ただし王族の間では、正式な婚礼の儀式を経た後でなければ、肉体関係を持ってはならないとされていました。
ちなみにダビデとバト・シェバの場合、片方は王ですが他方は家臣の妻であって王族ではないので、正式な儀式を通さずいきなり肉体関係でもオッケーということになっていました。
さてアムノンですが、結局正式な儀式を経ずにタマルを無理やり犯してしまいます。
あのダビデの息子ですから、タマルに迫ったのは単に下半身がそう命じたからだと考えるのは難しく、タマルを通じて自分の王位継承権をより確かなものにしようとしたと考えた方が自然です。
強姦という結果になってしまったのは、どこかでボタンの掛け違いが生じたためではないでしょうか。
「サムエル記」では、タマルを犯したアムノンは、その直後からタマルを激しく憎むようになったというのです。
アブサロムはまもなくタマルが長兄に何をされたのかを知り、それを父ダビデに告げます。
ダビデは激怒したと言います。
一方、アブサロムは兄に対して感情を押し殺して接します。
この人もやはりダビデの息子らしいですね。
異母妹を強姦するという、決定的なスキャンダルのネタを握り、早々にライバルを葬り去る決意を固めたとは思いますが、それを最も効果的に果たせる機会を待っていたようです。
満二年後、アブサロムはバアル・ハゾルの街で「羊の毛を切る」という儀式を開催します。
彼はそこに王の息子、つまり自分の兄弟たちを、同母異母問わず呼び集めました。
アブサロムは父ダビデの元に行き、王と王の部下たちにも来て欲しいと頼みましたが、ダビデは「いや行く必要はない」と断りました。
ダビデは何かよからぬことが起こると察し、現場に行かないことで自分の身の安泰をはかったのでしょう。いつものやり口です。
アブサロムは儀式の会場に、ごく当たり前のように自分の部下を伏せておきました。
そしてタイミングを見計らうと、部下たちを起たせて兄弟たちの面前でアムノンを殺害したのです。
兄弟たちは、自分たちがターゲットであったわけでもないのに恐怖して逃げ散ってしまいました。
アブサロムは最大のライバルを消すと同時に、他の競争者に「アブサロムには勝てない」という意識を植え込もうと考えていたようです。
結果は思った通りになりました。
事件の後、まもなくダビデの元に「アブサロムが王の子を皆殺しにした」というニュースが飛び込みます。
ダビデは例によって着物を切り裂いて嘆き悲しみます。
この時、ダビデの甥にあたるヨナダブは、「王よ、アブサロムは王の子すべてを殺したのではありません。殺したのはアムノンだけです」とささやきます。
この人も、政治的に物事を考える人だったと見えます。
アブサロムは現場から逃走し、ゲシュル王タルマイ、つまり自分の祖父の元に身を隠します。
ダビデは密かに人を遣わし、アブサロムと交渉したようです。
アブサロムの潜在的な政治力を認めたのでしょう。
交渉は3年の長きに渡りました。
交渉の結果ダビデは、アブサロムを後継者とする他はない、と思うようになったようです。
ここでダビデの第一の部将ヨアブが仲介し、アブサロムはイェルサレムに戻りました。
アブサロムの叛乱
イェルサレムに戻ってからのアブサロムは、「辻立ち」を始めるようになりました。
つまり、朝早くからイェルサレムの城門に立ち、住民に手を振って挨拶をするようになったというのです。
現代の政治家のようなことをするものですね。
それと同時に、密かに自分の家に武器を蓄えるようにもなりました。
「サムエル記」はすべての事件が起こった後の人物の視点から描かれていますから、アブサロムはイェルサレムに帰還してからすぐに叛乱を企んだように見えます。
ですが本当にそうだったでしょうか。
当初は単に自分の政治的な立場を強化したいがために、地元民とのふれあいを重視したと考えられます。
何しろアブサロムの政治力の源泉は、母方の祖父が支配する王国なのですから、イェルサレムではかなり弱体化してしまいます。
そのことを察知し、弱点を補強しようと考えるのは、徹底した政治人間であるダビデの息子としては当たり前の行動のように思われます。
同じようなことは、世界中の王位継承権者がやっていることです。
ただし、少なからぬ王位継承権者が、この手の行動を熱心にやりすぎた結果、父である王そのものの権力機構と激突しています。
アブサロムも、このパターンに見事にはまってしまったように見えます。
アブサロムは4年の後、旧都ヘブロンで挙兵します。
イスラエル国内の各勢力は大部分がアブサロムの側につき、ダビデの側に残ったのはクレタ人・ペレティ人・ガト人だけだったと言います。
勝ち目がないと思ったダビデはイェルサレムを退去します。
しかしただ逃げただけではありません。
ヤハウェ神官団はイェルサレムに残り、都の情報を随時ダビデに送ることにしました。
ダビデの元に次々とイェルサレムからの情報がもたらされます。
その中に「アヒトフェルがアブサロムの側についた」というものがありました。
アヒトフェルはすでに説明したように、バト・シェバの祖父とされる賢者・大軍師です。
ダビデは「アヒトフェルの計略がことごとく外れますように」と祈りますが、どこまで本気だったのかはわかりません。
さてアヒトフェルはアブサロムに、「夜襲をしよう」と持ちかけます。
アブサロムはその申し出に乗り気になったのですが、イェルサレムに残っていたダビデのスパイが反対します。
「ダビデとその配下は歴戦の勇者揃いだから少数で激突するのは不利だ。味方に被害が出ると『やはりダビデは強い』という噂が流れ、離反者が出る。だからひたすら数を集めて押しつぶすべきである」と。
アブサロムはアヒトフェルの策を取らず、スパイの策の方を採用しました。
アヒトフェルはアブサロムの元を去り、自分の故郷に戻って自殺した、といいます。
中国・漢楚の攻防戦の時の項羽側の老軍師・范増の最期を連想させます。
ダビデとアブサロムの戦いは、アヒトフェルの退場により形勢が逆転したようです。
この間にダビデは反撃体勢を整えるための時間を稼ぐことができました。
なお、イスラエル王国最強の将軍であるヨアブはダビデから離反せずに健在です。
ダビデは手元の兵力を三つに分け、ひとつをヨアブに、もうひとつをヨアブの兄弟アビシャイに、もうひとつをガテ人のイッタイに預けます。
そして例によって自分は動かず、部将たちをイェルサレムに突入させました。
「アブサロムを殺すなよ」と諸将に伝達していましたが、それを額面通り受け取っていたものがいたかどうか。
アブサロムの軍は壊滅し、アブサロム本人は逃亡の途中で森の木にひっかかり、身動きが取れなくなってしまいました。
そこにヨアブの軍が迫ります。
アブサロムを最初に発見した兵士がヨアブにそのことを告げます。
ヨアブは「なぜ殺さない」と一喝しました。
兵士は「王が殺すなと言ったから、自分にはできない」と反駁します。
ヨアブは自らアブサロムのところに行き、槍を投げてアブサロムを殺しました。
王が「殺すな」と言っていたにも関わらず、ためらわずアブサロムの命を絶ったのは、「王の本音」を知っていたからでしょう。
伊達に長く付き合っているわけではありません。
アブサロムが死んだという報告を受けた老王ダビデは、例によって衣服を切り裂いてその名を呼び、泣き叫びました。
ヨアブは命令違反を犯したとして全軍の指揮官を解任されましたが、それでおしまいで刑罰を与えられることはありませんでした。
ただ、ダビデの側ではいつでもこの古傷をほじくり返してヨアブを処分できるようになったとも言えます。
新しいイスラエル軍司令官には、アブサロムの配下だったアマサという人物が指名されます。
滅ぼした勢力側の人物を登用してそれ以上の叛乱を防止しようという、ダビデらしい人事と言えます。
ただこのような「気配り人事」をしたにも関わらず、叛乱は収まりません。
「サムエル記」には詳しいことは書かれていませんが、どうやら晩年のダビデはイスラエルを一種の官僚国家に変えていこうとしており、それが旧来の部族制の伝統を守ろうとしていた人々の利害と衝突したらしいのです。
次に武力蜂起したのは、ベニヤミン部族のシェバという人でした。
ダビデは新将軍アマサを派遣して鎮圧しようとしましたが、うまく行きません。
ここで引退したはずのヨアブがまた出てきます。
ヨアブはアマサの陣中に行くとアマサを殺害してしまい、まだ軍内部で勢力を持っていた兄弟のアビシャイと一緒にシェバを討伐したのです。
戦いの後ヨアブはイェルサレムに凱旋し、ダビデはヨアブを全軍の総司令官に再任してしまいました。
「サムエル記」の終わり
上下に分かれている「サムエル記」は、士師サムエルの名を冠してはいますが、サムエルは「サムエル記上」の前半部分にしか登場しません。
「サムエル記上」の後半の主役はサウルですし、「サムエル記下」ではダビデが主人公となっています。
その「サムエル記下」の最後の部分には、ダビデが老いてその支配が緩んでいった(ように見える)有様が記されています。
「サムエル記下」は全部で22章ありますが、その最後になる第22章は、「ダビデが民の数を数えた」という記事が記されています。
「サムエル記」では、これは神に対する大きな罪であった、としています。
ダビデがなぜ民の数を数えたかというと、それは「動員できる兵数の確認をしたかったから」と言われています。
普通の支配者は、「どれぐらい徴税できるか」を確認するために人口調査をするものですが。
これがなぜ神に対する罪になるのでしょうか。
古代イスラエルにおいては、戦争は「神によって起こされるもの」でした。
戦闘の結果は、ヤハウェが決めるものであり、イスラエルの民の指導者であっても、ヤハウェが現れなかった戦いには敗れるとされていたのです。
動員兵数を確認する、ということは、戦いの結果を神の意思ではなく、人間の王の戦略に帰そうとすることです。
これがヤハウェとヤハウェを担ぐ神官団の不興を買うのです。
「戦いに勝ちたければ神に祈れ。兵数を数えて戦略・戦術で勝とうとするんじゃない」。
現代の常識からすれば信じがたいことですが、これが当時の「常識」だったのです。
戦争の結果に責任を負うものが、神から王へと移っていくと、民の信仰の対象も神から王へと移っていきかねません。
世界中どこの地域でも、こうした「神と王」との抗争は発生し、最終的には「王」、つまり人の勝利で終わります。
ただ、イスラエル王国の場合、他の王国と比べるとこの抗争そのものが発生するのはかなり遅れていました。
ダビデ王はイスラエル王国を「神の支配する国」から「王(人)の支配する国」に近づけようとしましたが、その目的を完全に果たすことはできなかったのです。
ソロモンの即位
ダビデが老いたことを匂わせつつ「サムエル記」は終わり、その後を「列王記」が引き継ぎます。
内容的に重複がなくぴったり続いているので、「サムエル記」と「列王記」は元々ひとつの文書だったのではないかと考えられています。
「サムエル記」同様、「列王記」も上・下巻に分かれています。
「列王記上」の冒頭に登場するのは、「サムエル記」よりもさらに老いが進んだダビデの姿です。
夜眠る時に身体が冷えてしかたがないので、抱き枕代わりに若い乙女が欲しい、と老王は訴えます。
その結果アビシャグという美少女が選ばれるのですが、「王は彼女を知ることがなかった」のだそうです。
あれだけ大量の美女に子を産ませたダビデ王が、です。
アブサロム死後、ダビデの存命の息子の中での最年長者はアドニヤでした。
彼の母はハギテと言いますが、名前とアドニヤの母であること以外の事績が伝わっていません。
ちなみに次男キルアブはこの頃生死不明ですが、多くの聖書学者は死んでいたとしているようです。
以前述べたように、政治的な能力があり、賢かった母アビガイルの助言によって、王位争いから早々に手を引いていた可能性もないわけではありませんが。
アドニヤは賢い母を持っていたわけでもなかったので、アブサロムの叛乱以後「次の王は俺だ」と思い込むようになりました。
そしてアブサロムと全く同じコースを辿って転落していきました。
つまり、父王が生きている間に自分の回りに危険な連中を集めすぎ、父の側近たちに疎まれて討伐されてしまうのです。
今回アドニヤの周辺に集まったのは、大祭司アビヤタルや軍の総司令官のヨアブなど、ダビデ政府の高官中の高官です。
この二人についてはアドニヤが王になろうと思ってすぐに相談した、となっていますので、実態はこの二人を代表とするダビデの草創期の家臣団(すでにかなり出世していた)が、アドニヤを担いだというものだったのかも知れません。
保守層はダビデがその治世の後半に行った「神からの王権の独立運動」に対して批判的だったと思われますから。
逆に民の数を数える企てを推進していった若い層は、アドニヤを支持しませんでした。
祭司団ではザドクが、軍人ではベナヤと、恐らく彼が率いていた「ダビデの勇士」つまり現役の近衛兵団が、さらにはナタンなどの「預言者」たちが反アドニヤ派を形成したのです。
彼らはダビデとバト・シェバの間の第二子(第一子は生まれてすぐに死んでいました)であるソロモンを王とするように活動を開始します。
アドニヤはイェルサレムの郊外で、大規模な犠牲の式を執り行なおうとし、自分の兄弟や王国の高官たちを招待します。
ただ、ソロモン派と考えられていた人々は呼びませんでした。
宴を行う場所の背後にはヨアブ率いる軍隊が集結しているはずで、その力を背景にアドニヤは王への即位を宣言し、そのままイェルサレムに突入してダビデを拘束、自分の王位を認めさせようと考えたのでしょう。
完璧な作戦でした。
情報が事前に反アドニヤ派に漏れていなければ、ですが。
預言者ナタンはいち早く「アドニヤ即位を宣言(か)」という情報を入手し、ダビデの晩年の妻バト・シェバの元に駆け込みます。
そして「このままではあなたの子ソロモンの命が危ないので、ダビデ王の元に行きソロモンを王とするように嘆願しなさい」と告げたのです。
バト・シェバはナタンの言う通りにしました。
どうやら、以前にダビデはバト・シェバに対し、「お前の子ソロモンを次の王とする」と約束していたようでした。
バト・シェバはその約束を今すぐ履行するようにと訴えます。
バト・シェバによる説得が一段落した頃合いを見計らって、今度はナタンがダビデの前に現れ、アドニヤが事実上謀反を起こした、すぐに対処せよとダビデに迫ります。
四十年におよぶダビデの治世における、最後の政治的な危機でした。
老いてはいましたが、ダビデはここでもいつものように緻密な政治的な計算を行い、最適解を弾き出したようです。
「ソロモンを王とする儀式を行う」とダビデはふたりに告げました。
祭司ザドクとナタンはイェルサレムに残っていた人々をかき集め、ソロモンに聖油を注ぐ儀式を行います。
油が注がれた瞬間、人々は「ソロモン王万歳」と叫び、ラッパが鳴らされます。
その音は郊外で「即位宣言」をしようとしていたアドニヤとその愉快な仲間たちの耳にも届きました。
ヨアブが「街のあの騒ぎは何だ」と叫びます。
その直後にイェルサレムからの使いがやってきて、「ソロモンが即位しました」と一同に伝えます。
アドニヤの周囲にいた人々は、これで蜘蛛の子を散らすように去ってしまいました。
こちらにはヨアブがいましたが、精鋭中の精鋭である近衛部隊はダビデおよびソロモンの手中にあります。
加えてダビデには同じようなシチュエーションでアブサロムの軍を撃破した経験もありました。
ついでに言うとヨアブにはこういう時に何度も叛乱側を裏切り、王に味方したという過去がありました。
アドニヤの周りにいた人々が「もうダメだ」と思ったのもやむを得ないと言うべきでしょう。
アドニヤはソロモンに降伏し、命乞いをしました。
ソロモンは一応アドニヤの命の保証をしてやりましたが、それがいつまで続くかはわかりません。
ダビデの死
波乱万丈であったダビデの生涯最後の大事件が終わりました。
後継者もソロモンと確定したので、ダビデはもう静かに死を迎えるだけ、という状況になります。
死期を悟ったダビデはソロモンを呼び寄せ、遺言を語ります。
イスラエルの王の遺言ですから、その大半は「ヤハウェにしっかり仕えてその律法を守るのだ」といった感じの内容ですが、そうでないものもありました。
それは「わしが死んだら軍総司令官のヨアブを殺せ」というものです。
その理由は、サウルの子イシュ・ボシェテの将軍であったアブネルをヨアブが殺したから、というものでした。
ヨアブはアブネルだけでなく、ダビデの子であるアブサロムを殺した張本人でもあるのですが、そちらについてはなぜか不問となっています。
実を言うとダビデはソロモンに「ヨアブを殺せ」とダイレクトに言ったわけではありません。
「あなたの知恵にしたがって事を行い、彼のしらがを安らかに陰府に下らせてはならない」と言ったのです。
腹芸の名人ダビデらしいもって回った言い方ですが、どう解釈しても「殺せ」となりますよね。
さてダビデは死に、ソロモンは名実ともにイスラエルの王となります。
そして「自分の知恵で考えて」邪魔者を消し始めるのです。
ダビデがヨアブとともに「殺せ」と遺言したのは、生前ダビデを呪詛し続けたシメイという男でした。
しかしソロモンは熟慮の末に、まず異母兄アドニヤを始末しようと考えたのでした。
「列王記上」は、ダビデの死後ほどなく、アドニヤがバト・シェバに対して「父ダビデの最後の妾であったアビシャグを私の妻として与えてくれ」と要求したことを伝えています。
アビシャグが美人であったから結婚したくなった、と額面通りに受け取ることはできません。
ダビデの死後その妻妾はソロモンとバト・シェバの管理下に入っており、そのメンバーを妻として受け入れることは、自分の家の中のことがソロモンに筒抜けになることを覚悟した結果とも思えます。
ただ、「列王記」の記述からは、「俺は元々この王国全部を手に入れるはずだったんだ。すべてを失った今オヤジの手つかずの愛妾ぐらい受け取ったっていいだろ」という奢った気持ちを抱いていたように読み取れもします。
しかしこんな感じで「俺はまだ反省してない」という発言をしてしまうと、必ず弟はそれを理由として自分を殺すだろう、ということをあのダビデの息子であるアドニヤが想像できないとも思えません。
実際、ソロモンはこれを口実としてすぐさま将軍ベナヤに命じてアドニヤを処刑させてしまいました。
続いてソロモンは、大祭司アビヤタルを追放します。
これを聞いたヨアブは、次は自分の番だと思い、「主の幕屋」に逃れますが、ソロモンはまたもベナヤを派遣し、これを殺してしまいました。
シメイについては、父ダビデは「必ず殺せ」と言っていましたが、ソロモンはとりあえず除名し、「イェルサレムの外に出るな」と言いつけて事実上の監禁状態とします。
しかししばらく後にシメイがイェルサレム市外に出てしまったことを聞きつけ、それを理由に処分してしまいました。
今度も実際に手を汚したのはベナヤです。
ソロモンはこうやって、ベナヤが自分の手足となっていかなる汚れ仕事でもやってくれるかどうかを試したのかも知れません。
ベナヤはソロモンの期待どおりに行動してくれたので、ソロモンは彼を死んだヨアブに代えてイスラエル全軍の司令官の地位につけました。
またベナヤと並ぶ側近であるザドクを大祭司に任じています。
ソロモンの大岡裁き
サウルからダビデの時代は、言ってみれば「大征服の時代」でした。
イスラエル王国は周囲の部族に対して攻勢に出、支配領域を拡大し続けたのです。
これはその前の「士師の時代」に有力な指導者がおらず、イスラエルの民が周囲の民族の支配下におかれていたことの反動ですから、ある意味やむを得ない部分があります。
特にダビデは有能な軍人だったので、大征服活動はうまく行きました。
ただ、周囲を侵略する征服国家には、それなりの弱点も生まれるようになります。
軍隊の規模が大きくなり、王が直接管理できないようになると、将軍たちに実権が移り、クーデターが発生しやすくなってしまうのです。
言ってみればヨアブは、そういう「危険な将軍」でした。
ただ軍人として有能であり、外部勢力と戦う場合には欠かせないので、ダビデは死ぬまでヨアブを使い続けたのです。
さてダビデが死に、後を継いだソロモンは、国家の方針を外征中心から内政中心に切り替えて行きます。
積極的に外征を行いませんから、軍隊の規模を縮小することができます。
父ダビデがヤハウェの不興を買いながら人口調査を行い、自国の兵数を正確に把握できるようにしましたから、軍縮もまた可能となったのです。
一方的な軍縮を行うと、周囲の国家に軽く見られ、再び侵略を受けるようになりかねませんが、ソロモンはその点を外交力でカバーしようとしました。
ダビデは大量の妻を持っていました。
彼女たちは一部を除くと王の娘ではなく、イスラエル内部の有力部族または集団の出身です。
ですからダビデの晩年には、それぞれの妻の出身部族がその妻の産んだ子を押し立てて、イスラエルの実権を握ろうと画策し、内乱を引き起こしていました。
ソロモンはこうした内部抗争を避けるため、外部の大国から妻を迎えることにしました。
もちろん、父ダビデが熱心に外征を進め、イスラエルを大国に押し上げていたからこそ可能になった政策です。
ソロモンの妻となったのは、エジプトのパロ(ファラオ)の娘です。
またヤハウェ祭司団との関係も良好であったようです。
ある時ソロモンの夢にヤハウェが現れ、ソロモンは神のしもべとしてヤハウェの民を裁くことのできる知恵を求めました。
ヤハウェはこれをよしとしたのです。
王としての名誉であるとか、財産であるとか、長命であるとかを求めず、あくまでも神の代理人の立場で人々を裁くための知恵が欲しい、と言ったところをヤハウェは気に入ったようです。
こうしてソロモンは「知恵ある王」ということで、周囲に評価されるようになりました。
ある時、二人の遊女がソロモンのところにやってきて、裁きを求めました。
一人の遊女は、彼女たちは最近それぞれ子を産んだのですが、片方の遊女は寝ている時に自分の子を押しつぶして死なせてしまいました。
子を死なせてしまった遊女は別の遊女から子を奪い、自分の死んだ子をその遊女に押し付けた、と言いました。
もちろん、もう一人の遊女は、これは奪った他の遊女の子ではなく、自分が産んだ子である、と主張します。
ソロモンは「刀を持ってこい」と近臣に命じます。
そして刀を受け取ると「子供を二つに分けてそれぞれをお前たちに与えよう」と言いました。
一人の遊女は「分けてください」と言いましたが、もう一人は、「この子はあちらの子ということで構いません。ですから命は取らないでください」と言ったのです。
そこでソロモンは「子の命乞いをしたこの女こそ真の母親である」と厳かに宣言したと言います。
これ、どこかで聞いたことのあるような話ではないでしょうか。
子供を刀で二つに分ける、という物騒な展開にこそなっていませんが、名奉行と言われた大岡越前守忠相による「大岡裁き」のエピソードと酷似しています。
実は大岡裁きのエピソードは、ソロモンのこの話を元ネタとしているのだそうです。
外交と土木事業
さてソロモンは、父ダビデが築いた土台の上に、平和外交政策を展開します。
「ソロモンは賢者である」という評判があちこちに流れていったため、賢者ソロモンをひと目見ようと遠方の大国から王やそれに準ずる使節がイェルサレムを訪問するようになりました。
こうなると、外国からのお客を驚かすような大建築物が欲しくなってきます。
イスラエルの民はずっとヤハウェを崇拝していましたが、これまでヤハウェのための神殿を建てることはありませんでした。
ダビデはこの神殿を建てようと計画をしたのですが、ヤハウェに拒絶されています。
ヤハウェは自分の偶像を作ることを厳しく禁じていますが、契約の聖櫃のような礼拝の対象になるようなアイテムは存在しました。
この聖櫃は、「ヤハウェの幕屋」というテントに納められていたようなのです。
はるばる遠くからやってきた外交使節にテントを見せるのはいくらなんでもちょっとアレです。
なので、ソロモンはイェルサレムにヤハウェの神殿を建てることにしました。
ソロモンはこの神殿建設に、七年という月日をかけています。
ソロモンの土木事業は、イェルサレム神殿の建設だけではありません。
彼はイェルサレム王国内の各都市を、通商拠点として整備していきました。
同時に、城壁などをしっかりと作り、周辺の異民族からの攻撃に対応できるようにしたのです。
みだりに軍を動かし、戦争をしなかったという点では、ソロモンの治世は善政であったと言えるでしょう。
こうした土木事業や通商がスムーズに進むように官僚制度も整えていたので、ソロモンが賢者であったというのも嘘ではなかったと思われます。
ソロモンの名声は遠くエチオピアの地にまで達し、その地を治める「シバの女王」が、ソロモンが本当に賢者であることを確認するためにイェルサレムにやってきました。
シバの女王はソロモンに次々と問を発しますが、ソロモンはそのすべてにすらすらと答えました。
シバの女王はソロモンの叡智は噂通りであったと感心し、ついでイェルサレムの神殿と王宮の壮麗さを褒め称えます。
そして大量の贈り物をソロモンに献じました。
ソロモンもまたシバの女王に大量の贈り物をしました。
他の国の王侯がイェルサレムを訪問した時も同様にしたのですが、この「交易」は全体としてはイスラエル王国の黒字ということになっていたようです。
ソロモンは莫大な富を手に入れたと言われます。
ただ大規模な土木事業の陰には、その経費を賄うための重税があったと想像され、これが徐々にソロモンの統治に対する不満として蓄積していったようでもあります。
国際化のツケ
ソロモンは平和攻勢・通商国家化で、イスラエル王国にかつてない繁栄をもたらしました。
歴史学的に言えば間違いなく「全盛期の王」なのですが、イスラエルの民からの評価は父ダビデに及びません。
その理由は「あまりにも国際化を推し進めてしまったから」という点にあります。
ソロモンはその治世の末期になると、父ダビデと同様に大勢の女性を自分の妾とするようになります。
ダビデの場合には自分の立場を固めるための政略結婚ですが、ソロモンの場合そんなことをする必要性はかなり薄くなっているので、単に女好きだったからではないかと思われます。
外国の使者が「貢物です」と女性を連れてきて、それを受け取ってそのまま妾とした、というケースもあったでしょう。
どうやらこれと似たようなことが、ソロモン王だけでなくイスラエルの国民全体に起こったようなのです。
つまり、通商で富を蓄えた商人が財産の延長のような形で外国人の妾を集めるようになり、一般の国民も他民族の妻を普通に迎えるようになった、ということです。
普通の国ならどうということはないことなのですが、イスラエル王国というちょっと特殊な国にとっては、これは大事でした。
イスラエル王国は、ヤハウェという個性的な神を唯一絶対の信仰対象とする宗教を根底に持つ国家です。
他民族との結婚がごく普通に見られるようになると、他民族の信仰がイスラエル王国内部に流れ込んでくることになります。
主に流れ込んでくるのは、中東地域でイスラエルの民以外に広く信じられていたバアルやアスタルテの信仰です。
バアルは若くてイケメンの男の豊穣神、アスタルテはその妹にして妻であるチャーミングな女の豊穣神です。
ヤハウェは堅物なので、子を授かることを目的としない性行為を厳しく制限していますが、バアルやアスタルテはそんな無粋なことは言いません。
男も女も「あっこれいいな」という相手が見つかったら、すぐ性行為をしていいよ、と教えています。
こうした異なる教えを突きつけられて「どっちを選ぶ?」と言われてヤハウェの教えを選ぶ人は少ないのではないでしょうか。
どう考えても「異教」の方が明るく楽しげです。
実際、イスラエルの民はこうした周囲からの「文化侵略」をこれまで何度も受けており、それを内戦の原因にしてきた、という歴史を持っていました。
ソロモンによる繁栄の陰で、またも分裂の気配が漂いはじめていたのです。
肝心のソロモン王ですが、これら忍び寄る「異教」に対しては寛容であり、民衆レベルでのバアルやアスタルテ信仰については黙認していました。
この変化について「列王記」は、ソロモンは七百人の妻、三百人の妾を持っていたので、彼女たちがソロモンを惑わした結果である、と述べています。
しかし、女の色香で迷うほど、ソロモンの知恵のレベルが低かったとは思えません。
合わせて千人の妻妾を得たのは多分に個人の趣味が混じっていると思われますが、宗教政策に関しては、今後イスラエル王国は通商国家として生きていく以上仕方がない、と割り切っていたのでしょう。
ヤハウェはソロモンの「心変わり」を激しく責めています。
ですが、ソロモンほどの智者が、そうなることを予想していないはずはありません。
何しろダビデ家は、敵味方の心理を詳しく分析し、その時点で打倒すべき敵以外は全部抱き込んで目的を達する、ということを繰り返してきた家です。
だからソロモンのこの「反逆」は、あえてやったものであると思わざるを得ないのです。
ヤハウェは異民族であるエドム人のハダデの味方をし、これをソロモンの対抗馬とします。
エドム人はかつてダビデの命を受けたヨアブによって、「男子皆殺し」の目に遭ったことがあります。
まだ少年だったハダデは殺戮を避けてエジプトに逃れ、パロの庇護を受けていたというのです。
ハダデはエジプトで頭角を現し、パロの娘を娶ったといいます。
なんだかヤコブの子ヨセフに似ています。
ヤハウェはさらに多くの異民族出身の人物を、ソロモンの敵として立てます。
その大部分は、ダビデによって滅ぼされた民族の生き残りでした。
ヤハウェが契約を結んだイスラエルの民以外の人物を引き立てたのは、何度も述べたようにソロモンが異教の神々を容認したからです。
その神々について、「列王記」は、「シドン人の女神アシタロテと、モアブの神ケモシと、アンモンの人々の神ミルコム」と列記しています。
アシタロテはアスタルテのことです。
何度も言及したので解説は不要でしょう。
「モアブ人の神ケモン」というのはメソポタミアの太陽神シャマシュのことだと言われます。
最後のミルコムですが、モレクまたはモロクと呼ばれた神だと言われます。
この神は信者に子供を人身御供として捧げることを強要する神で、バアルやアスタルテなどの明るいイメージの神とは一線を画しています。
どちらかというとその性格はヤハウェの方に近いと言えるでしょう。
これらの反逆者のその後については、あまり詳しいことは残されていません。
ソロモンと敵対したとはいえ、その王権を脅かすまでにはいかなかったようで、ソロモンが死ぬまでイスラエル国外に隠れていたような記述が、「列王記」には見られます。
ソロモンが治世四十年で死ぬと、王位は子のレハブアムに継承されました。
レハブアムは父ソロモン同様の政策を推し進めましたが、ソロモンの治世中に蓄積された矛盾(重税による民の疲弊など)が顕在化します。
北部の十部族はエジプトからヤロブアムという人物を呼び寄せ、レハブアム王から独立します。
ヤロブアムの王国はイスラエルを名乗り、レハブアムが引き継いだダビデ・ソロモン以来の王国はユダ王国と呼ばれました。
ソロモンと七十二柱
オカルトやファンタジーの世界では、ソロモン王のイメージはイスラエル王国最盛期の王ではなく、悪魔たちを使役したオカルティックな王、というものの方が強くなっています。
すでに述べたように、ソロモンはそれまでのイスラエルの民の指導者と比べると、桁外れに「異教」に寛容な人物でした。
また偉大なる賢者であるという噂が生前からありました。
これらが元になり、「ソロモンはその底しれぬ知恵により、異教の神すらも支配したのだ」というイメージが作られていったのでしょう。
このイメージが確定するのは、「旧約聖書」や「新約聖書」ではなく、イスラームの世界においてです。
イスラームの伝承(もちろん、正統な教えとされるものではありません)では、スレイマーン(ソロモン)はジン(精霊)の力を借りてさまざまな魔神を使役したとされているのです。
これが中世になってから、ヨーロッパに輸入され「悪魔学」の元ネタとなっていきます。
旧約聖書に登場する「異教の神」は、何度も言及しているバアル・アスタルテに、ダゴン、ケモン、ミルコムなどが中心で、全部合わせても十指に足りません。
これを「七十二」にまで広げたのは、ヨーロッパの悪魔学徒たちでした。
彼らは定数を七十二にして箔をつけるために、他の地域の異教の神々も手当たりしだいに悪魔化し、「ゴエティア」と呼ばれる一種の経典の中に放り込んでいきます。
圧倒的な定数不足だったのに、なぜかダゴンだけはゴエティアの悪魔の中に数えられませんでした。
その代わり、20世紀になってから「クトゥルフ神話」に「深きものども」の一柱として取り込まれます。
ソロモン七十二柱は、中世になってからオカルト研究者によって、言ってみればでっちあげられた存在であり、その多くの起源はそう古いものではありません。
名前だけ起源が古いものであっても、その神格(悪魔格?)の中身はかなり誤解されており、ほとんど原型を留めていませんでした。
例えばバアルは「バエル」として「七十二柱」の筆頭に挙げられていますが、オリジナルの「イケメンの豊穣神」という面影はかけらもありません。
ゴエティアのバエルは猫・人間・カエルという三つの頭を持ち、蜘蛛の身体を持つキメラ的なモンスターだとされています。
それぞれに何か由緒があるわけではなく、人間から見て不気味そうなものを何も考えずにひっつけただけです。
それでもバエルの場合、旧約聖書に何度もその名が登場するので、悪魔学者も「こいつは重要そうだ」と思い、「七十二柱」の筆頭に置いたのでしょう。
しかしバアルと並んで「旧約聖書」での言及が多いアスタルテは、アスタロトとして序列29位という、意外に低い位置に置かれています。
ご丁寧に性別まで変えられて。
実は「悪魔学」における悪魔の序列というのは文献ごとにバラバラで、「七十二柱」の序列がすべてだというわけではありません。
悪魔学者によっては、アスタロトの地位はルシファーやサタンと並ぶほど高い、とするものもあります。
これらはすべて、統一した原典があってそれを調査したのではなく、悪魔学者たちが「ぼくのかんがえたさいきょうのあくま」を妄想力の赴くままに記していった結果です。
しかし、数多くの悪魔を体系的にまとめあげ、序列をつけたということで「七十二柱」は現代の「永遠の中二」たちの心をがっちりと捕まえてしまったようです。
「七十二柱」の悪魔たちは、さまざまな漫画・アニメにモチーフ的に使われるようになりました。
古いところでは、「デビルマン」にアモン(漫画版だとカイムも)が登場します。
ただ「デビルマン」にはオリジナルの悪魔(ゼノン・サイコジェニー・ジンメンなど)や、悪魔扱いされていなかった古代の女神(シレーヌ=セイレーン)なども出てきます。
ずっと時代が下って、「マギ」では一応七十二柱すべてに出番(ダンジョンの生成者としてですが)があります。
さらに、「機動戦士ガンダム・鉄血のオルフェンズ」には、ガンダムシリーズのモビルスーツの名前として「七十二柱」が使われるはずでした。
とはいえ、結局活躍したのはバルバトスとグシオンぐらいで、バエルは登場はしたものの全くと言っていいほど活躍しない見掛け倒しの機体になってしまっています。







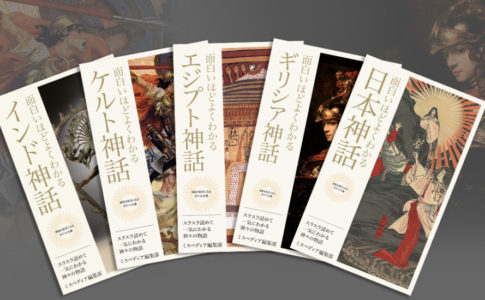































コメントを残す