スポーツが苦手な人はいても、スポーツという単語自体に嫌悪感を持つ人は少ないのではないかと思います。
しかし、宗教という単語を耳にするだけで、何だかぞわっと嫌なものを感じるという人は多いのではないでしょうか。
その一つの理由として、知られていない宗教の実態があります。
今回は世界に存在する様々な宗教の起源と教えを比較、分類し、それが社会に、そして人々にどのような影響を与えているのかを考察していきます。
宗教って何だ?
じつは曖昧な宗教の定義
子供向けの辞書である「国語学習辞典」(日本標準)では、宗教を以下のように説明しています。
神やほとけなどをしんじることによって、心がおちついたり、幸福になろうとすること。また、そのための教え(原文通り)
Goo辞書ではこうなっています。
神・仏などの超越的存在や、聖なるものにかかわる人間の営み。古代から現代に至るまで、世界各地にさまざまな形態のものがみられる(原文通り)
全ての辞書を網羅することはできませんが、この二つの引用を見ても、宗教の説明としてはやや不十分に感じてしまいます。
「じゃあ、宗教ってなんなのさ?」と突っ込みたくなるほどです。
ある学者は世界中にいくつの宗教があるのか数え始めました。
しかし、彼が出した結論は「わからない」というものでした。
つまり世界中に数多くの民族があり、その民族の数よりも多くの宗教があります。
また、明確な教義を保持していなくても、漠然とした神や霊の存在を信じている民族も多くあります。
一般的な表現で「あの人は宗教をやっている」と言えば、それは何かしらの宗教団体に属している、という意味になります。
「私は無宗教です」といえば、それはどの宗教団体にも属していない、ということになります。
しかし実際には、どの宗教団体に属していなくても、神や霊的な存在を信じている人達もいます。
その人達は宗教者ということにはならないのでしょうか。
こう考えていくと、宗教の定義そのものが曖昧であり、何が宗教で何が宗教ではないのか、区別することすらできない、という現実が見えてきます。
じつは宗教という単語は学問用語です。
政治、経済、といった単語と同列に置かれており、人間社会を分類し、整理するために使われています。
では、宗教という単語が登場する以前、古代人が神という存在をどのように感じていたのかを見ていきましょう。
古代人にとっては当然だった神の存在
古代人にとって神の存在は当然の事でした。
それが太陽や月、像であったり、形のない霊的な存在であったり、時には人であったりと違いはあるにせよ、世界中の民族が何かしらの霊的な存在を礼拝していました。
その中で特異な民族が存在していました。
像や神羅万象ではなく、目には見えないけれども人格を持ち、人に語りかける神を礼拝し、その神の言葉を記した聖書を持つイスラエルでした。
イスラエルの神は自分自身を「唯一の神」「真実の神」としてイスラエルに現しました。
そして他の民族が礼拝している神々はすべて偽物であるとしました。
聖書によれば神は世界を造り、支配しておられるお方です。
人は神に愛される大切な存在として造られましたが、人は神に背き、罪人となりました。
神はその人を愛し、罪を許してくださるお方であり、イスラエルはその神の言葉を記した聖書を保持するために特別に選ばれた民族である、とされています。
聖書によればこの唯一の神以外の神々はみな偶像であり、偶像を礼拝する事は罪であり、真実の神への反逆です。
このイスラエル人の信仰は、現在はユダヤ教、そしてキリスト教として分類されています。
この信仰のゆえに、イスラエルは多くの民族に敵視されました。
他民族にとってみればイスラエルは自分達だけが正しい、聖なる民であるというプライドの塊にしか見えません。
またイスラエルにとっても偶像礼拝者である他民族は関わりを持ってはならない存在となりました。
このように、唯一の神の存在を信じる宗教を「一神教」、様々な神々の存在を信じる宗教を「多神教」と呼びます。
一神教にとって多神教は罪深いものであり、多神教にとって一神教は排他的な存在となってしまうため、この二つの間にある溝は埋まることがありません。
ローマの時代~宗教という枠組みの登場~
さて、一神教であれ、多神教であれ、神に対する礼拝が一般的であった人々の価値観は、ローマ帝国がヨーロッパと中東における支配権を確立した頃から変わり始めます。
ローマがもたらしたのはギリシャ文化と呼ばれる価値観でした。
ギリシャ文化は物事を分類し、整理することを好みます。
知的な事柄と霊的な事柄は区別され、肉体と感情は区別されます。
現在の学問と社会はこのギリシャ文化に強い影響を受けており、算数、国語、理科、社会と教科が分かれているのもギリシャ文化から生まれた学習方法です。
その中で「宗教」という枠組みが生まれました。
つまり、知的な事柄の探求と霊的な事柄の探求は違う方向を向くものであり、知的な探求は学問、科学などと称され、霊的な探求は宗教と称されるようになったのです。
この時代が一つの分岐点となり、神の存在そのものを否定する無神論、無宗教と呼ばれる価値観に立つ人達が登場するようになりました。
無神論の立場によれば、宗教とは人間にとって価値がないものであり、宗教にのめりこんでいる人達は理性的ではない、ということになります。
進化論も無神論の立場から登場してきました。
こうして一神教と多神教の対立に加え、宗教者と無神論者という新たな対立の軸が生まれたのです。
人が中心となった現代の宗教観
現代においては、よりギリシャ文化の影響は顕著になっています。
神の存在が当たり前であった時代は過ぎ去りました。
かつての世界観では神の存在は当然のことでした。
それに対して現代の世界観は人が中心です。
哲学者デカルトが語った「我思う、ゆえに我あり」という言葉は、この世界観を的確に表現しています。
つまり、人が考えること、思うこと、感じることが世界の中心なのです。
ですから、神の存在についても、その存在を信じるか、信じないかを人が選択するようになったのです。
しかし不思議な事に、このような時代になっても多くの宗教が力を持っています。
調査によると世界人口の7割が神の存在を信じているそうです。
宗教者は宗教をやっているとは思っていない
これは特定の神の存在を信じていない人にはなかなか理解し難いことかもしれませんが、じつは俗にいう「宗教に入っている」人達は「宗教に入っている」「宗教をやっている」という認識を持っていません。
神を信じるのは空気を吸うように当然のことであるからです。
わたしはキリスト教の牧師ですが、自分が宗教家であるとは思っていません。
なぜなら、わたしにとって神は真実であり、現実の存在であり、人格的に関わってくださっていると分かるからです。
神が存在しない世界なんてありえませんし、神が存在しないなら世界すら存在できないと信じています。
ですから、「キリスト教」という名称も学問的な分類のための用語に過ぎず、私自身はあまり好んで使いません。
むしろ私の全てである神が、一つの宗教という枠に収められてしまうことのほうが不本意に感じてしまいます。
このように世間一般の宗教に対する認識と、実際に神を信じる人達との認識には大きなギャップが存在します。
神を信じていない人には不思議な世界であり、信じている人には通常の世界なのです。
同時に信じていない人には今の生活が自然ですが、信じている人には神なしの生活は不自然です。
しかし、それでも多くの人が信仰に入っていきます。
性別、職業、国籍に関係なく、全ての世代において神を信じる人達がいます。
自然が不自然になり、不思議が通常になっていく人達がいるのです。
その理由は何でしょうか。
次の章では各宗教の特徴について解説していきます。
宗教の教えを比較してみる(キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンズー教、神道)
実際の宗教者達は、彼らの「宗教」をどのように認識しているのでしょうか?
そしてその宗教、そして神にどのような魅力を感じているのでしょうか?
今回は代表的な宗教の教えを比較してみましょう。
宗教は主に5つのタイプに分けることができます(詳しくは後述)が、それぞれのタイプを代表する存在であるキリスト教、イスラム教、仏教、ヒンズー教、神道を取り上げます。ポイントは3つです。
- 神の姿:神はどのようなお方で、人は神とどんな関係を持つのか。
- 救済の条件:神が人に救いを与えるために必要な事。この救いとは人生の苦しみからの救い、魂の救い(来世への約束)を含む。
- 死後の世界:人は死んだらどうなるのか。
(これらの考察はなるべく客観的にまとめようとはしていますが、実際の宗教者の中には別の意見をお持ちの方もおられると思います。あくまでも一つの意見としてお読みください)
キリスト教
神の姿
世界のすべてを造り、人間を造った創造主です。
神は人格を持っており、人に語りかけます。人は神にとって愛する子どもです。
救済の条件
すべての人は神に逆らい、罪人です。
しかし、神の子であるイエス・キリストが人となって地上に来られ、十字架で死に、人の罪を身代わりに引き受けました。そしてキリストは復活しました。
この事を信じるなら人は罪が赦され、死んでも天国に行く特権が与えられます。これを「救い」と呼びます。
救われるためには、良い行いをする必要はありません。
むしろ良い行いは無意味で、キリストの救いを信じているかどうかだけが問われます。
死後の世界
キリストの救いを信じ、罪が赦された人は天国に行きます。
天国は痛みも悲しみもない場所で、神と共に永遠に楽しく生きることができます。
キリストを信じない人は火の池で裁かれます。
イスラム教
神の姿
全能で比べるものがない、宇宙の創造主であり維持者である、慈悲深いお方です。
アラーの他に神は存在しません。(イスラム教徒は神に向かって「アラー(アッラー)」と呼びかけますが、これはアラビア語で「神」という意味で、名前ではありません)
救済の条件
「六信五行」を保ち続けることが必要です。
「六信」は、「神」「天使」「啓典」「預言者」「来世」「天命」を信じることで、「五行」は「信仰告白」「礼拝」「断食」「喜捨」「巡礼」を行うことです。
「六信」は以下の通りです。
- 神 アラーの存在を信じること
- 天使 天使の存在を信じること
- 啓典 コーランを信じること
- 預言者 イスラム教の創始者であるムハンマドを信じること
- 来世 天国と地獄の存在を信じること
- 天命 神の意志を信じること
「五行」は以下の通りです。
- 信仰告白 「アラーの他に神はなし」と唱えること
- 礼拝 一日に五回の礼拝
- 断食 ラマダーン(断食月)と呼ばれる期間は、日が沈むまで断食すること
- 喜捨 貧しい人への施し
- 巡礼 聖地に詣でること
死後の世界
最後の審判があり、天国と地獄に振り分けられます。
天国では絶世の美女である乙女をめとり、浴びるように酒を飲むことができます。
しかし、酔わず、頭痛がすることもありません。
特に殉教者には多くの乙女が待っています。
女性達も天国に入れますが、女性達には何が待っているのか、コーランには記されていないそうです。
仏教
神の姿
本来、礼拝されるべき神は存在しません。
仏教の祖と言われる釈迦(ゴーダマ・シッダールタ)も、人間を超越した存在について語っておらず、自らを神と称することもありませんでした。
仏や阿弥陀と呼ばれる神のような存在は後世になって生まれたものです。
救済の条件
それぞれの宗派によって異なりますが、「南無阿弥陀仏」と唱え続ければよいという浄土宗、法華経の教えを守る日蓮宗が有名です。
ブッダ自身は人生とは苦であり、無常であり、良い行いと修業を続け、欲や執着心を絶てば苦悩に満ちた輪廻(命の繰り返し)から解放される、と教えました。
死後の世界
これも宗派によって理解が異なります。
極楽と地獄も後世になって付け加えられたもので、釈迦自身は極楽と地獄について述べておらず、むしろ「死後のことは考えるな」と教えていました。
この世のものは常に移り変わっていくもので、永遠のものは存在しない、という仏教の概念です。
ヒンズー教
神の姿
ブラフマー(創造の神)、ビシュヌ(維持の神)、シヴァ(破壊の神)が重要な神々ですが、多くの土着の神々も取り込んでいる多神教です。
かつてヒンズー教の指導者は様々な土地をめぐり、そこで礼拝されていた神々を「これはヒンズー教の神だ」と教えたと言われています。
救済の条件
牛を神聖視すること、食生活における禁忌を守り、沐浴、ヨガなどの修行をして汚れを清めることが求められます。
死後の世界
輪廻転生(生まれ変わり)を繰り返すとされています。
牛が神聖視されるのは、生まれ変わりの最上位が人間、次が牛であるためです。
神道
神の姿
天照大御神をはじめとする様々な神々です。
過去の偉人、自然界の事物も神とされます。
基本的には世界を創造した絶対的な神はいません。
天照大御神も自然界の中から誕生した、と日本書紀に書かれています。
救済の条件
神社ごとに様々な神が祭られており、人は自分のニーズに応じて神社に参拝し、安らぎやご利益を求めます。
まとまった教義もなく、魂の救済という概念は存在しません。
死後の世界
これもまた明確な教義は存在しません。
宗教のタイプを分類してみる
さて、この中でキリスト教は他のどの宗教とも違う特殊性がありますが、その他の宗教は大まかな分類が可能です。
行い重視型
イスラム教のように「〇〇〇をしなければならない」という掟があり、その行いを繰り返し続けることによって、魂の救済を得ます。
組織化された多くの宗教はこのタイプで、掟への服従、良い行い、宗教団体のリーダーへの忠誠、熱心な布教活動などによって信者の信仰の度合いが測られます。
哲学・道徳型
仏教に代表されるタイプで、明確な掟や死後の世界の定義を持たず、自分の中での問答や修行により、新しい自己を確立しようとします。
神との関係よりも、哲学的、道徳的な探求が重要視されます。
道教、儒教などもこのタイプに入ります。
厳しい修行を続けることもありますが、自己の鍛錬と探求という側面が強く、神との関係を行いによって保とうとする行い重視型とは目的がやや異なります。
アミニズム型
アミニズムは自然崇拝、精霊信仰とも呼ばれ、明確な教義を持ちません。
神道がこの部類です。
世界中に存在する土着の宗教もほとんどがアミニズムと呼ぶことができます。
物事を呪いや報いのような概念で判断することも多く、死生観に大きな影響を与えます。
占い、呪術、魔除けといった行為もよく行われます。
民族型
民族のアイデンティティと宗教が一体化しているタイプで、代表的なものがヒンズー教です。
インドにおけるカースト制度はヒンズー教の価値観に基づいており、宗教というよりは民族の構造そのものになっています。
中世のカトリック教会も同様の傾向がありました。
広い意味では中東におけるイスラム教、ユダヤ教もこのタイプです。
独自の型を持つキリスト教
これに対して、キリスト教は全く違う教えを持っています。
人が神に対して持っている責任は、神が人に与えた「イエス・キリストの救い」(前述のキリスト教、救済の条件を参照)を信じることです。
修行や、精神世界における悟りや、宗教団体に属する事や、お金をささげる必要は一切ありません。
もちろん聖書には信者に求められている良い行いについて書かれている言葉がたくさんありますが、それは信じた人が神への感謝として行うものであり、神に愛されるための条件でも、救われるための条件でもないのです。
多くの宗教は人が神に近づかなければなりませんが、キリスト教においては神が人に近づいてくださるのです。
また、ユダヤ教も同じ聖書を信じていますので、概念は同じです。
ただ、ユダヤ教は神の一方的な愛と選びを信じていますが、キリストによる救いは信じていません。
人が頼んだり、良い行いをすることによってではなく、神が一方的に特別な存在として守り、愛してくださっている、という聖書に書かれている大切な概念です。
信じる、信じないは別として、生活の様々な場面で、あなたも宗教の影響を受けています。
日本国憲法に定められている基本的人権は、人は神に愛されている大切な存在である、という聖書の概念から来ていますし、宣教師によって始まった病院や大学もいくつもあります。
お盆、正月などの習慣には仏教や神道の影響が見られます。
「因縁」「道場」など、普通に使われる単語は仏教用語です。
あなたはどの宗教に魅力を感じましたか?
それともどの宗教も信用ならないと思いましたか?
現代における宗教と、これからの宗教
現代においては、前章で紹介した主流の宗教とは毛色の違った新しいタイプの宗教が登場するようになりました。
この章では現代の様々な新しい宗教を分類し、続けて現代における宗教の問題について取り上げます。
そして宗教の本質と、これからの宗教について考察していきます。
新宗教の比較と分類
まずは近年の新宗教を大きく四つに分けてみましょう。
キリスト教系
世界平和統一家庭連合(旧:統一教会)、モルモン教、エホバの証人、クリスチャンサイエンスなどがこれに当たります。
その教えは聖書を用いつつも、聖書の主要な教えから離れており、聖書の翻訳そのものを変えたり、聖書以外の本や指導者の教えに聖書以上の権威を持たせる傾向があります。
指導者が「再臨のキリスト」であると自称することもあり、本来のキリスト教からは異端とされています。
聖書によれば、キリストは十字架で死に復活した後、天に昇っていきました。
そして世界が終わる時、再び地上に戻ってきます。
これを「キリストの再臨」と呼びます。
仏教系
仏教の教えを土台にしつつ、現代的な解釈を付け加えた宗教で、創価学会、顕正会などです。
日本人には馴染みやすい教えであるため、日本でも多くの信者がいます。
仏教の主流の宗派からは異端とされることもあります。
ミックス系
キリスト教、仏教、ヒンズー教などの主流の宗教の教えの一部や、世界各地の古来の宗教や習慣も取り入れた宗教です。
有名なところではかつてのオウム真理教、幸福の科学、崇教真光などがこれに当たります。
ニューエイジ系
すべての宗教は、じつは皆同じ神を礼拝していると考える宗教多元主義を土台としています。
ミックス系と違う点は教義や組織よりも、精神世界における活動が重要視されるところです。
宇宙から届くメッセージやエネルギーを受け取ろうとする、占星術を土台にしたスタイル、東洋の宗教やヨガなどを用い、自己と自然を調和させようとするスタイル、自己問答や霊的存在との対話によって自分をもっと高めようとする自己啓発を中心とするスタイルなど、様々な活動があります。
指導者のような存在から教えを受けることはあっても、宗教団体のような組織に発展することはあまりありません。
現代のもう一つの問題~宗教のカルト化
オウム真理教の事件が起きてからしばらくの間、私が「私はクリスチャンなんです」と自己紹介すると、「え? もしかしてオウムじゃないよね?」とか、「怪しいグループじゃないよね?」とそれこそオウム返しのように尋ね返されることが何度かありました。
そしてオウム事件以降、宗教、教会、聖書、神などといった単語に対して、世間の中に宗教アレルギーが育ってきた印象があります。
つまり、宗教にのめりこんでいる人達は危ないから気を付けよう、宗教とは距離を置こう、と感じる方々が増えてきたのです。
大きな社会問題を起こした宗教団体はオウムが初めてではありません。
世界を見渡せば集団自殺や大量殺人、性的虐待、暴行、マインドコントロールなどの事件を起こした団体は多く存在します。
やや色合いは違うとしても、中東で力をもったイスラム国もその中に含まれるでしょう。
不思議なもので、宗教以外のコミュニティにおいて、例えば企業やスポーツチーム、学校などでここまでひどい問題が起こることはまずありません。
それは宗教というコミュニティが持つ特殊性にあるのです。
さて、古い時代から宗教が残虐性を持つことは多々あったわけですが、かつては政治や民族意識と宗教はほぼ一体化していたため、それが問題視されることはありませんでした。
中世のカトリック教会による魔女裁判や異端審問、十字軍などの残虐な行為の数々も、むしろ悪を正し、神の意志を行う教会の正当な行いと見なされていたのはそのためです。
現代になってカルト化した宗教が目立つようになったのは、前述のとおり宗教が政治や民族と分離した位置に立つようになったからです。
さて、宗教がカルト化し、社会を不安に陥れるような残虐性を持ってしまう理由は、宗教がそもそも人間を超越した存在を求め、礼拝し、服従するコミュニティであるからです。
人間の常識や慣習、国家や自治体の定めた法よりも更に上に立つ存在である神や、神と自称する人間、神の使いと名乗る人間が一番大切な存在であるため、その信仰が極端になると社会のルールに逆らう事はむしろ善であるかのような教えに変容していってしまうのです。
現代の新宗教は特にカルト化しやすい傾向がありますが、古くから続く主流の宗教でも、カルト化の問題は起こっています。
大量殺人を起こすことはなくても、団体のリーダーが権威を振り回し、信者達を支配していくというケースは一つや二つではありません。
しかし不思議な事に、歴史を振り返っても現代の社会においても、宗教は大きな問題を起こし続けてきたにもかかわらず、多くの人が宗教を求め続けているのです。
終わりに~人の心は信じるものを求めている
さて、最初の問題に戻りましょう。
宗教とは何でしょうか?
最も単純な表現をすれば、「何かを信じること」となるでしょう。
人は何かしらのものを信じ、その信じているものに従って生きています。
無神論ですらも、「神はいない」と信じているとすれば、それも一つの宗教です。
恋人だけしか信じられないというなら、それもまた宗教です。
つまり、宗教とは結局、人の心に存在している、何かを信じたいという欲求が形になったものなのです。
聖書は面白い言葉で人間の心を表現しています。
神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた(伝道者の書3:12・口語訳)
全ての人の心には、何か人間を超えた永遠のもの、つまり神のような存在を求める欲求があるのです。
それを「礼拝欲」と呼んでもいいでしょう。
プロのサッカーの試合におけるサポーターの熱狂ぶりは、ある意味宗教的です。
声をからしてチームを応援し、観戦のためにお金をつぎ込み、ユニフォームやグッズを買い求めます。
アイドルグループの追っかけも、宗教と言えるかもしれません。
大好きなメンバーと握手するために何十枚もCDを買い、コンサート会場でそのメンバーの名前を叫びます。
人の心には、熱狂的に礼拝する対象を求める礼拝欲があるのです。
スポーツやアイドルにのめりこまなくても、お金や恋人にのめりこむことはあるはずです。
「礼拝」とは英語で「worship」です。これは「価値がある」という意味の、「worth」から派生した言葉です。
人は皆、のめりこむほどの価値があるものを求めているのです。
だからこそ、宗教による悲惨な出来事が頻発しても、人は宗教を求め、神の存在を求めます。
これだけ人の知性が発展し、世界の仕組みや人間の体や内面がデータとして表されているにも関わらず、新しい宗教が生まれ続けています。
そしてこれからも生まれるでしょう。
神など信じない、という人達は、逆に言えば神はいないという事を信じ、その信仰によって生きています。
宗教に嫌気がさした人は、無神論を信じます。
またある人達は、「私は誰も信じない。自分だけを信じる」と語ります。
皆、何かを信じたいのです。全ての人は宗教者であり、宗教を求めているのです。
それが人の心にある「永遠を思う心」というものなのかもしれません。
いかがだったでしょうか?
宗教なんて自分とは遠い世界の話だと思っていた方も、これを機に神の存在と、人の心が求めているものについて考えていただけたら幸いです。




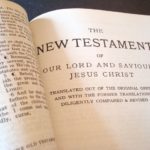



































コメントを残す