皆さんは妖怪と聞いて、一体何を思い出すでしょうか?
有名なところでは鬼であり、日本全国各地に鬼にまつわる伝説があります。
河童もまた広く知られた妖怪であり、民俗学の書物で有名な柳田国男の『遠野物語』でも、河童伝説が取り上げられています。
以下では遠野の河童と共に、首都圏の中から埼玉県志木市に関わる河童を取り上げ、独自の視点から河童伝説について考察しています。
河童の特徴

かつて河川には、河童の絵が書かれた看板が立てられていました。
この川危険という文字が書かれ、河童が中央に描かれていました。
現在はあまり目にしないかもしれませんが、それだけ河童が身近な妖怪でもあったのでしょう。
河童は全国各地で特徴が異なる点もありますが、共通している点もあります。
たとえば子供のような背丈で、緑色の肌で頭にお皿があることです。
背中に甲羅を背負い、カメのようですが人に似た体型をしています。
泳ぎが得意で相撲が好きで、時折イタズラをしますが、あくどいことまではしません。
キュウリが大好物でもあり、寿司のカッパ巻きの語源でもあるでしょう。
子供たちに人気のアニメ「妖怪ウィッチ」でもベースとなる河童像は上記のようでもあります。
水と共に暮らしているため、川やその近辺で見かけるのが一般的でもあるでしょう。
おそらく水と何らかの関係から生まれてきたのでしょうが、妖怪の中で割合親しみやすいのが河童であるのかもしれません。
遠野と河童

すでに民俗学の古典とも言えるのが、柳田国男の『遠野物語』でしょう。
岩手県遠野地方で語られている伝説や昔話等を集め、独特の雰囲気を感じられる書籍でもあります。
『遠野物語』の中でもいくつか河童のことが語られていますが、その中の一つに現在では観光地になっているカッパ淵にまつわる話が取り上げられています。
ある夏の日に、農夫が愛馬を川へ連れて行くと、河童が川から出てきて馬を奪おうとしました。
しかし馬の力が強くて川へ引きずり込めず、馬と共に農夫の家まで行ってしまいました。
河童は見つからないように農夫の家の桶に隠れましたが、すぐに見つかってしまい、村の裁きを受けました。
もうイタズラしないことを誓約させられ、以後河童は人にイタズラをしなくなったとのことです。
おそらくお分かりでしょうが、上記の話の川はカッパ淵を指しています。
イタズラ好きの河童がよく現れていたようで、どことなく間の抜けた感じもあるでしょう。
今風に言えば、天然だったのかもしれません。
しかも裁きにするという時点で、村の人々は河童と共存していたとも言えます。
先でも少し触れていますが、現在の遠野は伝説にちなんだ観光地でもあり、カッパ淵の他にカッパ狛犬やカッパを祭った祠などがあります。
それだけ遠野においては河童が身近であったと同時に、妖怪とは一体何か、ということを考えさせてくれるのかもしれません。
志木と河童

首都圏の中でも埼玉県志木市は、カッパ探訪のサイクリングコースを公的機関が自ら紹介している程、河童との関わりが深いようです。
志木市には柳瀬川や荒川等が流れ、現在でも葛西臨海公園行の水上バスを利用することができ、水の町とも言えるでしょう。
東武東上線志木駅前にはカッパ像もあり、自治体そのものがカッパの町を売りにしているところがあります。
当然河童伝説もあり、その中から次のようなものをご紹介します。
ある船頭が川下りをしていると、河童から相撲をせがまれました。
ヌルヌルした体に触れたくない船頭は要求を拒んでいましたが、河童が悪口を言うことに腹を立て、河原で相撲を取ることにしました。
体に触れたくないので、のど輪や張り手で突き飛ばしました。
何度も何度も倒されながら河童は起き上がり、船頭へ向かっていきます。
これでもかこれでもかと船頭はのど輪や張り手をし、それでも河童が負けを認めないので、ついに抱えあげて地べたに叩きつけました。
さすがの河童も「参った」といい、這いつくばるように川へ戻っていきました。
仲間からは「船頭と坊主には近寄るな」と言われたそうです。
以上の話から河童の相撲好きがよく理解できると言えるでしょう。
志木市は都心から60分圏内にあります。
そういう都市部でも河童伝説があるということは、やはり河童が身近な妖怪だった証のようでもあります。
一体河童とは何だろうか?

一体河童とは何だろうか?、という疑問は古くからあったようです。
妖怪に数えられますが、空想上の生物であることは確かでしょう。
しかし空想上の生物であっても、そこにはなにかしら人々の思いが込められているのかもしれません。
ある説では間引きされた子供の分身と言われています。
あるいは水と関わりが深いながらも山の神の使いというものや猿に似たようなもの等もあります。
日本民俗学の祖である柳田国男は『遠野物語』の他にも何冊もの書物を著し、『妖怪談義』のような妖怪を取り上げたものもあります。
一説によれば柳田は日本の先住民の痕跡を求めるため、民俗学を起こしたとのことです。
遠野物語の冒頭にある「平地人を戦慄せしめよ」は先住民の痕跡ともいえる山人からの声とも解釈できるでしょう。
柳田の説を踏まえれば、河童もまた先住民の痕跡であり、主に水辺で暮らした人々を象徴的に表したものかもしれません。
先住民と言っても、果たしてはそれは現在の日本人の祖先とは違うのでしょうか、どうなのでしょうか?
もし違うなら縄文人とは一体どういう人々だったのでしょうか?
たかが伝説と言えばそれまでですが、わたしたちの祖先についてまで考えさせられるのが、伝説でもあるのかもしれません。







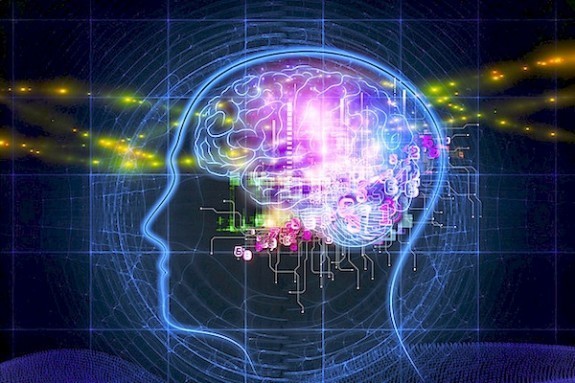
































コメントを残す