Contents
ナンナの基本情報
- 名:シュメール語名「ナンナ」、「ナンナル」、別名「スエン」「アシムバッバル」「ナンナ・スエン」とも アッカド語名「シン」(スエンの転訛)
- 出典:シュメール神話(メソポタミア神話)
- 所有:ラピスラズリの長いひげ、長い王侯の服、強靭な角とたくましい四肢、有翼の牡牛に乗る、満月の王冠、三日月型の武器
- 特徴:シンボル数は30(一ヶ月が30日であることに由来ー月齢)、三日月、ウル市の主神、主神殿はエキシュヌガル
- 関連:ニンガル(配偶神)、エンリル(父)、ニンリル(母)、エレシュキガル(娘)、ウトゥ(息子)、イナンナ(娘)、メスラムタエア(兄弟 冥界神)、ナムタル(兄弟 冥界神)、ネルガル(兄弟 冥界神)、ニンアズ(兄弟 冥界神、医療の神)、ニヌルタ(兄弟 英雄神、戦闘の神)
ナンナの概要
月神として、月の運行、月の光、暦、農業、出産、癒し、正義を司る。
夕暮れになると彼は三日月型の船に乗り天空を旅した。
彼の放つ聖なる光は夜陰に乗じて悪事を働く悪人たちの犯罪を暴き、夜闇にはびこる悪霊どもも退散させる力があった。
シュメール古来の七大神、運命を定める七神の一人。
アッカド王朝時代後にメソポタミアを平定したウル第3王朝時代、首都となったウル市の主神ナンナの地位は向上し、この頃までに最高神エンリルの長子とされ、太陽神ウトゥ、豊穣と金星の女神イナンナが娘とされた。
古代世界の中では例外的に太陽神、月神の地位が低かったシュメールでは、彼らが最高神となることはなかった。[注1]
しかしながら農耕を主産業とするシュメール文明において、暦における月の役割は最重要である。
メソポタミアでは月の運行を基準とした太陰暦が採用されていたからだ。
月の満ち欠けに応じた月毎に繰り返す祭があったほどである。
欠けてもまた満ちる月は死と再生の象徴であり、それすなわち豊穣と結びつけられていた。
ナンナの説話
ナンナの数奇な誕生神話
月の光のように非常に穏やかな性格の神として愛されるナンナ・スエンだが、出生にまつわる神話はなかなかセンセーショナルである。
叙事詩『エンリル神とニンリル女神』に詳細が語られる。
父であるエンリル神が若者であった頃、ニップル市のヌンビルドゥ運河で水浴びする美しい乙女ニンリルを見初めた。
瞬く間に口説き落としにかかり、稚いあまりにかえってあられもないことを口走るニンリルを船の中で犯してしまう。
このことは「50柱の偉大な神々」と「運命を決定する七柱の神々」の知るところとなり、最高神であるにも関わらず冥界追放の極刑が下される。
シュメール社会は文明社会を強く自負しており、正式な段取りなく処女を手篭めにした男性は厳しく断罪された。
『ウルナンム[法典]』第六条には次のように書かれている。
もし人が若い男性の(床入りを済ませていない)処女である妻を、暴力におよんで犯したならば、その男性は殺されるべきである。[1]
何と、現代より手厳しい!
初夜前の花嫁姦通は死罪だ。
エンリルが追放されるはずである。(するとエンキの娘たちとの浮気はなぜ神々に裁かれなかったのだろうか?)
ただ一度の交わりで月神(ここでは名はスエン・アシムバッバル「輝く者」)を身ごもったニンリル女神は、エンリル神が忘れられず、身重の身で彼の後を追って冥界に下る。
エンリル神の不名誉な振る舞いはここでさらにエスカレートする。
後を追うニンリルのことをなぜかエンリルは知っており、先手を打って冥界脱出の手段に利用しようと企む。
冥界に落ちた神が現世に戻る唯一の手段、「身代わりの神を置く」を、新たにニンリルを身もごらせ、その子を使うことで解決してしまうのだ。
冥界の都市の門番、冥界を流れる河の人、渡し舟の人、と三度変身してニンリルを騙し、受胎させることで…。
エンリルの反省の無さが分かるところだ。
すでに胎内にはナンナ神がいるわけだが、ネルガル・メスラムタエア神(別々の神ともされる)とニンアズ神とエンビルル神が受胎させられる。
三人を冥界に置き去りに、エンリルとニンリル、ナンナの親子は揚々と天に帰っていくのである。
とんでもない出生秘話だが、その後『エンリル神とスド(後でニンリルと改名)女神』という叙事詩で、シュメール社会の結婚習慣をわきまえた手続きを踏んで、つつがなく正式に結ばれる。
後腐れなく仕切り直したかのようである。
かの時に誕生した神々は全員豊穣神の神格を合わせ持っていた。
ナンナ・スエン神は新月の間は冥界で眠って過ごすと考えられていた。
冥界の兄弟神は神話ではあまり活躍しないのだが、もしかしたら天上の兄とは仲は悪くなかったのかもしれない。
『ナンナ・スエン神のニップル詣で』
ある時、ウルの都市神の月神「ナンナ・スエン・アシムバッバル」は「そうだ、父上エンリル神と母上ニンリル女神を訪ねてニップルへ行こう!」と思い立つ。
ご機嫌伺いと観光がてら、両親に甘えに行く感じである。
ちなみにいくつかの文書の中でスエンは三日月、ナンナは満月、アシムバッバルは満ちていく月を表すとされている。
他にも月の満ち欠けと関係する名としてインブ(「果実」の意)とも呼ばれた。
彼はニップル詣でのために聖船を作らせることにした。
シュメールの初期王朝からウル第三王朝までの様々な文書によれば、神々は聖船を使って都市から都市へ訪問していた。
行き先は最南端のエリドゥ市か、シュメール・アッカドの境目にあるニップル市に集中していた。
エリドゥへは知識と魔法を司る創造神エンキから「メ」を授かりに。
ニップルへは神々の王エンリル神の祝福を受けるべく伺候するのが目的だった。
前者では『イナンナ女神とエンキ神』、『ニンウルタ神のエリドゥ詣で』などの叙事詩が知られている。
後者では、このナンナ神以外にも『エンキ神のニップル詣で』、『パビルサグ神のニップル詣で』、『ニンイシンナ女神のニップル詣で』などがある。
かつてどこからともなく海を越えて巧みな航海術でメソポタミアに突然現れたと言われたシュメール人。
大木も建材も育たないメソポタミアの地で、発達するすべもない大掛かりな聖船を作る技術はどこから来たのであろうか?
それは未だに解明されていない。(そもそもシュメール人自体、民族系統も出自も言語系統も不明の人類史最大の謎である!)
瀝青(れきせい)や甲板や肋骨材、外板、梁材、樅材などを遠方から調達して建造する様が語られる。
聖船建造については王讃歌『シュルギ王とニンリル女神の聖船』[注2]に詳しく語られている。
聖船建造は都市国家の王の最重要国家事業であった。
聖船には神にまつわる名が付けられていた。
- 「エンキ神の船マダラアブズ(深淵の牡鹿)」
- 「エンリル神とニンリル女神のための聖船マグルマフ」
のように。
完成した聖船に犠牲用の上等な牛や羊、山羊を積み込み、土産として亀や鯉、鳥類、籠盛りの卵などを積んでニップルを目指す旅が始まる。
ナンナ神の聖船は、ウルを発ってエンネギ、ラルサ、ウルク、シュルッパク、トゥンマルに寄港し、それぞれの都市の守護神の歓待を受けつつ、ニップルに到着する。
エンリル神の神殿エクルで供物を捧げると、父なる神は大いに慶び、幼子にするように優しく甘い菓子や蜜、美味しいパンや上等のビールでもてなした。
すっかり満足したナンナ神はウルへ帰還するに際してさらに沢山の賜り物を願い出て、それら全てを賜った。
大麦や各種の鯉、葦やぶどう酒などの他、鯉の洪水(⁈)や長寿まで、エンリルの祝福と共に与えられる。
それらはウルの民にとっての恵みである。
豊富な農作物と豊かな漁獲はシュメールの主要な交易品として輸出されていた。
シュメール人の統一王朝時代であったウル第三王朝では、エンリル神は統一国家の守護神と考えられるようになっていたので、各都市の支配者は多くニップルのエンリル神殿に奉献し、碑文を残した。[2]
『ナンナル神に対する「手をあげる」祈祷文』
紀元前1000年〜600年の間に粘土板に刻まれた祈祷文。
シュメール語とアッシリア語(アッカド語のアッシリア方言)の文が一行ごとに交互に書かれている。
アッシリア時代に書かれていても、内容は古い時代からコピーされ続けてきたものらしい。
前半ではアッシリアの主神となったアッシュール神の父・全天の神アンシャル、天神アンの呼称アンガル、バビロニアの月神シンの名でナンナル(ナンナと同義)に呼びかける。
ウル第三王朝期のウル市、メソポタミア北部ハラン市で、最高神としてほぼ唯一神のごとく崇拝されていた頃に作られた祈祷文ではないかと思われる。
最後はひたすら月神が平安であるようにと願い奉る繰り返しの祈祷で幕を閉じる。
都市の最盛期を過ぎても、月の象徴する力への崇拝が根強く続いていた証拠である。[3]
『ウルの滅亡哀歌』
シュメール人による最後の王朝、ウル第三王朝時代末期は深刻な内憂外患に陥っていた。[注3]
度重なる周辺民族の侵入、貧富の差の拡大により疲弊した民と奢侈に奢る富裕層が人手のかかる灌漑農業の衰退を招いた。
文明はその興隆の要因が常に滅亡の原因となるという。
食糧生産の衰退は致命的な弱体化を招いた。
誰の目にも衰亡明らかな国のありようも、シュメール人の思考は「神々の業」と考える。
ウル第三王朝滅亡の悲劇は、先ず『ウルの滅亡哀歌』でシュメール古来の都市ウルの滅亡として長大な哀歌に歌われた。
更に『第二のウル滅亡哀歌』では神々がシュメールの民と都市を見捨てて立ち去り、暴虐の嵐のうちに全てが無に帰す。
そこには歴史的事実は語られない。
全ては神の意思のままという思想の元にある。
エンリル神をはじめとするアヌンナキ(神々の集団のこと)の命により、シュメールは滅びねばならなかった。そこには理由も道理もない。
人間全てを滅ぼそうとした大洪水伝説と同じく、神々が自ら生み出した「黒頭の民」を滅ぼすことに王でさえ疑問を挟むことはない。[注4]
エンリル神の覆らない決定により、滅亡定まったウルから、更にはシュメール全土の都市から神々は去る。
地上に築いた都市と神殿を見捨てて天に還る神々。
ウル市の守護神ナンナ(ル)とニンガル女神も立ち去らねばならない。
だが、滅びゆく都市のそばを離れられない。
命運尽きるとき、都市をエンリル神の放つ嵐と洪水が襲う。
史実では侵入者の侵攻が嵐であり、戦乱が洪水であった。
飢饉も追い討ちをかけた。
シュメールの心臓たるウルとニップルを護る大城壁も崩壊する大洪水となって、敵は侵攻する。
それ以外の諸都市はとっくにウルの支配を離脱していた。
『ウルの滅亡哀歌』ではウルの女主人であるニンガル女神が繰り返し激しく嘆き悲しみ、神々の王に慈悲を乞う。
『第二ウル滅亡哀歌』ではナンナ神が父なる大神エンリルにウルの繁栄を取り戻して下さいと懇願する。
確かに暴虐の嵐が去った後、荒廃したウルの再建は神々に保証された。
都市ウルは、修復されメソポタミアの重要な聖都としてして蘇り、存続した。
ナンナ神とニンガル女神の神殿は再建された。
ただ、歴史の表舞台にシュメール人が再び立つことはなかったのである。
脚注
注釈
- [1]:最高神といえどもシュメールの神は都市神としての性格を失わず、それぞれの神が1人神として同等の立場で並び立つ形でパンテオンを成していた。一つの都市が強力になればその主神を軸に神統譜が書き換えられることがよくあった。そのため、メソポタミアの神話の親子兄弟関係は曖昧なのである。統一王朝の時代になり、民族が変わっても、最後までエンリルはニップル市の、マルドゥクはバビロン市の、アッシュールはアッシュール市の都市神であり続けた。守護神と都市は切っても切り離せないのがシュメール〜メソポタミア神話の特徴である。
- [2]:「王讃歌」はウル第3王朝以降に発展した文学形式。神々の恵みやいさおしを讃える詩は古来世界中に存在するが、これは王が自らの功績を自讚する珍しいものである。特に第二代王シュルギは最多の二十あまりの王讃歌を残している。
- [3]:内政的には人類史上初のインフレが起き、細々したものまで税がかけられ、ヤミ金まがいの高利貸し業も生まれていた。貧富の差は拡大し、収奪される庶民は生活苦に喘ぎ、王にも力を誇示するほどの富裕層はインダス川から地中海、エジプトからメソポタミア北部までに世界初の貿易網を展開していた。弱者保護、福祉充実をモットーとしていた歴代の王の力は弱体化していた。すでに資本主義社会の弊害を体験していたのである。対外的には、ユーフラテス川上・中流地方で遊牧生活していたセム系アモリ人の西方からの流入が続き、末期には東方からのエラム人の脅威が深刻になってきた。第二代シュルギ王の代に万里の長城のような長大な国土の防壁を建設していたが、最後の第五代イッピ・シン王の代には用をなさなくなっていた。さらに追い討ちをかけるようにウル市で数年続く飢饉が発生し、配下のマリ出身のアモリ人イシュビエルラが叛旗をひるがえして、ウル第三王朝およびシュメール人の支配は終わりを告げたのである。
- [4]:シュメール人は自らは「ウンサンギガ(黒頭の民)」と名乗っていた。それはエンリル神が、労役のため粘土の穴から生み出した最初の人間を見て呼んだ名前と同じである。全ては神々の思し召すまま…ウル第三王朝最後の王イッピ・シン王の終末期の書簡に、“なるほどエンリルをはじめとする神々はシュメールの主権をイシュビエルラに与えることを決定し、後者はそれにのっとって行動しているのではあるけれども、エンリルは他方、今やマルトゥ人を立ち上がらせ、エラム人を私の援助者としてやって来させ、イシュビエルラを捕らえようとしているのだ。”という意の文面が残っている。これは若干後代のコピーなのではあるが、シュメール人の思考を表している。[4]
出典
- [1][2][4]:岡田明子、小林登志子『シュメル神話の世界 粘土板に刻まれた最古のロマン』中公新書
- [3][4]杉 勇、尾崎亨訳『シュメール神話集成』ちくま学芸文庫
参考文献、URL
- 岸本通夫、伴庚哉、富村伝、吉川守、山本茂、前川和也『世界の歴史2 古代オリエント』河出書房新社
- ファンタジィ事典mini
- ウィキペディア(シン)
- シュメールの心 その16 シュメール都市文明の滅亡 栁 幸夫
※ライター:紫堂 銀紗



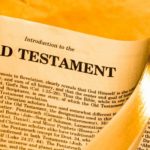

































コメントを残す