茨城県を家族ドライブしていたら、とんでもないものを見つけてしまった!
茨城県の、坂東市。
この町にある『茨城県自然博物館』は、恐竜好きの子供にオオウケする博物館であると聞きました。
「それはいい、たまにはオカルトや都市伝説と関係のない家族旅行でもしようか!」と、子供を連れてドライブへ。
ところがその途中、飲み物を買おうと、ふいに入ってみた地元のスーパーマーケット。
そこで(私からすると)とんでもない商品が、山積みで販売されているのを、見つけてしまいました!

『商標登録:将門煎餅』
「ま、、、まさかどせんべい??」
そんなまさか!
という私のとっさのダジャレに家族は誰も気づいてくれなかったのですが、それはともかく。
私のささやかな驚きは、オカルトや都市伝説に詳しい方ならわかっていただけるのではないかと。
普段東京で働いている人間からすると、平将門(たいらのまさかど)といえば、
- 大手町に将門の首塚がある。ここを工事しようとすると必ず凶事が起こるスポットとして有名
- 実際、戦前にここに庁舎(大手町ですから)を立てようとしたところ、関係者が連続で急死し、工事中止に
- 戦後、GHQの命令でこのエリアに開発が入った時も、工事関係者に死者が出た為、GHQに事情を説明して中止してもらった
- 2020年オリンピックに向けた開発でも、「ここのエリアには手を出さない」が関係者間の暗黙の了解
というイメージのほうが強い。
それが茨城県の地元では、どちらかといえば「勝利運を呼び込む軍神」として、愛されているようです。
茨城県を調べると、他にも平将門にまつわる遺跡がいろいろあります。
しかし、運気をあげるパワースポットとして扱われているようでした。
それにしても、「将門煎餅」を買っていって、これを東京の丸の内や大手町界隈のオフィスでおみやげに配ったら、人によってはギョッとするんじゃなかろうか?
それとも、これを受け取ってギョッとするのはオカルトに詳しい人だけで、世の中では少数派なのか?
つまり、私は実は、世の中では少数派だというのか!?
たしかに、妻に聞いてみても「そもそも平将門のことなんて、よく知らない」という反応。
田舎の母にラインを送ってみると、「ああ、将門公ね、あれは怖いね」という反応(ちなみに母は関西出身)。
けっきょく、平将門は怨霊なのか、軍神なのか?
それに対する答えは、「怨霊でありつつ軍神」というところかもしれません。
言われてみれば、私自身も平将門は怖い、と思いつつも、どこかで「かっこいい!」とも思っているところがあるわけです。
親愛と畏怖がミックスされた感情なんて、いかにも日本らしい、伝説との向き合い方ではないでしょうか?
というわけで知らない人には雑学として、知っている人にはおさらいとして、「平将門」伝説について、私見も交えまとめてみましょう!
※あ、ちなみに、ちゃんと子供は恐竜博物館に連れて行ってあげましたよ!私の頭の中は、将門公のことでグルグルいっぱいでしたが・・・
将門怨霊化のきっかけは、平安時代の「呪術のコンペ?」

史実の平将門は、平安時代に朝廷に対する反乱を起こしました。
関東の武士たちを味方につけ、一時期は「関東地方独立か?!」と京都の貴族社会をおののかせたほどの大勢力圏を築いた人物。
彼が怨霊として扱われるきっかけのひとつは、どうやら時の平安朝廷が「平将門を呪術でやっつけてくれないか」と、各地の寺社に相談をしたことがあるかららしい。
以下は半分は私の想像なのですが、平安時代という背景を考えると、こんな雰囲気になったのではないでしょうか?
伊勢神宮も高野山も比叡山も、地方の神社も寺院も、多少いかがわしい民間宗教のリーダーも、「これは大変だ、平将門を呪法でやっつけると朝廷に誉められるらしいぞ!」と、それぞれのやり方で平将門抹殺の祈祷を開始した。
つまり、呪いのコンペになっちゃった。
当の平将門の反乱軍は、朝廷側についた武士たちが結成した討伐軍によって武力で鎮圧され、将門自身も戦死しました。
しかしそうなったところで、当然、各寺社は「いや、平将門が戦死したのは、わしの呪術が効いたからだ」、「いやいや、うちの寺でやった呪術が効いたからだ」と主張する。
「そんなら、お前らの呪術が効いたという証拠をなにか出せ」という朝廷に対して、
「わしが関東の方角をむきえ呪術をしていたある晩に、謎の火の玉が夜闇にゆらゆらあらわれるという不吉なことが起こったが、『なにくそ、将門め』と徹夜でがんばっていたら、火の玉が消えた。その翌日に平将門は戦死したのだから、あの夜の私のがんばりが効いたのだ」
「そ、そんならうちはな、平将門が戦死する前の晩、大量の爬虫類が現れて祈祷の邪魔をしてきたんだけど、こんなにがんばったんだからな!」
「そ、そんなら、うちはなー!」
とやっているうちに、平将門は「なみの呪術は効かないスーパー悪役」ということに話が膨らみ、なんとなく、朝廷や民間信仰でも、そういうことになり、、、という次第。
実際に命をかけて働いて平将門を打ち取った武士階級はそうとう、ふてくされただろうな、、、
……と思いきや、源平合戦の頃の武士たちの間では「平将門は体が鉄でできていて、矢を受け付けなかったが、唯一まだ鉄化していない、こめかみが弱点と見抜いた勇者が、そこを矢で撃ちぬいて倒したのだ」という伝説が好まれて流布されていたようです(山田雄司氏『怨霊とは何か』より)。
こっちはこっちで、「呪術ではなく武士の力で将門を倒したのだ」と主張はしているものの、やはり将門が超人化していますね。

なんというか……こういう話のふくらみ方、いかにも平安時代、ですね! 日本中世ですね!
反乱の首領という現実的な人物が、酒呑童子やら九尾の狐やらのような「スーパー妖怪」と同列に、引き上げられています。
こうして将門は、その遺跡を粗略に扱うと大変なことになる怨霊として見られると同時に、どこか格好いいダークヒーローとして愛されるようにもなったのでした。
・・・それでも、やっぱり、怖い!
さて、歴史的な経緯をまとめると、上述のとおりなのですが。
最期にひとつだけ、言っておきたいことが。
大手町にある首塚の話は、二十世紀の事件です。かなり最近の話です。
そればかりか、かのGHQすら寄せつけなかったことを見ると、日本人に対してだけではなく、アメリカ軍人にすら「やばい」と思わせる何かがあるらしい。
となると、単純に「平安時代の雰囲気の中で伝説化した」だけでは済まない何かが、平将門にはあるのかもしれません。
それがあるから、オカルト好きの間では「平将門と聞くと、格好いいと思うと同時に、やはり、怖い!」となる。
私自身も、今回の記事を含め、平将門の話題をするときは、独特な緊張感で筆を進めています。
そうなると、やはり「平将門煎餅」の山積み販売は、気になる。
「お菓子扱いにして、大丈夫なの?」という気持ちと、
「民衆からの愛情の現れだから、これはよいおみやげなのではないかな」とも思い直す気持ちと。
ちょっと私もおみやげとして買ってみて、東京でいろんな人に配ってみて、相手がどう反応するか見てみたい誘惑に駆られましたが……
うーん、いや……
そんな遊び半分な気持ちは、やはり、やめておきましょう。











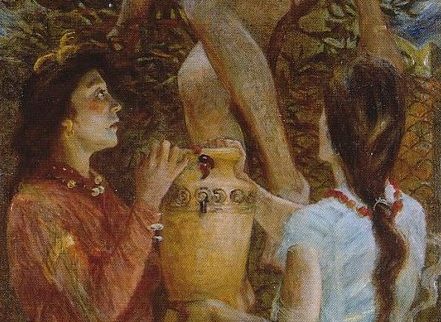





























コメントを残す