6世紀後半から7世紀初頭は蘇我氏の全盛期。
蘇我稲目(そがのいなめ)から始まり息子の馬子の時代には、婚姻政策により天皇家に蘇我一族の血を入れることに成功しました。
蘇我の血を引く天皇を皇位につけ、一族は繁栄していきます。
一方、繁栄の過程の中で邪魔になる存在とされた多くの皇族、皇子が政争に巻き込まれ命を落とし、また政権の中枢から遠ざけられました。
この犠牲になった皇族のなかから、今回は蜂子皇子(はちこのおうじ)を紹介したいと思います。
従弟である聖徳太子は、政界での輝かしい活躍もあり良く知られていますが、蜂子皇子についてはあまり知られていません。
容貌が怪異であったこと。また、人の悩みをよく聞き苦悩を取り除いたことから「能徐仙(のうじょせん)」と呼ばれていたこと等が伝わっています。
さっそく、恐れられながら慕われていた蜂子皇子こと能徐仙についてみていきましょう。
Contents
蘇我氏の台頭
物部氏との宗教戦争
天皇の妻に一族の女性を送り込んで外戚となったことの他に、蘇我氏の権勢を決定づけた出来事があります。
「丁未(ていび)の乱」と言われる、蘇我氏VS物部氏の武力衝突です。
当時、蘇我氏と並ぶ勢力を持っていた物部氏。
2つの氏族は権力闘争を繰り広げていました。
そんな折、日本に仏教が伝来します。
日本にも元々神様がいます。
しかし、この外来の神様(仏教)を受け入れるか受け入れないかについて論争がおこります。
崇物派は蘇我氏で、神道派が物部氏です。
論争はエスカレートし、武力衝突に発展します。
これに蘇我氏が勝利し、物部氏は離散。
権力は蘇我氏に集中します。
天皇殺し
そしてこの後、蘇我氏の権力の暴走が始まります。
ここから蘇我氏の本宗家が滅ぶまで、多くの皇族が排斥・殺害されていくのですが、最初の犠牲者となったのが蜂子皇子の父:崇峻 (すしゅん)天皇なのです。
丁未の乱後、馬子は崇峻天皇の即位に尽力します。
しかし即位後、天皇はほぼ蘇我氏の操り人形状態に。
天皇は、どんどん馬子を疎んじるようになり、これが本人に伝わってしまいます。
殺害の危険を感じた馬子は先手を打って天皇暗殺に及んだ、というのです。
天皇の中で臣下に暗殺されたのは、崇峻天皇のみ。
その異常性が、蘇我氏の力を立証しています。
次に天皇の位を継いだのが、蘇我氏の血を引く推古天皇。
もう誰にも蘇我氏専制体制をとめることができません。
このような政局の中で蜂子皇子は生まれ、成長しました。
蜂子皇子
逃亡
諸説ありますが、生まれは562年。
長ずるに及び蘇我氏より迫害されることをおそれ、従弟である聖徳太子の勧めによって仏門に入ります。
政権の近くにいないことが身を守ることになるため、「弘海」と称し、諸国を廻る旅にでます。
そして、父:崇峻天皇が殺害され推古(すいこ)天皇が即位した592年に、丹後の由良から出発し日本海を船で北上。
能登半島、佐渡を経由して出羽の由良(出発した港と同名)に到着したと言われています。
父が殺されたことにより、自分への直接的な危害が加わることを恐れての逃避行だと思われます。
出羽三山(でわさんざん)の開山伝承
逃避行の末、蜂子皇子は現在の山形県鶴岡市由良にたどり着きます。
この時、八乙女浦にある舞台岩と呼ばれる岩の上で、八人の乙女が笛の音に合わせて神楽を舞っていました。
蜂子皇子はその美しさにひかれて、近くの海岸に上陸します。
この土地に住むようになったある夜、「ここは永く住む所ではない。月の山の麓にある霊地を開いて民人を救うべし」という夢告がありました。
蜂子皇子は月の山へと向けて出発します。
その途中、どこからともなく三本足の烏が飛んできて、道案内をします。
その後、羽黒山に登り権現(仏の仮の姿)を感得し、月山・湯殿山にも登り同様に権現を感得。3神を祀りました。
これが、現在の「出羽三山」の開山伝承とされています。
出羽三山は、修験道を中心とした山岳信仰の場として、現在も多くの修験者・参拝者に親しまれています。
山をご神体とし、そのご神体(山)に籠もり修行や呪術的な儀式を行うことで、ご利益などが得られる。という考えのもと行われる修行。
その他の伝承
東北という土地
蜂子皇子という、当時の朝廷から疎まれる存在が流れてきたことに加えて、同じエリアに同時期に物部氏も流れてきた、という伝承があります。
『秋田「物部文書」伝承』には、前述の丁未の乱の後日譚について触れられています。
負けた物部氏の配下であった捕鳥男速(とっとりおはや)という男が、物部守屋の子で3才になった「那加世(なかよ)」という男子をかくまい、東北の地へ落ち延びた、というのです。
物部那加世は丁未の乱の後(587年)、蜂子皇子は崇峻天皇暗殺後(592年)。
逃れた土地(東北)、時期が重なります。
東北の地は大和朝廷にまつろわぬ者が集る場所だったのかもしれません。
蜂子皇子の容貌・人との関わり
「生まれつきの悪面で身色黒く、人倫の類とも思えないほど醜い容顔の長さは一尺九寸。鼻の高さは三寸余、目尻は髪の中に入り、口は裂けて耳の脇まで伸び、耳は一尺余り垂れ下がり、その声も悪音であった」
このような怪異な容貌についての伝承があるとともに、羽黒では、人々の面倒をよく見て多くの苦悩を取り除いたと言われています。
現在に残されている怪異な容貌は、多くの人の悩みを聞いた結果そのような顔になったとも言われています。
人々の苦悩を一心に請け負った、徳の高い皇子だったのかもしれません。
まとめ
同時代にいた従弟である聖徳太子。
若くして政界に登場し、隋との外交、冠位十二階、十七条の憲法など輝かしい実績を重ねてきました。
しかし、晩年は政界から疎外され、その最後は暗殺説があるほど不自然な死を遂げています。
対照的な蜂子皇子は、前半生は蘇我氏に怯えながら生き、都を追われ東北の地に逃亡します。
しかし、その土地で羽黒修験を開き、人の悩みを聞き苦悩を取り除きながら生きていきます。
出羽三山神社にある蜂子皇子の墓は、東北地方で唯一の皇族の墓として、現在も宮内庁によって管理されています。
- 参考文献
- 『秋田「物部文書」伝承』
- 『羽黒山縁起』
- 『羽黒山伝』











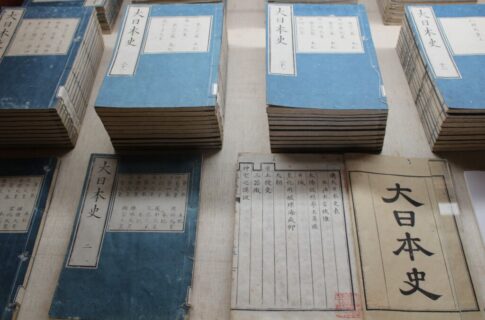





























蜂子皇子について詳しいお話ありがとうございます。