Contents
- 1 あなたの「ジャンヌ」は聖女? それとも魔女?
- 2 「百年戦争」の複雑な背景
- 3 「女系相続」が認められていたフランス王位
- 4 「アーサー王マニア」のプランタジネット家
- 5 「女系相続」に対するフランス諸侯の抵抗
- 6 ジャンヌ活躍の舞台となった「百年戦争」の発端と経過
- 7 ジャンヌ・ダルクの謎その1:ジャンヌは実在したのか?
- 8 ジャンヌダルクの謎その2:ジャンヌは本当に「フランス人」だったのか?
- 9 ジャンヌ、天使の声を聞いてオルレアンに向かう
- 10 ジャンヌはなぜイングランドのロングボウ部隊に勝てたか
- 11 「人間に大砲をぶっ放した」最初の例:ニシンの戦い
- 12 続・ジャンヌはなぜイングランドのロングボウ部隊に勝てたか
- 13 ジャンヌ、廃太子シャルルを王にする
- 14 ジャンヌの捕縛とイングランドへの売り渡し
- 15 ジャンヌ・ダルクを魔女と決めつける宗教裁判
- 16 「異端の再犯者」として火炙りにされるジャンヌ
- 17 「フランス」を作った少女ジャンヌ・ダルク
あなたの「ジャンヌ」は聖女? それとも魔女?
「ジャンヌ・ダルク」は恐らく日本で一番有名なフランス人女性でしょう。
歴史上実在したジャンヌの伝記や関連文書も多数和訳されていますし、さまざまな小説・漫画・アニメ・ゲームに登場するキャラクターの元ネタとしても大人気です。
作品によりその性格は「聖女であった」とするもの「いや魔女だった」とするものの両極端にわかれます。
外見については、こと最近においては「金髪ロング」「プレートアーマーを日常的に着用」という設定が鉄板となっているようです。
バストはどうやら豊満であるようだ、というのも、なんとなくお約束化されつつあるようにも思われます。
平野耕太著「ドリフターズ」では短髪貧乳とされ「バレー部主将」などとネタにされていますが…。
実際のジャンヌの外見は、写真などなかった時代の人物ですからよくわかりません。
死後に描かれた「肖像画」も赤毛または栗毛が多いようです。
顔については「美人であった」とする記録も、「かなりかわいそうな顔だった」とする記録もありません。
つまりごく普通の平凡な顔だった可能性が高いようです。
ただすべてのジャンヌが登場するフィクションにおいて、彼女は美女として描かれています。
さてこのように、外見についても謎や誤解が多いジャンヌですが、彼女が歴史上果たしたことについても、多数の誤解がつきまとっているのです。
ここでは、どうしてそういう誤解が生じたのかを、ジャンヌが生きた時代の背景、ジャンヌが戦った「百年戦争」の発端から掘り起こすことによって解説していくことにします。
ジャンヌの活躍については、その後にたっぷり説明するので、しばし「背景」の方をお楽しみください。
「百年戦争」の複雑な背景
ジャンヌ・ダルクは「百年戦争」の末期に活躍した人物です。
ですから、その歴史的役割について物語るためには、まず「百年戦争」がどういう戦争だったのかについて説明しなければなりません。
世界史の教科書では「百年戦争」は、フランス王位を巡ってフランスとイギリスが争った戦争である、などと書かれていると思います。
ですが、これを聞いて不思議に感じることはないでしょうか。
まず、「なんでフランス王位を巡ってフランスとイギリスが争ったのか」が謎です。
フランスの王様になるのはフランス人以外にあり得ないのではないか? と。
ちょっと詳しい参考書では、フランスにおいてカペー王家の男系が断絶したので、母経由での継承権を持っていたイングランド王がフランス王位の継承権を主張した、と書かれています。
これでちょっとわかったような気になりますが、まだ謎は残りますね。
「女系相続」が認められていたフランス王位
この流れを理解するには、「ヨーロッパにおける王位継承は、女系相続が認められていた」という知識を、前提として持っていなければなりません。
日本の皇室の場合は男系相続です。
天皇の後継者がいなくなった時は、その時の天皇と最短の父系の共通先祖を持つ方まで戻り、その男系子孫で最上位世代の最年長者の男性が継承する、ということになります。
ですがヨーロッパの場合、王朝最後の王に娘がいれば、その娘の産んだ子に王位継承権が認められるのです。
女系相続とは言っても男子の継承権が優越するルールになっています。
ですから、王朝最後の王に娘がいても、その娘が女王となるケースはあまりありません。
その娘が夫を迎え、男子を産んでいたらそちらの方が優先するのです。
さて、「百年戦争」が勃発する前のフランス王家は「カペー朝」でした。
この王朝の最後の方は、フィリップ3世→フィリップ4世→ルイ10世→フィリップ5世→シャルル4世と続きます。
フィリップ3世・フィリップ4世・ルイ10世までは親子間の相続です。
ルイ10世・フィリップ5世・シャルル4世は兄弟で、それぞれ子がなかったため死後弟に王位が受け継がれました。
しかし、最後のシャルル4世で弟も子も打ち止めになってしまったので、王朝断絶に至ったのです。
ただ、ルイ10世・フィリップ5世・シャルル4世には姉妹もありました。
順番的にはフィリップ5世の妹でシャルル4世の姉に当たるイザベルです。
この人物はイングランドのエドワード2世の王妃となっており、息子エドワードはカペー朝断絶の前年にイングランド王に即位し、エドワード3世を名乗っていました。
当時のフランス王家のしきたりにおいては、イザベルに王位継承権は認められませんでした。
ですが、イザベルの夫や息子には、王位継承権があるとされていたのです。
どうしてこういう複雑なルールになっていたのかを理解するには、ヨーロッパにおいて「王」がどのようなものとして認識されていたか、を知っておく必要があります。
「王」、「王位」には二つの側面がありました。
ひとつは「特定の領地と財産の継承者」であり、もうひとつは「領地と財産を守護するための軍隊の最高指揮官」です。
中世ヨーロッパにおいては、ごく一部の例外を除いて女性は戦場に赴きませんでした。
ですから「軍隊の最高指揮官」である王になることはできません。
しかし、「領地と財産の継承者」になることはできるのです。
ですから、その女性の夫または男子は、「領地と財産を継承」することができ、なおかつ「軍隊の最高指揮官」にもなれます。
そのため、「女系相続」が認められるのです。
エドワード3世がフランスの王位継承権を主張するのは、いいがかりでもなんでもありませんでした。
「アーサー王マニア」のプランタジネット家
エドワード3世は「イギリス王」だと思われていますが、厳密に言えばそうではありません。
現在漠然と「イギリス王」と呼ばれているのは、いわゆる「連合王国」の首長であるエリザベス2世です。
女性ですから「イギリス女王」であり、国歌も「ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン」というタイトルになっていますね。
この国歌は男性の王を戴いている時は、「ゴッド・セイヴ・ザ・キング」になります。
で、「連合王国」ですが、イングランド・ウェールズ・スコットランド・北アイルランドの4つの国によって構成されている、とされています。
それぞれ別の国ですが、ひとりの人物がすべての地域の最上位者を兼任しているので、なんとなく一つの国扱いしている、というのが実態です。
ちなみに、ウェールズの君主は「王」ではなく「公(プリンス)」です。
イングランドでは古くから第一王位継承権者に「プリンス・オブ・ウェールズ」という称号を与えますが、これはウェールズの君主であるウェールズ公の意味です。
連合王国における「公」は、プリンスとデュークの2種類がありますが、「プリンス」が付くのはウェールズ公のみです。
あまり知られていませんが、連合王国の第二位王位継承権者には「ヨーク公」の称号がつけられます。
こちらは「デューク・オブ・ヨーク」となっています。
イングランドとスコットランドの最上位者は「王」です。
北アイルランドは「アイルランド卿(ロード・オブ・アイルランド)でしたが、16世紀ぐらいにイングランド王位に吸収・統合されてしまいます。
ともかく、現在の連合王国は、イングランド王・スコットランド王・ウェールズ公・アイルランド卿の4つを兼任する王を共通の元首とする国家なのです。
百年戦争の当時、イングランド王はアイルランド卿・ウェールズ公を兼任していましたが、スコットランド王は兼ねていませんでした。
だから「今のイギリス王とは違う」のです。
エドワード3世当時のイングランド王は、スコットランド王は兼ねていませんでしたが、別の称号を持っていました。
アキテーヌ公です。
この公爵領は現在のフランスの南西部にありました。
エドワード3世の属するイングランドの王家はプランタジネット家と呼ばれます。
この王家は、もともとはフランスの貴族であるアンジュー伯の家系でした。
アンジュー伯であったアンリ1世は、女系相続でイングランド王位を手に入れ、イングランド王ヘンリー2世として即位します。
また、妻アリエノール・ダキテーヌがアキテーヌ公領の継承権を持っていたため、その子となるリチャード1世は、イングランド王・ウェールズ公・アンジュー伯・アキテーヌ公を兼任することになりました。
リチャードはさらにメーヌ伯・ガスコーニュ公・ノルマンディー公位も兼任しており、ブリテン島に持っている領地よりもフランスに持っていた領土の方が広かったのです。
なお、アリエノール・ダキテーヌはいわゆる「騎士ロマンス」が大好きな女性で、吟遊詩人たちを呼び寄せてアーサー王伝説などの武勲詩を語らせるのを日常としていました。
そんな母のお気に入りだったリチャードは自分自身をアーサー王になぞらえる程の「騎士道マニア」になっています。
リチャードは死ぬ時に、イングランド王位とアキテーヌ公位は弟ジョンに継承させましたが、アンジュー伯領は甥のアーサーに譲るよう遺言しました。
ちなみにこのアーサーの名前は、騎士道マニアの伯父リチャードがアーサー王になぞらえて付けたものです。
このアーサーが若死にしてしまった(ジョンによる暗殺説があります)ため、アンジュー伯領はフランス王家であるカペー家に没収されてしまいます。
それでもフランスの領土をすべて失ったわけではありませんでした。
というか、アンジュー伯領を失ってもなお、プランタジネット家がフランス内部に所有する領土は、フランス王家の領土よりも広かったのです。
「女系相続」に対するフランス諸侯の抵抗
エドワード3世は、母方から正統な王位継承権を受け継いでいるだけでなく、フランス最大の諸侯でもありました。
普通ならすんなりその王位継承は認められるはずでした。
しかし、他のフランス諸侯の中に、「イングランド王がフランス王位を兼ねるのはどうか」という意見が出てきたのです。
法的な根拠があるわけではありません。
「ただなんとなく」という理由で出てきた異議に過ぎませんでした。
ある国の王が他国の王を兼ねるということはさほど珍しいことではなく、10世紀終わりには、アニメ「ヴィンランド・サガ」の登場人物であるデンマーク王クヌートが、イングランド王位とスウェーデン王位を兼ねた例があります。
にもかかわらずフランス諸侯は結託し、エドワード3世の母イザベルの従兄弟を引っ張り出してきます。
つまりフィリップ3世の息子で、フィリップ4世の兄弟であるヴァロワ伯シャルルの子フィリップをフィリップ6世として即位させました。
実はルイ10世の時代にすでにカペー家断絶の可能性が高まってきており、フランス諸侯は「サリカ法」という根拠を持ち出して「フランス王家では女系相続禁止」というのをルール化しようとしていたのです。
「サリカ法典」は、フランク王国の時代にローマから法学者を呼び寄せて作らせた法典です。
無理やり作ったものなのであちこち穴もあり、そのせいかすぐに誰も使わなくなってしまった代物です。
そのカビの生えた法典を引っ張り出し、王家の相続に強引に適用したのですが、なぜかサリカ法典が効力を生じるのは王位の相続のみで、貴族の相続に関しては適用しない、という不思議なルールに書き換えられていました。
なお、当時フランス王国と同君連合の関係にあったナヴァラ王国では、王位の女子相続が認められていたので、ルイ10世の娘・ジャンヌ(ジャンヌ・ダルクとは別人です)が即位することになりました。
実を言うと、ジャンヌは嫡出性に疑問が持たれていた(つまり不倫の子疑惑があったということです)王女です。
先程のサリカ法典によるこじつけは、エドワード3世の継承権排除を目的としたものではなく、ジャンヌの即位を回避するために引っ張り出された根拠だったとする説もあります。
ジャンヌ活躍の舞台となった「百年戦争」の発端と経過
ともあれ、エドワード3世のフランス王位継承権というのは、現在のわたしたちの多くが想像するよりずっと「正統なもの」でした。
エドワード3世からすれば、正統な王位継承権を持っていたはずなのに、フランス諸侯の抵抗等でこじれまくったため、反対派の貴族をちょっと叩いて実力で自分の権利を認めさせようとした、といったところだったでしょう。
イングランド王がフランス全土を自分のものにしようと起こした「征服戦争」ではなかったのです。
ちなみにカペー朝の末期の王は、プランタジネット家のフランス内部の領地に対して何度もちょっかいをかけていました。
またイングランドはスコットランドに侵攻してスコットランド王デイヴィッド2世を追放しましたが、デイヴィッド2世はフランス王家の助力を受け、抵抗を継続したのです。
エドワード3世はフランス王家によるそれらの干渉を一気にやめさせる好機、と考えたのかも知れません。
百年戦争はその勃発当初においては、「国家対国家」の戦争ではありませんでした。
ですが、フランス王家(ヴァロワ朝)側が優勢になってイングランド軍本隊が母国に引き揚げると、「国対国」の戦争のように見え、イングランド軍(≒アキテーヌ公軍)がフランス本土内部に深く侵攻すれば侵攻するほど、フランス諸侯の内乱のように見える、という不思議な性格を持っていました。
フランス本土以外でも、さまざまな場所でヴァロワ朝 とエドワード3世は対立していました。
百年戦争は、エドワード3世がヴァロワ朝に挑戦状を送付することにより始まりましたが、戦いはフランス王家とイングランド王家が対立していた各所で散発的に発生する局地戦という形態を取りました。
イングランド軍がフランスに上陸したのは開戦後10年ほど経ってからのことです。
イングランド軍はフランス諸侯軍よりも数的に劣勢だったのですが、ロングボウの部隊を中心とした、統率の取れた軍でした。
フランス諸侯側は、多くの諸侯がめいめい自分の手勢を率いて集まった軍です。
このため指揮系統が統一されておらず、部隊ごとにばらばらに騎兵突撃をし、ロングボウ部隊に各個撃破されてしまいます。
この結果、戦争は長期化することになります。
イングランド側には、エドワード3世の息子エドワード黒太子という有能な軍隊指揮官が登場し、戦いを優勢に進めます。
しかしこの黒太子が父よりも早く死に、その後黒太子の子リチャード2世が若くして王位を継ぐとイングランドが政情不安になりました。
リチャード2世は最終的に廃位され、プランタジネット朝は断絶してランカスター朝が始まります。
ランカスター朝初代のヘンリー4世はリチャード2世の叔父なので、こちらはちょっと強引な父系相続ということになります。
ヘンリー4世の子・ヘンリー5世の代に、イングランドはまた攻勢に出ます。
この時のフランス王シャルル6世は幼少かつ精神薄弱で、フランス諸侯はブルゴーニュ派・アルマニャック派の二派に分かれて内ゲバを始めます。
ヘンリー5世はブルゴーニュ派と同盟を組み、フランスに侵攻します。
イングランド軍はフランスの北西部を完全に押さえてしまい、ブルゴーニュ派は王家内部の実権を握ります。
シャルル6世の息子シャルル(7世)は、母の不品行を理由に王位継承権を剥奪され、追放されてしまいます。
シャルルは先に言及したナヴァラ女王ジャンヌの同母の弟なので、姉同様不倫の子疑惑があったのです。
さらに、ブルゴーニュ派は王家の代理としてヘンリー5世と「トロワ条約」を結びます。
トロワ条約とは、1420年にフランスのトロワで調印された条約のことです。
すでに発狂していたシャルル6世に代わり、フランスの国政を運営していたブルゴーニュ公が、シャルル死後のフランス王位を、イングランド王ヘンリー5世か、その子孫に継承させるということが定められました。
また、シャルル6世の子シャルルは、この時にすべての称号を剥奪され、ロワール川の南に追放されています。
これによりシャルル6世の王位はシャルル6世が亡くなるまで保証されましたが、ヘンリー5世はシャルル6世の娘と結婚して王位継承権をさらに強め、フランスの摂政に就任します。
シャルル6世の死後については、ヘンリー5世が継承するか、ヘンリー5世の子が相続する、ということで決着しました。
これは一応国際条約ということになります。
シャルル6世が死んだ時、ヘンリー5世もまたこの世にいなかったので、ヘンリー5世の子ヘンリー6世がイングランド王・フランス王を兼任しましたが、これは完全に「合法」ということになります。
少なくとも追放された元王太子シャルルの側には、これをひっくり返せるだけの根拠はありませんでした。
ジャンヌ・ダルクの謎その1:ジャンヌは実在したのか?
ジャンヌ・ダルクについてはさまざまな書物が書かれていますが、その実像はというと、あまりはっきりはしません。
というのは、ジャンヌを聖女とし、そのやることなすことを無条件で正義とする側と、その逆で魔女だとする側で評価が両極端に分かれ、中立的な書物というのは案外少ないからです。
中にはジャンヌ・ダルクの実在を疑う人すらいます。
本当に神の言葉を聞いたのかどうかはともかく、百年戦争の末期に廃太子シャルルとともに軍勢を率いて戦ったジャンヌという女性の存在は、その後の裁判記録等によって確認することができます。
実在したことは疑いようがありません。
ここではジャンヌが歴史上何をしたかについて理解を深めるため、百年戦争そのものについてちょっと掘り下げてみました。
ジャンヌ登場時のフランスは、王の弟の派閥(アルマニャック派)と王の従兄弟の派閥(ブルゴーニュ派)が抗争をしていました。
そしてブルゴーニュ派がイングランド王と同盟して内戦において優位を占め、ヘンリー5世とその子を正統な王位継承者とする条約が結ばれていたのです。
ジャンヌはこうした時期に登場し、実質的な勢力も王位継承の正統性も失い、南部の町シノンに引きこもっていた「廃太子」シャルルを担ぎ上げた、というのが実態です。
ジャンヌは「王太子を助けろ」と神の声を聞いた、と周囲に言います。
その声は「廃太子」にも届き、シャルルはジャンヌの言うことを「確かに神の声だ」と認めます。
認めるしかなかったでしょう。
そうでもしないと自分の王位継承権を正統なものにできなかったのですから。
しかし、田舎から出てきた神がかった少女の「お告げ」であっても、それを教会などが正統なものだと認めてくれれば、シャルルはフランス王となることができます。
そして、戦いに勝利すれば教会は自然と自分の側になびいてジャンヌの言うことを「神の声だ」と言ってくれるでしょう。
後はとにかく勝てばいいのです。そしてその勝利も、ジャンヌが持ってきてくれました。
ジャンヌはイングランド軍に包囲され、陥落寸前だったオルレアンの街を解放します。
オルレアンは、アルプスに源を発し、ビスケー湾に注ぐロアール川の北岸にある都市です。
ロアール川にはほとんど橋がありませんが、オルレアンにはその数少ないひとつがありました。
しかも、パリから一番近いところにある橋ですから、ここを押さえればロアール川南岸の広大な地域を守ることができる、という戦略的に極めて重要な土地だったのです。
王の住まうパリを確保しているブルゴーニュ派とイングランド軍は、フランス南西部も手中に収めようと、オルレアンを包囲します。
イングランド軍はオルレアン近郊の砦を攻略し、橋を渡ってオルレアン城内に突入する姿勢を示しました。
しかしここでイングランド軍の総指揮官ソールズベリー伯が負傷し、やがてこの時の傷が元で亡くなってしまいます。
総指揮官を失いイングランド軍の攻勢が緩んだ隙に、オルレアン側は橋を爆破してイングランド軍の城内乱入を困難なものとしました。
イングランド軍はオルレアンを包囲し、物資の流入を止めて城内の住民を飢えさせる戦術に変更します。
かくしてイングランド軍の手によって多くの攻城用の砦が作られ、オルレアン市民とイングランド軍の睨み合いが続きました。
しかし全体的に見ればオルレアン側が劣勢で、オルレアン陥落は時間の問題だと誰もが思うようになります。
イングランド軍の包囲網は、当初穴だらけでしたが次第に緻密なものになり、オルレアン城内に運び込まれる物資が不足するようになっていました。
ここにやってきたのがジャンヌなのです。
ジャンヌダルクの謎その2:ジャンヌは本当に「フランス人」だったのか?
ジャンヌは後に「オルレアンの乙女」と呼ばれるようになります。
オルレアンはパリに近いフランス中部の都市です。
ただしジャンヌは、オルレアン出身だったわけではありません。
フランスの東の辺境のドンレミ村というところの出身です。
この村はジャンヌの生きた時代の前後、「ロレーヌ公国」の一部となっていました。
「ロレーヌ」は、「ロタールの国」という意味の「ロタリンギア」をその名の元とする地域です。
「ロタール」はフランク王国のシャルルマーニュ(カール大帝)の息子で、父の死後ふたりの弟たちとフランク王国を三分割してその一部を領有しました。
弟たちの領地が後のフランス・ドイツへと繋がっていくのですが、ロタールの王国は早い段階で王不在の状態になってしまったので、フランス・ドイツ(神聖ローマ帝国)に領地を削り取られていきます。
このロタリンギアは、北端部はベルギーやルクセンブルクとして独立を維持しましたが、残りはドイツ・フランスに吸収されてしまっています。
そして「ロタリンギア」を名前の由来とする東部のロレーヌ(ドイツ語読みでロートリンゲン)は、「アルザス(同エルザス)とともに独仏両国の間の係争の地となります。
アルザス・ロレーヌがフランス領として確定したのは第二次世界大戦後のことです。
ドンレミ村は近代まで独仏の係争地となった「アルザス・ロレーヌ」そのものではありませんでしたが、その地域を含む「ロレーヌ公国」の中にあったのです。
ジャンヌが生まれたのは、このような複雑な因縁のある土地でした。
一般的にはジャンヌはフランス史上1・2を争う愛国者であり、彼女のアイデンティティはフランス人以外の何者でもなかった、とされてしまっています。
しかし出身地の由来をちょっと調べるだけでも「ホントかな?」と思えてしまう部分があるのです。
ジャンヌの生地の西側はブルゴーニュ公国で、ジャンヌの生地の領主に対して圧迫を加えていました。
そのためジャンヌがブルゴーニュ公に敵意を感じていたとしても不思議ではありません。
「うちの領主様をいじめているからブルゴーニュ公は悪い人。悪い人だから海の向こうから知らない人を連れてきてこれが王様だと嘘を言っている。ブルゴーニュ公にいじめられている王太子様(シノンの廃太子シャルル)こそが正しい人」。
文盲の少女が思いつく「理屈」としては、このあたりが精一杯だったのではないでしょうか。
故郷の村に留まっていた時点では、ジャンヌが果たして「イングランド」という国の存在を明確に意識できていたかどうかすら疑問です。
「フランス王国」とは言ってもその中にはブルゴーニュ公国やアキテーヌ公国を含んでいて、フランス王はその盟主にしか過ぎないのが実際のところですが、そのあたりの理解がなくてもまた当たり前であろうと考えられます。
漠然と「フランス」と考えられている地域の各種貴族は、フランス国王に臣従の礼を取っており、これによってフランス王を頂点とする連邦のようなものを形成していました。
ただ、別途イングランド王位を持っているアキテーヌ公は、フランス王に臣従礼を取った時期もあり、拒否した時期もあります。
これによりアキテーヌ公国はフランス王国に含まれたり離脱したりすることがあったわけです。
結局、当時の人にとっては「フランス」とはなんだかよくわからない存在だった、ということなのです。
文盲の無学な少女ジャンヌにとっては、「フランス」は「世界」とほとんど同じ意味を持っていたものと思われます。
なので、「フランスを救え」は「世界を救え」と同じ意味であり、「フランス人」は「人間」とほぼ意味は同じであったのでしょう。
ジャンヌ、天使の声を聞いてオルレアンに向かう

ジャンヌは、12歳(自称)頃「フランスを救え」という神の声を聞いたと言っています。
これが男装してオルレアンで戦うきっかけとなったのですが、神の声を聞いたからと言ってすぐさまオルレアンに行けるわけではありませんでした。
先にも述べたように、ジャンヌの故郷のすぐ西側には「悪の総帥」が統治するブルゴーニュ公国があります。
ここを突破する方法を考えなければなりません。
ジャンヌがブルゴーニュ公国突破のために使った方法は、非常に現実的なものでした。
つまり、地元の貴族に神の声の話をし、信じてもらってブルゴーニュ領通過のための手配をしてもらったのです。
地元の貴族は最初ジャンヌの話を信じてくれませんでしたが、何度も話をし、かつ「オルレアンの近くでフランス軍が敗北する」という予言を的中させたため、信じてもらうことに成功しました。
ちなみに、フランス軍というかアルマニャック派ですが、ここ15年ぐらいイングランド軍やブルゴーニュ軍に勝ったことはありません。
ともあれ、こうしてジャンヌはシノンへ行き、「廃太子」に会うことになります。
もちろんシャルルもジャンヌも、シャルルのことを「王太子」としていますが、先の述べた通り、国際条約上では彼の立場はあくまでも廃太子でしかありません。
ジャンヌは廃太子と会話し、シャルルはジャンヌを信用したとされていますが、そこですぐ軍を率いて前線へ、となったわけではありません。
シャルルはジャンヌを軍指揮官として起用する前に、かなり綿密に「身体検査」を行っているのです。
これまでの百年戦争は、アキテーヌ公兼イングランド王とヴァロア朝の王によるフランス王位継承の争いに、フランスとその関連国の諸侯が介入していったという「俗世」の争いでした。
誰の参戦動機も私利私欲にまみれていたのです。
ジャンヌの登場は、この俗臭極まりない争いに、宗教を持ち込むことになりました。
シャルルの王位継承権は、俗世の法ではすでに否定されてしまっています。
彼が一部にまだ王太子として扱われているのは、アルマニャック派の私利私欲を満たすための駒としての価値があるからです。
オルレアンが陥落してアルマニャック派が再起不能なまでに弱体化すると、シャルルは完全な「廃太子」になってしまいます。
この苦境を逆転するためには、もはや神にすがるより他にないのです。
俗世の争いに宗教的要素を入れると、現在でもかなり厄介なことになりますが、神の存在を建前上すべての人が信じていた中世においてはそれどころの話ではありません。
近い将来起こり得る面倒をかなりリアルに想像することができたため、ジャンヌの素性や生活習慣などを徹底的に調査し、指導者として適格かどうかを確かめたのです。
結果は「合格」でした。
こうしてジャンヌは一軍の指揮官として、オルレアンへと送り込まれました。
ジャンヌはなぜイングランドのロングボウ部隊に勝てたか
オルレアンに到着したジャンヌはイングランド軍の包囲を打ち破り、その勢いに任せてロアール川の周辺地域の掃討戦の指揮をとりました。
このあたりについても、当時およびジャンヌ死後の名誉回復裁判の時の記録などを読んでも、詳しいことはわかりません。
ジャンヌを聖女だとする立場の人々は、ジャンヌには天賦の軍隊指揮の才能があり、フランス軍が勝てたのはそのせいだ、としています。
ジャンヌ聖女説に対して批判的な人は、ジャンヌは単なる田舎娘に過ぎず、勝てたのは単なる偶然だ、とする傾向が強いようです。
ジャンヌ自身は、十代の少女に過ぎません。
ですから槍を持って全軍の先頭に立って突撃する、という戦い方はできなかったと考える方が自然です。
当時の記録にも、肉弾戦は不得意としていたとか戦場で泣き出したとかいうものが残っています。
その代わり、武器は持たずに旗を持って全軍から見える場所に立った、とする記録も多く、これにより「フランス軍」の士気を高めることはできていたようです。
オルレアン解放は、どちらかというとこの士気高揚の効果の結果だと見た方がよいでしょう。
また、正規の軍人ではなかったため、当時の「戦いの作法」に通じていなかったのも、初期の戦いで勝利を重ねた原因であったと思われます。
当時の戦争は、両軍が陣形を整え、相手に挑戦の宣言をした上で始めるのが常識でした。
しかし、素人であるジャンヌは、敵軍が陣形を整え終える前に戦闘を開始してしまったというのです。
結果としては奇襲になるので、勝利を収めやすくはあったでしょう。
大砲という新兵器をよく使いこなした、というのもジャンヌの勝利の原因として挙げられています。
最近では、「それまで攻城兵器だと考えられていた大砲を人間に向かってぶっ放したのはジャンヌが最初」などと言われるようになっていますが、実際にそうだったのかは疑問が残ります。
というのは、この当時大砲は攻城兵器として発展途上であったためです。
ヨーロッパにおいて、大きな石を砲弾として撃ち出す大砲が使われだしたのは15世紀の始め、つまりジャンヌが活躍していた時代です。
つまり大砲はできたてほやほやの最新兵器であり「人間に向けて撃ってはいけない」などというルールが確立していたとは考えにくいのです。
ヨーロッパにおける最古の大砲らしきもののスケッチは1326年に描かれています。
これが想像で描かれたものなのか、実物があってそれを絵にしたのかよくわかりません。
ただ、この「大砲」は砲身長も口径もかなり小さく、城壁に向けて発射しても傷を付けることができるかどうか疑問が残る代物でした。
攻城兵器としてはとても使えないので、人間相手に使ったと考えるのが自然です。
その後100年近く、大砲は「人間相手に使うしかなかったもの」だったのですが、ジャンヌの時代になってようやく「攻城戦に使えるもの」になったと思われます。
記録が少ないので本当にそうだったのか断言はできませんが。
「人に向けて撃つ」戦法をジャンヌが創始したのかはともかく、大砲はその頃のイングランド軍の主力であったロングボウ部隊とは恐ろしく相性の悪い兵器でした。
ロングボウ部隊は小部隊ごとにバラバラに突撃してくる相手には無類の強さを発揮します。
しかし、部隊全体の機動性が低く、なおかつ低防御であったのです。
大砲はロングボウよりも長い射程を持ちますので、アウトレンジから砲弾(石)を弓兵陣地に叩き込むことができました。
「人間に大砲をぶっ放した」最初の例:ニシンの戦い
実を言うと、ジャンヌがオルレアンに行くきっかけの一つになった予言の元になった戦いに、フランス砲兵がイングランド弓兵を圧倒する予兆が出ていました。
この戦いは、「ニシンの戦い」と呼ばれます。
「ニシン」は魚の名前です。
これはイングランドの輸送部隊を、フランス・スコットランドの連合軍が襲ったというものです。
イングランドの指揮官は、荷馬車を輪形に配置して陣地を作り、周囲に積荷の樽(ニシン入り)を置いてバリケードとします。
そしてロングボウ部隊をその内部に置き、連合軍の突撃を待ち受けました。
これに対し、フランス軍はロングボウの射程外から大砲を撃ち込み、イングランド軍は窮地に立たされます。
が、フランス軍に手柄を総取りされるのを嫌ったスコットランド人部隊が突撃を開始しました。
同士討ちを避けるため、フランス軍が砲撃を停止すると、イングランドのロングボウ部隊は息を吹き返し、矢の雨を降らせてスコットランド人部隊を殲滅します。
この戦いが「ニシンの戦い」と呼ばれたのは、フランス軍の砲撃によってバリケードの材料になったニシン樽が破壊され、あたり一面にニシンが転がったからだと言われます。
いずれにしろ、ジャンヌ登場の直前に、「大砲を人に向けて撃った例」はあったのです。
続・ジャンヌはなぜイングランドのロングボウ部隊に勝てたか
ジャンヌがなぜ勝てたかについて、さらに解説します。
当時のヨーロッパの軍隊、特にフランスのそれは貴族の混成部隊です。
貴族にはそれぞれ爵位があり、その爵位によって戦場での指揮命令系統の上下が決まりました。
しかし、末端の兵士はその直属の上司である貴族の言うことしか聞きませんから、最高指揮官と言えども軍全体を手足のように操るのは困難…というかほぼ不可能だったのです。
ジャンヌはこの爵位を持っていません。
つまり戦場以外での上下関係のしがらみがない人物でした。
しかもその役目の大部分は「全軍の士気高揚」です。
自軍のどの部隊にも出向いて「立って敵に立ち向かいなさい」と命じることができたのです。
また当時の貴族は、数代遡ればどこかで血がつながっていることが多く、戦争になっても「親戚だから」という理由で適当に手を抜くこともよくありました。
敵将を生け捕っても基本的に処刑してしまうことはなく、後で身代金を受け取って帰らせてやる、というのが常識だったのです。
イングランド軍の主力を形成するロングボウ兵は、貴族ではなくその下の自営農民層です。
彼らはフランス貴族との間に血縁関係などありませんから、容赦なく矢の雨を降らせることができました。
このあたりも、ジャンヌ登場までフランス兵がイングランド軍に押され続けた理由となっています。
貴族の血のしがらみと無縁で、なおかつ「フランスを救う」という熱情を抱いていたジャンヌは、すべての戦場において積極策を取ります。
軍議に出てきた他の将軍たちが「ここは慎重にことを進めよう」と言っても、ジャンヌは「いや攻めます」と譲らないのです。
最高司令官が「慎重策を取る」と命令しても、ジャンヌは一人で旗を持って進み、後を追ってきた兵士たちとともに敵を撃破する、ということもしていました。
敵軍からすれば、どんな時でも襲いかかってくる命知らずの敵将がいる、ということになりますから、恐怖して逃げ腰にもなるでしょう。
また、ジャンヌは戦闘終了後、抵抗した敵軍捕虜や市民を平然と虐殺することがありました。
これも敵兵の間に恐怖の感情を撒き散らし、進軍を有利にしています。
もっとも、これは戦闘が一段落すると、敵対した相手から返ってくる「ブーメラン」だったのですが…。
ジャンヌが軍の指揮者として活動したのは1年少々で、参加した戦いは14にのぼるそうです。
そのうち9つが勝ち、4つが負けまたは劣勢だったと言います。
勝っていたのは砲兵部隊が充実していた時期で、弾薬が不足して砲兵を自由に使えなくなると負け始めています。
火薬の原料である硝石などを送ってほしい、という内容の手紙が、今なお残っています。
14戦9勝4敗で.692という勝率は、豊臣秀吉(84勝8敗7分、勝率.852) 織田信長(59勝16敗8分、勝率,719)より下ですが、徳川家康(47勝8敗12分、勝率.701)と同等です。
なお、同じフランス人(こちらもよく調べると純粋なフランス人か? という疑問が出てくるのですが)のナポレオン・ボナパルトは41戦38勝3敗で.928というとんでもない勝率を挙げています。
ナポレオンの用兵は、砲兵の集中運用、平民出身の士気の高い兵士中心と、ジャンヌのものとよく似ています。
ナポレオンと比べるとかなり勝率が低くなってしまいますが、これはジャンヌが軍司令官としては並だったせいなのか、ナポレオンが規格外だったせいなのかわかりません。
ジャンヌ、廃太子シャルルを王にする
オルレアンを「解放」した後、ジャンヌとその軍勢はロアール川周辺の掃討戦を行います。
その間「今後どうするか」が廃太子シャルルを中心としたアルマニャック派幹部で話し合われました。
この場でジャンヌは、「ランスを攻略すべきだ」と進言します。
ランスは、今では人口約18万の小さな都市に過ぎませんが、フランク王国時代の首都のひとつであり、代々のフランス王はここで戴冠式を挙げることにより「真のフランスの王」と認められたのです。
つまり、シャルルもランスを奪還してここで戴冠式を挙げてしまえば、それまでのあやふやな根拠を全部チャラにして、フランス王としての法的正統性を獲得することができるのです。
一般的には、ランス奪還作戦はジャンヌが強く願って実現させたことになっています。
しかし、成功の可能性が低くてもランスを手中にしなければならない切迫した理由があるのはシャルルの方です。
1429年6月18日、ジャンヌの参加した軍がパテーという地でイングランド軍に対し圧倒的な勝利を収めます。
勝因はイングランドのロングボウ部隊の布陣が終わる前にフランス軍が奇襲攻撃を仕掛けたためですが、この攻撃を敢行したのはラ・イルという人物でジャンヌではありません。
ちなみにラ・イルというのはあだ名で、日本語にすると「ブチ切れ男」ぐらいの意味になるそうです。
この人物はトランプのハートのジャックのモデルになっているとも言われます。
ジャンヌの「戦友」にはこのラ・イル以外にもジル・ド・レ(少年に対する性暴行致死の未公認世界記録保持者)が有名です。
またパテーの戦いではリッシュモン大元帥という人物がジャンヌ軍の指揮を取っています。
このいずれもが「性格に問題あり」だったと言います。
ジル・ド・レについては、おかしくなったのはジャンヌという戦友を失った後だ、と言われることが多い(小説などではたいがいこの説になっています)のですが、記録を調べるとジャンヌの生前から悪事を重ねていました。
どうやらジャンヌがオルレアンで華々しい勝利を挙げてから、「こいつと一緒に一旗揚げよう」という怪しげな人材が続々集まってきたような雰囲気です。
そういう人たちによる戦場でのルール無視をきっかけとした勝利が、「ジャンヌ名将説」の基礎になったように思えなくもありません。
パテーの戦いでイングランドのロングボウ部隊は壊滅してしまいました。
イングランド側は本国から再編成した部隊を補充しないと戦うことができません。
この結果、当初「無理だ」と思われていたランス攻略戦がスムーズに進行し、それから一ヶ月もしないうちにフランス軍はランスを無血占領してしまいました。
占領の翌日、シャルルは市内のノートルダム大聖堂で戴冠式を挙げ、「シャルル7世」であることを宣言しました。
ジャンヌがいくら「王太子」だと主張しようと、それまではなんら法的な裏付けがなく、「廃太子」でしかなかったシャルルですが、ここで一気に対抗馬のヘンリー6世と同等の法的正統性を手に入れたのです。
それぐらい「ランスでの戴冠式」には大きな意味がありました。
ヘンリー6世もその後パリのノートルダム寺院で戴冠式を挙げるのですが、時すでに遅しです。
世間はランスで先に戴冠式を挙げたシャルル7世を「正統なフランスの王」と認めるようになってきました。
ジャンヌの捕縛とイングランドへの売り渡し
「正統な(最低限対抗馬と張り合える程度の)王」となったシャルル7世は、この時点でブルゴーニュ派との講和を模索するようになります。
彼が望んでいたのは、「フランスと呼ばれる地域内の諸侯の盟主」であり、後のブルボン朝の諸王のような、「フランス全土を絶対的権力で支配する王」ではなかったのです。
「フランス」という概念がまだ固まっていなかった(ジャンヌですら「ブルゴーニュ公国はフランスではない」と思っていたことが残された書簡からわかっています)のですから、「フランス全土の絶対君主」などという存在は、当時の誰にも想像できるものではありませんでした。
ただ、ジャンヌの思想は、それを突き詰めていけば、絶対君主のようなものを作り上げようとする性格を持っていました。
ジャンヌの考えは非常にシンプルで、「神-王-民衆」によって構築される「自分の国」がすなわちフランスだと思っています。
このためジャンヌは、シャルル7世が王位を確保して満足しているとは夢にも思わず、「パリを攻略しましょう」と提案します。
王は一応これを許可しますが、何が何でもパリが欲しかったわけではありません。
ですから小競り合いの最中にジャンヌが負傷したと聞くと、さっさと撤退命令を出してしまいました。
これ以後ジャンヌはほとんど戦闘に勝利することができなくなります。
翌1430年5月、パリ近郊のコンピエーニュで発生した小規模な戦闘で、ジャンヌはブルゴーニュ公国軍の捕虜となります。
当時、貴族は戦闘で捕虜になると、親戚なりなんなりが身代金を払って解放してもらう慣習となっていました。
一応ですが、1429年のうちに、ジャンヌとその家族は貴族に叙されています。
とはいえにわか貴族のジャンヌの家に、身代金を払えたとは思われません。
立場からすれば、シャルル7世が払うのが筋だったでしょう。
しかし、王はなんだかんだと理屈を述べて身代金を支払おうとはしません。
シャルル7世の本音としては、「正統な王位」を確保できたので、今後はゆっくりと各派と交渉を行い、話し合いで自分の地位を固めていきたいのです。
長期間に渡る戦争とペストの流行で、フランス全土は疲弊していましたから、これは非常に現実的な政策と言えました。
そういう状況においては、原理主義を振りかざし、全方向に喧嘩を売りまくるジャンヌは狂犬のようなもので、王にとっては邪魔なのです。
しかも、当人には喧嘩を売っている自覚はありませんから、さらに始末に困ります。
ヘンリー5世とその子孫にフランス王位を認めた「トロワ条約」はまだ有効であり、シャルル7世のアキレス腱となっています。
王としては、「条約破り」の責任をジャンヌに押し付け、ジャンヌをブルゴーニュかイングランドに処断させることにより、「トロワ条約違反」を不問とさせようと考えたとしても不思議ではありません。
というわけで、フランス王はジャンヌについては「無視」を決め込み、ブルゴーニュ側がイングランドにジャンヌを売り渡すのを黙って見ていたようです。
なお、ジャンヌは「売られた」のではなく、建前上はイングランド側がブルゴーニュに身代金を支払って引き取ったことになっています。
ジャンヌの身柄は、フランス国内におけるイングランドの策源地であるルーアンに送られ、そこでフランスの司教の手によって異端裁判にかけられます。
フランス王もブルゴーニュ公もイングランド王も、誰も責任を負うことなく、ジャンヌを殺す陰謀が進められていきます。
ジャンヌ・ダルクを魔女と決めつける宗教裁判
身代金を払い、ジャンヌの身柄を引き取ったのはイングランドでしたが、彼女を異端者であるとして告発したのはイングランド政府ではありません。
パリ大学です。
パリ大学はカトリック神学の権威ある研究機関です。
パリはまだイングランドの占領下にありますから、イングランドの息がかかっている可能性は高いのですが、「ジャンヌを殺したい」という動機はブルゴーニュ公国にもシャルル7世にもあります。
決して、イングランドの意思だけによるものとは言えないのです。
この裁判については後世詳細な記録が発見され、多くの研究者によって検証が行われているのですが、筋書きそのものは非常にシンプルです。
1.ジャンヌ本人に自分が異端者であることを認めさせ、改悛させる。
2.その後異端者であると認定された行為を再び行わせ、処刑する。
こういう方法を取ったのは、当時の異端審問では、異端者であっても改悛すれば、異端行為を再犯しない限り処刑できない、という規定があったためです。
逆に言うと、改悛者が異端行為を繰り返せば、問答無用で処刑できた、ということでもあります。
ところが、最初の「異端ポイントの発見」が難航します。
一番やりやすいのは、ジャンヌは自分が処女であると公言して活動していましたから、この点に突っ込むというものです。
本人が覚えがない、と言い張っているのに調べてみたら処女ではなかった、というのが一番都合が良い結果となります。
悪魔と交わったのだ、と断罪することができるからです。
しかし実際に身体検査をしてみたらジャンヌは確かに処女だったので、この目論見は失敗します。
裁判でジャンヌは、自分のことを「だいたい19歳」と言っています。
19歳の処女というと、現代ではあまり不自然ではありませんが、15世紀当時ではかなり異様なことでした。
この時代から300年ほど先でも、フランスの農民の平均寿命は20代半ばだったのです。
これは乳児死亡率が異様に高かったことが主因なのですが、それでも農民は30を越すとよぼよぼの老人のような外見になってしまったと記録されています。
百年戦争の時期は、さらに疫病(ペスト)の流行が重なっていますから、18世紀と比べ大幅に寿命が長かったとは考えられません。
当時の19歳は熟女とまではいかないまでも、十分「嫁き遅れ」ではありました。
貞操をあまり強く要求されない農民あがりでこの歳まで処女だったというのは、かなり異様なのです。
裁判では次に、神に対して不品行な行いがあったかどうかを確認することになります。
ジャンヌの郷里から人を呼んできて証言をさせたのですが、ジャンヌは絵に描いたように品行方正であり、こちら方面からのツッコミも失敗します。
シャルル7世は、ジャンヌを起用する前にこういった点はすべて調べて「問題なし」と判定してからオルレアンに送ってますから、当たり前と言えば当たり前ですが。
困った異端審問官は、「男装していた」ということを理由にしようとします。
当時女性用の鎧というものはなく、女性が戦場に出る場合、「男用」の鎧と鎧用の下着をつけなければなりません。
ですから「女物がないのだからしょうがないじゃないか」という言い訳が成り立ちます。
ついでに、聖書には「女は戦場に出てはいけない」とは書かれていないので、ますます異端の証拠にはしにくかったのです。
なお、男装問題は裁判の当初から焦点となっていたものではなく、他のどこをつついてもツッコミどころが見つからなかった検察側が苦し紛れに出してきたものでした。
ここで異端審問官はちょっとしたズルをします。
ジャンヌが文盲であり、書類が読めなかったのをいいことに、宣誓供述書の内容を、ジャンヌが自分は確かに異端者であったということを認めているものに書き換えたのです。
これにより書類上、ジャンヌの有罪が確定します。
自ら異端であることを認めたので、逃げも隠れもできません。
「異端の再犯者」として火炙りにされるジャンヌ
こうなるともう後は楽です。
何らかの手を使ってジャンヌに再び男物の服を着せれば、「改悛後の再犯」ということで処刑できるのです。
この仕掛けのために、教会側は牢番を使いました。
やったことは単純で、牢内のジャンヌにセクハラをさせたのです。
中世ですからジャンヌの体に触ったとかその程度で済むはずはありません。
19年守り続けた処女を奪われてしまったという記録が、複数残っています。
ジャンヌは牢番に襲われないようにするために、また男の服を身に着けました。
ある記録では、牢番がジャンヌから女物の服を取り上げ、「これを着ろ」と男物の服を投げたともされています。
いすれにしろジャンヌは男物の服を着てしまったわけで、これは「異端行為の再犯」ということになります。
ジャンヌは規定通り火刑に処せられることになりました。
この火刑の模様も、微妙に違った話がいろいろ伝えられています。
しかし、大部分の記録は「二度焼いた」としており、共通しています。
キリスト教における火刑は、遺体を灰にしてしまうことで、「最後の審判」の後の蘇りを不可能にしてしまう、という意味が込められています。
また、近世になるまで死刑は公開処刑とするのが基本でしたから、「これこの通り蘇りは不可能になった」ということを処刑を見物しに来た民衆にしっかり見せなければなりません。
このため、死んだ姿を衆目に晒し、その後完全に灰になるまで焼く、というのは教会側の理にかなっています。
ただこの二度焼きの過程の詳細が、文献によって異なっているのです。
ある説では、服が焼けた段階で一度火を弱め、ジャンヌが確かに女性であることを確認されてからまた焼いた、としています。
別の説では、黒焦げになって確かに死んでいるところまで焼き、そこから完全に灰にした、となっています。
酷いものになると黒焦げの状態で遺体を処刑台から降ろし、全身バラバラにして子宮を取り出し、それを観衆に見せてからまた焼いた、などというものもあります。
実際の火刑においては、体のあちこちが燃えるより先に、受刑者は一酸化炭素中毒または酸欠で死んでしまうようです。
「フランス」を作った少女ジャンヌ・ダルク
最初に述べたように、「百年戦争」はフランスとおおざっぱに呼ばれる土地に所領を持っていた貴族による王位争奪戦として始まりました。
決して「イングランドとフランスの戦争」ではなかったのです。
これを「イングランドとフランスの戦争」と再定義したのが、何を隠そうジャンヌでした。
百年戦争そのものは、ジャンヌの死後20年以上も続きます。
最終的に、イングランド王家は大陸の領土をすべて放棄し、イングランドだけの支配者となるのですが、それはジャンヌの戦いがもたらした結果ではありません。
ブルゴーニュ派が担いでいた王・ヘンリー6世が暗君で、統治能力をほとんど持っていなかったことが主因です。
ジャンヌの時代、ヘンリー6世は生まれたばかりの赤ん坊でした。
が、成長しても全くしゃきっとせず、イングランドでは貴族の内紛が止まらない状態になります。
この結果イングランド軍は大陸で負け続け、1451年にはボルドーが陥落します。
ボルドーはヘンリー2世がアリエノール・ダキテーヌと結婚して以来イングランド王家の所有となっていたアキテーヌ公領の中心都市です。
もうイングランド王家は、「フランスの諸侯」ではなくなってしまいました。
一般的にはジャンヌが「フランスを救った」と思われていますが、歴史的にはどう見てもそうにはなりません。
イングランドがフランスから撤退しなければならなくなる種は、ヘンリー5世が赤ん坊しか後継者に残さない状態で早死してしまった段階で撒かれていたのです。
これはジャンヌがまだドンレミ村にいた頃の話です。
ジャンヌが成し遂げたのは、せいぜい「トロワ条約の空文化のきっかけを作った」程度でしかありません。
これにしても、直接的にはシャルル7世がジャンヌの身柄と引き換えにイングランド側と交渉したためであり、ジャンヌは間接的にしか関与していません。
このように、ジャンヌは「フランスを救って」はいないのですが、それより偉大な業績を残しました。
彼女は概念としての「フランス」を作ったのです。
それまで雑多な諸侯の領地の盛り合わせでしかなかったフランスを、神と結びついたフランス王の統治する土地、と解釈しなおしました。
この考えは、ルイ14世などのブルボン王朝の王の思想に結びつき、最終的には「国民国家」の形勢に大きく寄与しました。
彼女が現代でも大きく評価されているのは、この業績が不朽のものであるためでしょう。
ただ、ジャンヌの偉大さは、彼女が生きていた当時は、「かなり変なこと」でしかありませんでした。
この文章は、そのことの一端を皆さんに理解してもらうために書かれたものです。



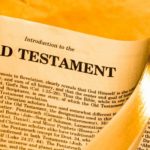




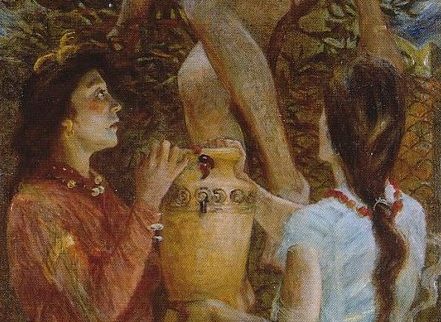

































コメントを残す