「私は、我が子にすべてを奪われるのだ」
それが、我が夫の口癖であった。
子が生まれるたび、レイアが腹を痛めて産んだ愛すべき子らはすべて夫の体内へと収まってしまう。
レイアが泣いても、懇願しても、夫はその奇行をやめようとはしなかった。
こんな男からは離れるべきだろうか、何度思ったか知れない。
それでも、レイアは彼の傍にいることを選んだのだ。
いつか、我が子に権力を奪われる。
そんな予言を受けたことは知っていた。
夫の名はクロノス。
大地と農耕の神であり、全宇宙を統べる、我々神の王である。ーー二代目の。
初代の王は、クロノスの父であるウーラノス。
クロノスは自らの父を追放し、その権力を手に入れたのだ。
因果は巡るとはよく言ったもの。
自らもいつかは、なんて恐怖におびえているらしい。
もう今にも生まれそうな腹を抱えて、レイアが訪れたのは実母であるガイアの元だ。
ガイアはクロノスの母でもあるのだが、神の間ではよくあることである。
「母さん」
ぱちり、と瞬きをひとつして、それからガイアは呆れたように溜息を吐いた。
「まったく、男っていうのはバカな生き物だねぇ。でも、今の今まで相談にも来ないおまえもバカだよ、レイア」
レイアは呼びかけただけなのに。
ガイアはどうやら、すべてを理解しているらしい。
「子供を奪われるのは辛かっただろう」
涙ながらに頷くのが精一杯だった。
「まったく、仕方のない子だこと。大人になったのに、泣いてばかりで」
言葉は厳しいけれど、レイアを見る呆れたような視線には目一杯の甘さが溶け込んでいる。
ガイアは厳しいけれど優しい母なのだ。
「無事にその子を育てたいのなら、私の言うとおりにするんだよ、レイア。そろそろ私に孫の顔を見せておくれ」
そう言ってガイアは、いたずらに笑った。
「どうすればいいの?」
泣いてばかりいたレイアの声は、情けなく震えていた。
「簡単なことよ。ーー隠せばいいの」
レイアは首を横に振った。
もうお腹は大きくなっているし、隠せる段階ではない。
ガイアだってそれはわかっているだろう。
首を振るレイアを、ガイアが笑う。
「誰が腹の子を隠せって言ったんだい。生まれてから、隠してしまえばいい」
それこそ考えてもみなかった方法で、レイアは驚いて飛び上がりそうになった。
「で、でも、クロノスは子供が生まれることを知っているのよ? 隠したって、きっと草の根をかきわけてでも探そうとするわ」
「それは私がなんとかするよ。おまえは安心して、元気な子を産みなさい」
こうしてレイアは、ガイアに促されるままにクレタ島という島に移り住み、そこで子供を産んだ。
力強い泣き声が耳を打つ。
胸に抱き寄せた我が子は、小さな体を震わせ、真白い肌を赤く染めながら大きく元気に泣いている。
ゆりかごのように体を揺らし、息子の頭を撫で、唇を寄せる。
爆発的な号泣によって平熱よりも熱くなった体が、この子は生きているのだとレイアに強く訴えてきた。
「ゼウス」
この子のために考えた名前を呼んで、頬に頬をすり寄せる。
上の子たちにだって、みんなみんな名前はあった。
助けてあげられるものなら助けてあげたいのだ。この子だけではなく。
なんて、贅沢だろうか。
「レイア」
名を呼ばれて、素直に子供をガイアに渡した。
本音を言えばずっと抱いていたいけれど、レイアがずっと抱いていたらこの子はクロノスに食われてしまうから。
ガイアはレイアの子を腕に抱いたまま、洞窟の奥へと消えていった。
食われるのも、奪われるのも、離れて暮らすのも、すべて変わらないのではないか、とレイアの中の本能が泣き叫ぶ。
生きていてくれるだけで充分だと言えない自分を嫌悪しそうになって、それでもそれが普通の反応である、と自分を納得させる。
「レイア」
その呼びかけに、自分の体が大きく跳ね上がったのを感じた。
「クロノス」
ノシノシとこちらに歩いてくるクロノスは普段どおりだ。
今から我が子を食らおうというのに、罪悪感のひとかけらすらも見つからない。
クロノスにとってはそれはあたりまえの行為であり、罪悪を感じる必要もないことなのだろう。
「生まれた子供は?」
「母さんが散歩に連れて行っているわ」
大きく舌を打たれたけれど、それだけだった。
クロノスは実母であるガイアにはそれほど強くは出られない。
「なんで母さんがいるんだよ。しかも、こんなところで産むなんて」
「母さんの勧めなの。景色が綺麗だから、落ち着くだろうって。今までの子供たちは母さんも会ったことがなかったし、孫を抱いてみたいって言われたのよ。これも親孝行でしょう?」
「そうか」
それっきり、クロノスはなにも言わなかった。
すべてをガイアに任せきったこの計画がうまくいくのかどうか、レイアにはまだわからない。
そもそも、計画の全貌すら聞かされてはいないのだ。
いつもはいないガイアがいて、いつもと場所も違う。
そんな差異にクロノスが違和感を抱いていたらどうしよう。
計画に気付かれて、やっと助けられると思ったあの子まで奪われてしまったら。
体中の血液が冷え切って、一瞬で足の方に集まってしまったかのような感覚がレイアを襲う。
「ああ、もう来たのかい」
そのタイミングで、ガイアが洞窟の方から戻ってきた。
その腕の中に赤子の姿を見て、レイアは目眩を感じた。
ああ、どうして。
今度はきっと大丈夫。そう信じていたのに。
信じ切っていたところに突きつけられた裏切りは、言葉に出来ない絶望となってレイアに襲いかかる。
「おまえたちときたら、一向に私に孫の顔も見せないんだから。まあ、私たちが予言なんかしたせいかもしれないけど」
そう。
権力を子に奪われるだろうという予言をしたのは、他でもないウーラノスとガイアだ。
「仕方ないんだ、わかっているだろう? 母さん、その子を早くこちらに」
「まあ、お待ちよ。最後に母親に抱かせてやってもいいだろう」
ガイアはそう言ってレイアの腕の中に赤子を押しつけてきた。
この子ともこれで最後なんだ。
そう思うと、涙があふれて止まらない。
ぎゅっ、と強く抱きしめてーー違和感に、目を見開いた。
不自然にならない程度にゆっくりと体を離して見た産着の中には、先程産んだ息子と同じサイズの石が入っていた。
「ほら、あんまり抱いていると情が移るだろう。こっちによこしなさい」
ガイアはなんでもないことのようにそう言って、レイアの腕から赤子を、いや、赤子サイズの石を取り上げてしまった。
赤子サイズの石はクロノスの手に渡り、クロノスは大きく口を開けて、いつものごとくその赤子を丸呑みにした。
レイアが咄嗟に取った行動は、いつものごとく泣き叫ぶことだった。
私が腹を痛めて産んだ子なのに、と泣いたって、クロノスが意に介さないことなどとうの昔から知っている。
それでも、ガイアが吐いてくれたこの大きな嘘を嘘にしないために、いつもどおりに振る舞わなければならないと強く感じたのだ。
クロノスは泣き叫ぶレイアを面倒臭そうに一瞥しただけで、なにも言わない。
それが、子供を産んだ後のいつもの流れだった。
「ウーラノスだって、おまえに権力を奪われても毎日幸せそうに生きてるっていうのに、おまえは嫌だって言うのも不思議な話だね。父さんを見てみな。権力に執着なんてしてないじゃないか。はぁ。私が孫の子育てをできるのはいつになることやら」
ガイアはそう言って肩を竦めた。
父さんは確かに幸せそうだ。
けれど、権力に執着していないのはクロノスが王座を引き継いだ際の母さん激怒、父さん去勢事件のせいで母さんに頭が上がらないからだと思う。
「俺は父さんとは違う」
少し拗ねたようなその声は、幼い子供のようだ。
レイアはクロノスに背中を向けて、その存在をシャットアウトするように座り込んだ。
我が子を食われたあと、いつもそうするように。
クロノスはレイアの行動に疑問は抱いていないようだ。
背を向けたまま、レイアは笑った。
ようやく、ようやく。生きた子供を抱きしめることができる。
成長を喜ぶことができる。
もっと早くガイアに相談していたら、もしかしたら上の子供たちも助けられたんじゃないだろうか。
そう思うとどうしたって涙があふれそうになるけれど、それはグッとこらえた。
物心ついたときには父も母もいなかった。
代わりに、ゼウスはおしゃべり好きなニュンペイたちに育てられた。
ニュンペイたちは、母であるレイアが祖母であるガイアの手を借り、ゼウスを救ってくれたという話を耳にタコができるくらい聞かされて大きくなったゼウスは、レイアのことを恨んではいなかった。
むしろ、たまに人目を忍ぶように会いに来てくれるレイアのことを好いている。
野山を駆けまわり、体も大きくなったゼウスは、ようやっと成人した。
ひさしぶりにクレタ島を訪れたレイアは、ゼウスを見て笑顔のまま涙を流した。
「本当に、大きくなったわね」
若干の居心地の悪さを感じながらも、ゼウスはレイアが泣き止むまで傍にいた。
傍にいることしかできなかったけれど、ほんのしばらくでレイアはまた元のように美しく笑ってくれるようになった。
「この子がこんなに立派に大きくなれたのはあなたたちのおかげよ。息子を守ってくれてありがとう」
そう言ってレイアに微笑みかけられたニュンペイたちは恥ずかしそうに頬を薄く染めながら、照れ隠しだろうか、プイッ、とそっぽを向いてしまう。
ゼウスに対しては口うるさい母親のようなのに、レイアに対しての態度はなんだか可愛らしいことに納得がいかないが、もう成人もしたことだし、子供っぽいことは言わないでおく。
「上の子たちも、無事に育っていてくれればいいんだけど」
寂しそうな、悲しそうなレイアの言葉に、ゼウスは首を傾げた。
「兄さんや姉さんたちは、父さんが食べてしまったんでしょう?」
こくり、とひとつ頷いてから、母さんは少し笑った。
「母さんがーー母さんの母さんが、子供たちはクロノスのお腹の中で生きているって言うのよ。神がそう簡単に死ぬわけがないって」
ゼウスの頭に浮かんだのは、気の強い祖母の顔だった。
ガイアは決して無責任な嘘を吐くような性格ではない。
むしろ、嘘を吐いたら最後、大変な目に遭わされそうだ。
「案外、嘔吐薬でも飲ませれば吐くかも、なんてーーごめんなさい、やめましょう」
そう言うと、レイアは悲しく笑った。
ゼウスはそんなレイアの笑い方が大嫌いだった。
悲しいのに、ゼウスだけでも無事だったから、とそれで納得しようとする。
母親として、ゼウスの兄や姉たちも守りたかっただろうに。
「ーーやってみようか」
「え?」
ぱちり、とレイアが目を瞬かせる。
なにを言われているのかわからない様子のレイアに、ゼウスは同じテンションでもう一度続けた。
「やってみようか、嘔吐薬」
パチパチと何度も瞬きが繰り返される。
思ってもみない言葉だったのだろう。
「でっ、でも、成功するとは限らないし」
「でも、やってみる価値はあるでしょ?」
「クロノスに勝てる保証はないわ」
「俺だってもう成人した男だよ? 老いぼれには負けないって。大丈夫」
「でも、もしもあなたが怪我でもしたら」
「心配しすぎだよ」
ゼウスはレイアの手を取って、安心させるように微笑んだ。
「ねえ、母さん。兄さんや姉さんたちが無事だったら嬉しいでしょ?」
こくり、と頷きが返される。
ならば、ゼウスのやることはひとつしかない。
「絶対大丈夫だから、安心してよ。ね?」
ゼウスは驚くレイアには目もくれず、生まれてはじめてクレタ島を飛び出した。
目指す先は、祖母であるガイアの元だ。
「そろそろ来るころだと思っていたよ。これであの子の時代も終焉を迎えるねぇ」
そう言って、ガイアはうっそりと笑った。
まるで少し喜んでいるかのようなその口調と表情が、なんだかゼウスにはひっかかりを感じさせた。
それに気付いたのだろうか、ガイアはニンマリと笑った。
「自分の権力を奪われるからって子供を次々に飲み込むだなんて、そんなバカにつける薬はないだろう?」
クスクスと笑い声をあげながら、ガイアは棚の中から小瓶を取りだした。
そしてそれをゼウスの手の中にしっかりと握らせる。
「これを飲ませれば、おまえの兄姉たちはたちまち出てくるだろう。今は兄姉だけど、生まれ直すことになるから系譜の上ではおまえの弟妹になる。これで母親と兄姉たちを救ってやりなさい」
こんなものまで用意しておいて、何故ガイアが直接手を下さないのだろうか。
そんな疑問が顔に出ていたのだろうか。
ガイアは、ふるり、と首を横に振った。
「あの子から権力を奪うのは、あの子の子供でなければならない。予言で、そう決まっているのだから」
「そんなのはおかしい。そんなバカみたいな予言のせいで、母さんはずっと辛い思いをしていた」
「いいわけをするつもりはない。だからといって、多くを語るつもりもない」
ゼウスの言葉は、そんな言葉で簡単に切って捨てられた。
悔しいことに、ゼウスは黙り込むしかなかった。
生きた年月の長さが、言葉の重みに繋がって、若輩者であるゼウスにはガイアの言葉に反抗するほどの重みのある言葉を持ってはいなかった。
「さあ、行きなさい。そして、おまえの兄姉たちを救ってくるんだ。それは、おまえにしかできないことなんだよ」
幼い子供のように、そんな言葉で使命感に駆られるということはさすがになかった。
それでも、ゼウスはまるでその言葉に思い切り背中を突き飛ばされたかのように、転がるような勢いで走り出した。
この嘔吐薬を飲ませ、兄姉たちを救い出すのだ。
そうすればきっと、レイアはもっと心からの笑顔を見せてくれるだろう。
ゼウスは躊躇いなくクロノスの眼前に躍り出た。
ゼウスを見るクロノスの目は胡乱げだ。
「見ない顔だな。名は?」
「ゼウス」
聞かれたままに答えたのだが、クロノスの反応は鈍い。
顎に手を当て、首を傾げている。
どこかで聞いた名のような気がするが、はてさて誰の名だっただろうか。
そんな風に考え込んでいることは瞭然だった。
喧嘩はきちんと名乗ってからするものだという程度の常識はあるが、名前は名乗ったのだからもういいだろう。
ゼウスは躊躇いなくクロノスに喧嘩を売った。
クロノスは多少驚きながらも、余裕綽々の態度でゼウスの売った喧嘩を買ってくれた。
いつか子供に失脚させられるという予言を信じきっているクロノスにとっては、我が子以外の誰が喧嘩を売ってきても詮無きことなのだろう。
とはいえ、ゼウスはクロノスが危惧している彼の子なわけだが、それは気付かないクロノスが悪かったのだ。
クロノスが吠えると、大地が揺れた。
ゼウスにはこれといった大きな力はない。
だから、若さに任せた捨て身の作戦に出ることにした。
ゼウスは一気に距離を詰め、クロノスの口内で小瓶を叩き割った。
ガラスの破片とともに、嘔吐薬がクロノスの体内へと流れ込んでいく。
この嘔吐薬を飲み込ませて、兄姉たちを助けられれば。
それだけで、ゼウスにとっては圧倒的な大勝利である。
「き、貴様、一体なにを……!」
最後まで言い切ることも許されず、クロノスは口許を掌で覆って、体を折り曲げ、嘔吐きはじめた。
「なにを飲ませた!」
「心配しないで、ただの嘔吐薬だよ」
クロノスの表情が苦痛に歪む。
それを心のどこかで愉快だと思っている自分がいることを、ゼウスは受け止められなかった。
自分の中にこんなにも非道な一面があっただなんて。
でも。
「母さんが、悲しんでいるんだ」
クロノスが目を見開いた。
ようやっと、ゼウスという名前が脳内で繋がったらしい。
「兄さんと姉さんを、返してよ」
クロノスは応えなかった。
それは、クロノスの口からすでに最初の兄か姉ーーいや、弟か妹の腕が一本飛び出してきたからだ。
そのまま、押さえられないのであろう嘔吐感に任せて、クロノスは一柱の神を吐き出した。
堰を切ったように、二柱、三柱と続いていく。
新たに父の口から生まれ落ちた弟妹たちは皆、抱き合って生還を喜んでいる。
「ありがとう。おまえのおかげで助かった。俺はハーデス。長男……いや、三男になるのだろうか?」
そう言って握手を求めてきたハーデスに、ゼウスも笑顔で応えた。
「ガイアは、兄さんたちは生まれ直すから系譜が逆になると言っていたよ」
「まあ、俺はどっちにしても次男だからあんまり関係がないわけだが。というわけで、次男のポセイドンだ。よろしく、ゼウス」
握手に加えて、ポセイドンはゼウスの肩を抱いてきた。
正直、こういった男兄弟らしい接触なんて今までしたことのなかったゼウスは、肩をだかれたその姿勢でしばらく硬直してしまった。
「お礼はなにがいいだろうか?」
「そうだな、ゼウスは俺たちを救ってくれたんだから」
「いらないよ、お礼なんて。俺は母さんのためにやっただけだし」
照れ隠しが多分に含まれていることには自分で気付いていた。
ハーデスとポセイドンはゼウスをからかうようにツンツンと指先でつついてくる。
兄と弟は逆転したはずなのに、なんだか遊ばれているのは気のせいだろうか。
「もう、遊んでないで。ゼウスへのお礼を考えなくちゃ……」
ハーデスとポセイドンを窘めながら、妹はチラリ、とクロノスを見た。
「かみなり……」
「雷?」
突然の突拍子のない単語に、ゼウスは思わず聞き返してしまう。
「雷はどうかしら? この世界で、最強の武器になるわ」
そう言い切ってから、妹は再びクロノスをチラリと見た。
腹を抱えて蹲っているクロノスは決して危険には見えない。
だが、嘔吐薬の効き目が切れたらどうなるかは誰にもわからない。
妹はそのあとを危惧しているのだろうと思った。
ゼウスはありがたく雷の力をもらうことにした。
このままお礼はいらないと言い続けたところで、弟妹たちが引くとは思えなかったからだ。
それに、もしかしたらそう遠くない未来で真正面からぶつかるであろうクロノスとのことを思うと、武器は多いに越したことはないと思ったのだ。
「母さんは無事なのか?」
「ああ。多分、クレタ島にまだいるんじゃないかな」
レイアも、まさかあの会話から今までの短期決戦で弟妹たちが助かったなんて思ってもみないだろう。
「母さんに会ってくれないか? とても、とても喜んでくれると思う」
ゼウスの申し出に、弟妹たちは皆一様に明るい笑顔で頷いてくれた。
善は急げ、とばかりに、ゼウスは弟妹たちを伴ってクレタ島へと急いだ。
地面に倒れ伏して、ゼウスを恨みがましい目で見ているクロノスのことなど、喜びに舞い上がったゼウスは見てもいなかった。
この戦いで、ゼウスは晴れて全宇宙を統べる神の王となったのだ。
あまりの驚きに、レイアはあふれる涙を止められなかった。
ゼウスは照れくさそうに鼻の頭を指先で掻きながら、そっぽを向いている。
その照れ方がニュンペイたちにそっくりすぎて、レイアは泣きながら笑い出しそうになってしまう。
どうやら、ニュンペイたちに大切に育てられたゼウスは、育ての親に似てしまったようだ。
子供たちを順々に抱きしめて、息子たちはその逞しい体躯に、娘たちはその柔らかな肢体に、レイアは喜ばしいとともに寂しさも感じてしまう。
ゼウスだって、その成長のすべてを見ていられたわけではない。
クロノスから離れられずに長い間クレタ島の訪問ができなくて、久方ぶりに見たら一気に大きくなっていた、なんてことはよくあった。
けれど、ここにいる息子は、娘は、本当に一切レイアの目が届かないところで、自力でここまで大きくなったのだ。
この姿を見て喜びだけを感じられるような母親は、きっとこの宇宙には存在しないだろう。
「心配をかけたね、母さん」
「ポセイドン」
名前を呼べば、しっかりとした頷きが返ってくる。
「呑み込まれる瞬間の、あなたの悲鳴がずっと耳に残っていた。こうしてまた会うことができて、本当に嬉しく思っている」
「ハーデス」
あの予言を受けたとき、すでに生まれていたハーデスは一番恐ろしい思いをしただろうに。
自我のない赤ん坊のまま誰かもわからないものに呑み込まれるよりも、僅かながら自我が芽生えたのちに父親だと認識しているものから呑み込まれる方が耐えがたい、と思ってしまうのはレイアの主観だろうか?
「あなたたちにまた会えるだなんて、思ってもみなかったから本当に幸せよ。ありがとうね、ゼウス。あなたのおかげよ」
「……俺を呑み込ませなかった、母さんのおかげだよ」
相変わらずそっぽを向いたままだけれど、それがなんだか可愛らしくてレイアは今度こそ笑ってしまった。
「あなたたちはこれから、どうするつもりなの?」
レイアの問いかけに、子供たちは一斉に視線を交わした。
そして、視線ひとつで意識を共有したらしい子供たちは、レイアをまっすぐに見た。
「クロノスに、復讐したい」
母親として、止めるのが正しいのか、背中を押すのが正しいのか。
レイアには判断がつかなかったけれど。
「そう。思い切り、やりなさい」
案外、レイアの怒りも根深いのかもしれない。
ティーターノマキアーはもう何年も続いている神々の戦争だ。
ガイアとウーラノスとの間に生まれたティタン神族と、ゼウスを中心とするオリュンポス神族とのこの戦争は、両者ともに不死の身であることから一種の停滞期に入っていた。
「おまえたちは本当に情けないね。こんなことの尻拭いまで私にさせる気かい?」
ゼウスを呼び出したガイアは、心底面倒臭そうにそう言った。
けれど、その瞳には一抹の憐憫が見て取れて、この長く続きすぎた戦争の行く末を憂いてくれていることは瞭然である。
「ヘカトンケイルの話は覚えているかい?」
ガイアの問いかけに、ゼウスは大人しく頷いた。
ウーラノスの手によって冥界よりもさらに下にあるタルタロスの領域に封じられた、ガイアとウーラノスの子供たちだ。
コットス、ブリアレオス、ギュゲスという三兄弟で、それぞれが五十の頭と百の腕を持っているという。
「あの子たちは、自分たちを幽閉したウーラノスを恨んでいる。味方になってもらえば、オリュンポスの勝利は間近になるよ」
ゼウスはその助言を聞き入れ、タルタロスの領域まで自ら出向き、ヘカトンケイルの三兄弟を解放した。
彼らはその感謝の印に、ゼウスには万物を破壊し燃やし尽くす雷霆を、ポセイドンには大海と大陸を支配する三叉の矛を、ハーデスには姿を見えなくすることのできる隠れ帽を与えてくれた。
その最強の武器と、頼りになる味方の出現に、均衡状態であった戦況は、一気にゼウス率いるオリュンポス有利に傾いた。
ポセイドンの矛の力で全地球はすさまじく揺れ動く。
姿を消したハーデスはティタン神族の武器を奪う。
そして、ゼウスは容赦なく雷霆を世界中に落とした。
そのすさまじい光に、ティタン神族たちは目を焼かれ、なにも見えない恐怖に戦いながら右往左往するしかない。
雷霆から迸る聖なる炎は地球を破壊し、全宇宙とその根源を成すカオスすらゼウスの雷火によって焼き尽くされた。
ヘカトンケイルたちはその合計三百本の腕で休みなく巨大な岩石を投げつけ続けた。
ティタン神族たちは予想以上だったオリュンポス神族の猛攻に耐えきれず、ようやく長すぎた戦いに終止符が打たれる。
戦いがはじまり、すでに十年の月日が流れていた。
休む間もなく、ゼウスたちは不死であるティタン神族たちを、ヘカトンケイルたちがいたタルタロスの領域のさらに深淵に封じ込めた。
こうして、ティーターノマキアーは今度こそその長い歴史に終止符を打ったのだった。


























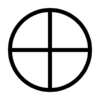















コメントを残す