かつて地球上には、恐竜と呼ばれる大きな生物が闊歩していました。この「恐竜」という名称が使われるようになったのは、1825年にイグアノドンの化石が発見されてからであると言われています。
その後、様々な発見が続き、私達が知っているような恐竜の姿が明らかになってきました。
そして旧約聖書にも、恐竜という言葉は使っていないにしても、明らかに恐竜としか考えられない大きな生物の存在が描かれているのです!
今回は現役牧師の私が、「聖書と恐竜の関連性」について紹介していきます。
Contents
旧約聖書には恐竜と思われる生物が登場する!
旧約聖書のいくつかの言葉は、他の動物とは明らかに違う巨大な生物の存在を示しています。
神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物……を創造された。
(創世記1:21)
ここで「大きな怪物」と訳されているヘブライ語は「ガドール・タニン」で、「ガドール」は「偉大な、大きな、力強い(英語ではgreat、mightyなど)」、「タニン」は「竜、大蛇、怪物」という意味がある言葉です。
竜も怪物も大蛇も、元々大きな生物で、それがさらにgreatなわけですから、これはかなり巨大な生物であることが分かります。
また、他の個所では、同じく恐竜としか思えない生物が登場します。
お前はレビヤタンを鉤にかけて引き上げ、その舌を縄で捕えて、屈服させることができるか。……誰がその顔の扉を開くことができようか。歯の周りには殺気がある。背中は盾の列、封印され、固く閉ざされている。その盾は次々と連なって、風の吹き込む透き間もない。一つの盾はその仲間に結びつき、つながりあって、決して離れない。筋肉は幾重にも重なり合い、しっかり彼を包んでびくともしない。
(ヨブ記40:25)
このレビヤタンは聖書に何回か登場する海に棲む生物で、その描写は恐竜にしか思えません。(「海の恐竜」で画像検索してみますと、「モササウルス」に近いようです)
見出し2:進化論との矛盾
これらの聖書の記述は、進化論を前提とした世界観から考えるとおとぎ話になってしまいます。
進化論においては、恐竜は約6500年前に絶滅したことになっているからです。しかし、聖書では恐竜と人間が同じ時期に存在しています。
じつは考古学的見地から考えてみますと、恐竜と人間が同時期に存在していたと考えられる発見が存在します。そのうちのいくつかを見てみましょう。
1、世界中に存在する竜の伝説
世界中の民族に古くから伝わる伝説の中には、竜が多く登場します。もちろん、それぞれの言語によって呼称は違いますが、我々が竜と呼ぶ生物に似た姿をしているのです。
また鼠、牛、虎……と続く十二干支の中に竜が出てきます。
十二干支の中で竜だけ現存しない動物、というのも不思議な話です。これは竜が伝説なのではなく、古代の人々が日常的に恐竜を目にしていた証拠ではないかと考える事もできるのです。
2、恐竜のような姿の土偶や壁画の発見
ペルーのヤモン遺跡や、アメリカユタ州レイク・パウエルの遺跡では、恐竜のような生物が描かれた壁画が見つかっています。
また、メキシコでは恐竜のような形をした土偶が出土しています。
3、哺乳類と恐竜が同時期に存在していたことを示す化石
2005年には恐竜の赤ちゃんを丸ごと飲み込んでいる哺乳類の化石や、恐竜といっしょに埋まっていたカモの化石が発見されました。
恐竜も哺乳類も、同じ時代に生きていた可能性があります。
4、比較的新しい恐竜の化石
あるテラノサウルスの骨を、顕微鏡で観察してみたそうです。すると骨の中に赤血球とヘモグロビンが見つかったのです。
科学者達は仰天してしまいました。ヘモグロビンは数千年も経つと分解されてしまうものだからです。
またアラスカでは、化石化されていない恐竜の骨が発見されました。そのうちのいくつかには、まだ靭帯が付着していたのです。
恐竜は本当に数千万年前の生き物なのでしょうか?
見出し3:実は地球がすごく若い可能性
進化論の世界観によれば、地球の年齢は約46億年前と言われています。
そして生物は段階を追って地球上に登場し、単純な生物から複雑な生物へと進化し、やがて爬虫類が地球上で覇権と握り、それが恐竜の時代である、とされています。
しかし、実はこの説を裏付ける明確な証拠があるわけではないのです。
生物が進化するには非常に長い時間が必要である、という前提が進化論にはあります。
その前提に基づいて、何十億年かかって生物が進化したはずだ、という仮説が立てられ、それが進化論としてまとめられているに過ぎません。(日本の教科書では進化論が全てであるように教えられていますが、学問の世界では、進化論は未だに仮説の一つなのです)
そしていくつかのデータは、実は地球はそこまでおじいさんではない、という可能性を示しています。
1、太陽の直径
太陽の直径は、1時間あたり180センチほど短くなっていることがわかっています。
そうなると10万年前は太陽の直径は現在の倍で、地球は人が住むことができない環境だったことがわかります。
2千万年前には太陽と地球はくっついていたことになります。
2、大気中のヘリウムの量
地球上の岩石からは少しずつヘリウムが放出されています。
もし、地球の年齢が数十億年なら、現在の大気中のヘリウムの量は実際の2000倍もの量になることになります。
3、かなりいい加減な地層
地層と地層の間には、何百万年もの隔たりがあるというのが、一般的な進化論の考え方です。
しかし、いくつもの層にまたがっている木の化石や、くじらの化石が見つかっているのです。何百万年(もしくは何千万年、何億年)も生き続けるクジラが存在するのでしょうか?
あるところでは、古いとされている地層と、新しいとされている地層が上下逆さまになっているところもあるのです。
4、曖昧な年代測定法
実は地球の年齢や、化石の年代を正確に測定することはできません。
よく使われるのは放射性年代測定法ですが、この方法でAD1800年に噴火した火山の火山岩を測定してみたところ、1億6千万年前から30億年前のものだという測定値がでたそうです。
炭素14測定法というものもあります。しかしこれも、死んだばかりのアザラシを調べてみると、1300年前に死んだという測定値がでるような曖昧なものなのです。
まとめ
このように、いくつかのデータは人間と恐竜が同じ時代に存在していても、おかしなことではない、という可能性を示唆しています。
聖書といえば神話やおとぎ話の世界だと思われがちですが、このように考古学の観点から考察してみると、なかなか面白い洞察が得られます。
聖書にはこんな言葉もあります。
神は御自分の雲を広げて、玉座を覆い隠される。原始の海の面に円を描いて、光と暗黒との境とされる。
(ヨブ記26:9、10)
主が天をその位置に備え、深淵の面に輪を描いて境界とされたとき……。
(箴言8:27)
「地球が丸い」ということは、1519年から1521年にかけて行われたマゼランの世界一周旅行によって証明されましたが、実はそのはるか昔から、聖書は地球が丸い事を語っているのです。
いかがでしょうか。世界のベストセラーである聖書は研究すれば研究するほど、私達に新しい視点を与えてくれます。
宗教の本と敬遠せずに、歴史的、考古学的資料として聖書を読んでみるのも、また一興かもしれません。




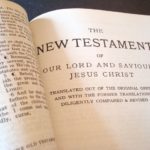





































コメントを残す