メキシコに「死者の日」(ディア デ ロス ムエルトス)と呼ばれるお祭りがあります。
ユネスコの無形文化遺産にも指定されている、世界的にも有名なお祭りです。
骸骨の扮装をして練り歩く人々の姿や、死をモチーフにしたカラフルな装飾で飾られた町などが、近年では写真や映像などで日本でも紹介されることが多くなり、なじみも深くなってきているのではないでしょうか。
映画やアニメにインスピレーションを与えることも多いようで、最近では、
- ダニエル・クレイグがジェームズ・ボンドを演じた『007 スペクター』の冒頭では、メキシコの死者の日を背景に壮大なアクションが展開される
- ディズニーのアニメ映画『リメンバー・ミー』で、まさにメキシコの死者の日が物語の背景として使われている
といったことがありました。
それにしても、世界においては「死」というものをどちらかといえば忌避する文化が多い中で、メキシコの死者の日はむしろこれを堂々と正面から描き、とても明るいお祭りとして楽しんでいるように見えます。
一体このお祭りは、どのような背景で行われているものなのでしょうか?
Contents
3,000年以上の知恵の継承:先住文明のなごりとしての「死者の日」
この「死者の日」のそもそものルーツをたどると、メキシコの先住民の文明に行き当たります。
西欧による侵略よりも以前のメキシコには、一般に「アステカ文明」という名前で知られている高度な文明が栄えていました。
現在の「死者の日」のルーツはその先住民の死生観に遡ることができます。
一説にはこの伝統は3,000年近くも遡ることができるとか!
現代社会でも華やかに行われているお祭りの背景を探ると、そこまで昔の古代文明にまで遡れるとは!
そのスケールの壮大さ、さすがは中米というところです!
生きることと死ぬことは一体のこと:死者たちと陽気にお祭りをしよう!
「死者の日」の特徴であり、かつ我々異国人を驚かせ魅了させるポイントは、「死」というものについてのそのおおらかな捉え方ではないでしょうか。
「死者の日」においては、死んだ人々が時間限定ながら生者の世界に帰ってきている、と解釈されています。
日本でも「お盆」の時期には先祖の霊が村に帰ってきているのだ、という信仰がありますよね。
お盆の間、伝統としては、お仏壇に毎日先祖様のための食事を用意したり、もてなすためのお茶を用意したりして、「あたかも目に見えない先祖霊が家の中にお客様として滞在している」かのように振る舞います。
死者の日もどこかそれに似ています。
ただし日本のお盆が「あくまでも目に見えない死者へのおごそかな尊敬」というムードであるのに対して、メキシコの死者の日の場合は、「堂々と登場する死者たちと、一緒になってパーティーをする!」というとてもポジティブなムードなのが、対照的です。
メキシコの場合、そもそも「死ぬことは人間みんなにいつかは起こること、よって生者と死者はもともと表裏一体の世界に共存している」という、おおらかでポジティブな死生観が民衆の知恵になっているようですね。
そのようなもともとおおらか生と死の境界線がいっきに取り払われてしまうのが、11月2日(※メキシコの中でも地域によって異なる場合があるようですが、一般的には)の「死者の日」。
その日には、死んだ人たちも街に帰ってきています。
生者たちも骸骨の扮装をして町に繰り出し、パーティーを行います。
それにより、生者と死者の見分けがつかない、双方が混在となっての大パーティーが始まるわけです。
「生者がおそれおおい死者をお迎えする」というような厳粛さではなく、あくまで「生者と死者が一緒にパーティーでどんちゃん騒ぎをする」という陽気さが、とてもユニークですし、なんだか教えられることも多い考え方ですよね。
死者の祭りでは実際にはどんなことをやっているの?
冒頭で述べた通り、アクション映画やディズニーアニメでもモチーフに採用されることが多くなってきた「死者の日」。
その中ではどんなことが行われているのかを、簡単に紹介しましょう!
- オフレンダと呼ばれる祭壇を事前に準備しておく
- お墓をカラフルに装飾する
- 特にマリーゴールドの花は「その香りで死者を導くことができる」と伝えられている為、祭壇やお墓をマリーゴールドで鮮やかに飾る
- 派手なペイントを施した骸骨をつくる
- 当日には骸骨の扮装やメイクで着飾る
などなど。
特にオフレンダは、各家庭において準備され、その周りで一家が団らんをすることで「先祖との一体感を高めつつ、今の家族の絆を深める」という意味合いのあるもの。
家庭というものが先祖たちに見守られながら成り立っているのだ、と考えるところについては、日本の「お盆」にも似ていて、親近感が湧くところかもしれません。
この「死者の日」は、近年では西欧の影響でハロウィーン(10月31日)と似たものに変わってきていたり、単なる若者のパーティー口実になってしまっていたり、核家族化が進んだおかげでなかなかオフレンダを用意できない家も増えてきていたりと、伝統の継承には苦労をしているようです。
ともあれこの「死者の日」は、世界中の人から、生涯に一度はぜひ訪れてみたいお祭りとみられている有名なもの。
是非今後も、3,000年もの背景を持つこの伝統をうまく現代社会の中で継続させていってほしいものです。




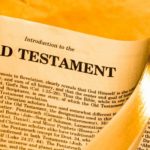





































コメントを残す