占い師がクロスの上でタロットカードをおもむろにシャッフルして、1枚ずつ並べていくのを見たことがありますか?
占いをしてもらう方は自分のために並べてもらったカードの絵しか見ることができません。
しかし、何枚かのカードを見るだけで、その不思議な絵にひきつけられてしまうことでしょう。
タロットカードはフルセットで78枚、それぞれに意味のある絵が描かれています。
それは長い歴史の中で、宗教家や魔術師たちの思いを受け継ぎ、たくさんの種類のタロットカードとなって世界中に広まっていったのです。
不思議な魅力を持つタロットカードの世界を少し覗いてみましょう。
タロットカードはどこから来たのか

タロットカードの起源はエジプトやユダヤという説もありますが、定かではありません。
12~13世紀にヨーロッパで作られたのが最古の記録で、現存する最古のカードは15世紀にイタリアで作られたものです。
セットの一部しか残っていませんが、王族・貴族が画家に描かせた豪華なカードです。
一枚一枚手描きのカードは不思議なことに現在使われているカードと内容はあまり変わっていません。
ということは、今のタロットの原型はもうこの頃にできていたということなのです。
ですが、最初は占いではなく遊戯用だったのではないかと言われています。
そのうち、宮廷お抱えの占い師がタロットカードでいろいろなことを占い、王に助言をするようになったのかもしれません。
タロットカードの不思議な構成
タロットカードは大アルカナ22枚、小アルカナ56枚の計78枚で1つのデッキになります。
大アルカナは、0~21まで「愚者」「魔術師」~「世界」とそれぞれのタイトルの絵が描かれています。
小アルカナは、ワンド(魔法の杖)・カップ(聖杯)・ソード(剣)・ペンタクル(五芒星形・コイン)の4スート(種類)、それぞれが1~10の数札と4枚の絵札(ペイジ・ナイト・クイーン・キング)で構成されます。
4種類のマークと数札・絵札といえば、トランプを思い浮かべますが、まさに、この小アルカナがトランプになったと言われているのです。
トランプはクラブ・ハート・スペード・ダイヤの4種類、絵札が3枚になって、13枚×4の52枚です。
こう見ていくと、大アルカナと小アルカナとはまったく別物に思えますが、この2種類のカードが1つのタロットカードのデッキを構成しているというのが不思議ですね。
タロットカードの不思議な絵に込められた魔術師たちの思い
今、世界中に数え切れないほどの種類のタロットカードが存在しますが、大きく分けて、2種類の系統があります。
1つはイタリアからフランスへ伝えられた伝統的な「マルセーユ版」と言われるもの、もう1つは1900年代に作られた「ウェイト版」と言われるものです。
ウェイト版の特徴は、それまで小アルカナの数札がトランプのようにマークの数だけ描かれていたものを、それぞれ意味を持つ絵に描き直したところです。
ウェイト版を作ったイギリス人「アーサー・エドワード・ウェイト」は魔法結社ゴールデンドーンのメンバーで、タロットカードの魔法色を濃くしたと言えます。
ウェイト以降はタロットカードにオカルト的なものが加味され、絵は謎めいたものが多くなったのです。
黒魔術師として名高いアレスター・クロウリーが作った「トート・タロット」は、不思議な雰囲気が漂う絵柄になっています。
魔術師たちは78枚のカードに森羅万象を重ねて、宇宙のすべてのことをタロットカードで説明できるとしています。
そして今、占い師たちは自分と波長の合うカードで占いをするようになったのですね。
まとめ
タロットカードは、単なる占いの道具ではなく、手にした者の「思い」や「気」のようなものを取り込み、不思議な力を持つと言われています。
占い師がカードを大切にしているのには、ちゃんと理由があったのですね。
カードによっては、古代エジプトの神が描かれていたり、ヘブライ文字や占星術のサイン、魔術の儀式の道具などが見られるものもあります。
その意味が全部わかったら過去も未来も見えるのかもしれません。
もし、タロットカードが手元にあったら、それは誰がどんな思いを込めたものか調べてみるのも面白いですよ。





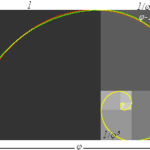




































コメントを残す