民放の地上波テレビ放送というもの、一昔前とはずいぶん位置づけも番組構成も違ってしまいました。
それでも各季節にどこかの局が、2時間くらいの特番で「怖い話」「不思議映像」特集を今でもやってくれるのが、生来の怖いもの好きとしてはたまらなく嬉しいところです!
ところで、その手の「幽霊バナシ」や「怪談バナシ」をドキドキしながらテレビで見ているとき、ふと気になったことがあります。
古代ギリシャや古代ローマの人たちも、幽霊バナシを語り合ったりしていたのでしょうか?
もし、現代人とは信仰も世界観もまるで違うはずの古代人たちも「幽霊が出た」という話を口から口に広めあって楽しむ趣味を持っていたとしたら、面白い!
そう思って、調べてみました。
Contents
紀元前ギリシャのアテネより報告あり!幽霊物件を買ってしまったアテノドロスさんの証言!
なんと、ありました!
そのまま現代日本の「怪奇現象2時間スペシャル!」みたいな番組に、再現ドラマ映像付きで登場してもおかしくないような、まとまりのあるゴーストストーリーが!
紀元前の人、ストア派哲学者のアテノドロスという方が、ギリシャのアテネで遭遇した心霊体験です。
しかも記録に残っているのは、古代ローマ帝国の書籍の中ですから、後世のオカルト好きがでっちあげた話というわけでもなく、きちんと古代ギリシャ・ローマ時代に口伝されていた実録体験談といえそうです。
その中身があまりにも「現代風」でオドロキ!
さて肝心の話の内容は、以下のようなものです。
- 哲学者アテノドロスがアテネにやってきて、家を買おうと不動産屋に相談すると、めちゃくちゃ安い屋敷があった
- 「どうしてこの物件はこんなに安いのかね?」
- 「いえね旦那、この物件はどうも幽霊が出るらしいんでさ、ですからこちらも強いてオススメはしませんがね」
- 「ふむ、幽霊とな、それはむしろ面白い!」と、勇敢なアテノドロス(なにせ「ストア派」ですから、、、)はその物件を迷わず購入した
- さて引っ越し後の最初の夜、アテノドロスが深夜まで書斎で書き物をしていると、鎖を引きずるような不気味な金属音が、だんだん近づいてきた
- やがて両腕に鎖をつけた幽霊が、書斎に入ってきた
- しかしアテノドロスは怖がりも逃げもせず書き物を続けていた
- すると幽霊は、アテノドロスに「ついてこい」といわんばかりの仕草を見せて、また歩き出した
- アテノドロスが後をつけていくと、幽霊は屋敷の外に出て、庭の真ん中のある場所に立ち、そこですうっと消えてしまった
- 翌日、市の許可を得て、幽霊が消えた場所を掘り返してみると、そこから鎖に繋がれた人骨が出てきた
- それをアテネの共同墓地にキチンと埋葬してやると、以来、もう幽霊は出てこなくなったという
なんと!
これって日本の現代怪談でも定番モノの「事故物件」系の怪談とまるで同じ構造じゃないですか!
物語の導入が「異常に安い物件を不動産屋で見つけた」となっているあたりなんて、もはや定番中の定番と言っていい。
ひょっとして「定番の幽霊バナシ」というものは古代も現代も発想は同じ!?
これはどう解釈すればよいのでしょうか?
二通り、考えられる可能性があります。
ひとつめは、「現代人も古代人も、幽霊が出てくるハナシを考えると、だいたい同じような展開のストーリーを思いつくのだ」という仮説。
もうひとつ、「現代の怪談と思っていた『幽霊物件』系のストーリーは、実は古代の世界から既にあった怪談のパターンが、世界に拡散してそれぞれの時代のシチュエーションにあわせて変化しながら生き延びてきた、寿命の長い物語なのではないか」という仮説を採ることもできるでしょう。
どちらの解釈を採っても、今後まさにテレビの「怪奇特番」なんぞで、「また『激安物件を買ったところ幽霊物件だった』っていうパターンのエピソードをやっているよ、もうマンネリだなあ!」と叫びたくなったときにも、「いや、でもこういうパターンの話は2000年以上も昔の人たちともつながっている普遍的な物語なんだよな」という感想がふいに沸き起こるようになり、「たかが定番の幽霊バナシ」についても見方が変わってくるのではないでしょうか?
もう一点の指摘:この話を報告している古代ローマの博物学者について
このアテノドロス氏の幽霊譚については、もうひとつ、面白いことを指摘できます。
先述した通り、この物語を「かつて起こった事件」として記録に残しているのは、古代ローマの博物学者です。
その人の名前はガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥス。
漫画家のヤマザキマリさんが連載している『プリニウス』という歴史学者の主人公の、甥っ子にあたる人です。
古代においては幽霊バナシも立派な「博物学」の研究対象として、動物や植物や薬学に関する報告と一緒に語られていたということになるわけで、これはこれで古代人の世界観が伺えてなんとも面白い!
アテノドロスがそんなに幽霊に対して驚いたり慌てたりしていないところも、古代人の幽霊観が見えるところとして、面白いのではないでしょうか。
もっとも、これはアテノドロスがストア派哲学者ゆえに、精神が強靭だったからということなのかもしれませんが。。。











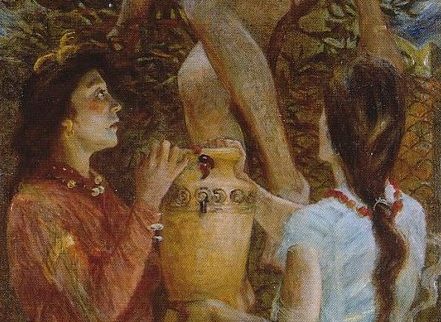






























コメントを残す