あなたは、ウィルオウィスプというものをご存知でしょうか?
英語圏ではWill-o’-the-wisp(ウィル・オー・ザ・ウィスプ)と書きます。ヨーロッパに古くから伝わる、夜の墓地や沼地に出没するナゾめいた光の玉のこと。
ふわふわ宙に浮かびながら(たいてい)青白く輝くもの、と描写されることが多いようです。
日本ではゲームのモンスターキャラという位置づけで出てくることがありますね。
私などは「ウィスプ」といえば、小さいころに夢中だった『ドルアーガの塔』というゲームを思い出します。時間切れが迫ると地図上に登場するブルーウィスプとレッドウィスプが怖くて怖くて仕方なく、夜の夢にも出るくらいだったものです(おっと、世代がバレてしまう!!)。
それはともかく……。
先ほどの説明を聞いて、ピンときた方も多いのではないでしょうか?そう、このウィルオウィスプ、日本の「鬼火」「ひとだま」「きつねび」の類とそっくりなのです!
遠く離れているはずのヨーロッパと日本との双方で、そっくりなモノの目撃情報が昔から多発しているということは、これは単なる架空の存在ではなく、実在する妖怪変化だといえるのではないでしょうか!!
世界中に現れる「鬼火系」のモノたち
……と、早合点してはいけません。
ウィルオウィスプや鬼火に限らず、「墓場や沼地にフワフワ出てくる謎の光体」伝説は、世界中にあるのです。
古今東西ひろく目撃されてきたということは、やはりこれは実在のバケモノなのではないか……?!
……と考えれば夢があるのですが、残念ながら年を食った大人はむしろこう考えてしまいます。
墓地や沼地と出現位置が特定できるのが、怪しい。つまりこれは、科学で説明できる自然現象なのでは?と。
というわけで近年、この手の「光体」の正体といえば、死者の腐敗ガスやリンが引き起こす発光現象であるという説が一般的です。
だから衛生環境や死者の埋葬技術が発達すればするほど(=近年になればなるほど)目撃情報も少なくなっているのですね。そう言われてみれば、そう説明がつきます。なんとも味気ないですが。
ですが、夢をあきらめてはいけません。
こういう科学的説明を聞いた後に付け足したい言葉は、「すべての目撃証言が、腐敗ガスやリンで説明できるわけではない」ということ。
墓場や沼地に特定されない、例外的な場所での遭遇証言もあるのですから、ひょっとしたら目撃証言の中には本物の鬼火も……!?
ウィルオウィスプといえば、イギリスとアイルランド
ところで、ウィルオウィスプはヨーロッパで広く目撃されていますが、風景として似合うのは圧倒的にイギリスやアイルランドと思いませんか?
妖怪や幽霊の話の多さでは日本にひけをとらない土地柄ですし、だいいち湖沼や森の多いイギリス・アイルランドでこそ、夜にフワフワと怪しく輝くウィルオウィスプも生き生きと元気そう。
ステレオタイプなイメージかもしれませんが、ウィルオウィスプというのは、やはり妖精やゴブリンと一緒に出てきてほしいものだと思います。
そうなると、やはり生息地として似合うのはブリテン島やアイルランド島ではないでしょうか?
あのラフカディオ・ハーンが日本の風物を翻訳するのに「ウィルオウィスプ」を援用していた!
イギリス・アイルランド出身の作家といえば、明治時代の日本に帰化して『怪談』を執筆した、小泉八雲ことラフカディオ・ハーンを思い出す人も多いのではないでしょうか?
キリスト教的な教育にどうしてもなじめず、どちらかといえば妖精や妖魔の伝承に慣れ親しんで育った彼は、日本にやってきてこの国の幽霊や妖怪の伝承を聴いて、むしろ懐かしい印象を受けたようです。言われてみれば『雪女』なんて、日本の妖怪のはずなのに、一種の悲恋物語になっているところが、どこかアイルランド妖精物語っぽいし。
そんな彼の深層心理の中には、もちろんウィルオウィスプの伝説もしっかりと刻み込まれていたようです。
「まだテレビもインターネットもない時代に、英語圏の読者に、日本で聞いた幽霊や妖怪の描写をうまく活字で説明したい!」
この課題には彼も苦労をしたと思いますが、西欧にウィルオウィスプがいてくれたおかげで、「鬼火」「ひとだま」「きつねび」の類については、説明に困ることはなかったようです。
実際にラフカディオ・ハーンの全集を紐解いていくと、もろに”Will-o’-the-wisp”という単語を使っている箇所に出会います。
ひとつ紹介すると、日本では『妖魔詩話』という題材で没後出版された詩集に、以下のような記載があります。
「日本ではウィルウィスプのことを「きつねび」と呼ぶ。なぜならば魔物と化したキツネ(goblin-fox)がこの現象を起こすとされているからだ。」
ラフカディオ・ハーンが、鬼火やきつねびのゆらめく山陰民話の情景を英語圏に伝えるときに「つまりWill-o’-the-wispのことだよ」と説明しているのが、西欧妖精と日本妖怪の数奇なめぐり会いのようで、面白い。
そして、ついでながら先ほどの「きつねび」の説明の中で、人を化かす力を得たキツネのことを「ゴブリンフォックス」という造語で呼んでいるところも、言葉の選び方としてとても親近感が持てるのでした。
グローバル化がさらに進めば、さらに「異文化間での妖怪妖精のイメージのめぐり会い」なんてことも、世界中で起こってくるのでしょうか?
そんなふうに未来を考えるのは、なかなか夢があって、楽しい想像ではないでしょうか?
などということを考えながら寝床についたところ、夜中、数十年ぶりにウィスプに追い回される夢を見てしまいました。。。




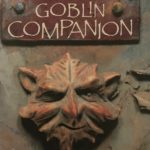







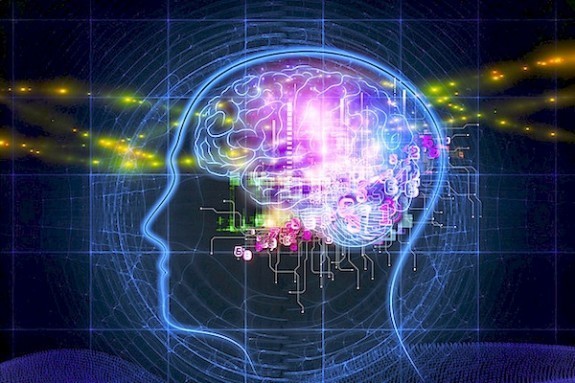




























コメントを残す