ゲーム「Fate/Grand Order」の登場人物紹介、今回は「織田信長」の関連人物紹介の5回目として「森長可(読み方:もりながよし)」のお話です。
多数の勢力が実権を巡って戦いに明け暮れていた日本の戦国時代。
そうした時代においてなお、味方にすら恐れられる文字通りのバーサーカーとして名を遺しているのがこの人物です。
戦国時代をまっすぐ駆け抜けた彼の生涯を見てみましょう。
森蘭丸の兄・長可

森長可は1558年、織田信長の家臣であった森可成(よしなり)の次男として生まれます。
父・可成も「攻めの三左」の異名を取る有能な武将でしたが、この家系で歴史的に最も有名な人物はやはり「森蘭丸」でしょう。
信長に可愛がられた小姓として知られる蘭丸はこの家の三男坊。
長可の弟になりますが、美少年のイメージの強い蘭丸に対し、兄の長可はその正反対に父の武勇を受け継ぐ立派な武将……を通り越して、その強さと粗暴さに周囲が手を焼くほどの暴れ馬でした。
しかしその見事な戦いぶりからか、彼も弟とは別の意味で信長にいたく気に入られていたようです。
彼の生まれ年は1560年「桶狭間の戦い」の2年前。
正に信長が天下へ踏み出そうとしていた波乱の中で生まれ育ちます。
戦に次ぐ戦の中、父と兄が相次いで命を落としたため次男である長可が急遽その後を継ぐ事となりました。
彼は父の城・美濃国(現在の岐阜県)の金山城の城主となります。
この時長可は齢わずか13歳。
戦国時代、戦乱の真っただ中で一つの家の長となるには幼すぎる少年にも思えます。
が、その後の彼の活躍を見ると、それは過酷な運命の始まりというよりも、願ってもいないチャンスであったと言えるかもしれません。
長可の武功
長可が森家を継いでから最初の戦いであり、彼の実力を最初に知らしめたのが「長島一向一揆」です。
三度に渡って合戦が行われたこの戦いの、最後となる1574年の戦いに長可は出陣しました。
名だたる織田家の武将たちに並んで僅か15歳程度で戦場に出た長可ですが、彼は単身川を渡って敵軍に突撃をかけ、一人で27の首を取った、という初々しい若武者とは思えないすさまじい戦果を挙げました。
ちなみにこの頃から愛用していた槍の銘が、FGOの宝具(必殺技)の名にもなっている「人間無骨」。
刀匠・和泉守兼定作の槍であり、「人体に骨など入っていないかのように簡単に砕く威力」をうたった名前です。
初陣から武功としても、荒武者ぶりとしても強烈な功績を挙げた長可。
その後もその強さで多くの戦で暴れ回り、数々の戦で戦果を挙げます。
彼が最も功績を挙げた戦いが、1582年の「甲州征伐」。
甲斐国(甲州)は名将武田信玄が率いる武田家の本拠地です。
しかしこの戦いの直前の時期に信玄が亡くなり、これを好機と見た織田家が同盟勢力と共に一気に武田家を落とそうと、その領地である甲斐国・信濃国(現在の山梨県・長野県辺り)を攻めかかったのがこの戦。
長可は信濃国の戦いにおいて、先陣を切ってその槍をふるい、武田家の城を次々と落とす活躍を見せました。
……正確には先陣を切ったというより、信長からの「前進するな」という命令を無視して単身突撃してしまったという事情もあったりしますが、ともあれ武田家の領地を削り取る事に大きく貢献したのは確かです。
特に、武田家側の要地の一つであった高遠城を落とした事が彼の大きな戦果でした。
ちなみにこの時の長可の荒くれぶりを示す逸話として、城内に単身突撃して敵を薙ぎ払って帰って来た彼の姿は返り血を浴び過ぎたあまり、当時の織田家当主である信長の子・信忠が彼の身を案じるほど真っ赤に染まっていたという話があります。
この戦の後、貢献を評価されて長可は信濃の海津城という城をもらい受け、石高20万石という織田家の中でも有数の富を与えられました。
海津城近隣には未だ武田の残存勢力などの敵は残っていましたが、これらも長可の武力をもって従わせ、この地を我が物にしていきました。
荒々しさと雅さを兼ね備える不思議な性格
このような戦場での働きぶりからも見られるように、長可は戦乱の時代の申し子ともいえる程の荒武者でした。
その強さから、信長からは武蔵坊弁慶のようだとして「鬼武蔵」とも呼ばれたと言われています。
戦場において荒れ狂う嵐のようだった彼ですが、その激しすぎる気性の犠牲になったのは敵だけでなく、身内である織田軍の兵にまで及んでいます。
その気の短さと粗暴さときたら、城門を通ろうとする彼を呼び止めた門番や、命令を無視して出撃する彼を止めようとする兵を殺して押し通ったという逸話がいくつもあるほどです。
ある話には、馬に乗って橋を渡ろうとした際、橋守に下馬を求められた事に逆上して橋守の一人を斬り、更に自分を通らせないなら火を放つと脅して引き下がらせたという恐ろしいものもあります。
(一説には「鬼武蔵」の異名は、この橋の上で門番を殺した事を弁慶になぞらえて称したとも言われています。)
このように命令違反や身内に対する暴力も多く、味方も手を焼く性格ではありましたが、信長は「長可ならば仕方なし」と彼の行動を看過していました。
実力を買っている者に対しては甘い所のあるのが信長ですが、流石に少々甘すぎの感じもします。
一方、狂戦士めいた戦いぶりと裏腹に、彼には意外と知性的な側面もあります。
領主としては、各地をおさめる配下たちと積極的な対話を行い、彼らとの結束を安定するための人質(協力を保証するため、親族を相手の領地に預ける当時の習わし)をしっかりと取り交わすなど、領土を治めるための采配はきちんと振るっていたようです。
また戦場の荒々しさとは真逆の、静謐さと儀礼が要求される書道や茶道といったものも好んでたしなみ、侘び寂びを重んじる文化人の側面もありました。
FGO内のボイスでも、「好きなもの」に茶道と書道を上げている会話がありましたね。
もっとも普段の粗暴な雰囲気のまま話の上で語るのみなので、実際彼が静かに茶をしたためる姿はちょっと想像しづらいものですが……。
その他、負傷してふせってしまった家臣の身を案じ、毎日のように見舞ったという逸話もあります。
人を人とも思わないような鬼武者ぶりを見せる一方で、このような人間味のある部分も持つ、不思議な人物です。
信長の死後に訪れた長可の危機
さて。この時代の信長の家臣として避けて通れないのが1582年の「本能寺の変」。
明智光秀により織田信長とその子織田信忠が突然討たれ、織田家家臣が大混乱に陥った事件です。
この折、長可は信濃を拠点として、越後(現在の新潟県)の上杉家に襲撃をかける最中でした。
そこに届いた信長と、信長のもとにいた弟・蘭丸らの死の報。
長可は急遽進軍をとりやめて撤退し、信長の仇を討つための軍議を開きました。
が、ここで彼を大きな危機が襲います。
それまで信長という巨大な後ろ盾があればこそ従っていたものの、長可の傍若無人ぶり耐えかねていた配下の信濃の武将達が、信長の死をきっかけに一斉に反旗を翻したのです。
一瞬で回りのすべてが敵となってしまった長可。
しかし長可ほどの武人が諦める事もなく、ここから彼自身の生き残りをかけた壮絶な戦いが幕を開けました。
初手から四面楚歌という状況を打開するため、まず長可は城内にいた人質を盾に取る事で身を守ります。
人質とは先述の通り同盟者から預けられた親族。
反逆を起こそうとした信濃の武将たちもうかつに手を出せず、長可の脱出を許してしまいます。
その際、信濃の者達の裏切りに対する報復か、あるいは単に長可の性分故か、盾にされた人質たちは皆殺しにされてしまいました。
自分を裏切った信濃の国は放棄せざるを得ず、長可は生まれ故郷である美濃の金山城に戻る事を余儀なくされました。
その途上、彼は信濃の他にも長可を敵視する勢力は多く、中でも「木曽義昌」という人物が自分の暗殺を企てている事を知ります。
長可はそれを逆手に取って義昌を利用する事を思いつきました。
事前に義昌の城へ訪問する旨の書状を送り、油断させたところで伝えた到着日のその前日、城門を破壊するという荒っぽい手段で奇襲をかけます。
当然ながら混乱に陥った義昌の城で、更に義昌の息子を人質に取る事で相手の策略を封じ、また他勢力にも長可の命を狙う事のないよう懇願させました。
そうしてひとまずの安全を手にした長可は再び美濃への旅路に戻ります。
義昌を利用した事が功を奏してか、金山城までは無事に帰還する事が叶いました。
しかしこれで安泰、という訳には行きませんでした。
信濃国と同様、故郷である美濃にすら、長可に耐え兼ねて反逆を起こす家臣が出てきました。
……色々な意味で、普段の彼の振る舞いがいかに凄まじかったかがわかる状況です。
こうした反発も持前の武力で押さえながらなんとか美濃の領地を守りつつ、その頃勢力を強めつつあった秀吉につく事で、森家の存続のため画策と戦いを続けます。
が、そう遅くない時期に長可の最期は訪れました。
彼が命を落としたのは1584年の「小牧・長久手の戦い」。
織田家の残存勢力の一つ、織田信雄率いる軍と秀吉の勢力の戦いでした。
戦そのものは長可のついた秀吉軍の勝利に終わりましたが、長可は鉄砲玉で眉間を撃ち抜かれて戦死します。享年27歳でした。
最期に願ったのは「家族の安息」
戦乱の世に生まれ、若くから戦に身を投じ、最期も戦いの真っただ中であった長可。
戦に明け暮れる人生を送って来た彼には、ある種彼らしい最期とも思えます。
その一方で、彼は自分の死にあたり、後に残される娘や弟のその後を案じる内容の遺言を遺していました。
特に末の弟であった忠政は、蘭丸ら他の弟たちが信長のもとに居たため命を落とした中、一人別の所に人質として預けられていたため難を逃れたただ一人の生き残り。
思い入れはひとしおだったのでしょう。
死ぬ瞬間までひたすらに戦い抜きながら、最期に願ったのは家族が安らかに生き延びる事。
両極端な面を併せ持つ人物ですが、そうした己に正直な生き方が長可という人物の魅力とも言えるでしょう。




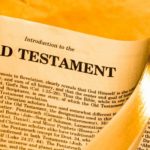




































コメントを残す