Contents
エレシュキガルの基本情報
- 名:シュメール語名「エレシュキガル」、「ニンキガル」、アッカド語名「アルラトゥ」、「イルカルラ」、「ベリリ」など
- 出典:シュメール神話(メソポタミア神話)
- 特徴:主要信仰地「クタ市」
- 関連:アン神(父 イナンナ女神と同じくエンリル神もしくはナンナ神を父とする説も)、イナンナ女神(妹)、ウトゥ(弟)、ヌンガル女神(娘)、ナムタル神(息子、冥界の宰相)グガルアンナ神(配偶神〈天の大いなる牛〉の意)、ニナズ(息子)、ゲシュティンアンナ女神(書記官)
冥界の女王エレシュキガルの概要
冥界の女王エレシュキガル誕生を語るには、シュメール神話古層の創成神話を知らねばならない。
シュメール神話には明確な宇宙開闢の観念がない。
そのため宇宙誕生の瞬間は語られず、無限の時の彼方から存在する原初の海アブズがあった、とされる。
原初の海の女神ナンムは一体となった天地を産む。
これが初期の宇宙創造に近い概念、天地が合わさった宇宙の誕生である。
ちなみに宇宙を表すシュメール語表現はan-kiである。
やがて天地の間に生まれた空の神エンリルが天地を切り離し、天神アンが天を(天界に)運び去り、エンリル神が母なる地(地球)を運び去った。
エレシュキガル女神はこの時にはアン神もしくはエンリル神の娘、そして天空神として誕生していたようだ。
分離による激動によって、地球の地殻と原始海(深淵)アブズの間に広大な空が生まれ、蛇身の竜クル(kur)となった。
クルはどさくさに紛れて幼い少女エレシュキガルを誘拐する。
そこで(さらに時代が下った紀元前三千年期のテキストにおいて)エレシュキガルを取り戻すべく深淵の水神エンキがクルと闘う。
クルは大小あらゆる種類の石で激しくエンキの船を攻撃する。
(今のところ)人類史上初の海戦の表記であり、ドラゴン殺しの神話記述である。
竜は殺害されたが、エレシュキガルはそのまま地下世界の女主人と定められた。[注1]
『ビルガメシュ神、エンキドゥと冥界』と言う物語の冒頭数行の創成神話の中で、エレシュキガルに贈り物として冥界が与えられたことになっている。
冥界はエンキ神が統治する深淵アブズのさらに下層に置かれている「kur」、あるいは「ki-gar」と呼ばれた。
エレシュキガルという名は「冥界(キガル)のエレシュ(女主人)」の意味である。
シュメール時代には深淵と冥界どちらが下層かはあまり考えられていなかった。
文明初期では冥界ははるかかなたの山のどこかにある異世界というほどの場所だった。
時代が下るにつれて地下深い最下層の世界となったが、冥界は生前の罪を裁かれる地獄ではなく、地上に生きた人間が死んで行くべきところに過ぎなかった。
天界の高位の女神として生を受けたエレシュキガルも、不活性な冥界にあって次第に性格が暗くねじくれていったとされる。
しかし二項対比を常とするシュメール文明の特徴として、反面である豊穣の地母神イナンナとの差分が開いていった結果に過ぎない。(このことは後ほど詳述する。)
エレシュキガルの説話
シュメール神話の冥界とは
メソポタミアにおいて葬送儀礼は死者の霊を冥界に送り届ける一種の移行儀礼であった。
死者は冥界で死霊(GIDIM)として生き続けると信じられていたのである。
冥界の住民は「食物を知らず、飲み物を知らず、穀物の奉納を受けず、御酒を飲まない」者と考えられた。
古くは(日の没する)西方の彼方(エレシュキガルの別名に「日没するところの女主人」がある)、更に地下深くにある冥界は「地(ki、kur ) 」あるいは「荒野(EDIN)」と呼ばれた。
シュメール神話では深淵もまた冥界同様に、地上に対する反世界として扱われる。
「深淵」は生命に活力を与え、魔を祓う崇高で湿った世界であり、「冥界」は土色に枯れた乾いて埃っぽい世界として記されている。
冥界は、やがて地上世界とは完全に隔絶された異界として「不帰の地」「一度降れば二度と帰れない世界(kur-nu-gi)」「誰も見ない覆われた地」「そこに踏み込むものが光を奪われる家」など様々な文学的表現で語られた。
不活性で暗く乾き切った陰鬱な世界。若く美しい少女神が与えられた世界は何の喜びもない世界であり、神ですら出入りの叶わない一方通行の閉鎖空間であった。(ただ一部の死と再生の豊穣神のみが移動可能であった。)
やがて生あるまま下るものを厳しく拒む鉄壁の城塞都市として冥界は完成する。
大河と七重の門に護られた冥界の詳しい構造についてはその完成を見たアッシリア神話に項を譲るとする[1]。
グレートマザーの分裂〜補完から対立へ「エレシュキガルとイナンナ」
旧石器時代に誕生した大いなる母神、万物の起源である原初の女神。
彼女は独り身でありながら婚姻を結んでおり、処女でありながら母であり、その息子は配偶者でもあり得る。
万物に惜しみなく生命を与え、残忍に奪い去る。
大地母神、豊穣の女神、死と再生を併せ持つグレートマザー……青銅器時代始めのシュメールでは、その名は「イナンナ」。
シュメール文明初期の神権政治の時代、最も崇められたのは大地母神とその眷属の女神であった。
当時は神官、農民、職人で構成され、自然と共存した農耕共同体だった。
そのころは、自然は霊的な神秘のエネルギーに溢れる神秘的な神々とされていた。
それが青銅器時代の中頃になると、豊かな収穫物を狙う異民族の侵入に対抗する戦士集団の誕生、村落から都市、都市から都市国家への移行などが起こる。
牧歌的な母系文化は荒ぶる男神と王権政治にとって変わられ、父なる神の元に創世神話が語り直される。
生と死を併せ持つ母なる豊穣の女神像は変容し、もはや二つに引き裂かれて対立し合う者としてイナンナは天上に、エレシュキガルは冥界に捉われた。
天界の高位の女神として生を受けたエレシュキガルも、不活性な冥界にあって次第に性格が暗くねじくれていったとされるが、二項対立を常とする(青銅器文明後期からの)シュメール文明の特徴として、反面である豊穣の地母神イナンナとの差分が開いていった結果に過ぎない。
二人は生の季節のイナンナ、死の季節のエレシュキガルとして、お互いを補完しあっていた。
豊穣の元に循環する死と再生の象徴。
天上の光り輝くイナンナと闇の冥界の黒き唇のエレシュキガル。
正反対の彼女たちはかつて二人で一人の死と再生の大女神であった。
『イナンナの冥界下り』の最古の形象は、おそらく一人の豊穣の女神が植物の枯死する季節に冥界に下り、新たに再生する循環神話だったのであろう。
石器時代の原初の女神が配偶神の助け無く無限に生命を生み出した時代。
冥界を出るための身代わりの配偶神など必要としない。
後代にも伝わったシュメールでの唯一母神(グレートマザー)と言えば原初の海のナンム女神であった。
配偶神なくして天地の母、神々すべての母と呼ばれたナンムはエンリル神の天地分離にあって地の下に置かれた深淵アブズとなった。
その時ナンム女神は最初の冥界神ともなったと言われる。
エレシュキガルはそのナンム女神の後を継いだことになる。
冥界女王エレシュキガルの誕生とともにナンムの役は解かれ、深淵の統治者エンキ神の母としての役割だけが取ってつけられたように与えられたのも、時代とともに消滅して行く大母神グレートマザーの運命と言えるだろう。
原初の大母神ナンムがイナンナとエレシュキガルに分かれ、役割を補完しあっていた二神が、相反するライバルへと成り下がって行く……そこには姉妹でありながら、どこまでも対立しか存在しない。
永遠に冥界を離れられないエレシュキガルの恨みと嘆きは数千年の時を堕ちていったグレートマザーの悲嘆である。
その前に飾り立てたイナンナが現れることは冒瀆であったろう。
問答無用の死の裁きは、もはや並び立つことさえ物理的にも不可能な反身の二人であってみれば当然の業であったのだ。[2]
エレシュキガルの最初の配偶神グガルアンナ
グガルアンナは、大いなる地(冥界)の女主人の最初の配偶神。
「gu gal Ann na」という名は(天、または天神アン/アヌ)の大いなる牛という意味である。
じつのところ、冥界神としての彼の記述はこれだけと言っても良い。
いつエレシュキガル女神と結ばれたのか、どんな容姿だったのか。
名が現れるのは『イナンナの冥界下り』の中で冥界の大門番ネティに答えるイナンナ女神の台詞である。
「私の姉上エレシュキガルのために、彼女の夫、主グガルアンナがお亡くなりになったとき、彼の葬儀に参列するために、私は彼への供物のビールを大いに注ぎました。まさにそうなのです。」
グガルアンナは冥界神でありながら死亡したことになるのだが、その経緯すら語られない。添え物のような冥界王であったのだ。
さらに深掘りするなら、冥界落ちしたドゥムジ神がくり返し「天の雄牛」と呼ばれていることから、天のイナンナ冥界のエレシュキガルに対応する配偶神として地上のドゥムジ冥界のグガルアンナという図式があったのではないか。
その関係は二人の女神が一人の地母神の半身ではなく、相反し完全に対立する関係となって行ったことで忘れられて行ったのかもしれない。
次に彼の名が語られるのは、ウル第三王朝時代の『ビルガメッシュ神(ギルガメッシュのシュメール語名)と天の牡牛』の一節である。
この時のグガルアンナは天神アンによって創造された青玉石の角を持つ巨大な猛牛である。
それもビルガメッシュにこっぴどくふられた愛の女神イナンナが腹いせのために父神にねだったものである。
復讐のためにビルガメッシュの統治するウルク市に放たれ、イナンナの命ずるままに破壊と死をもたらす怪物に過ぎない。
最後は怪力ビルガメッシュ王が「7グ」(210kg )もある剣斧で首を打って殺害、肉はウルクの貧しい人々に振る舞われる。
早くから天文学と占星術が発達していたシュメール文明では、ギリシャに先立って星座の知識が存在していた。
シュメール時代(前2900〜前2350年)の記録にグガルアンナが牡牛座(金牛宮)として登場している。
一等星アルデバラン、プレアデス星団を構成に含むことから星座の構成も同じで、ギリシャ・ローマの星座表がシュメール時代からの移入であったと確認されている。
冥界で死に、天上で生まれ変わり、地上を蹂躙する大暴れの後、彼は今に至るも天上の星座として存続しているのである。[3]
脚注
注釈
- [1]:クルを殺害する神話は後代に二つあり、一つめの主人公はエンリルの息子ニンウルタ、もう一つはエレシュキガルの妹イナンナ女神である。この時のクルは本来の名前の意味「山」の魔物として現れる。
出典
- 杉 勇、尾崎享「シュメール神話集成』ちくま学芸文庫
参考文献、URL
- MYTHS OF KUR
- 創世神話の系譜 : 古代メソポタミアの資料から(1)
- 古代メソポタミアにおける死生観と死者儀礼
- [1]月本昭男『古代メソポタミアの神話と儀礼』岩波書店
- [2]アン・ベアリング、ジュールズ・キャッシュフォード『図説世界女神大全 1原初の女神からギリシャ神話まで』原書房
※ライター:紫堂 銀紗



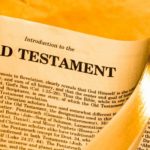

































コメントを残す