妖怪と聞いて、どんなものを思い浮かべるでしょうか?
水木しげる氏の「ゲゲゲの鬼太郎」?
それとも人気ゲームの「妖怪ウォッチ」でしょうか。
重要文化財にもなっている、真珠庵所蔵の「百鬼夜行図」かもしれませんね。
このような作品に登場する妖怪たちは、それぞれ奇怪な姿形をしていますが、どこか可愛らしく、ユーモラスな印象を与えるものが多いでしょう。
ところが、妖怪にも色々なタイプがいます。
可愛らしいものもいれば、恐ろしい妖怪もいるのです。
中には出会っただけで死んでしまう、というものも。
ここではあえて、そんな危険な妖怪をご紹介していきたいと思います。
牛鬼 ~出会ったら最後!襲って食い殺す~

西日本に伝わる「牛鬼」は、「出会ったら死ぬ系」の妖怪の中ではメジャーな部類ではないでしょうか。
牛鬼は海岸に現れることが多く、人間を襲って食い殺すと言われています。
蜘蛛のような胴体に、牛のような顔を持つ姿で描かれることが多いでしょう。
この牛鬼には、人を食い殺すと言われるほか、出会っただけで病気になるとか、影を嘗められると死んでしまう、などといった伝承があります。
牛鬼は普通に襲いかかってくるだけでなく、次のような罠をしかけてくるパターンもあります。
赤ん坊を抱いた女に呼び止められ、「赤ちゃんを抱いていてほしい」と頼まれます。
ところが赤ん坊を抱いていると、その赤ん坊がどんどん重くなって手から離れなくなり、動けなくなっているところを牛鬼に食べられてしまう、というものです。
牛鬼に襲われながらも、運よく助かった…という話もありますが、基本的には逃げることが難しく、出会っただけで死んだり、病気になったりすると言われることが多いようです。
できれば一生会わずに済ませたい妖怪のひとつですね。
朱の盆 ~それはこんな化け物でしたか?~

寛保(かんぽう)の時代に作られた、会津地方などの伝承を集めた「老媼茶話(ろうおうさわ)」に、朱の盆(しゅのぼん、本来の名称は「しゅのばん」)という妖怪の話が紹介されています。
この妖怪もまた、「出会ったら死ぬ」系統の化け物のように思われます。
奥州会津の諏訪の宮に、朱の盆という化け物がいると言われていました。
ある日の夕方、若い侍がこの宮の前を通りかかりました。
するとそこに、ちょうど同じくらいの年の侍がやってきます。
二人は道連れになり、話しながら歩いていきました。
話している最中、侍はふと、かねてから聞いていた化け物の噂を思い出しました。
そこで、「この辺りには朱の盆という化け物が出るそうですが、ご存じですか?」と尋ねてみました。
すると、後から来た侍が、「それはこんな化け物でしょうか」と言うなり、突然恐ろしい怪物の姿に変貌したのです。
顔は朱く、額からは角が生え、何とも恐ろしい見た目をしています。
その姿を見て、恐怖のあまり侍は気を失ってしまいました。
しばらくして気が付いてみると、彼は未だ諏訪の宮の前にいました。
歩いてやっとのことで一軒の家にたどり着くと、その家の人らしき女性が出て来ました。
「水を一杯いただけませんか」侍が頼むと、女性は「どうかなさったのですか?」と尋ねてきました。
そこで侍は女性に、朱の盆に出会った話をしました。
すると彼女は、「それは恐ろしい思いをなさいましたね。ところでその朱の盆とは、こんな化け物でしたか」
侍が見ると、今度は女性の顔が、さっきの朱の盆の顔に変わっているではありませんか。
またしても恐怖のあまり、彼はその場に気絶してしまいました。
そしてしばらくして目を覚ましましたが、それから百日後に死んだといいます。
一体どうすれば若侍は助かったのか…
やはり朱の盆に出会った時点で、運命は決まっていたのでしょうか?
ところでこの話を聞いて、小泉八雲の『むじな』という話を思い出したという人も多いでしょう。
一度怪異が去ったと見せかけて安心させ、「こんな顔だったかね?」ともう一度畳みかけるというパターンは、いくつもの怪談に採用されているようです。
なお、『老媼茶話』より古い『諸国百物語』にも同様の話が納められていますが、こちらでは化け物の名前が「首番」となっているようです。
殺生石 ~温泉地では要注意!?~

原典:663highland
栃木県の那須湯本温泉付近にある殺生石は、鳥や獣が近づくと死んでしまうと言われる恐ろしい石です。
殺生石は、九尾の狐に関するエピソードで知られています。
白面金毛九尾の妖狐が化けた「玉藻の前」という美女が、正体を現して退治され、この殺生石になったと言われています。
近づいただけで死ぬ、と言われるだけあって、これも物騒なものですが、牛鬼のように襲いかかってこないだけマシかもしれません。
もっともこの殺生石、実際に温泉地にあるだけあって、付近には硫化水素などの有毒な火山ガスが噴出するとか。
「近づくだけで死ぬ」というのもあながち根拠のない話ではなく、それだけによりシャレにならない…という見方もできそうです。
まとめ
「出会ったら死ぬ」系の妖怪譚、いかがでしたか?
悪いことをして罰されるならともかく、出会っただけで死ぬとは、恐ろしいだけでなく、理不尽で腹立たしいような気さえしてきます。
しかし可愛さ・親しみやすさだけでなく、恐ろしさ・理屈の通じなさも妖怪の魅力のひとつ。
奇妙な話に不可欠なスパイスと言えるでしょう。




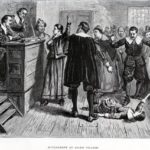


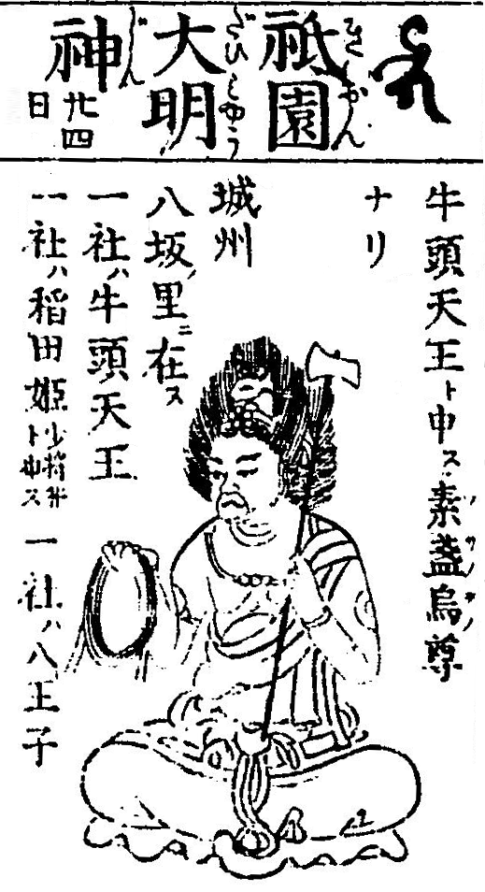


































コメントを残す