前回までで『プリニウスの博物誌』に溢れる空想や奇想の話を追ってきましたが、今度はプリニウスの「宇宙」像を追っていきましょう。
これほどの情熱をもって世界中の動植物や鉱物の情報を(アヤしい情報も含めて)大量にコレクションしていたプリニウスという人物は、宇宙とか、地球とか、そして現世と来世との違いとかについては、どのような信仰を持っていたのでしょうか?
そのテーマを追うと、プリニウス先生はかなり含蓄の「深い」宇宙論を持っていたことがわかってきます。
この人は決して怪獣話を列記するいい加減なオッサンではなく(笑)、さすがは古代ローマの文人、「宇宙」とか「生命」とか「神」とかいった哲学的なテーマを語らせると、壮大かつ深遠な相貌を見せてくれる懐の深い哲人気質であることが、わかってくるかと思います!
プリニウスを「ストア派の哲学者」として分類してみると、見えてくる新しい相貌

これも諸説の中のあくまで一説ですが、プリニウスは「ストア派の哲学者」として分類されることがあるようです。
「自然」というものは大いなる力がある圧倒的な存在であると認め、その仕組みを謙虚に理解することだけに努め、そうやって理解した自然の摂理に従って生きることが正しい人間の道であると考えるのが、ストア派哲学の考え方です。
なるほど、プリニウスはこの道をまさに貫いた人と言えるでしょう。
彼があれほどの情熱をもって自然界を細かく調べ上げていたことについても、自然を支配してやろうという発想ではなく、「自然の神秘を理解しそれに逆らわない謙虚な生き方を見つけ出そう」という企図が感じられます。
たしかにプリニウス先生の文章には、たとえ大自然のもたらす災禍についての記述になっても、楽天的とか悲観的とかを超えた、どこか「悟った」ような境地を感じることがあります。
やさしさと厳しさが一体となっている自然観と言いますか。
このあたりは、仏教や神道の考え方に似ている部分もあり、日本人にも共感しやすいところがあるのではないでしょうか?
プリニウスが見ていた宇宙像と人間像
そのプリニウスが「宇宙」全体をどうとらえていたかは、『博物誌』の第二巻においてかなり細かく展開されています。
「宇宙は、それ自体がひとつの神である。永遠にして無限である。存在し始めたこともなければ崩れ去ることもない存在、と信ずるのが適切である」
「宇宙の外側には何があるのか、などという問いは、人間に無縁なものであり、それを解明することは人間精神の理解力を越えているのだ」
「この宇宙の外部へ出て行きたいとか、外部になにがあるかを調査したい、などということは、純然たる狂気の所業である」
プリニウス先生が前提としている宇宙観は、「宇宙は球体であり、地球を中心に二十四時間で一回転自転するプラネタリウムのような機械状のものである」という古代ローマの発想に基づいているので(いわゆる天動説ですね)、ここでプリニウスが言っている「宇宙の内側と外側」とかいう話はすでに現代人の宇宙物理学とはかみ合わないのですが、
そういう時代の限界には目をつぶってプリニウス先生の論理を追ってみると、なかなかハッとさせられる名文の連続ではないでしょうか。
宇宙の内側について調べつくすことが人間知性に必要なことであって、宇宙の外側はどうなっているのかを見たいなどというのは無用のことという警句の響きには、現代人である我々も思わず襟を正してしまいます。
意外な世界観! プリニウス先生の世界には奇跡は起こらない?!

あれほどモンスターや不思議伝説に満ち溢れている『博物誌』を著した人だというのに、プリニウスが説明する宇宙というものはきわめて論理的で、奇跡が入り込むスキマがありません。
言われてみれば、プリニウスが考えるモンスターたちも、現実に存在する動物の特徴を拡大したり、現実に存在する動物を奇形的に改造したりして生み出されている産物で、とても論理的です。
モンスター達ですらも、あくまでも自然が生み出す神秘の結果として解釈されていて、神や悪魔のような「宇宙の外のパワー」が入りこむ余地は用意されていないようです。
では、プリニウスにとっての「神」とはなんなのでしょうか?
『博物誌』の中に、まさに「神について」という章が入っているので、そこを参照してみましょう。
「ひ弱で苦労している人間が、その弱さを自覚し、そういう神々をいくつかの群に分類し、部門々々でめいめいが自分にもっとも必要とする神を崇拝した。
したがっていろいろな民族が自分たちの神々にいろいろな名をつけている」
「神々自身の間に姦通が行われ、その結果激論や怨恨が生じたとか、窃盗・悪事を働く神々があるなどということを考え出すとは、厚顔無恥も度が過ぎているというものだ」
なんと少なくとも人間界で信仰されている神様などというものはたいていがツクリバナシだ、と言ってしまっています。
少なくとも、神様が人間にいけにえを要求したり、祟りを及ぼしたりするという発想は、誤りであると。
では結局、「神」というのは何なのか?
プリニウス先生の説明は、以下の通り。
- この自然そのものが神であり、それを超えるものではない。
- たとえば「神はなんでもできる」と言うが、神様は自殺ができないはずである(着眼が面白いですねえ、、、!)
- それに神も人間に永遠の命を与えることはできないし、死者をよみがえらせることもできない
- 神といえども10×2の答えを20以外にすることはできない(これも着眼が面白いですねえ、、、!)
そしてプリニウスが付け足すところによると、この世界で真に奇跡的なのは、神の力などではなく、人間たちの「努力」のほうだ、というのです。
「人間が人間を助けること、これが神であり、これが永遠の栄光への道だ」
古代ローマという時代でこのような考え方が力強く表明されていたのは感動的ですし、最終回で触れますが、このような主張を強く打ち出したプリニウスが、けっきょくは火山の調査のためにその命を落としてしまったというのは、さらに感動的な話であります。
というわけで、次回はこのシリーズの最終回、プリニウス先生の死について触れ、あわせてプリニウス先生が死後の世界や霊魂についてはどう考えていたのかを追ってみましょう。



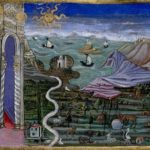





































コメントを残す