みなさんは「見てはいけないタブー」をご存知ですか?
「振り返ってはいけない」「見てはいけない」と言われてついつい見てしまう、そんな昔話やストーリーを一度は見たことがあるのではないでしょうか。
本稿では、その中でも神話に登場する「見てはいけないタブー」について紹介し、その魅力に迫ります!
Contents
見てはいけないタブーとは?
神話にみられるモチーフの一つとして、「振り返ってはいけない」「見てはいけない」というタブーがあります。
いつの世も、禁じられるほどにその魅力に負けてしまうのが人の常。そしてそれは、人間だけではなく、神々も同じであったようです。
旧約聖書、ギリシャ神話、古事記、さらには現代にいたるまで、古今東西さまざまな神話に登場する「見てはいけないタブー」を読み解くことで、場所や時代を超えて共通する神様や人々の姿をみつめてみませんか?
旧約聖書にはどんな「見てはいけないタブー」のエピソードがあるの?
旧約聖書では、2つの有名なエピソードが「見てはいけないタブー」と密接に関わっています。
ノアとハム親子~カナンへの呪い~

ノアといえば、ノアの箱舟。
かの有名な洪水のその後の話です。
ある日、ノアは葡萄酒を飲んで酔っ払い、裸で寝てしまいます。
ノアの息子のハムは父が裸になった姿を見てしまい、兄弟のヤムとヤフェトに知らせますが、彼ら2人は父の姿は見まいと父の裸身を着物で覆ってあげるのです。
これにより、ノアは唯一裸を見たハムに怒り、その息子(つまり自分の孫!)であるカナンに対し「カナンは呪われよ」と発言します。
突っ込みどころ満載の、理不尽で勝手な話のようですが、裸をさらすということはとても不名誉なことであり、なかにはこれを男色の暗喩だと裏読みする人もいます。
漫画『聖おにいさん』では、ノアの激しい言葉遣いに驚いたブッダに対し、イエスが「あっ、びっくりしたよねごめん!旧約聖書の人はちょっと怒りっぽいとこあって・・・!」(11巻)と弁解するシーンがありますが、これもカナンを呪うノアのエピソードを知っていれば、納得の発言です。
ソドムとゴモラ~振り返ったら塩の柱~

創世記に、ソドムとゴモラという二つの町が登場します。
神の怒りに触れて滅ぼされたこの町は、キリスト教圏では退廃的な都市の代名詞としても知られています。
狭心、性的堕落、男色などで堕落した町に神は硫黄の火を降らせ、ソドムとゴモラは滅ぼされることになります。
ソドムに住むロト一家は命からがら逃げだしますが、神は「逃げる途中、決して後ろを振り返ってはいけない」と告げます。
しかし、過去への執着を捨て切れないロトの妻はつい後ろを振り返ってしまい、塩の柱となってしまうのです。
なぜ塩なのでしょう?
死海が近くにあること、清めの意味、過去に固執し凝り固まった象徴・・と複数の解釈がなされています。
ちなみに、映画「Hedwig and the Angly Inch」に、「Wicked Little Town(邪悪な町)」という劇中歌があります。
そこで、同性愛者である主人公Hedwigは歌います。
Remember Mrs.Lot and when she turned around
(忘れるな、ロト夫人が振り返って塩の柱になってしまったことを)
訳詩カードにある「塩の柱」の意味は、旧約聖書のこのエピソードを知らないとなかなかたどり着けません。
幼いころから聖書に触れている西洋人は、こうした引用や示唆に対する理解度の土壌がしっかり出来ているんだろうな・・とうらやましく感じますね。
ギリシャ神話にはどんな「見てはいけないタブー」のエピソードがあるの?
ギリシャ神話にも、見てはいけないタブーをモチーフとするエピソードは多く存在します。
ここでは、代表的な3つの神話をご紹介します。
パンドラの箱~開けたらこの世の災いが!~

神様の中の神様・ゼウスは、人間たちが知恵をつけることを良しと思わず、地上にパンドラという一人の美しい女性を送り込みます。
ゼウスは「この箱の中には贈り物をいっぱいにつめておいたが、絶対に開けてはいけないよ」と言ってパンドラに託しますが、地上に舞い降りたパンドラは、人間との生活に慣れるにつれ、我慢できず箱を開けてしまいます。
すると、その中からは憎しみ、裏切り、嫉妬、争い、災害、病気、悲しみ・・といったこの世の災いが一瞬にして飛び出していきます。
慌ててパンドラが箱を閉じたときには、箱の中には「希望」だけが残っており、人間たちはこの後、あらゆる災いの中でも希望だけは失わずに生きていくこととなった・・というのが、かの有名なパンドラの箱の逸話です。
見るな、開けるなと言われれば言われるほど気になるもの。
また、ロトの妻がそうしたように、禁戒を破ってしまうのは女であるということから、女性が災いをもたらす存在であるという描かれ方がここでもなされています。
プシュケーとエロース~旦那の顔を見てはいけない!?~

美しい娘、プシュケーは、夫に「決して私の顔を見てはいけない」と言われていたのも関わらず、姉たちに「あんたの夫、大蛇なんじゃないの?」とそそのかされ、眠った夫にランプを照らしてその顔を見てしまいます。
そこにいた夫は見るも麗しい愛の神エロースだったのですが、愛する夫を信じなかった罰として、夫エロースはプシュケーのもとから離れて行ってしまうのです。
オルフェウスと妻~妻を生き返らせたくば、振り返るな!?~

ギリシャ神話における吟遊詩人、オルフェウス。
彼の妻・エウリディケは、毒蛇に噛まれて死んでしまいます。
悲しみにくれたオルフェウスは冥界へ行き、妻を返すよう頼み込みますが、これに対し、冥界の王ハデスは「地上に着くまで、決して振り返ってはいけない」と条件を出します。
結局オルフェウスはあと少しのところで振り返ってしまい、妻は悲しみの表情を浮かべて再び冥界へと戻されてしまうのでした。
古事記にはどんな「見てはいけないタブー」のエピソードがあるの?
我らが日本神話の古事記の中でも、見てはいけないタブーは多く描かれます。
ここでは、代表的な2つのエピソードを見ていきましょう。
イザナキとイザナミ~黄泉の国に行った妻は変わり果てた姿で・・~
イザナキ(夫)とイザナミ(妻)の夫婦は二人で日本を創造していましたが、火の神を生んだことからイザナミは火傷を負って死んでしまいます。
悲しみにくれたイナザキは妻を追って黄泉の国へと追いかけます。
すでに黄泉の国の食べ物を食べてしまったイザナミは、「すぐには帰れないけど神様に頼んでみるから、そこで待っていて。ただしその間、決して私の姿は見ないでね」と夫に伝えます。
待ち続けたイザナキが辛抱たまらず黄泉の国の扉を開けてしまうと、そこには全身が腐敗し雷神が乗り移った、変り果ててしまった妻の姿がありました。
この話は、ギリシャ神話の「冥界に妻を追いかけたオルフェウスの話」と酷似していますが、このあとイザナミは変わり果てた姿でイザナキを追いまわし、派手な夫婦喧嘩をしています。
ギリシャ神話と対比すると、日本神話の大胆さが感じられ、興味深いですね。
トヨタマビメと山幸彦~立ち合い出産禁止!?~
「出産する姿を見ないでください」とトヨタマビメに言われたのにもかかわらず、のぞき見てしまった山幸彦。
産屋の中ではサメに姿を変えた姫が子を産んでおり、この姿を見られたことが原因で、トヨタマビメは海に帰ってしまいます。
ちなみに、この時生まれた子の4人目の子供が、初代天皇である神武天皇です。
神話と歴史がひと続きとなっている不思議な国・日本。
こうして、おとぎ話のような神話の世界から、現代へとつながっていきます。
現代ではどんな「見てはいけないタブー」のエピソードがあるの?
さて、私たちを取り巻く現代でも、古代と変わらず、いたるところに見てはいけないタブーは隠されています。
現代の心理学では?~カリギュラ効果~
‘禁止されるほどやってみたくなる’、そんなあるある現象を、心理学的には「カリギュラ効果」と呼びます。
最近(2019年現在)では、Amazonプライムビデオで『今田×東野のカリギュラ』という番組が放送されており、聞いたことのある方も多いのではないでしょうか?
この番組は、地上波では取り上げられない、危険でありながら見てみたい・・そんな企画を放送する番組のようです。
さて、そんなカリギュラの語源ですが、
かつて、ピューリタンによって建設された保守的なボストンの町では、性的描写や汚らしい表現は禁止されていました。
1980年(わりと最近!)公開のローマ皇帝カリグラを描いた映画「カリグラ」は、その過激な内容から、ボストンなどの一部地域で公開禁止になりました。
しかし、それがかえって世間の興味を惹き、アメリカには「ボストンでは禁止(Banned in Boston)」なる慣用句まで生まれました。
新作映画に「ボストンでは禁止!」と煽り文句をつければ、その映画がどれほどエロチックで暴力的なのかを観客に想像させることができるのです。
受け手側の知識が求められる、なかなかおしゃれなキャッチコピーですよね。
千と千尋の神隠しにおけるタブー
日本歴代興行収入1位であるスタジオジブリ作品「千と千尋の神隠し」でも、この禁忌は重要な意味を持って描かれています。
物語の終わりに、ハクは千尋にこう告げます。
「決して振り返ってはいけないよ」と。
誘惑に負けて千尋が振り返っていたら、おそらくそこに優しいハクの姿はないでしょうし、千尋が両親と現代の世界に戻ることはできなかったでしょう。
この作品は、様々な姿かたちをした八百万の神様たちが住む世界が舞台であることからも、多くの神話や民話で描かれている「見てはいけないタブー」を表現していることは想像に難くありません。
私たちの身の回りにも・・~携帯・ドリフ・ダチョウ倶楽部!?~
「見てはいけない、見てもいいことなんかひとつもない・・」そう知っておきながら、彼氏彼女の携帯を覗いてしまう男女たち。
はるか古代から「見るな」と数々の神話が教えてくれているのにもかかわらず、人々はいまだに間違いをおかすのです。
ひとつ、現代にだけ見られる、楽しい「見てはいけないタブー」の逆転現象があります。
それは、ドリフにおける「志村―!うしろうしろ!」であり、ダチョウ倶楽部における「押すなよ?絶対に押すなよ?」の法則です。
悲しい結果につながる「見てはいけないタブー」ですが、現代ではなんとも楽しい形式美と姿を変えて、私たちを楽しませてくれています。
まとめ
いかがでしたか?
時代も場所も越えて存在する「見るなのタブー」を知ることによって、古代から現代にいたるまで、人間も神様も根本は変わらないのだということがわかります。
また、その不変的な側面があるからこそ、何千年何万年もの悠久の時を超えていまなお神話は私たちを魅了してくれるのかもしれません。





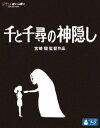


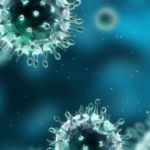






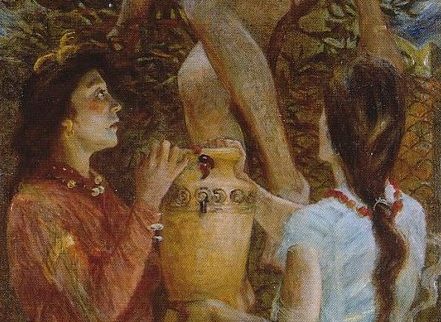






























コメントを残す