よほどの日本史通でなければ知らない名前かもしれませんが、奈良時代、東大寺の大仏建立で有名な聖武天皇の治世の頃に、玄昉(げんぼう)という名前の僧侶がおりました。
中国から貴重な仏典を輸入したり、聖武帝の信任を得て政治の場でも活躍したりと、この人の経歴はなんとも華麗です。
個人的には、かの空海や最澄にも並ぶような日本仏教への貢献者として扱われていてもおかしくないような人物と思います。
この人については、そのお墓が一種奇妙なことになっています。
福岡県に正式なお墓が今でも残っているのですが、それとは別に、奈良県に「玄昉の頭だけ」が飛んできたと伝えられる、「頭塔」なる首塚があるのです。
首と胴体が別の場所でお墓になっている?!
いったい、何があったのでしょうか?!
経歴は華麗そのもの!僧侶玄昉の史実の事績
まずは史実の整理から。
玄昉の生年は不詳ですが、世代としては吉備真備や橘諸兄と同じ時代、八世紀に活躍した人物となります。
かの阿倍仲麻呂と同じ時期に遣唐使として中国にわたり、楊貴妃との恋で有名な玄宗皇帝に評価されて、結局は十八年間も唐にとどまりました。
そして帰国した際には大量の仏典と仏像を持ち帰りました。
書籍が何よりも貴重だったこの時代、中国の最先端の仏教書を見定めて購入し持ち帰ったというだけでも、仏教界への貢献度は多大だったはずです(本人が中国語に堪能でかつ仏教史にも相当詳しくなければ、そもそも書籍の価値の目利きもできませんし、どの文献が日本に必要でどれが不要かの判断もつかなかったはず、とても大事な役目だったはずです)。
帰国の彼の活躍は、以下のようになります。
- 皇族の病気を祈祷で治し、それによって聖武天皇に目をかけられ、吉備真備と一緒に重用されるようになる。
- 仏教界と朝廷政治をつなぐ役割の高僧として栄華を極める。
- 晩年は藤原氏と橘氏の政権争いに巻き込まれて失脚し、左遷されて九州太宰府に赴任、そこで没した
- 現代でも、法相宗では教派の中興の祖としてたいへん尊敬されている。
こうしてみると、晩年に左遷という憂き目を食ったものの、基本的には仏教僧としては最高の出世コースを歩んだと言えそうです。
事跡としても、優秀な学者肌の人物のようで、特に暗い点は見当たりません。
日本史を代表する怨霊の一人、藤原広嗣とかかわったことが後世の伝説化の背景!
このような人物が、どうして「胴体と首がばらばらにちぎられた」という凄惨な伝説の基となってしまったのかというと、時の権力闘争が背景にあります。
吉備真備と玄昉は、橘氏の派閥の重要人物であり、敵対する藤原氏からは常に嫉妬と警戒の目で見られていました。
ついに西暦740年、橘氏中心になっていた中央の政治に不満をもっていた藤原広嗣が、九州で大規模な反乱を起こします。
決起に際しての上奏文では、「吉備真備と玄昉を政治の要職から除くこと」が条件となっていたとされますから、直接的にこの二名をターゲットにしたクーデター目的の反乱であったとされています。
この反乱は朝廷に大きな動揺を与え、聖武天皇も討伐の指示を出した後は、伊勢神宮を筆頭に各地に行幸に出かけてしまい、なるべく「関わり合いになりたくない」という態度を貫きました(あるいは、既に藤原広嗣の怨霊化を恐れていて、所在を始終変えながら神仏の加護を乞い続けることで呪力から逃れようとしていたのだ、という解釈もあります)。
藤原広嗣の乱はやがて武力で鎮圧され、関係者は死罪となります。
ですが、これはとにかく「怨霊信仰」の強かった時代の話、ましてや特にその手の「怨霊」「鎮魂」といったキーワードを気にする聖武天皇が政治のトップだった時代です。
乱が鎮圧された後は、その藤原広嗣の怨霊化を警戒して、さまざまな鎮魂の催しや、神社仏閣が建立され、そのムードの中で藤原広嗣のターゲットであった吉備真備や玄昉もどんどん居心地の悪い思いをするようになったのでした。
やがて藤原氏が勢力を盛り返すと、まさに報復人事として、玄昉は九州の太宰府に左遷されてしまいます。
九州といえば、先ほどの藤原広嗣が反乱の拠点に据えた場所。
当然、藤原広嗣びいきな人もたくさん残っている土地だったはずです。
そこで玄昉は謎の暴漢に襲われて負傷し、それがもとで亡くなってしまうという、不幸な最期を遂げたのでした。
ところが話がそれで終わらなかったのは、後世になって「藤原広嗣の怨霊」という伝説が一挙にブームになってしまったのです。
藤原広嗣の怨霊による壮絶なバラバラ殺人!
吉備真備や玄昉の失脚とその死は、世間ではいつのまにか「藤原広嗣の怨霊によるたたりであった」という解釈がされるようになりました。
この「解釈」は後世になるほどエスカレートしていき、『今昔物語』や『平家物語』にも「怨霊に殺された玄昉」として言及されるようになるなど、知識層や公職の人の間でも「常識」化してしまっていったようです。
その怨霊伝説によると、
「晩年の住まいであった九州にて、玄昉が読経をしている際、空がどんよりと曇って、そこから黒い雲が手のように伸びて玄昉をつかまえ、空へとさらって行ってしまった。
死体として、その胴体のみがその場にどさっと残されたものの、首だけがどうしても見つからない。
それから一か月ほどした時、遠い奈良の興福寺にて、やはり暗雲が空に渦巻き、そこからけたたましい笑い声がしたかと思うと、玄昉の首だけがどさりと落ちてきた」
という次第。
なんともすさまじい話です。
そして実際に、現在でも福岡県の太宰府市には「僧正玄昉の墓」がちゃんと残っておりますが(観光で訪れることも可能です)、いっぽうで奈良県奈良市には「頭塔」なる、玄昉の首塚とされる史跡が存在しています(こちらも観光スポットとなっています)。
その他、「玄昉の体の一部が落ちてきた」という伝説が残る土地は日本各地にあるらしく、「胴塚」や「肘塚」や「眉目塚」(!)など、玄昉伝説の名残が見られる地名がいろいろあるそうです。
おまけに伝説にはさらにオヒレがついて、「玄昉が藤原広嗣の怨霊に残酷な殺され方をしたのは、皇后と実は不倫の関係にあったからだ」というようなとんでもない悪評が加わってしまったのでした。
経歴を見る限り、本人は別に悪人でもなかった様子なのに、完全に後世の伝説が一人歩きしてしまった玄昉。
同じ古代中世の高僧でも、弘法大師空海は「日本各地で奇跡を起こした」という伝説が拡散したのに、玄昉については「日本各地に死体の一部が飛散した」という、ずいぶん違う伝説の拡散となってしまったのでした。
これは完全に後世の人々のゴシップ趣味の犠牲だったのか、それとも「火のないところに煙は立たぬ」のことわざの通り、玄昉には何かしら同時代の人からも嫌われる欠点があったのか?
それはもはや謎ですが、たとえ「雲から現れて五体を引き裂いた」などというのが伝説だとしても、ターゲットの歴史上の評価をここまで貶めてしまったというのは、ある意味、怨霊パワーは機能している、とも言えます。
古代中世の日本史については「怨霊信仰の影響」というものを常に注意していないと、歴史上の人物評価さえうかつには信じられないということで、これはこれで恐ろしい結論ですね。



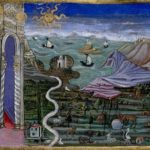





































コメントを残す