前回までで、浩瀚かつ摩訶不思議な書物、プリニウスの『博物誌』の、動物に関する記述を追ってきました。
この書は、続いて「植物」をめぐる記載に入っていきます。
そこで我々も、今回はその「植物」の巻の記述を追ってみましょう。
またそのあとで、『博物誌』後半の重要なテーマである「鉱物」、特に「お金」の話についても、プリニウス先生の見解を見ていきましょう。
Contents
プリニウスの植物学は古代の実用書?!「この植物はああせい、こうせい」と親切心に溢れている!
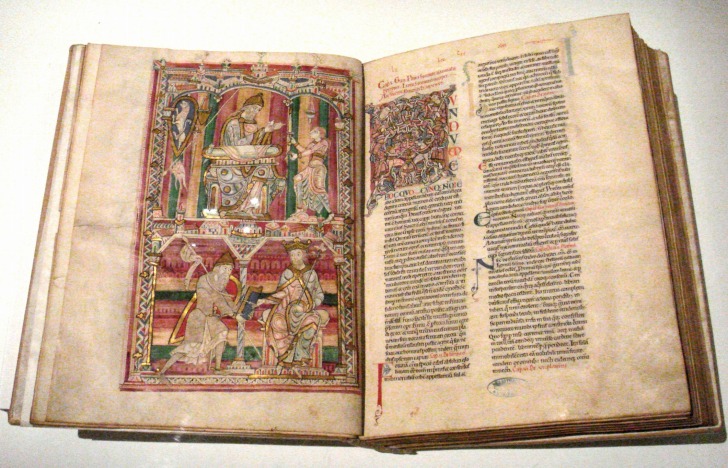
植物についてのプリニウス先生の記述の特徴は、とにかく実用的であることでしょう。
「この樹木は葉を煎じて飲むと何に効く」とか、
「この草はこう加工するとよい紙になる」とか、
そういった生活の知恵につながる話が、実に多彩で、いちいち細かい。
動物の章では、あれほど現実とフィクションが入り混じっていたというのに、「植物の章」はそんなに突飛な話は出てきません。
むしろ古代人の知恵や慣習の記録として興味深い、生活臭あふれるエピソードが続々と登場します。
こういうあたりの記述を読むと、『博物誌』にはもうひとつの側面として、「この草花はこうやって食べましょう」「病気の時はこの草花を薬にしましょう」「この植物はこういうふうに栽培すると増やせます」といった、実用書の役割も持っていたようだと、推測できます。
まるで古代のグルメガイドブック?第14巻のワインのウンチクを語る筆が軽妙に冴え渡る!
ともあれ、一筋縄でいかないのが『プリニウスの博物誌』。
植物に関する章の中に、個人的にめちゃくちゃ気になる箇所があります。第14巻です。
この巻は、まるまる一巻分が「ブドウ」という一種目の植物の解説だけにあてられているという、贅沢な分量となっています。
プリニウスが、たった一種の植物「ブドウ」にまるまる一巻分を注ぎ込んでアツく語っている理由は……もうピンときましたでしょうか?
はい、そうです、ワインのウンチクを垂れているのです!
そしてこれがまた面白い!
「ある種のワインは他の種のワインよりも味がよい、ということを疑う人はいないだろう」
「そのうえ、不思議なことに、同じ樽でつくったはずのワインであっても、ひとつがもういっぽうよりもなぜか味がよくなる、ということも知らない人はいまい」
「そういうわけで、誰でも、あのワインが優れている、いやこのワインのほうが優れている、という問題については、たちまち自分が批評家になってしまう」
いやあ、古代人も現代人と変わらず、「あの酒はどうだ、この酒のほうがどうだ」でアツい議論になっていたのだとわかると、親近感が湧きますね。
そもそも、ここでやや斜視的に語っているはずのプリニウス先生自身も、絶対にワインに対するウンチクでは止まらなくなるタチの人と見受けられます。
この第14巻、産地グレードわけまでを含めてプリニウス先生が延々とワイン論を語り、とどまるところを知りません。
タレントゥムやセルウィティア産のもの、コンセンティア、テンプサ、そしてバリなどでできるもの、そしてルカニアワイン、これはトゥリイ産のものより上位を占めている。
などなど。
ここに登場する膨大な地名がそれぞれ現代のどこを示しているのかは浅学な私には追いきれませんが、プリニウス先生がワイン産地の名前を書きならべる筆が、やけに楽しげに弾んでいるのは確か。
そのうえ、このくだりの締めくくりは、このようになっています。
こういう話題について語っている間に、わたしにこういう考えが浮かんだ。
全世界にワインと名付けられる酒は多いし、著名なものだけで八十銘柄くらいがあるが、そのうち三分の二はイタリアのものであり、そういう点でイタリアは他の国々をはるかに凌いでいるのだと。
さんざん世界のワインを語っておいて、結局最後には自分の故郷のご当地ワイン自慢が出てくるのも、現代のワイン評論家のロジックとあんまり変わらないようですね。。。
「黄金」への人間の欲望に対するプリニウス先生の鋭い警告!

動植物の食用・薬用を含んだ利用をさんざん語った後、話題は「地下資源」の話に移ります。
ここでの主役は「鉱物」です。
特に第33巻には、黄金を巡る話の中で、「指輪」というアイテムについてのウンチクが語られています。
「はじめて黄金を指輪にして指にはめることを思いついた人は、人類に対して最大の罪を犯したと言っていい」
「はじめて黄金の指輪を作ったのはプロメテウスであると言われているが、確かに罪作りなことをした」
「古代ギリシアのミダス王の伝説には、指にはめるとその人の姿が見えなくなる魔法の指輪が登場する」
「多くの人が、黄金を加工して指にはめるという行為の虚飾に人生を惑わされることとなった」
魔法の指輪をめぐるウンチクがあふれるパートとしてとても興味深いところですが、しかしどうやらプリニウス先生は、「黄金」というものに対してネガティブな感情をもっているようですね。
その後に登場する、「金貨」という項目の記述は、もはや辛辣そのものです。
「高利貸しが考え出されたときの貪欲、そして儲けの多い怠惰な生活の最初の源は貨幣の発明にあった」
「急速に、もはやただの貪欲などというものではなく、金に対する絶対的な飢餓が、一種狂乱状態をもって燃え上がった」
プリニウス先生の価値観では、黄金を取引で転がして儲けようとする営為は最低の行為にあたるようです。
特にいわゆる「金融業」などというものは、もってのほかな稼業であった、ということになりそうです。
「不幸なことに、黄金の発見が人間を自然に対する競争者に追いやり、堕落の道を開いたのだ」とも言っています。
彼の眼から見れば、現代のグローバル金融社会はどのように見えるでしょうか?
そもそも地下資源を人間が貪欲に掘り出すこと自体に「待った」をかけるプリニウス先生!
「地下資源」についてのプリニウス先生の記述はなかなか含蓄に富んでおり、目を引きます。
「人類は、いろいろな方法で地中に潜り込み、せっせと地下資源を掘り当てようとしている」
「戦争屋は武器にするための鉄を求めて地中を掘り進めるし、商人たちはただ単に自分のカラダを飾り立てたい人々の贅沢心を満足させるためだけに、きれいな宝石を探して地中を掘り進める」
「それだけ地中を穴だらけにしておいて、いざ大地震が発生すると、大地というものがこんなふうに反逆してくるなどというのは夢にも思わなかったような顔をして大慌てするわけだ」
「だが自然を見渡せば、われわれが人生を幸福に送るのに十分すぎる資源が、わざわざ地中に穴を掘らずとも大地の表面で手に入るではないか?」
「我々が身近にある資源だけで満足する術を心得れば、なんと幸福な社会が地上に実現するであろうか」
実は、このように書いているプリニウス先生自身が、実は著作家になる前の若いころ、古代ローマ帝国の役人だった時代にヒスパニア(今のスペイン)の鉱山開発の指揮をとる仕事をやらされていた、という経歴があります。
おそらくは、そのヒスパニアの地で鉱山の仕事の監督ということをやっている間に、よほど腹にすえかねる現実をいろいろと自分の目で見たのでしょう。
それゆえ、地下資源の乱獲に対する批判的な視点が養われたのかもしれません。
一説には古代ローマ帝国の滅亡は、まさにプリニウスも関わっていた「ヒスパニアの鉱山産業」がだんだん枯渇してきた頃から始まったともいわれています。
そうだとすると「欲望にかられるままに地中を掘り進めるのをやめて、地表で手に入る資源で継続可能な社会を作れ」というプリニウスの主張は、プリニウス本人の思惑すらも超えて、古代ローマ帝国の終末を見事に予見していた重要な警告だったということになりますね。
次回は目を天空のほうに向けて、プリニウス先生が宇宙や神といった問題についてはどう考えていたかを、追っていくことにしましょう!


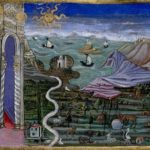






































コメントを残す