「文化英雄」。
あまり聞き覚えのない単語だと思います。これは一般的に神話、あるいは神話学における用語であり、神話において人類に特定の知恵を齎(もたら)し、文化の発展に貢献した者を指します。
文化英雄は「物事の起源を語る神話の主人公」とも言えます。そういった神話は「起源神話」と呼ばれ、「人類起源神話」や「宇宙起源神話」など、いくつかの種類があります。
ギリシア・ローマ神話や聖書、はたまた未開社会における神話まで、多くの神話の中に文化英雄は登場します。また、世間一般の認識では悪役とされている者であっても実は人類の発展に貢献していたりするのが特徴です。
善と悪の双方の要素を内包する神や英雄は「トリックスター」と呼ばれ、物語を引っ掻き回す役回りを担います。代表例であれば北欧神話のロキが挙げられるでしょう。
中には文化英雄とトリックスターの両方の性質を併せ持つ者も存在します。
今回は、世界の神話における代表的な文化英雄たちを紹介していきたいと思います。
プロメテウス

文化英雄の筆頭格として挙げられるのが、ギリシア神話におけるプロメテウスです。
母はティタン神族の海神オーケアノスの娘クリュメネー。父は同じくティタン神族であるイーアペトス。彼はティタン神族の系譜でありながら、ティタノマキアではゼウスらが率いるオリュンポス神族に味方するという立ち回りをした人物でもあります。
ギリシア神話における、オリュンポスの神々以前の神々。天空神ウーラノスと女神ガイアの間に生まれた十二の神々、あるいはゼウスに与しない神。
クロノス(ローマ神話におけるサトゥルヌス)が支配していた時代は、神々と人間は互いに理解し合っていたとされ、ギリシアの創世神話・宇宙論の原典である『神統記』を著した詩人ヘシオドスは「当時、食事は一緒に行われた。人々と不死の神々は共に腰を下ろした。」と遺している。
オリュンポス神族とティタン神族による戦争。終結までには10年の歳月を要したとされ、ヘシオドスの『神統記』に語られる。
プロメテウスのプロは「先の」という意味であり、メテウスはメティス、つまり「知恵」という言葉に由来します。よってプロメテウスという名前は「先見の明を持つ者」と解釈できます。
神話に於いても、プロメテウスは最終的にゼウスが神界を統べる事を予見していた為、他のティタン達が敗北しタルタロスに投げ込まれたり、兄弟であるアトラスが天空をその身で背負い続けるという罰を受けたりしても、プロメテウスだけは罰される事がありませんでした。
プロメテウスが人類に齎した文化、それは「火」であり、その神話はギリシア神話の中でもとりわけ有名なエピソードの一つです。
ゼウスが統べる時代になり、捧げられた巨大な牡牛のどの部分を取るかという目的で神と人間の会合が開かれた。
プロメテウスはその分配役であり、勝手に牡牛を刻んで並べた。そこで彼は人間が有利になるように、肉と内臓と汁気の多い部分を皮に包んだものと、ゼウスを欺く為に骨を脂で覆っただけのものをそれぞれ出し、先にゼウスに選ぶように勧めた。
ゼウスは骨の方――つまり「食べる部位の無い方」を選んだ。白くぎらぎらした脂を取り除き、骨しかない事を知ったゼウスは激怒し、怒りのあまり地上に住む種族から火を取り上げてしまった。
しかしプロメテウスは、鍛冶神ヘファイストスの鍛冶場へ行き、そこから火を盗み出し、人間の所へと持ち帰った。
その後、ゼウスと人類の間には和睦が結ばれたが、プロメテウスはその盗みの罪の為に罰を受けなければならず、ゼウスの命を受けたヘファイストスに捕らえられ、コーカサス山(黒海とカスピ海の間の山脈)に縛り付けられ、鷲に肝臓を啄まれる事になった。
加えて悲しい事に、プロメテウスは神である為、鷲に食われた肝臓は夜中に再生してしまう。その刑期は三十年、あるいは三万年とされ、最終的には神となったヘラクレスによって助け出された。
この神話は有名な「パンドラの箱」の前日譚でもあります。人類の為に縛り付けられるという顛末は、何処か聖書におけるキリストに重なりますね。
上述の罰を受けるプロメテウスを描いた悲劇として、悲劇作家アイスキュロスの「縛られたプロメーテウス」という作品が有名です。最近だと岩波文庫から出ていますので興味ある方は是非ご一読を。
プロメテウスはヘシオドスの『神統記』の中で「さまざまな策に富むプロメテウス」と呼称されることもあり、彼の頭の良さが表れています。
余談ですが、ギリシア叙事詩『イーリアス』、『オデュッセイア』の両方に登場する英雄オデュッセウスも「策略巧みなオデュッセウス」という形で語られ、同じく知恵(メティス)に長ける者、そしてトリックスター的な性質を持つという点で類似点を見出す事もできます。
詩人ホメロスの叙事詩『イーリアス』『オデュッセイア』に登場する英雄。アキレウスや大アイアースといった英雄と共にトロイア戦争を戦い、アキレウスの死後に「トロイの木馬」を考案し遂にトロイアを攻め落とす事に成功する。『オデュッセイア』は彼の帰国までの物語である。
ちなみにプロメテウスが先見の明を持つ勇士であるのと対照的に、兄弟神であるエピメテウスは「後知恵に長ける者」という性格を帯びています。
古代アテナイの人々は、人類に味方し文明の発達に貢献した彼を人類の恩人、また全ての技術の父である、としてアカデメイアに彼を祀る祭壇を建てたとも伝えられます。
古代ギリシアの都市国家。パルテノン神殿が位置し、ギリシア神話のアテーナ―への信仰の中心地でもある。
古代アテナイの演武場。古代世界の大哲学者プラトンはここで教えを説いた伝承される。
ティタン神族という、かつてオリュンポスの神々と争った種族の出自でありながら、人の為にその身を捧げた「文化英雄」にして「トリックスター」。それがプロメテウスという神でした。
ルシファー

次に紹介する文化英雄は「ルシファー」です。意外にも、彼は実は旧約聖書の世界における文化英雄なのです。
ルシファーは悪魔の王であるサタンと同一視され、かつてはミカエルに並ぶ最高位の天使だったとされます。また、悪魔が元々天使だったことに言及していると解釈される箇所が旧約聖書内にあり、預言書の一つ『イザヤ書』には以下のような記述が見受けられます。
「ああ、お前は天から落ちた明けの明星、曙の子よ。お前は地に投げ落とされたもろもろの国を倒した者よ。かつて、お前は心に思った。「わたしは天に上り王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し雲の頂きに登っていと高き者のようになろう」と。しかし、お前は陰府に堕とされた。墓穴の底に。」(イザヤ書14章12-15節)
ユダヤ・キリスト教における大天使。キリスト教神学における天使の九階級では最高位の熾天使(セラフ)に位置する。旧約聖書、新約聖書、コーランにそれぞれ登場し、ガブリエルと共に聖書正典で固有名詞を持つ数少ない天使。
上の文で触れられる「明けの明星」とは金星を意味し、メソポタミア神話における大女神イシュタル、旧約聖書にも登場するアスタルテ女神、ギリシア・ローマ神話における美の女神アフロディーテ(ローマ神話におけるヴィーナス)など、古来より神格化の対象になっていた天体でした。
イザヤ書14章における「明けの明星」は本来、バビロニアの王ネブカドネザル二世を意味していたとされます。
明けの明星は「光を齎すもの」という意を持ち、ラテン語でルキフェルと訳されました。この語がそのまま「落ちた明けの明星」である堕天使ルシファーの語源になったとされます。
古代のキリスト教神学者であるオリゲネスは早くから悪魔サタンと明けの明星が同じだと解釈しており、彼はその著『諸原理について』の中で
と説いています。
ルシファーが人類に一体何を授けたのか、という点に関してですが、一言で言えば「知恵そのもの」です。
その話は旧約聖書の最初の部分である『創世記』に記されており、誰もが知る「楽園追放」になります。聖書箇所は創世記第三章です。
神が造った「最も賢い生き物」である蛇が、エデンの園に住まうアダムとイヴをそそのかして知恵の実を食べさせるという説話です。アダムとイヴはこの行為が原因でエデンの園を追放されてしまいます。この罪は「原罪」と呼ばれ、彼らの子孫はその罪を背負う事になりました。
創世記の蛇について、新約聖書最後の正典『ヨハネの黙示録』12章では
「この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わす者は、投げ落とされた。」(ヨハネの黙示録12章9節)
と、サタンと同一視していることから、ルシファー(後のサタン)は人類に原罪を背負わせると共に、無知だった人間に知恵を齎した文化英雄になるのです。
ルネサンス期の詩人ジョン・ミルトンの叙事詩『失楽園』では、他の天使達と共に創造主たる神に叛逆し、敗北するも神への復讐を諦めないルシファーが語られており、ある種英雄的に描かれています。
『失楽園』は旧約聖書の創世記をテーマにしていますが、キリスト教における天使や悪魔、ギリシア・ローマの神話に登場する地名や怪物など、異教神話の要素が多く含まれているというのが面白いポイントです。
キリスト教美術におけるルシファーは時に大天使ミカエルそっくりに描かれる事もあります。これは悪魔ですら元は天使であったと捉える考え方に基づいたものとされています。
エグリゴリの堕天使

次に紹介するのは旧約聖書の外典、あるいは偽典とされる『エノク書』に登場する堕天使の一団「エグリゴリ」です。その名は「見張り」を意味し、エノク書において重要な役割を果たす堕天使でもあります。
まずエノク書という文書について説明します。
エノク書にはエチオピア語で書かれた「第一エノク書」とスラヴ語で書かれた「第二エノク書」の二通りのバージョンが存在し、どちらも旧約聖書に登場するエノクという人物の視点、天使と堕天使など、共通の主題で描かれます。
しかし詳細な部分の記述には相違があり、エチオピア語エノク書が言わば「旧約的」であるのに対し、スラヴ語エノク書は「新約的」と表現されることがあります。
特に両文書を比較した際、スラヴ語エノク書の方が神の厳格さが柔げられ、その恩寵が協調されており、また新約聖書の一文書『マタイによる福音書』に似た箇所も見出されます。
大きな違いですと、エノクは天使達に壮大な宇宙の幻視を見せられるだけではなく、実際に七つの天を上昇し、最後には神と対面し天界の書記になると記されています。
少々前置きが長くなってしまいましたが、ここからエグリゴリの堕天使について掘り下げていきます。なお今回は、エチオピア語の『第一エノク書』を参照していきます。
エノク書の内容の大筋は両方とも旧約聖書『創世記』に準拠しており、創世記6章における
「神の子らは、人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだ者を妻にした」(創世記6章2節)
という一節の、人間の娘を娶った天使達について細かく掘り下げられています。エグリゴリ達について直接的に言及するのは『第一エノク書』第6章です。
「そのころ人の子らが数を増していくと、彼らに見目麗しい美人の娘たちが生まれた。これを見たみ使いたち、(すなわち)天の子たちが彼女らに魅せられ、『さて、さて、あの人の子らの中からおのおの嫁を選び、子をもうけようではないか』と、言いかわした。」(エチオピア語エノク書6章1-2節)
この天の子、つまり天使の言葉はまさに『創世記』6章2節のものですね。彼ら一同は人の娘を娶るという計画を反故にしないことを誓い、ヘルモン山という山に降り立ちます。
エグリゴリを構成するのは200名の堕天使であり、シェミハザ、アラキバ、ラメエル、コカビエル、アキベエル、タミエル、ラムエル、ダネル、エゼケエル、バラクエル、アサエル、アルメルス、バトラエル、アナニエル、ザキエル、シャムシャエル、サルタエル、トゥルエル、ヨムヤエル、サハリエルらを首長としています。
その後、彼らは地上に妻を娶り、女たちに「医療」「呪い」「灌木の断ち方」といった知恵を齎します。人間の娘は天使の子を身籠り、「ネフィリム」という巨人が生まれていきました。
「彼女たちははらんで、背たけがいずれも3000キュビトというとてつもない巨人を生んだ。彼らは人間の労苦の実を食い尽くしてしまい、人間はもはや彼らを養うことができなくなってしまった。そこで巨人たちは人間を食わんものと彼ら(人間)に目をむけた」(エチオピア語エノク書7章2-4節)
ここの部分で言う3000キュビトは1350メートルに相当します。
ネフィリムは聖書正典の『創世記』においても言及されており、6章4節では「大昔の名高い英雄だった」と言及されています。
エグリゴリ達は地上に降りた際、人間達に様々な知識を伝えました。誰が何を伝えたかは以下のように記されています。
「アザゼルは剣、小刀、盾、胸当ての造り方を人間に教え、金属とその製品、腕輪、飾り、アンチモンの塗り方、眉毛の手入れの仕方、各種の石のなかでも大柄の選りすぐったもの、ありとあらゆる染料を見せた。(その後)はなはだしい不敬虔なことが行われ、人々は姦淫を行ない、道をふみはずし、その行状はすっかり腐敗してしまった。シェミハザは、すべての魔法使いと(草木の)根を断つ者とを教え、アルマロスは魔法使いをいかに無効にするかを教え、バラクエルは占星家を、コカビエルは(天体の)兆を、タミエルは星の観察の仕方を教え、サハリエルは月の運行を教えた。人間どもは、滅んでゆく途中大声にわめき、その声は天に達した」(エチオピア語エノク書8章1-4)
他の堕天使達によって齎された知識は武具の作成や化粧、また魔術と魔術の対処法、そして占星術や天文学に纏わるものでした。それらは生活を豊かにしていくものでしたが、それが原因で人類は悪い方向へと向かっていきます。
地上に不道徳が蔓延っている有様を、ミカエルやガブリエル、ウリエル、ラファエルの四大天使が目にし、神は彼らに堕天使達を処罰するように命じます。
「主はまたラファエルに言われた。「アザゼルの手足を縛って暗闇に放りこめ。ダドエルにある荒野に穴を掘ってそこに投げこめ。」」(同章4節)
「また神はガブリエルに言われた。「ててなし子や不義の子、姦通の子らをねらい、姦通の子、寝ずの番人が生ませた子を人間の中から滅ぼし去れ。」」(同章9節)
「神はミカエルに言われた。「シェミハザとその同輩で女たちとぐるになり、ありとあらゆるけがらわしいことをして自堕落な生活をした者たちにふれよ。彼らの子孫が斬りむすんで果て、愛児の絶望を見たら、彼らを七〇世代、彼らの審判と終末の日、永遠の審判が終了するまで、大地の丘の下につないでおけ。」」(同章11節)
堕天使の裁きにおける、大天使たちの役割は上記のものになります。
ガブリエルに向けた文のうちの「不義の子」は天使と人の子であるネフィリムを意味しており、巨人たちを地上から滅ぼせ、というのがガブリエルの役割です。
ミカエルに向けた一節では「終末の日」というワードが登場していますが、エノク書は「黙示文学」と呼ばれる類の文書であり、旧約聖書の『ダニエル書』、新約聖書の『ヨハネの黙示録』と同じく世界の終末や最後の審判についての啓示というテーマが共通しています。
人類の生活を豊かにする知恵を授けるが、最後にはそれが理由で捕らえられてしまう。この『エノク書』に記される堕天使達の物語は先述したプロメテウスの神話と何処か似ていますね。
聖書における文化英雄として考えられるルシファーと同じく、一般的には悪のイメージが付き纏う者達であっても、見方によっては人類の発展に貢献したとも考えられるのが面白いところですね。
エンキ

次に紹介するのはメソポタミア神話における水神エンキです。
エンキはシュメール神話における名前であり、アッカド神話ではエアと呼ばれる知恵の神です。
シュメール神話や『ギルガメシュ叙事詩』、『アトラ・ハシース』などに語られる洪水神話において人間に方舟を造るように伝え、助けるという役を担っています。
そんな人間の味方のようなエンキ神ですが、彼はシュメール神話の一節『エンキとニンフルサグ』という説話において、妻のニンフルサグと娘のニンスィキルと共に、清らかだが「水の無い国」であるディルムンを訪れます。この国で町を築いていくというのがこの神話の主題となります。
神話において、彼は娘の質問に答えていく形でディルムンに「苦い水」に変わって「甘い水」を引いたとされ、その部分が以下の部分になります。
〔大地の水が流れ出る「口」から、あなたに甘い水を大地から運びますように!〕
そこからあなたの大きな〈 〉の中へ水を運びますように!
あなたの町に豊に水を飲ませますように!
ディルムンに豊かに水を〔飲ませますように!〕
あなたの苦い水の井戸を甘い水の(出る)井戸に〔するように!〕
(杉勇・尾崎亨訳『シュメール神話集成』筑摩書房、2019年、26-27pより)※〈〉や〔〕の部分は破損・翻訳困難な部分。
ここで言う「苦い水」とは塩水、「甘い水」は淡水をそれぞれ象徴しており、海水に満ちていたディルムンの沿岸の地帯を穀倉地帯に変えたと解釈されます。
続いて、エンキは妻ニンフルサグと寝て「青野菜の貴婦人」の意を持つニンサルを、娘のニンサルから「繊維植物の貴婦人」の意を持つニンクルラを、ニンクルラから「機織りの女神」の意を持つウットゥを生ませました。
このように、エンキは妻のみならず娘をも身籠らせています。
ですがギリシア神話のポセイドーンは非常に多くの愛人を持ちますし、中国神話における河伯は人身御供に美しい娘を要求するなど、世界の神話における水神は好色という類似点があります。
この『エンキとニンフルサグ』の説話は、始祖が子孫を増やしていくという天地創造神話の形になっており、エンキはディルムンという国に淡水を引いた治水事業者にして繊維植物、青野菜を齎し、機織りの技術をこの国に齎した文化英雄ということになります。
ディルムンの国は現在、ペルシア湾西部の群島のバーレーンであると特定されています。聖書学者の中には、この国を旧約聖書の『創世記』におけるエデンの園と考えた人もおり、エデンという語はシュメール語の「荒野(edin)」、ヘブライ語の「無上の喜び(eden)」という二つの語に重なります。
このディルムンの地はエンキによって開拓された後、大洪水を生き残ったジウスドゥラが住んだと語られています。
至高神エンリルや大女神イナンナ等、荒々しくも奔放な神々が多く登場する中で、人間側に立って動く事の多いエンキ神でした。
ヘルメス

次に取り上げるのは、ギリシア神話ではお馴染みのヘルメスになります。伝令の神として広く知られるヘルメスですが、彼はそれ以外にも非常に多くの性格を併せ持っています。
ヘルメスは時に盗賊や旅人の守護神としても信仰され、分かれ道や十字路に神像が造られた事もあり、故に道祖神のような性格を備えています。
道端や分かれ道などの境界に祀られ、旅行安全や外部からの疫病を防ぐとされる神。日本で言う地蔵菩薩が有名な例。ギリシアでは冥界の女神ヘカテーも似た性質を持つ。
他にも商業や雄弁を司り、更には「霊魂の案内人(プシューコ・ポンポス)」という、冥界を先導する側面も持っています。
彼の持つ性格はまだまだあり、アレキサンドロス大王の死後に始まったヘレニズム時代(紀元前323-30)には、彼の持つ杖カドゥケウスと共に錬金術においても象徴とされました。
また、その時代にはヘルメスはエジプト神話の知恵の神であるトート神と習合され、更に錬金術師ヘルメスと同一視されていき、その結果ヘルメス・トリスメギストスという伝説的な神人が生まれました。
アレキサンドロス大王の東方遠征により、古代オリエントと古代ギリシアが融合した文化。また、ヨーロッパの文明の根幹を成すギリシア的文化。
エジプト神話の一柱。知恵を司り、朱鷺、またはヒヒの頭を持つ。
ヘルメスが文化英雄たる所以を、ここでは二つほど紹介します。
まず一つ目です。ヘルメスは伝令神として世界を駆け回りますが、その疲れを知らない様から競争、また拳闘(ボクシング)を発案したとされ、オリュンピアの競技場の入口にはヘルメスの像があったとされます。
二つ目は、「竪琴の発明者」というポイントになります。ヘルメスは神話において、太陽神アポローンの牝牛を盗み出したという逸話を持っていますが、アポローンとの和解の際に亀の甲羅で竪琴を作って贈ったという説話があり、これが最初の竪琴であったと語られています。
ギリシア神話で竪琴と言えばアポローンや英雄オルフェウスが有名ですが、ヘルメスが竪琴を送って以降、音楽の神になったとされていますし、オルフェウスが妻エウリュディケを連れ戻そうと冥界に赴いた際にはヘルメスが先述した「霊魂の案内人(プシューコ・ポンポス)」として付き添っています。
このように、非常に多彩な性格を帯びるのがヘルメスという神です。最初に挙げたプロメテウスと同じく、トリックスター的な性質を帯びる神格であると言えるでしょう。
まとめ
神話における文化英雄は他にも数多く存在します。フィンランドの叙事詩『カレワラ』や未開社会に語られる神話にも、文化の起源に纏わる神の説話は多く語られています。
今回で紹介したものはほんの一部分に過ぎないので、興味のある方は是非調べてみて下さい。
※参考文献
- 左近淑ほか訳『聖書外典偽典第三巻 旧約偽典Ⅰ』教文館、1975年
- 村岡祟光『聖書外典偽典第四巻 旧約偽典Ⅱ』教文館、1975年
- 関根正雄・新見宏訳『旧約聖書外典(下)』講談社、1999年
- 金光仁三郎著『ユーラシアの創世神話[水の伝承]』大修館書店、2007年
- フェリックス・ギラン著、中島健訳『ギリシア神話』青土社、2011年
- 岡田温司著『天使とは何か』中央公論社、2016年
- 荒川紘著『龍の起源』紀伊國屋書店、2017年
- 岡田明子・小林登志子著『シュメル神話の世界』中央公論社、2019年
- 杉勇・尾崎亨訳『シュメール神話集成』筑摩書房、2019年
- 矢島文夫訳『ギルガメシュ叙事詩』筑摩書房、2019年
- ミルトン著、平井正穂訳『失楽園(上)』岩波書店、2020年
- ミルトン著、平井正穂訳『失楽園(下)』岩波書店、2020年
- グスタフ・デイヴィットスン著、吉永進一訳『天使辞典』創元社、2020年




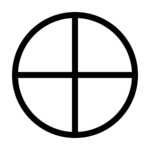




































コメントを残す