アヴァロンへ

「モードレッドはどこだ! 裏切り者はどこにおる!」
父の声だ。
怒号とともに剣が風を切る音、そして切っ先が騎士たちを両断する音が聞こえる。
ベイドン山で1日1000人近い兵士をひとりで屠った偉大なる戦士がそこに復活していた。
打った手はというと、実に簡単なことだった。
王の第1の騎士とうぬぼれる、世間知らずのランスロットをそそのかし、グィネヴィア王妃に接近させた。
王の崇高な使命などに何の興味も関心もなく、ただ自分の手の届く範囲しか見えぬ彼らは、たちまちのうちに恋とやらに落ちた。
単なる男と女の逢瀬である、それを純化したものだ、と彼らは考えただろう。
だが、王国第1の騎士と王妃の不倫は、それだけで王国の平和と統一にひびを入れるに十分な事件だったのだ。
事態が発覚したランスロットは、ドーバーの向こうへと逃げ、城に立てこもった。
アーサー王は苦悩のあげくに、兵を率いて海を越え、そしてランスロットの城を囲んだ。
一度和議がまとまり、ランスロットが拉致した王妃の身柄がキャメロットへと戻された。
その隙を狙い、俺が王位と王妃とを奪って兵を挙げたのだ。
父は一瞬にして、すべてを失ったかのように見えた。
眼の見えない連中は、いまだに父をそう見るだろう。
だが見よ。エクスカリバーを風車のごとく振り回し、万人の敵にひとりで立ち向かう雄々しい姿を。
血煙を上げつつ、戦場を疾駆するその姿は、他の何ものよりも美しい。
ローマを征服し、ヨーロッパ全土を手中に収めた英雄が今、復活したのだ。
人はそれを、血に飢えた野獣とか、狂戦士などと罵るだろう。
だがそういう連中の誰が、あのように卓越した武勲を戦場で現し続けることができるというのだ?
父が率い、ともにドーバーを超えてきた兵の数は数100に満たない。
俺の軍は、その10数倍はいた。
俺に味方したのは、秩序の破壊者にすり寄って、そのおこぼれにあずかろうというダニどもばかりだったが、それでも数だけは多かったのだ。
しかしよみがえった父の前に、兵数の数など問題ではなかった。
アーサーひとりが先陣にある限り、その軍は無敵だったのだ。
俺は戦場の英雄王の背に、白い翼が生えているのを見た。
その英雄が、俺を呼んでいる。
「モードレッド、出てこい。お前の主アーサーがお前を呼んでいるのだ! 正々堂々と姿を現せ!」
父が俺を「お前の主」と呼んだ。
その瞬間、俺は感動の涙で前が見えなくなった。
そう、俺は正しくあなたの僕だ。国王陛下。
裏切りはしたが、誰よりも誠実なあなたの臣下だ。
あなたをキャメロットの玉座に縛り付けていた鎖を断ち切り、戦場の勇者としての真の姿を取り戻させたものだ。
「モードレッド! 戦争はお前の勝ちだ! 俺は老いている。この戦場を制しても国と王妃は取り戻せまい。お前は見事に俺からすべてを奪うことに成功した!」
すべてを奪われた、と叫ぶあなたの何と気力に溢れたことか。
「俺の兵ももうろくに残ってはおらん! お前の勝ちだ!」
王の後ろから駆け寄ってきた執事のルーカンが、不意にのけぞり、腹から腸を飛び散らせて倒れた。
俺の兵に討たれたものか、父のエクスカリバーの餌食になったのかはわからない。
純粋な戦士に戻った父にとって、今や兵士は敵であろうが味方であろうが関係はないのだ。
己以外はすべて、全力をもって立ち向かうべき相手。
等しく危険な場所に自らを置き、敬意をもって撃ち殺すべき獲物なのだ。
その、獲物を屠る猟師が、最後の獲物としてこの俺を求めている。
俺は戦斧を引っ掴むと、雄叫びを上げながら父の元へと走っていった。
「アーサー! この俺の呪われた運命の元を作った罪深き王よ!」
「モードレッド! 来たか裏切り者!」
父は振り下ろした戦斧を、エクスカリバーで受け止めた。
老いを感じさせないみずみずしい力が、聖剣と戦斧を通して、この身に伝わってくる。
戦斧を叩き込んだはずの俺が、逆に押されてきた。
やっとの思いでエクスカリバーを振りほどくと、背中からどっと冷たい汗が噴き出す。
「呪われた運命の元とは、どういうことだ!」
父はそう喚き、上段に構えたエクスカリバーを振り下ろす。
「知らぬとはいわせぬ。お前が実の姉モルゴースに邪な想いを抱いたが故に、俺はこの世に生を受けたのだ」
「何!」
「5月1日に生まれた子をまとめて船に乗せて流したことを覚えていよう」
「あの中に貴様がいたというのか!」
「おお、いたとも。他の赤子は皆死んだ。生き残ったのは俺だけだ」
「その時の復讐をしようと考えたか、モードレッド!」
「復讐? 何をいうか。そんなことをいつまでも根に持つほど、俺は小さい人間ではない」
「ならばなぜ、俺に牙を剥いたか」
「俺は俺が正当に得るべき遺産を、あなたから受け取りに来たのだ、アーサー!」
「王国と妻のことか。なるほど正嫡の子ではないお前には、こうでもしない限り得られないものであったな」
「違う!」
「何が違うのだ」
「王国や王妃など、どうでもよいのだ」
「俺の半生を費やして築き上げた宝物の山が、どうでもいいというのか」
「そうよ。あなたと同様にな」
「俺も同様というか」
「今やあなたもどうでもよいと思っているはずだ。あなたは今、真にキャメロットが欲しいか。グィネヴィアを抱きたいか」
「……」
「俺はこの戦場に来る前に、グィネヴィアを辱めて殺し、キャメロットの宝物蔵に火を放ってきた。もう存在しないのだ。あなたが築き上げた宝物の山とやらは」
「モードレッド……」
「財宝を失ったと聞いて、落胆したか、王よ」
「かつて想像した程には、辛くはない……というより、ほとんど心に痛みを感じない」
「妻を失ったと聞いても、そうか」
「不思議と、悲しみを感じぬ」
「さもあろう。あれはただの女だった。最もあなたにほど近い所にいながら、あなたがどういう方かを理解することができなかった」
「わが妻が、俺を理解しなかったというのか」
「そうだろう。これから1000年の長きにわたってその勲を讃えられる英雄王の妻であると自覚しているのなら、ランスロットなどに走りはすまい」
「しかし俺との間に感じることのできなかった愛の喜びを、ランスロットとの間には感じることができたのではないか」
「英雄王の唯一の妻としての法悦に勝るものなどありはしない。アーサー、あなたが英雄である以上、あなたの人生に普通の女など何の意味も持つことはできなかったのだ!」
「女も、財宝もどうでもよいというのか」
「俺もそういうことはどうでもよい。ただ全力であなたと打ち合えれば、それでいいのだ!」
そういいつつ俺は、再び全力で戦斧を、父アーサーの頭上に振り下ろす。
エクスカリバーはその渾身の一撃を、火花を散らして食い止めようとする。
だが、戦斧の切っ先は一瞬早く、アーサーの兜を砕いていた。
どす黒い血の霧がばっと飛び拡がる。
「王の中の王と、単身で戦える勇者の証を示すことこそ、あなたの子が受け継ぐべき正当な遺産だったのだ!」
その言葉を聞いた時、父が笑った。
仁君、聖王として讃えられつつも、この何十年もの間、誰にも見せなかった笑顔を、この俺に向けた。
「モードレッド!」
次の瞬間、アーサー王は全身から獅子力を振るい起こし、俺を戦斧ごと突き飛ばし、エクスカリバーを横に薙いだ。

ばん、と水入りの大樽をハンマーで割ったような音がした。
俺の上体が崩れる。
目の前が、一瞬にして冥くなった。
「モードレッド……わが子よ。先にアヴァロンにて待て」
意識を失う寸前、俺は確かに父がそう呼ぶのを聞いた。
ああ、もうそれで十分だ。父よ、あなたは英雄であることをこの戦場で証明された。
俺はその父に祝福され、今、死出の旅に赴こうとする。
俺が行く先が、神や天使が待ち受ける天堂であるはずはない。
また、暗い穴の奥に悪魔がうごめく地獄であるはずもない。
英雄王の祝福を受けた俺は、勇者のみがゆけるアヴァロンの島へと行くことになるのだ。
父も、程なく行くであろう。
俺が頭に加えた一撃は、致命傷になっているはずだから。
父よ、アヴァロンへ行ったらまずは、ともに傷を癒そう。
そして、また心ゆくまで得物を振るって戦おうではないか。























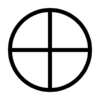















コメントを残す