このシリーズでは『プリニウスの博物誌』を読むことで、古代ローマに現れたこの希代の物知りおじさん(!)の魅力を追ってきました。
最終回の今回は、地震や火山噴火といった自然災害に対するプリニウスの情熱に満ちた知識欲に触れたいと思います。
そしてその情熱がもたらした彼の最期についても、触れておきましょう。
Contents
雷も地震も神のせいではなく自然現象である!古代人プリニウスが到達した力強い自然観!

この連載でも何度か述べてきた通り、プリニウスの発想の根幹には「自然哲学」の考え方があります。
彼にとって自然を研究するのは、それを克服するためではなく、その摂理を理解して「なるべく逆らわない生き方をする」ためでした。
それゆえ彼の自然災害に対する態度も、我々が一般にイメージする「西洋的な自然観」の中にあてはめようとすると、いっぷう変わったものに見えます。
プリニウス先生は、地震であろうと火山噴火であろうと、それらは別に神のせいでも悪魔のせいでもなく、当然善でも悪でもなく、「起こるときには起こるもの」であると冷静に見ているところがあるのです。
それでいて「だから災害に対しては諦めよう」となるわけでもなく、「起こるべき災害が起こってしまったときには、なんとか人間どうしが助け合ってうまく乗り切ろう」という発想に行くあたりが、「自然には絶対に勝てない」「すべては無常である」といった東洋流の諦念ともまた違っています。
このバランス感覚が面白いところですし、なんとも、「現代的」な自然観だと思います。
なにせこの人、この時代にあって、
「星が落ちてくるのも自然現象のしわざであって、何の吉兆でも凶兆でもない」
「雷はユピテル神(ギリシア神話でいうゼウス)が起こすものだというのは間違いである」
と言い切っている人なのですから。
占星術を信じている高官や貴族もたくさんいたはずの時代、ユピテル神への信仰も盛んだったはずの時代だというのに!
ポンペイの悲劇とともに倒れた、その最期について

プリニウスの死は、火山噴火で滅んだ町、「ポンペイの悲劇」と関係があります。
ヴェスビオ火山の噴火のニュースを受けたプリニウスは、急いでポンペイに駆けつけます。
火山や地震の研究を長らくやってきた経験から、何か役に立つことがあると思ったのか、それともこれほどの大災害のニュースをきいて、歴史に残る大噴火を自分の目でも見たいという好奇心にかられたのか。
いずれにせよ、最初は快速船を出させて災害現場に急行したのですが、そこで自分の目で現地の危機的な状況を見るや、追加の船を後発させる指示を出します。
噴火に取り残された住民たちを、一人でも海上に助け出そうとしたものと思われます。

船団を用意して、噴煙巻きあがる火山をにらみながら上陸したプリニウス先生。
しかしもともと気管支に持病をかかえていた彼は、そこでめまいを起こし、急死してしまいます。
あふれていた有毒ガスを吸ってしまったのか、あるいは噴煙を吸ったことで持病の発作が起こったものと思われます。
いずれにせよ家族のところに届けられたプリニウスの死体は、眠っているような安らかさだったと伝えられています。
最後まで自然の驚異に引き込まれ、最終的には自然のパワーに打ち砕かれてしまったものの、その死の直前まで災害から人間を救い出そうとする前向きな姿勢を崩さなかった博物学者。
人生の締めくくりとしてあまりにも完璧でした。
この時に火山噴火で滅亡したポンペイは、火山灰に埋もれたおかげで当時の建物がきれいに残った状態で、現代では世界的な観光地となっております。
イタリア旅行のハイライトのひとつとされていますが、このプリニウスの最期の話を知ってから訪れると、なおさら感慨深い旅行になるかもしれませんね。
プリニウス先生の論理の一貫性:来世をばっさり否定!大事なことは現世での助け合いの精神である!
ちなみにプリニウス先生自身は、死後の世界についてはいったいどう考えていたのでしょうか?
まさにこの問題を扱った章が『プリニウスの博物誌』の中にもあるのですが、そこにおける「死」についての記述は、以下のような、なんともそっけないものです。
「誰でも死んでしまったら、生まれる前と同じ状態に戻る。
つまり、肉体も精神も感覚をもたない状態に戻る。
これは生まれる前と同様に戻るというだけのことで、悲しむべきことでもない」
「ところが人間の空しい望みが、自分だけは死後も永遠に続くというツクリバナシをでっちあげる」
「こういうことは子供くさいばかげた空想なのだ。
人間の肉体を保存しておくだとか、デモクリトスが、人間はまた復活すると約束したというようなことも、同じむなしい望みなのだ。
だいいち、死後の復活を説いていたデモクリトス自身が、ぜんぜん復活などしていないではないか」
どうやらプリニウス先生の世界観に、霊魂とか来世とか、天国とか地獄とかはないようですね。
これも東洋的と言いますか、あくまでもすべてを自然にゆだね、しかるべき時には静寂に死を迎えることが、人間の理想であるとみているようです。
来世を否定し、神も悪魔も否定し、地上において価値のあるものは「人間同士の相互の助け合い」のみであると主張をしていた人物、プリニウス。
その彼が実際に自然災害の現場に駆けつけて命を落としたとは、なんという首尾一貫性!
まとめ:プリニウスの博物誌の魅力はまだまだ語りつくせない!
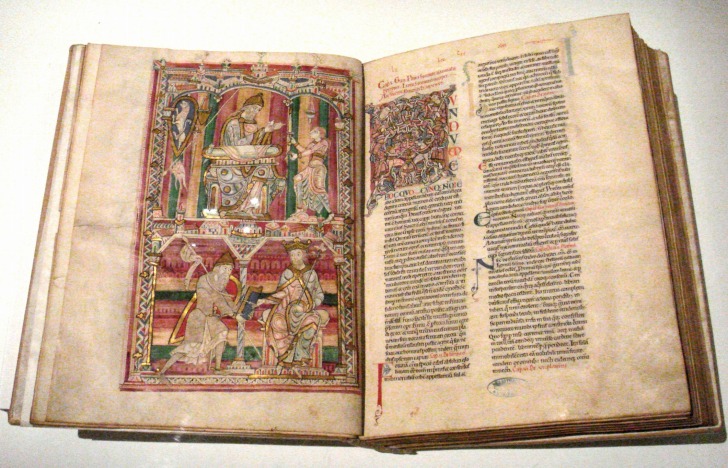
これまで6回にわたって、『プリニウスの博物誌』を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
おそろしいことですが、これだけ語っても、『プリニウスの博物誌』の中には、まだまだ語りつくせていないテーマが豊富に眠っています!
たとえば第36巻、エジプトのピラミッド、エフェソスのディアナ神殿、ローマの劇場や水道、アレクサンドリアの大灯台などの「驚異の建造物」をめぐる筆致を軽やかに滑らせつつ、その巻のしめくくりに、「タルクイニウス・プリスクスの治世に起こったことだが、彼の炉の灰の中から突然男根が出現し、そこに座っていた囚われの娘で、王后タナクイルの侍女であったオクレシアがそこから起き上がると、身重になっていたという」というあたり。
こういう、またしてもアヤしい伝説が平気で挿入されてくるあたりが、まさに『プリニウスの博物誌』の読みどころですね。
こんなふうに細かいところにまだまだオモシロいポイントは織り込まれていますし、私自身もまだまだ見落としているポイントは眠っているでしょうし、読む人によって気づくポイントも変わってくるでしょう。
最初から順番に読んでも、
最終巻から逆流に読んでも、
偶数巻だけ読んでも奇数巻だけ読んでも、
ランダムな巻を抜き出して適当に読んでも、
果ては好きな巻ひとつだけをとってパラパラとめくってみるだけでも、
読み方によってまるで違う景色が見えてくる、万華鏡のような不思議な本。
古代には大迷宮(ラビリントス)の伝説などもありますが、この『プリニウスの博物誌』という書物自体が、一つの摩訶不思議な迷宮になっているような気がします。
そしてもうひとつ。
プリニウスの博物誌を読むと、なんだか無性に博物館へ行きたくなってきますね(笑)!
次の休みの際には、子供心にかえって、博物館に出かけ、動物や植物、鉱物や宇宙の構造の不思議など、自然界の偉大さひとつひとつに改めて胸を躍らせてみるのも、よいのではないでしょうか?




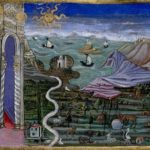





































コメントを残す